
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第10回 姜尚中 学問は誰のためのものなのか
第10回は政治学者・姜尚中さんにご寄稿いただきました。本企画の発端となった「日本学術会議問題」については、メディア等で様々な議論がされてきました。しかし、そうした中で、「学者の社会的立場」をめぐる重要な論点が見落とされているのではないか、と姜さんは指摘します。
姜さんによれば、今回の学術会議問題の深層に迫るにあたってヒントを与えてくれるのは、二度にわたる世界大戦の頃の社会情勢だといいます。わたしたちは過去の教訓から何を学び取れば良いのでしょうか。歴史的観点を交えて論じて頂きました。
学問の自由と大学の現状
日本学術会議の新会員任命拒否問題をめぐる一連の議論の中で、「学問の自由」ということが重要なキーワードとして浮上してきた。きわめて大切な問題なので、この問題は本質論から深めていくべきだと考える。以下、本稿では大きく二つの観点から検討していきたい。
第一に、日本学術会議は、選ばれたアカデミシャンたちが、国に対して一定程度独立した立場から提言やアドバイスを行っていく学者の組織だが、その構成メンバーは、ほとんどが大学人である。そのため、今、大学の実態はどうなっているのか、という問題を考えなければならない。
第二に、科学、あるいはもう少し広く科学技術というものが、普通の人が生活している一般社会から乖離して、独自のオートノミー(自律性)を持った世界を形成しているという問題がある。科学の専門家や、あるいはその専門家によってつくられる学術文化が、普通の人々の日常生活を土台として成り立つ常識や社会的なコミュニケーションなどから切り離されてしまっているのである。それをいかにして日常生活、社会に接合させるか、ということが課題となるだろう。
まずは第一の論点について考えてみよう。「学問の自由」とは、学問の研究・教育を職業とする専門家だけのものだろうか。第一義的には確かにその通りである。しかし、その専門家の自由が保障されなければならないのは、学問というものが大学の教員や研究機関の研究員などといった特定の職業の範囲を超えて、例えばワクチンの開発などのように、広く社会に影響を与えるからである。こうした側面を無視して、我々が日常を暮らす生活世界から遊離した議論を続けていると、おそらく一般の人々の間では、学問の自由の意義に対する関心は深まらないのではないか。
日本学術会議新会員任命拒否問題も、初期の段階と比べると社会的な関心が弱まっているように見える。結局、自分たちとは離れた空中戦のような形で議論が展開されているという風に、普通の人々は受け止めているのではないか。本来ならば、これは「表現の自由」にまでかかわる私たちにとっても身近な問題なのだが、なかなかそのような深掘りができていない。専門家集団、科学者集団がオートノミーを持った一つのシステムとして、研究の自由を死守していくべきだという議論だけに終始すると、社会的な共感が広がらないのではないか。
本来ならば、科学技術と一般の人々との回路を開く役割を大学が果たさなければいけなかった。ところが、国公立大学の法人化によって、大学の組織はそれ以前に比べてかなり官僚制的になり、「大学人としての研究者」は、ともすれば研究や教育よりも研究予算の獲得のための書類づくりに追われ、悪く言うと官僚制的システムの中の一つの部品になってしまった。内心忸怩たるものを抱えながら、しぶしぶ組織人として行動している大学人も多いと思われる。
また、科学について言えば、一口に科学の研究者と言っても、アインシュタインやハイゼンベルクのような一部の天才的科学者ばかりをイメージするのは大きな誤りである。多くの研究者は多数の構成員から成るプロジェクト単位で共同研究に所属している。現在、特に自然科学系の研究は、大型プロジェクトとして行われることが普通となっており、個々の研究者はますます組織の歯車としてふるまわざるを得なくなっている。しかし一方で、研究者には個人としての良心もある。いわば、研究者はその二重性の中でジレンマを抱えて生きているのである。
実は、そうした問題は既に第一次世界大戦の頃からあらわれ始めていた。
第一次世界大戦は近代的化学兵器が次々と開発・投入される化学戦の様相を呈していたため、ドイツの研究所にはヨーロッパ各地から俊英たちが集まっていた。今、我々が軍事研究を考えていく場合の雛型は第一次世界大戦の中で成立したのである。
今からおよそ100年前、第一次世界大戦末期の1917年に敗色濃厚となったドイツで、社会学者マックス=ヴェーバーは「職業としての学問」と題する講演を行った。ヴェーバーはその講演の前半部分で、大学という組織の中で、研究者はどのような社会的条件のもとで、いわば一人の人間として生計を営んでいくことができるのかについて、かなり詳しく議論をしている。ヴェーバーがこの講演で、研究者の生計や就職にかんする問題をあえて具体的に述べたのは、学問が国家に動員される時代にあって、いかにして学問に忠実な研究者として生きていけるのかという危機意識があったからだろうと思う。
チューリングの悲劇が伝える教訓
世間や政治家の中には「軍事研究に手を染めても別に構わないではないか。何が問題なのか」と簡単に言う人がいる。しかし、仮に情報戦にかかわるような最先端の軍事研究に個人や研究機関が手を染めた場合には、その研究成果は軍事機密ゆえに発表できなくなってしまうことを考えてみてほしい。学者(科学者)のキャリアアップには、論文にせよ、あるいは共同研究の発表にせよ、一定の「業績」が求められる。しかし、軍事研究はそれを「業績」として発表できない。若手の研究者を集めて、防衛省なり、あるいは国なりの外部資金で共同研究をした場合に、若手研究者たちは、その後、研究者としてのキャリアを絶たれてしまうこともありえないわけではない。
軍事研究は当然のことながら、国家の機密事項にかかわってくるので、かかわった研究者の行動範囲が制限され、場合によっては言動が監視の対象となる。仮にその人物がかかわった研究の内容が国として数十年の単位で封印しておくべき問題であるならば、その研究者は生涯、口を閉ざしたままでいなければならない。ここで思い起こされるのはチューリングの悲劇である。
第二次世界大戦中のイギリスの政府暗号学校に、アラン=チューリング(1912―54年)という天才数学者がいた。コンピュータの基礎的な考え方をつくった人物としても知られている。チューリングは、第二次世界大戦中、ドイツ軍の暗号「エニグマ」を解読するという功績を挙げる。イギリスはこのエニグマの解読で、ナチス・ドイツの裏をかくことができた。
その一方で、戦後の1952年、プライベートなことでチューリングが同性愛者であることが発覚すると、当時のイギリスでは同性愛は違法とされていたため彼は逮捕され、政府機関での研究を続けられなくなった。2年後の1954年、チューリングは失意の中で自殺を遂げる(享年41歳)。イギリス政府はチューリングの戦時中の業績を、彼の死後も長く秘匿し、彼の公的な名誉回復は正式には2013年のエリザベス女王による恩赦を待たなければならなかった。
軍事研究に絡む限り、こうした機密保護の問題は今後も出てくるだろう。国家からすればそれは当然のことである。しかし、それでは軍事研究に携わる若手研究者の将来を国は保障できるのだろうか。一度そのプロジェクトに入ったならば、その研究者がその後、自由な研究者として大学に戻るなり、あるいは科学技術について市民に啓蒙活動をするなりしたら、場合によっては監視対象になる可能性が高いのではないか。
現在、工学系や理化学系から、日本学術会議の軍事研究抑制の姿勢を批判している人たちが出てきて、「学術会議は学問の自由を阻害している」と主張しているようだ。こうした言説は、とりわけ自然科学系の20代から30代の、一番働き盛りである若手研究者たちのキャリアパスのことをまったく考慮していないと思う。デュアルユースで「民間と軍事部門とを自由に行ったり来たりできる」かのように楽天的に考えている人たちは、チューリングの悲劇をどう考えているのだろうか。
国家・市場・科学技術
次に、第二の論点を考えてみよう。科学技術を社会の中にどう接合させるかが、コロナの時代を生きている我々が今、問われていることではないか。社会の根幹にあるものはやはり生活世界だ。学問の自由というものも、その視点から考えていかなければいけない。
生活世界とは、私たちの日常生活の感覚や経験、そこから生まれるコモンセンス、こうしたいわば普通に生きている人たちの相互行為から成り立っている世界のことである。私たちの生活上のモラルやコミュニケーション、ひいては社会も、この生活世界から生まれ、科学技術もその社会の上に成り立っている。
科学技術と同様に、生活世界を土台として成立しながら、生活世界から遊離しているものとして、国家と市場(マーケット)がある。国家と市場と科学技術、この三者は、私たちの生活世界を基盤としながら、そこから独立したシステムのように屹立している。
そして、現代の科学技術は、チューリングの悲劇の例で見たように、ともすれば国家に動員されるし、産業界の技術開発を通して市場の影響を受ける。つまり、私たちの生活世界から乖離した国家・市場・科学技術という三つのシステムが絡み合って、逆に社会に影響を及ぼしているのが現状である。
例えばグローバル化した株式市場は、私たちの生活世界における素朴な売買のイメージから遠く離れて、一般の人々にとってはなかなか理解しがたい、金融や証券のエキスパートによって営まれる一つのシステムとして動いている。ウォール街などでは既にAIを用いた超高速演算による、超人的なスピードでの株取引等が行われている。このように普通の人はもちろん、おそらくは市場で株取引をしている投資家たちにも実はよくわからないシステムが、私たちの生活世界を支配している。これはハーバーマス的に言えば、「システムによる生活世界の植民地化」である。本質的な問題はやはりそこにある。
国家と市場と科学技術は、自己組織的なシステムとなって、私たちが生きている社会の根幹をなす生活世界と乖離しているのである。学問の自由という時に、自分たちの行為をいかにして生活世界の中に接合させて、それを日常のコミュニケーションのあり方とどう接合させていくのかが、非常に大きな課題である。
例えば哲学者E・フッサールは、第二次世界大戦前に執筆した『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(原著1936―38年)で、科学が人間の理性から乖離してしまったことを学問の危機ととらえ、生活世界を科学の根源的な地盤として位置づけることで、人間の理性と科学を接合しようとした。フッサールは自らの構想した現象学こそ、それを可能にするという目論見を持っていた。結局、その見通しは実現しなかったが、やはり科学技術の営みを生活世界の中に接合させなければいけないという危機意識はよくわかる。
福島第一原発の事故の時も、原子力あるいは放射能とは何なのかということについて、専門家と一般の人々との認識が大きく乖離してしまった。実際に福島の汚染された区域で暮らしている女性たちにインタビューすると、自分の子どもが今後、放射能によって大変な目に遭うのではないかと心配していた。ところが専門家の一部は「自然界の中にも多くの放射性物質があるのに、そんなに恐れているのはバカバカしい」として、一般の人々の不安に応えようとしなかった。
原発事故のような、高度な科学を応用したテクノロジーによって生まれる深刻な事故に対して、一般の人々はどう対応したらよいのか。そこにはやはり専門家集団と普通の人々との間を繋げる媒介項(メディア)がなければいけないだろう。科学者集団と一般の人々との間を媒介する科学ジャーナリズムが発達していれば、科学技術を社会や生活世界に近づけてくれるはずなのだが、残念ながら現状はそうなっていない。
科学はニュートラルなものではない
今や我々は、「科学はニュートラルな道具」であり、ゆえに「科学技術のもたらす影響はその使い方次第」であって「科学そのものに責任はない」、というような理解はもうやめるべきではないか。現代の科学研究は、その規模が大きくなればなるほど、国家や市場、産業界の動向と深く結びついた開発プロジェクトとなっている。もはや科学はまったくニュートラルなもの、中立的なものではない。
原子力の研究者で小出裕章氏という人物がいる。小出氏は研究の過程で原子力の危険性を認識し、原発の廃絶のための研究に転じていった。ただし、そのために小出氏は、大学内での地位としては最後まで助教のままに留まり、ついに定年を迎えることになった。小出氏は、原子力研究を行ったがゆえにわかった危険性に向き合い、それを科学的にきちんと処理していくために、原発をスクラップにするための科学研究、いわば「反科学的な科学研究」に取り組んだのである。そこには、「原子力の研究はいったい誰のためのものなのか?」という問いがあったことだろう。
同様のことは、原子力についてだけでなく、広く自然科学系の学問、生命科学においても起こり得る可能性がある。「学問の自由」はもちろん大切なことだが、その自由の中で、研究者個人のボン=サンス(bon sens)、すなわち良識というものがやはり問われてくると思う。科学は善なるものだと妄信して「進歩を止めるな!」とばかりに新たな研究に邁進していくだけではなく、時には科学技術が社会にどのような影響を与えていくのかを社会的に議論し、そのリスクなどを皆が理解した上で、研究を進めるかどうか決めていくことが必要である。
もちろん、科学技術は日進月歩であるため、科学研究の最前線と一般の人々の理解との間にはギャップが生じるだろう。そのギャップを埋めていくうえで、実は人文社会科学系の知識が重要になる。人文社会科学系に属する科学史や科学社会学、生命倫理や技術倫理といった分野には、科学の最新研究やプロジェクトからは距離を取り、対象化してその危険性や問題点について批判的に検討する知の蓄積があるからだ。
一般的に言うと、原子力問題に見られるように、科学史の研究者と、原子力開発のフロントにいる研究者とでは、原発に対する考え方がかなり違う。それは、前者の場合はやはり社会や人々の日常生活に科学技術がどうかかわってくるのかということを、問題意識として常に抱えているからだ。日本学術会議も、いわゆる文理融合型の組織である以上、国の政策に提言をするという役割を果たす機能と資格は充分にあるはずだ。
人文知が果たす役割
今回、任命拒否をされた6人の人々は全員が人文社会系の研究者だった。これは、憲法や宗教や政治思想、あるいは行政法、歴史や国家やナショナリズム、こうした私たちの生きる社会にかかわる専門領域の人たちが、特に排除されたということになる。彼らが、様々な政府の法案に対して批判的であったことが拒絶理由として推測されているが、やはりここには、人文社会系軽視の姿勢があらわれているのではないか。
科学技術はあたかも、我々にとってはなかなか理解しがたい専門家の間でだけ共有された一つのシステムのように動いている。しかし、例えば生命科学の中では、万能細胞や新型コロナウイルスのワクチンの安全性など、私たちの価値観や健康、そして生死に直接的にかかわってくる問題がある。だから今必要なことは、そうしたことについて、科学者も一人の市民として、一人の生活世界の生活者として、専門知識のない普通の人にも理解できる言葉で議論に加わることだ。その議論の輪に生命科学の専門家はもちろん、生命倫理や哲学の専門家や、いろいろな人々が参画していく。こういう、市民に開かれた形での知のアリーナをつくっていく必要があるのではないか。
具体例をあげよう。2011年の福島原発事故のあと、ドイツのメルケル首相は自国の原発を止めて脱原発へとエネルギー政策を転換した。その際、メルケル首相は、専門家集団の意見を聞くだけではなく、非専門家の会議である「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」を組織して、その意見を取り入れている。この倫理委員会には宗教者や社会学者、哲学者ら、人文社会系の知識人・研究者が加わり、原発の専門家とは別の角度から安全性について議論したという。これに比して、日本はあまりにも人文社会系の「知」と「教養」というものを軽視している。
日本学術会議には幸いにして、第一部会として人文社会系の研究者が加わっている。だからもう少し人文社会系と自然科学系とがコミュニケーションを密にして、プロジェクト単位で動いていく科学研究のあり方について、その問題点を検討・指摘していくことも必要なのではないか。つまり、プロジェクトとしての科学研究をメタレベルで研究する、いわば「研究の研究」のような試みが必要だ。それができるのが人文社会系の知であろう。
今回の出来事をバネにして、かえって人文知の意義や役割へと再び目が向けられ、日本学術会議がより一般の人々へと開かれた組織へと生まれ変わることを、私は願ってやまない。
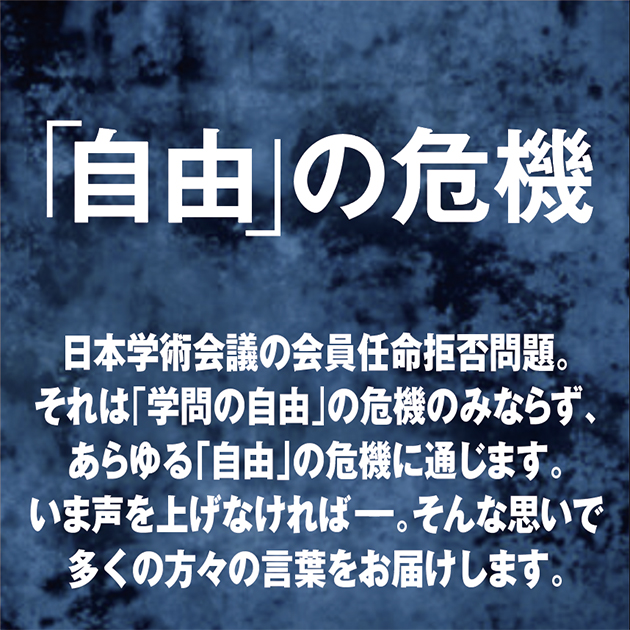
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。


 姜尚中
姜尚中










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


