
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第9回 苫野一徳 「自由な社会」を先に進める
これまで、日本学術会議の問題を発端として、「学問の自由」「大学の自由」「表現の自由」など、さまざまな自由について考えてきました。今回は、そもそも「自由」とはいかなる性質のものであり、現代日本で生きるわれわれにとってどのような意味を持った概念なのか、哲学者の苫野一徳さんに論じていただきます。
苫野さんによれば、自由とは「人間にとって最上の価値」であるとのことですが、なぜそう言うことができるのでしょうか。そして、私たちは「自由」に対してどう向き合って生きればよいのでしょうか。「自由」という概念の真の価値を問い直した上で、これからの社会の指針を示そうとした、とても刺激的な論考です。
「自由」は人間にとって最上の価値である
近代ヨーロッパの哲学者たちは、長く、「自由」を人間における最上の価値だと考えてきた。1万年以上もの間、「万人の万人に対する戦争」(トマス・ホッブズ)や、過酷な「支配―被支配社会」の中で生きるしかなかった人類にとって、生命の安全は言うまでもなく、個人の尊厳、すなわち生き方や思想信条の「自由」は、何としてもつかみ取りたいものだったのだ。
しかしいま、政治的自由も生き方の自由も、当時とは比較にならないほど手にしたわたしたちは、いつしか「自由」の価値をさほど自覚的には感じなくなってしまった。むしろわたしたちは、現代社会において「自由であることの苦しみ」(アクセル・ホネット)にさえ苛まれていると言っていい。
「どのように生きてもあなたの自由だ」と言われる。しかしだからこそ、わたしたちは、ではどう生きればよいのか悩み迷うことになる。そればかりではない。苛烈な自由競争社会の中で、わたしたちの多くは、むしろ「自由」の中に投げ入れられることの苦しみを味わっている。成功も失敗も、あなたの「自由」な生き方の結果である。多くの人が、そんな自己責任を突きつけてくる社会の中で生きることを余儀なくされている。
「自由」への道は、長いトンネルのようだ。トンネルの先と手前とでは、見える景色が全く違う。
いまだ政治的「自由」さえ手にしていない社会においては、人びとは生き方の「自由」を希求している。
他方、すでに「自由」を手に入れた多くの先進国の人びとが抱えているのは、むしろ「自由であることの苦しみ」だ。「自由」であるからこそ感じる不自由、これが、現代のわたしたちに「自由」の価値を見失わせる最大の理由になっているのだ。
しかしいまこそ、わたしは改めて言いたいと思う。
「自由」は人間における最上の価値である。
以下ではそのことを論証したいと思うが、もしこのことが忘れられてしまったとしたら、わたしたちの「自由」は、薄皮が一枚一枚剥がされていくように、気がつけばほとんどなくなってしまっていたということにもなりかねない。
本ウェブ企画の発端となった、日本学術会議の新会員6名の任命拒否問題について、当初、菅義偉首相はあれほどの騒ぎになることを予想していただろうか。もし想像していなかったとすれば、その背景には、「学問の自由」を、ひいては「自由」を軽視する世間の空気を、いくらか感じ取っていたこともあるのではないか。
杞憂であることを願うが、もし、社会の中にそのような「自由」軽視の空気が少しでもあったとしたなら、わたしたちは改めて、なぜ「自由」こそが人間における最上の価値であるのか、明らかにしなければならない。
人間的欲望の本質は「自由」である
人類の数万年におよぶ戦争の歴史は、つまるところ「自由」をめぐる戦いである。
そう言ったのは、19世紀ドイツの哲学者G.W.F.ヘーゲルである。
飢えや渇き、恐怖、自尊心、信仰など、戦争が起こる理由はむろんさまざまにある。しかしその最も根本には、わたしたち人類の「生きたいように生きたい」という「自由」への欲望がある。そうヘーゲルは喝破した。
だからこそ、人類はこれまで、戦争に敗れて支配されたり奴隷にされたりしても、長い目で見れば必ず「自由」のために戦ってきたのだ。そのことで、たとえ命を失うことがあったとしても。そしてそれゆえにこそ、人類はこれまで、何万年にもわたって戦争をなくすことができずにきたのだ。
この「自由をめぐる戦争」を、わたしたちはどうすれば終わらせることができるだろうか?
これは哲学における最も重要な問いの一つであったが、長い思想のリレーの末に見出されたその“答え”については、後で論じることにしたいと思う。
その前に、ここではまず、「自由」こそが人間にとっての最上の価値であるという、先に述べたテーゼについて明らかにしておこう。
なぜ、わたしたちはそのように言い切ることができるのだろうか?
これについても、ヘーゲルのすぐれた洞察がある。
ヘーゲルは、人間精神の本質、言い換えれば人間的欲望の本質は「自由」であることを、きわめて鮮やかに描いて見せた。その論旨を、わたしなりに簡明に言い直すと次のようになる。
まず、わたしたちはさまざまな欲望を持ち、それを自覚している存在である。
動物も、むろん欲望(本能)を持ってはいるだろうが、それを十分自覚しているようには見えない。彼らはおそらく、かなりの程度、その欲望(本能)のままに生きているだけだ。
しかし人間は、複数の複雑な欲望を持ち、しかもそれを自覚している存在である。少なくとも、自らの欲望を自覚しうる存在である。
それはつまり、わたしたちはこの欲望それ自体によって、つねに規定され——制限され——それゆえたえず何らかの不自由を自覚しているということである。
愛されたい、裕福になりたい、名声を得たい、認められたい、幸せになりたい……こうした人間的欲望は、わたしたちに否応なく“不自由”感を味わわせる。愛されたい、でも愛されない。認められたい、でも認められない……。わたしたちは、自らが欲望(を自覚した)存在であるがゆえにこそ、つねにすでに不自由を感じずにはいられないのだ。
さらに言えば、これら複数の欲望は、しばしば互いに衝突し合う。人に好かれたい、でも自分を曲げたくはない。裕福になりたい、でも努力はしたくない……。複数性を持つ人間的欲望は、まさにそれ自体が、わたしたちを規定する——制限する——決定的な規定性なのである。
したがってヘーゲルは言う。このように、わたしたちが欲望存在であるというそのことのゆえに、わたしたちは必ず「自由」を欲するのだと。これら諸欲望を、達成するにせよ、あるいはなだめるにせよ、わたしたちは何らかの形で「自由」になりたいと必ず欲しているのだと。わたしたちが欲望存在であるというそのこと自体が、人間的欲望の本質が「自由」であることを意味しているのだ。
では「自由」とはいったい何か?
これまでの考察から、「自由」の本質を次のように言うことができるであろう。すなわち、わたしたちを規定する——制限する——欲望を自覚しつつも、なおこの規定性(制限・限界)を何らかの仕方で克服し、そこから解放され、できるだけ納得して、さらにできるなら満足して、生きたいように生きられること、と。ヘーゲルの言葉を借りつつ概念化するなら、「諸規定性における選択・決定可能性の感度」。これが「自由」の本質なのだ。あるいは、20世紀の哲学者ハンナ・アーレントの秀逸な言い方を借りて、「自由」は「我欲する」と「我なしうる」との一致の感度が訪れる時、あるいはその可能性の感度が訪れる時に確信するものであると言ってもいいだろう。
さて、ここで注意が必要なのは、いまいみじくも「感度」という言葉を使ったように、「自由」の本質は「感度」(感じることとその度合い)であって「状態」ではないということだ。わたしたちは、どのような「状態」が自由な「状態」であるかを一意的に決定することはできない。何をもって自由な状態とするかは、結局のところ人それぞれであるからだ。
裕福になったことで自由になったと思う人もいれば、裕福になったからこそ不自由になったと思う人もいるだろう。「職業選択の自由」があるから自由になれたと思う人もいれば、そのために、先述したように、どう生きればよいか分からないといった不自由を感じる人もいる。
つまりわたしたちは、何らかのあらかじめ決められた「自由な状態」に置かれた時ではなく、「ああ、いま自分は自由だ」という感度を得られている時にそれを「自由」であると確信するのだ。そしてその感度の本質こそ、「諸規定性における選択・決定可能性の感度」、換言すれば、「我欲する」と「我なしうる」の一致、あるいは一致の可能性の感度なのである。
以上を要するに、わたしたちはこう言ってしまってよいだろう。
人間的欲望はさまざまにある。愛されたい欲、自己実現欲、権力欲、幸福欲……。欲望の“形態”は、このように無数にある。しかしわたしたちは、これら諸形態すべてを貫く欲望の本質を、「自由」への欲望と言ってよいのだと。これらさまざまな形態を取る諸欲望の規定性を乗り越えることで、わたしたちは絶えず「自由」の感度を欲しているのだと。
以上が、人間的欲望の本質は「自由」であるということの意味である。
だれもが「自由」を欲する。人間にとって最上の価値は、まさに「自由」なのである。
「自由の相互承認」の原理
さて、ではこの最上の価値である「自由」を、わたしたちはどうすれば現実のものとすることができるだろうか。
ヘーゲルは言う。「生きたいように生きたい」という「自由」への欲望を抱えたわたしたちの前には、絶えず「他者」が立ちはだかっている。この「他者」は、わたしたちの「自由」を妨げる一つの決定的な「規定性」である。それゆえわたしたちは、自らの「自由」を実現するために、この他者からの「承認」を何らかの形で求めるほかないのだと。
歴史的に見れば、それはまず「承認のための生死を賭した戦い」の形を取るとヘーゲルは言う。
この戦いを通して、人類は主人と奴隷に分かれることになる。しかし先述した通り、たとえ命を失うことがあったとしても、これまで人類は、「自由」を奪われたならその「自由」を奪い返すために必ず戦ってきた。そしてそのために、人類は長らく戦争をなくすことができずにきたのだ。
ではわたしたちは、どうすれば「承認のための戦い」を終わらせ、自らの「自由」を十全に確保することができるだろうか?
その考え方は一つしかない。そうヘーゲルは言う。お互いがお互いに対等に「自由」な存在であることを認め合い、そのことを根本ルールとした社会を作ること。すなわち、「自由の相互承認」に基づく社会を築くことによって。
もしもわたしたちが、「自由」に、そして平和に生きたいと願うならば、その限りにおいて、わたしたちは「自由の相互承認」を根本ルールとした社会を作るほかに道はないのだ。
「社会契約」と「一般意志」
以上が、ヘーゲルや、その前世代の哲学者ジャン=ジャック・ルソーなどが、文字通り命がけで見出した「自由な社会」の根本原理である。
ちなみに、ルソーの唱えた「社会契約」とは、「自由」を求める人類が、社会の中にあってなお、「みんながみんなの中で自由になるための契約」のことである。その契約の内容は、ルソーによれば、この社会を「一般意志」、すなわち「みんなの意志を持ち寄って見出されたみんなの利益になる合意」にのみ基づいて作っていくこととなる。
これはヘーゲルの「自由の相互承認」の原理といささかも異なるものではない。近代ヨーロッパの哲学者たちは、長い戦争の歴史の果てに、わたしたちが「自由」で平和に生きられるためには、まずはお互いを対等に「自由」な存在として承認し合い、その上で、互いの「自由」を調整しながら社会を作っていくほかに道はないことを見出したのだ。
以上から、わたしは改めて、「自由」は人間にとっての最上の価値であり、この価値を守るためには、「自由の相互承認」の原理に基づく「自由な社会」をめざし続けるほかに道はないことを主張したい。逆に言えば、もしも人間における「自由」の価値を軽んじることができるとするなら、それを試みる者は、以上の理路を根本からひっくり返すことができるのでなければならない。つまり、人間は「生きたいように生きたい」などとは欲していないということ、したがって、「自由の相互承認」の社会など必要ないことを。
念のため言っておくと、もし「だれかに支配されて生きたい」と思う人がいたとしても、それは人間的欲望の本質が「自由」であることの反証にはならない。なぜならその人は、そのような仕方で「生きたいように生きたい」と欲しているからだ。一見不自由な“状態”においてこそ、「自由」の“感度”を得られるものと考えているからだ。
しかしそのような支配―被支配社会が、本当にわたしたちが「自由」の感度を獲得しうる社会であるのかどうか、わたしたちは歴史をよく振り返って考える必要があるだろう。
それは支配者にとっても同様である。ルソーは『社会契約論』で、一見絶対的な支配者に見える王も、(裏切りの不安や権力簒奪の恐れなど)じつは全くもって「自由」ではないことを強調した。ヘーゲルも、主人と奴隷の関係を描く中で、主人もまた、じつは奴隷の「承認」がなければ主人たり得ないことを克明に描き出している。
わたしたちが「自由」に生きられるためには、その相互承認の社会を築くほかに、やはり道はないはずなのだ。
「自由な社会」の駆動力としての「学問の自由」
さて、しかし冒頭で論じたように、今日、わたしたちの多くは「自由であることの苦しみ」に苛まれている。
「自由競争」の社会においては、人生における成功も失敗も、その人の「自由」な生き方の結果、つまり自己責任とされてしまいがちである。それゆえに、いま、人びとの間には「自由」の価値への疑念がいくらか渦巻いているようにも見える。
しかし、本来批判されるべきは、「自由」の価値それ自体ではなく、人びとの「自由」を奪うこの苛烈な自由競争社会のあり方であるはずなのだ。
民主主義の危機が叫ばれて久しいが、特に経済的不平等に対する不満がピークに達した時、人びとは、不満の矛先を見つけようと排外主義に陥ったり、それらの問題を一挙に解決してくれる、アーレントの言葉を借りれば“強い男”を求めてしまったりする傾向がある。「自由であることの苦しみ」の中で生きるくらいであれば、何もかもだれかに決めてもらいたい。支配してもらいたい。むしろ支配社会の方が楽なのではないか。わたしたちは時に、そう思ってしまうことがある。21世紀の「自由からの逃走」(エーリッヒ・フロム)が、今日、そこかしこから噴き出そうとしているように見える。
しかし、政治的自由も生き方の自由も、言論の自由も学問の自由も、職業選択の自由も幸福を追求する自由もない、そんな絶対支配の社会に戻ることを、本当に欲する人などはたしているだろうか。
問題は、「自由な社会」の理念の中にあるのではない。この「自由な社会」の中で、多くの人が、いまなお、失敗したら二度と復活できないとか、貧困の連鎖などのためにそもそも「自由」に生きるためのスタートラインに立てないとかいった理由で、いまだ十分「自由」に生きられていないことにあるのだ。つまりわたしたちがめざすべきは、「自由」への疑念を抱いたり、あるいはこれに代わる理念を見出そうとあがいたりすることではなく、ルソーやヘーゲルらが構想した「自由の相互承認」の社会を先に進めることのほかにないのだ。
そうした「自由な社会」を作り出すには、各人がその意志を言論によって表明し続けるほかにない。またそのための学知を、互いに練り上げ合っていくほかにない。
先述したように、「一般意志」とは「みんなの意志を持ち寄って見出された、みんなの利益になる合意」である。この「一般意志」は、どこかにあらかじめ転がっているようなものではなく、多種多様な関心を持った人びとが、互いに対話を重ねることで見出し合っていく、あるいは作り出し合っていくべきものである。
その際、学問はきわめて重要な役割を果たすことができる。市民としての学者たちは、「自由な社会」を、このような仕方でもっと先へ進めようではないかと、“みんなの利益”になるアイデアをつねにテーブルの上に置き続けることができるし、またその必要がある。そしてそれを、人びとの吟味へとさらし、対話や議論を重ねながら、いっそう強靭なアイデアへと鍛え上げていく必要があるのだ。
たとえばそれは、貧困の連鎖を断ち切るための制度の構想でもあるだろう。マイノリティの権利を、制度的にもっと保障するための研究もそうだろう。苛烈なグローバル資本主義をコントロールするための経済学の構想や、国際的な新たな「社会契約」のアイデアを考えることもそうだろう。
わたし自身は、哲学者であると同時に教育学者として、「自由の相互承認」の社会を最も底で支えるものとしての公教育のあり方を、具体的にさまざまな形で提案している。
たとえば、「自分たちの社会は自分たちで作る」が市民社会の鉄則である以上、学校もまた、子どもたちが、単に決められた(時に理不尽な)校則に従うだけでなく、「自分たちの学校は自分たちで作る」をたっぷりと経験できる場である必要がある。では、そのような学校づくりを、全国で実際に進めていくことはいかに可能か。そのための研究や実践を、多くの人たちと行っている。
また、近代の学校は、子どもたちが校種で分けられ、学年で分けられ、さらには障害のあるなしで分けられるなど、同質性の高いコミュニティとして設計されてきたが、そのことが、異なる他者との相互理解や相互承認の機会を著しく妨げてしまっている現状がある。これを、年齢や世代、障害のあるなしや文化の違いなどを超えて、多様性がもっとごちゃまぜになって学び合える「ごちゃまぜのラーニングセンター」へと発展させていくことはできないか。またそれはいかに可能か。そうした研究や実践も、さまざまな形で進めている。
これらはあくまでも一例だが、学問は、そして学者は、こうした研究や実践を通して、ささやかではあったとしても、「自由の相互承認」の実質化に貢献することができるし、またそうである必要がある。
「学問の自由」は、そのためにも、決して手放すことのできない市民の自由である。「自由な社会」をさらに成熟させていくための、それは最も重要な駆動力の一つなのである。
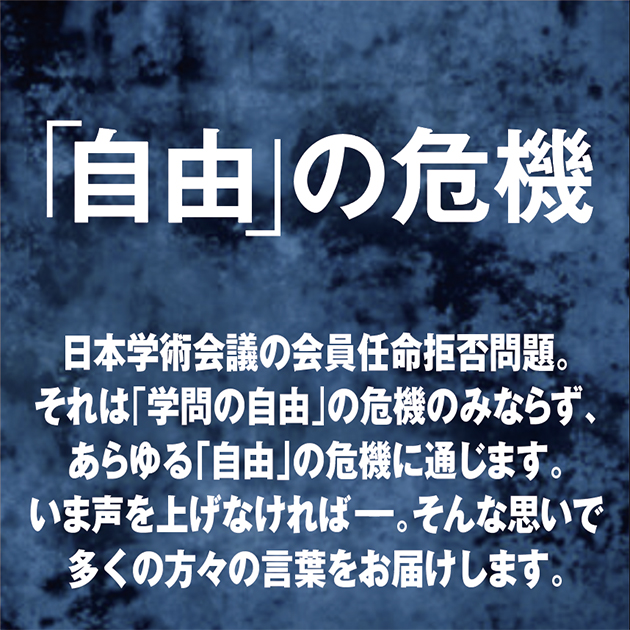
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

哲学者・教育学者。熊本大学教育学部准教授。1980年兵庫県生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。2020年4月に開校予定の軽井沢風越学園では理事を務める。著書に『どのような教育が「よい」教育か』(講談社選書メチエ)、『教育の力』(講談社現代新書)、『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『勉強するのは何のため?』(日本評論社)、『はじめての哲学的思考』(ちくまプリマ―新書)、『ほんとうの道徳』(トランスビュー)、『愛』(講談社現代新書)など多数。


 苫野一徳
苫野一徳









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

