メタ教養とは何か
「自分には教養がない」という宣言を、日常でよく耳にしたり目にしたりする気がします。わたしだけでしょうか。では、そこで教養と呼ばれているものが何なのかと尋ねてみると、あんまりスッキリした答えは得られません。これまでの経験から、なんとなくちゃんと答えられないのではないか、と思って、「自分には教養がない」という発言についてはだいたい無視をしている気がします。考えてみれば、教養とは何かという説明は、それ自体が教養に属している可能性があります。つまり「教養がない」と思っている人は、「教養が何であるか」も知らないのです。でも、もちろん、教養とは、教養が何であるかを知っていることに尽きるわけではありません。教養とは何かを知らなくても、教養と呼ばれうるものを既に身につけているのに、「自分には教養がない」と判断してしまっているのかもしれないのです。
この連載は「メタ教養」と題しました。メタとは、ギリシャ語で「上に」「後ろに」という意味の言葉に由来する接頭辞です。メタ認知や形而上学(メタフィジクス)で使われているあの「メタ」です。「メタ教養」という言葉でわたしが指し示そうとしているのは、教養を身につけている人も、身につけている自信のない人も、「教養」というものを別の視点から眺めてみることはできるのではないか、という提案です。
なぜ「家政学」か
第1回となる今回のテーマは「家政学」です。ここで、家政学のことを少しでも知っている人は「あれ?」と思うでしょう。家政学とは、料理、洗濯、裁縫、家事、病人の世話、衛生など、文字通り「家」のことを運用するための知識を体系化した学問です。
「教養」という言葉にはどこか浮世離れした、抽象的で高踏的なイメージがあるでしょう。
それに対して、「家政学」は先ほど書いたとおり、暮らしに密着した、いわば「足もと」の学問です。いっけんかけ離れているように思えるからこそ、「教養」を捉え直す「メタ教養」のためには、「家政学」から始めるのが適切なのではないか、というのが、この連載の第1回のテーマを「家政学」にした理由です。
「教養」の一種として最近もてはやされているリベラルアーツ(自由技芸)にも含まれず、学問の分野としても物理学や経済学などの分野ほどの知名度はなく、現在は軽んじられていると言ってもおそらく言い過ぎにはならない「家政学」。「教養」という、敷居の高そうなテーマをさらに上から眺める、あるいはその背後にあるものをうかがう、もしくは一歩横に離れてみるというときに、本当は身近なはずなのに、なぜか軽んじられている「家政学」の概念を経由してみよう、というのがここでわたしが試みようとしていることです。
「家政学」の概要を捉えるための入り口として、村田沙耶香と村上春樹の作品から、似たようなシチュエーションの筈でありながら、かなり異なった印象を与える場面を挙げてみようと思います。
村田沙耶香『コンビニ人間』の「餌」と、と村上春樹『1Q84』の「料理」
私は皿を出してテーブルに並べた。茹でた野菜に醤油をかけたものと、炊いた米だ。
白羽さんは顔をしかめた。
「これは何ですか?」
「大根と、もやしと、じゃがいもと、お米です」
(『コンビニ人間 』 村田 沙耶香、文春文庫)
村田沙耶香の小説『コンビニ人間』は、主人公である30代の古倉と、古倉の仕事先で出会った白羽とが一緒に暮らしはじめる過程を描く作品です。こう紹介してしまうと、コンビニ人間』がロマンティックな恋愛物語であり、その先には「幸せな家庭生活」が待っている、と勘違いさせてしまうかもしれません。『コンビニ人間』は、そんな作品ではありません。
古倉は子供の頃から、周囲の人たちの感情や心理をうまく理解することができません。喧嘩をしている同級生たちを「止めて」と言われ、スコップを持ち出して同級生を殴ってしまう、そんな常識のない人物として描かれています。古倉の家族は古倉を心配して、なんとか世の中と折り合いをつけられるように努力します。その結果か、古倉は周囲の人たちの話し方を真似ることで社会集団に馴染むことを覚えます。
古倉は10代後半からコンビニエンスストアで働き始めました。目標やルールが定まっており、バイト仲間や店長とのコミュニケーションは話し方を真似ることで乗り切り、店内の品出しや来店客への声かけなどを学習したことで、古倉は「コンビニ人間」として「生まれ直した」ような感覚を得ます。
古倉のバイト先に新人として応募してきた白羽は勤務態度が悪く、バイト仲間から嫌われています。来店客へのストーカー行為を問題視されて解雇された白羽でしたが、懲りずに客を待ち伏せしているところを古倉に発見されてしまいます。男女が同じ部屋で暮らしていると家族も職場の人も喜ぶということを学習した古倉は、白羽を自宅に住まわせることにします。さきほど引用したやりとりは、古倉が「餌」と呼ぶ食べ物を白羽に提供する場面です。醤油で味付けをしただけの「餌」は、自分が食い繋ぎ、「コンビニ人間」として十分に機能するのに必要な栄養を摂取するために作られており、少しも美味しそうには描かれません。
『コンビニ人間』では、古倉が仕事を「こなす」ことに感じる喜び以外のすべてを、まるで他人のように突き放して考えているのが特徴です。自分が日々、口にする食べ物ですら、その味わいに関心がない。恋愛も将来もどうでもいい。コンビニエンスストアの忙しなさのなかで、求められる仕事に自分を最適化することだけに集中していく。この作品は古倉の仕事への過集中をなかばグロテスクに描き出しつつ、同時に古倉が仕事のリズムに同期していく快感を的確に描き出しています。
『コンビニ人間』の古倉と鮮やかに対照をなすのは、村上春樹の『1Q84』の主人公である天吾が料理をする場面です。
天吾は『マザーズ・リトル・ヘルパー』や『レディ・ジェーン』を聴きながら、ハムときのことブラウン・ライスを使ってピラフを作り、豆腐とわかめの味噌汁を作った。カリフラワーを茹で、作り置きのカレー・ソースをかけた。いんげんとタマネギの野菜サラダも作った。料理を作ることは天吾には苦痛ではない。
( 『1Q84』村上春樹、新潮文庫 )
『コンビニ人間』の古倉と同様に30代の天吾は、古倉と同様にやはり結婚はしていません。古倉とは異なり、天吾は子供の頃から周囲とうまくやってきました。父親がNHKの集金係だったことを除けば、他の子供より好感を持たれる人物として生きてきたように描かれています。天吾以上に特殊な家庭環境にあった子供として描かれるのが、『1Q84』のヒロインである青豆です。とある宗教の熱心な信者の家庭に生まれた青豆は、NHKの集金に連れ出される天吾と同じように、布教のために親に連れられて家々をまわっているのでした。
子供時代に心を通わせた天吾と青豆は、それぞれに大人になり、互いに惹かれ合い、神秘的な仕方で再会します。
さきほど引用した箇所は、まだ青豆と再会する前の天吾が、青豆を探している途中、自宅にやってきた美少女「ふかえり」に手料理を振る舞う場面です。
いかにも村上春樹らしい、適度にディテールを記述しつつ、それが本当に美味しいのかどうかわからない、しかしきっと美味しいのだろうけれど、その美味しさに過剰に耽溺することのない場面です。
村上春樹の作品の登場人物たちは、『コンビニ人間』の古倉がコンビニエンスストアで働くときのように、組織の仕組みが求めることに自分を最適化し、流れるように仕事をこなしています。村上春樹作品においては、セックスから殺人まで、さまざまなことがスムーズに行われます。
料理を上手につくることも同じです。仕事に自分を最適化するという方向性では『コンビニ人間』の古倉と『1Q84』の登場人物は似ていますが、『コンビニ人間』の古倉は最適化の快楽に溺れているようにも見えます。
『コンビニ人間』で、仕事に自分を最適化していく古倉は、結婚や出産、正社員としての就職のような、世の中が成人した女性に押し付けてくるさまざまなステップを無視し続けます。白羽との同棲は、恋愛も結婚もしない古倉が、周囲からの厄介な追及を避けるために自ら提案したものでした。古倉と白羽の間には、ロマンティックな恋愛感情もエロティックな接触もありません。これは村上春樹の『1Q84』で天吾と青豆のあいだが「子どもの頃から互いを思っている」ような関係であり、終盤になって妊娠した青豆が天吾の子をみごもったと確信するのと、やはり対照的です。
『コンビニ人間』の古倉と、『1Q84』の登場人物たちは、それぞれシステムに馴染む快楽を知っている点では似ているのですが、古倉がコンビニエンスストアにだけ入れ込んでおり、他の社会的システムを拒絶しているのに対して、『1Q84』の登場人物たちは、古倉が拒絶したようなさまざまなシステムにも多様に適応している点が異なります。
村上春樹の作品と、村田沙耶香の作品、それぞれの登場人物をもっとも激しく対照的にしているのは、天吾たちが「世の中の仕組み」をある程度は把握しており、そのなかで歯車のようになる自分をメタに認識しているのに対して、古倉にはそのような意識がなさそうなところです。古倉がコンビニエンスストアの店員として、世界の部品として生まれ直した、と感じる場面はあります。しかしそれは、世界のことを対象として把握する主体を持たないまま、単なる部品としてうまく嵌り込める場所を得たに過ぎません。
家政学と経済学を繋ぐ「コンビニ」が省略し、不可視化するもの
『コンビニ人間』の舞台である、コンビニエンスストアという業態は、20世紀前半にアメリカで始まりました。それが日本に導入されたのは1970年代です。近代の消費生活を支えた百貨店の時代に始まり、食材から日用品まで揃うスーパーマーケットが普及する時代になり、さらにそのスーパーマーケットの大手資本が各地の中小商店をネットワーク化し、コンビニエンスストア各社が鎬を削る時代へ。この変遷は、消費のあり方の変化であるだけでなく、流通の最適化の過程でもありました。現代日本ではコンビニエンスストアは多くの消費者の生活インフラに近いものになっています。それと同時に、消費者に密着した販路となっているコンビニエンスストアは、総合商社と結びつき、全国の流通、また国際的な流通にも深く関わるようになりました。
コンビニエンスストアの店員は、規格化された製品を徹底して効率的に製造販売するというポスト・フォーディズム時代のテイラー主義的な働き方を代表するものだとも言えます。古倉の「世界の部品になることができた」という感覚は、高度消費社会のなかに居場所を見つけた、という意味ではしごく妥当なものなのです。
しかし、古倉にはコンビニエンスストアの経営史や労働者の社会的な位置づけのような巨視的な視点がありません。古倉が日々コンビニ店員として売っている商品がどのような流通経路を辿ってきたかも知りません。そのような巨視的な認知を持たなくても、店員を機能させられる、という仕組みが極めて現代的なのです。古倉を軽蔑している白羽はといえば、ネット起業のアイデアがあるとうそぶいており、なるほど古倉をバカにする程度の世界認識はあるようです。しかしその白羽にしても、自分のアイデアを実現するための資金集めをするような現実的な行動をする様子は描かれていません。
これに対して、『1Q84』で村上春樹が描く人物たちは、それぞれに世界の部品として居場所を得ながら、終始その立ち位置に自覚的な言動を続けています。日本にコンビニエンスストアの業態が導入されて普及していく時代である1970年代から1980年代にキャリアをスタートさせた村上春樹は、古倉が自分を部品として受け入れる「世界」を傍観者のように眺め、その「世界」の片隅に物語を紡いできました。
「世界」の仕組みを貨幣と商品と労働から分析して記述しようとした思想家は少なくありません。カール・マルクスはそのひとりです。マルクスの思想は20世紀には広く読まれました。教養として、エリート学生たちに共有されていたのです。村上春樹が学生時代を過ごした時代は、そのマルクス主義が教養としての権威を失墜させていく過程の時代でもあります。
村上春樹と同世代(1940年代後半生まれ)に上野千鶴子がいます。上野千鶴子は、マルクス主義が「教養」としての元気を失っていく時代にあって、マルクス主義がその理論から軽視していた「家事」をひとつの中心的な問題として焦点化しました。
『1Q84』に限らず、村上春樹作品の特徴になっている料理の描写、とりわけ男性主人公による料理の場面は「男性は家の外で仕事に励み、女性は家を守るべきだ」という旧来の考え方に対するささやかなアンチテーゼとして読めるものだったと考えることができるのです。そして、『コンビニ人間』の古倉が差し出す、およそ料理とは言えない、栄養を摂取するだけの「餌」は、上野千鶴子が焦点化しようとした「家事」の成れの果てだと言えるでしょう。
マルクスが構築しようとした「経済学」と、上野が注目した「家事」の間に、村田沙耶香の『コンビニ人間』と村上春樹の『1Q84』があるのです。
古倉と同居することになった白羽は「男性が狩りに出て、女性は家を守っていた」という先史時代の社会の仕組みが現代でも連綿と続けられている、と自説を語ります。白羽の世界観では、異物とみなされた存在は「ムラ」から排除されてしまいます。インターネットを使った事業でいつか大成功するとうそぶく白羽ですが、そのための具体的な行動はしていません。白羽自身もまた、彼が言うところの「ムラ」から疎外される異物なのです。大言壮語しながら自分を度外視した暴言を繰り返す白羽ですが、固定した性的役割をメンバーに強要する「ムラ」に居場所を持たない存在として消え去ってしまいたいというのが本心のようです。
ムラとオイコノミアと国家、ポリスと政治
「村」とも書かれる「ムラ」ですが、これはひとや家が集まり、暮らしが営まれる場所のことです。「村」のほかに「邑」という字があてられることもあります。「邑」は「ムラ」のほかに「くに」や「さと」、「みやこ」とも読まれます。
先史時代から人類は村落、村邑を形成し、暮らしてきました。そこに白羽の言うとおりの「しきたり」があったのかどうかはわかりません。しかし、何らかの掟があり、そこに住む者たちは、狩りをしたり、木の実を収集していたことでしょう。邑のうちいくつかは、やがて都市国家へと発展していきます。中国では実際、古代の都市国家も邑と呼ばれました。これは世界各地でみられる現象です。
古代ギリシャの都市国家はポリスと呼ばれました。そのポリスを複数の家の集合として捉えたのが、『家政論』を著したクセノフォンであり、そののちに『政治学』を書いたアリストテレスでした。アリストテレスのこの『政治学』には、国家を構成する家的共同体を論じる一節があります。ギリシャ語で「家」を意味するオイコスを論じるオイコノミコス(家政論)です。
科学思想史を専門とするカナダの哲学者マーガレット・シェイバスによれば、アリストテレス以降、オイコスを語源とするオイコノミア=エコノミーeconomyは、たとえば動物の生体の恒常性を論じる際にも使われていました。エコノミーとはまず、(「家」のように)境界で囲まれた領域内に、食事や家財のように限られた物資を分配する仕組みを指して使われていました。現在の経済学が成立するよりも前、エコノミーとは、たとえばキリスト教の神が創造した自然において、それを構成する諸要素がどのように分配されているのかを分析し記述するものを指していたのです。ここでは、神という家長が自然という「家」を采配しているという世界観がうかがえます。
オイコノミア、国家、惑星
アダム・スミスらによって近代的な経済学が成立してからも、ジョン・ラスキンのような思想家がオイコノミアの概念を重視して批判を展開しました。ラスキンはマルクスとほぼ同時代を生きた人物です。
ラスキンは、「19世紀の嵐雲」と題した講演で産業革命がもたらした自然破壊に警鐘を鳴らしました。マルクスが晩年、環境問題に関心を持っていたことは斎藤幸平『人新世の「資本論」』(集英社新書)でも詳しく論じられています。
オイコノミアをめぐる議論には大きく分けて3つのスケールがあります。ひとつは、家族または個人が営むパーソナルなスケール。ふたつめはそのパーソナルなスケールの集合としての共同体のスケール。3つめは、複数の共同体を内包する、もしくは複数の共同体のインフラ(基盤)になる環境のスケールです。それぞれのスケールに、取り組むべき課題があります。『コンビニ人間』や『1Q84』はもっぱらパーソナルなスケールを描いています。企業としてのコンビニエンスストアや、『1Q84』のラスト以降に天吾と青豆が運用していくであろう「家族」、あるいは古倉、白羽、天吾、青豆の家族たちは共同体のスケールに該当します。そして、コンビニエンスストア各社が互いに鎬を削り、その商品の材料を調達し流通させる世界はグローバルなスケールにあたります。
本連載では、この3つのスケールを行き来しながら、権威を失墜させた教養をメタに捉えなおしていきます。
参考文献
「コンビニエンス・ストアの経営史 ―― 日本におけるコンビニエンス・ストアの30年 ――」 川辺信雄、早稲田商学第400号、2004年
『人新世の経済思想史-生・自然・環境をめぐるポリティカル・エコノミー』桑田学、青土社、2023年
『政治学』アリストテレス、牛田徳子 訳、京都大学学術出版会、2001年
『オイコノミコス 家政について』クセノフォン、越前谷悦子 訳、リーベル出版、2010年
『家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平』上野千鶴子、岩波現代文庫、2009年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)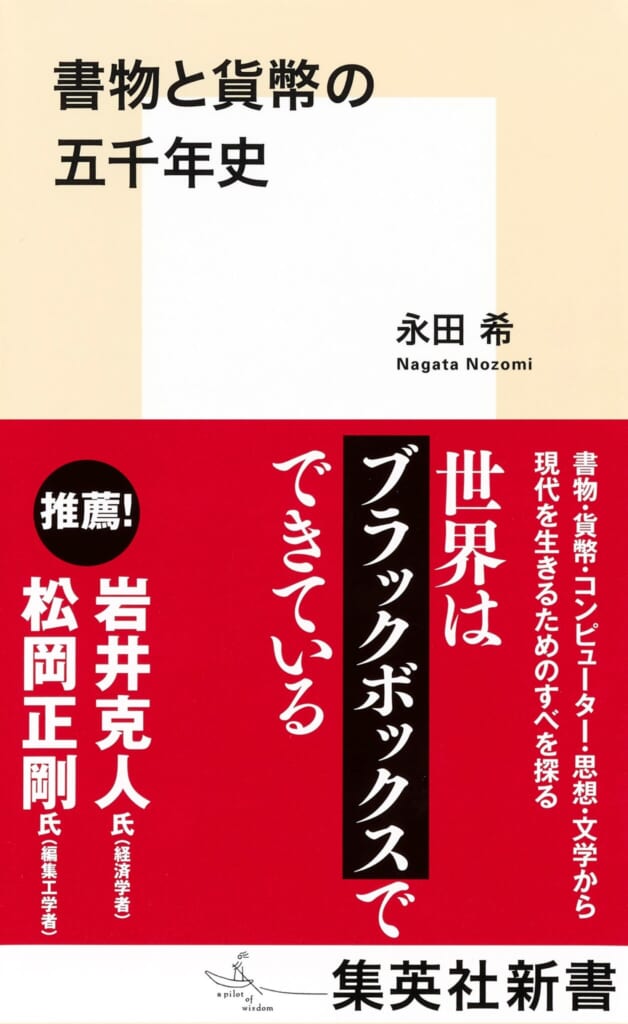










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

