歴史を学ぶこととは移動の経緯を知ること
これまで繰り返してきたように、「教養」とはその輪郭も本質もたいへんに捉えにくいものです。わたしは、直接「教養」を身につけることよりも、その裏側や上位から「教養」を捉える「メタ教養」にアプローチすることを提案しています。
メタ教養のためには、「パーソナル/共同体/環境」という3つのスケールを意識することを推奨しています。個人の、身の丈の、身の回りのスケールである「パーソナルのスケール」。オフィシャルな、複数人の関係する、社会的な「共同体のスケール」。そして、ヒトという種の枠を超え、空間的にも時間的にも巨視的(マクロ)な、あるいは個人の身体の身の丈よりもずっと微視的(ミクロ)な、「環境のスケール」。この3つのスケールです。
連載の第1回から第4回ではパーソナルなスケールとより強く結びついている家政学と、共同体のスケールに結びついた弁論術を主題にしました。第5回から第8回にかけては、環境のスケールに結びついたマクロなテーマを扱っていきます。前回は国家という大きな共同体を超える人類の規模で、その数を主軸に据える「人口論」を扱いました。今回は、人々の数ではなく、その内部での動きに注目します。すなわち、今回のテーマは「移動」です。
ヒトの移動に注目すればそれは移民論になり、ヒトのあいだでのモノの移動を追うならばそれは物流や流通を論じることになります。
歴史を学ぶということは、ヒトとモノの移動の経緯を知るということでもあるのです。国や地域の変化を辿る各国史や地域史というものは、ヒトやモノの移動を共同体のスケールでみたものです。そのなかで生きたヒトそれぞれの目線にたってそこからパーソナルなスケールでみれば個人史になります。たとえば『古代ローマ人の24時間 よみがえる帝都ローマの民衆生活』(アルベルト・アンジェラ、関口英子 訳、河出文庫、2012年)や『古代中国の24時間 秦漢時代の衣食住から性愛まで』(柿沼陽平、中公新書、2021年)、『古代ギリシア人の24時間 よみがえる栄光のアテネ』(フィリップ・マティザック、高畠純夫 監訳・解説、安原和見 訳、河出書房新社、2022年)は、パーソナルなスケールから歴史をみる試みだといえるでしょう。環境のスケールでみると、ヒトとモノの移動は数万年から数百万年の時間的なスパンをもち、大陸と大洋をまたぐ巨大な空間的な広がりをもった人類史や文化史になります。
環境のスケールで「移民」をみる
「移民」とひとくちに言っても、両親が国外から移住してきたという人や、親のどちらかだけが移民であるという人、また世代ごとに国を移動する人々、さらに一生のうちに複数の国を移動する人など、さまざまなタイプがあります。それだけではなく、自らの意志で移住をした人もいれば、出身国にとどまりたかったのに何らかの理由によりやむを得ず移住する人もいます。後者は難民と呼ばれることもあります。自らの意志かやむを得ずかも、一概には区別できませんから、たとえば「より良い生活を求めて」自らの意志で国を出る人も、もともと住んでいた国や地域の社会から多かれ少なかれ迫害を受けていたために生活が不自由だったと考えることができます。また、社会情勢はその国や地域だけで決まるものではありません。戦争や飢饉、さまざまな災害によってやむなく難民となる人々もたくさんいるのです。
また、移住先の国や地域でどのように「受け入れ」がされるかによっても移民は区別されます。世界人口が増加している現代、移民はいわば世界から溢れ出ているようにみなされ、温情的に「受け入れる」かどうかが議論されていますが、今後、各国で人口減少とそれにともなう経済の停滞や衰退が懸念されるようになるならば、市場を活性化してくれる移民は各国が競って「引き入れ」を企図するだろうという考えもあります。
「受け入れ」か「引き入れ」かという移民先の共同体が、移民をどうみるかという問題は、移民ひとりひとりを公的にどのように承認するか、彼らをどう呼ぶかにもかかわります。
いっけん明快なのが正規移民と非正規移民という分け方です。移住先で公的に登録された登録移民と、登録を避ける非登録移民とも呼ばれることがあります。さらには、法的な課題をクリアした合法移民と、そうではない非合法移民という呼び方もありますが、これは生き方そのものである「移民」のあり方に非合法なものがあると考えることであり、研究者のなかで強く反発する人がいます。そしてこれらのような単純な二項対立は、たとえば正規の方法で入国したものの入国してから期限が切れてそのまま移住先に住み続ける人を、安易に「非正規移民」として分類してしまいます。また、このように概念の定義が難しく曖昧な状態では統計も取りづらいという問題もあります。
「移民」はふつう「国境を越える移住」を指しますが、住む場所をうつす「移住」は、とうぜん移民より多く行われています。EUの例を考えれば分かりやすいように、国境を越えるかどうかは曖昧です。また、当初は単なる移住だった場合、つまり国のなかの国境を越えない移住だったものが、事後的に移住元から移住先のあいだに国境が引かれ、結果的に移民になってしまう場合もあります。なお、世代を超えて今後の世界人口を考えるときに重要になる「都市化」つまり都市部の人口増加は、田舎から都市部への人口集中のことです。これは田舎からの人口流出です。土地の値段が高く、物価も高い都市部では子供を持つことは基本的にコストが高いので、田舎にいるときよりも子育てをする意欲は下がります。単なる出稼ぎとして都市化を捉えると見えにくいですが、田舎から多くの人口が都市に移動してきていると考えると、人々の移動と将来的な人口動態の関係が浮かび上がってきます。
なお、移民は英語でimmigration、移住はemigrationといいます。ふたつのことばに共通する「migrate」は移動を意味しています。「em-」という接頭辞は「外へ」「出ていく」ニュアンスのある「ex-」に、「im-」という接頭辞は「内へ」「入っていく」ニュアンスのある「in-」に、それぞれ由来していると考えられます。移動(migrate)は、ある場所を出て(ex-、em-)、別の場所へと入っていく(in-、im-)ことです。3つのスケールに当てはめて考えるなら、もともと住んでいた場所を出て(ex-、em-)いくパーソナルなスケールの「移住 emigration」、国境をまたいで別の国へと入って(in-、im-)いく共同体のスケールの「移民 immigration」、俯瞰的な環境のスケールでみれば彼らはただ「移動 migrate」しているだけ、ということになります。
人口と移民、都市化
都市に集中して移住してくるのは、その都市を含む国の内部に住む人たちだけではありません。都市に住むメリットはその国の住人だろうと、国境を越えて流入してくる移民であろうと基本的には同じだから当然です。したがって、都市の人口増加は国内移住だけでなく、移民によっても加速させられます。
近年、いわゆる先進国は一般的に人口増加のピークを過ぎ、人口が減少に向かい、かつ高齢化していくことが懸念されています。移民、とりわけ非先進国から先進国への人口流入は、人口問題を解決してくれるものだと考える人がいます。人口問題を解決するどころか、人口増加によって国を乗っ取るのではないかと懸念する人がいるほどです。実際には移民の数は基本的に先住者たちと比較してあまり多くなく、乗っ取りの懸念は概して杞憂と言わざるを得ません。それだけではなく、先進国の都市部に移住した人は、移住先にある「少子化が当たり前」の考え方に影響されることになります。
労働や消費をして市場経済を活性化するという意味で移民はありがたい存在であり、またアメリカの例を見る限り、イノベーションにも移民がポジティブな役割を果たしていると言えそうですが、人口問題の解決に移民が直接的に果たす役割を考えるときには少し立ち止まって考えてみる必要があるといえるでしょう。
もっとも、市場経済が停滞すれば自治体の税収も下がり福利厚生の質も低下するため、子育てをしたいと思う人が減ってしまうと考えられます。移民によって経済が活性化するならば、これと逆の効果を期待することができる、とはいえるでしょう。
奴隷の世界史
15世紀から19世紀まで続いた大西洋奴隷貿易によって、1000万人を超えるアフリカ人が奴隷としてアメリカ大陸へと移動させられました。先述のとおり、ここ200年ほどの人口爆発が起きるよりも前の世界人口は多くても10億人なので、実に世界人口の1%が人格を否定され売買されていたということです。アメリカ合衆国は独立後も奴隷制を維持しましたが、南北戦争で北軍が勝利したことで奴隷制は廃止されることになります。もともと「奴隷」にあたる英語はスラブ人に由来するように、ユーラシア大陸の内部でも行われていました。戦争の捕虜や債務不履行により、人格と自由を制限され、動産として一生もしくは一定の期間だけ、労働に就く人々が奴隷とみなされました。
スウェーデンやベルギーの現在の人口がおよそ1000万人です。そもそも「移民の国」と言われるアメリカ合衆国は、独立以前の植民地時代からずっと移民を集め続けてきました。「ネイティブ・アメリカン」とかつて呼ばれていたアパッチやナバホといった部族はアメリカ先住民とも呼ばれますが、彼らも太古にアメリカ大陸に到達した人々の子孫であるという意味では移民の子孫です。
3つのT(Transportation、Tourism、Telecommunication)
移民という現象は人類史に常に関係のあることですが、とりわけ近代以降、次の「3つのT」といわれる要素によって加速されてきました。3つのTとはすなわち、トランスポーテーション(Transportation 輸送)/ツーリズム(Tourism 観光)/テレコミュニケーション(Telecommunication 通信)です。
産業革命によって生み出された蒸気機関は鉄道の敷設や道路の舗装を促進し、大量の移動を可能にしました。蒸気機関にとって代わる電力はそれをさらに加速します。モノの大量移動に並行して増大するのが人間の移動です。住処を移す移住とまではいかずとも、足を踏み入れたことのない土地への観光によって国と国、地域と地域、文明と文明、それぞれを隔てる距離を超えて、それぞれの住民が互いに関心を持ち、旅行をするようになります。観光ビザで入国し、そのまま移民となる人も現れます。そして、移民として住み着くわけでもなく、かといって観光客でもないようなグレーな人たちが、いわゆる正規の業者ではないインフォーマルな次元でビジネスを展開する場合もあります。
離れた場所で暮らすことは、それだけで魅力をもちます。旅先の様子をSNSにあげることは、単なる思い出の保存ではなく、友人や知人への「見せびらかし」の側面を持っています。インフォーマルなビジネスにおいて、その「見せびらかし」は遠隔地にいる自分をいわば粉飾し、事業への投資を促します。ひとつひとつは非正規であり大した規模ではないインフォーマル経済は、この「見せびらかし」によって移動先での「成功」のイメージを醸成していくという意味で無視できません。身体の移動を伴わず、限られた情報だけが流通する「通信」という要素は、拡大を続ける移民という現象にとって、見落とされがちですがとても大きな役割をになっているのです。
そして通信に着目するとき、輸送における鉄道の敷設や道路の舗装、あるいは航路の開発にあたるのが、通信インフラの整備です。通信デバイスの普及、コミュニケーションサービスの充実、基地局の開設、海底ケーブルの開通や通信衛星によるインターネットインフラによって遠隔地の人々は互いに結びつき、身体の移動につながる段階を準備していきます。
先に書いた通り、移民という言葉は基本的には国境を越えて移動する人々を指します。国境とは、文字通り国と国を隔てる境界であり、この境界を越えるかどうかで移民と移住者は区別されることになります。この限りで、移民とは共同体のスケールでみたときに現れてくる集団だといえるでしょう。パーソナルなスケールでみるとき、移民のひとりひとりは自分たちのことを特別に移民であるとは考えないはずです。自分たちが移民であるという認識を移民たちが持っているとすれば、それは国境を越えてきたという共同体のスケールの事情を強く自覚しているからです。
では、環境のスケールでみるとき、移民はどのような現象として現れてくるでしょうか。環境のスケールで移民をみるとき、パーソナルなスケールでみたときとは別の意味で、移民か移民でないかは問題ではなくなります。国境という共同体のスケールの線引きは無効化され、国内国外を問わない、人々の移動が浮かび上がってくることになります。災害や気候変動による分かりやすい環境スケールの現象にとどまらず、恐慌のような世界的な経済変動、戦争のような複数の共同体をまたぐ現象によって、人々の大きな移動は生み出されます。それまで住んでいた土地から人々は押し出され、そして移民を引き込める共同体が、移民たちを獲得していくことになります。
人類史と「移動」
「移動」に注目するとき、人類史の最初期に起きた「出アフリカ」という事件が目につきます。アフリカ大陸の片隅に発生した人類の祖先は、数百万年のあいだに大きく分けて2回、アフリカ大陸から地球上の各地へと拡散していったと考えられています。200万年前に始まったと考えられている1回目の「出アフリカ」、これは「古い出アフリカ」といわれますが、このときはホモ・エレクトスと呼ばれる古人類がユーラシア大陸まで到達しました。2回目の「出アフリカ」、これは「新しい出アフリカ」といわれるものですが、これが約5万年前に始まったと考えられています。新しい出アフリカで、人類はユーラシア大陸だけではなく、世界中に広まりました。紀元前6世紀になると、かつてメソポタミア文明が栄えた中央アジアに広大なアケメネス朝ペルシアの帝国が登場します。この国の大王となったダレイオス1世は、帝国を東西に結ぶ「王の道」と呼ばれる、よく整備された公道を建設します。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、この「王の道」での旅は当時最も速く移動できたと書いています。「王の道」は全長約2500キロメートルにおよびます。この長さは、ユーラシア大陸の東西の長さ(12000キロメートル以上)の約5分の1の長さです。
古代ギリシアの諸国を連合した軍を率いてアケメネス朝を滅ぼしたアレクサンダー大王は、中央アジアを横断してインドにまで版図を広げ、当時の世界最大の帝国を築きました。このとき、アレクサンダー大王の軍勢がインドの西側まで攻め上ることができたのは、アケメネス朝が「王の道」を整備していたからだといえます。
アケメネス朝も、何もない場所を「王の道」にしたわけではありません。「出アフリカ」以降、何千年、何万年と祖先たちが行き交い、踏み固めた道を整備し直したのが「王の道」だったはずです。このように、太古から人々が行き交い、踏み固められた土地が時の権力者たちによって「道」として利用されてきました。要所要所は宿場町となり、定期的に市が開かれていたでしょう。中央アジアからユーラシア大陸の東側(東アジア)までを結ぶ道のネットワークは総称してシルクロードと呼ばれます。シルクロードといっても、一本の幹線道路のようなものがあるのではなく、広大な領域を張り巡らされたネットワークが形成されていました。
シルクロードにはオアシスルート、草原の道、そして海の道の3つの主な経路があったといわれますが、これも3つしか道がなかったというわけではなく、実際にはこれらの3つの経路を繋ぐ無数の拠点が存在していました。
シルクロードを経由してヨーロッパにもたらされていた物品のなかで有名なものはスパイスでしょう。アジアで生産されたクローブや胡椒などの香辛料は、陸路や海路を経由してヨーロッパに到達します。その都度、地域の権力者たちが関税をとりたてるためにその価格は移動距離とともに高騰していきます。大航海時代と呼ばれる時代にヨーロッパ人が未開拓の航路に挑んだのには、この多重関税を回避して、産地から直接仕入れをしたいという願望がありました。
グローバリゼーション(グローバル化)がいつ始まったのかについてはさまざまな立場での議論がありますが、『物流の世界史 グローバル化の主役は、どのように「モノ」から「情報」になったのか?』(ダイヤモンド社、2022年)の著者マルク・レヴィンソンは、世界は太古から高度にグローバル化されていたとも言えるが、それが加速しはじめたのは19世紀からだと書いています。レヴィンソンの見立てでは、グローバル化をこの時代に促進したのは産業資本主義です。産業資本主義とは、工場のような生産設備を資本とする体制で、産業革命によって急速に発展しました。世界中にある植民地を結ぶ通商網が張り巡らされ、各地で独自に発展していた経済圏は欧米を中心とする体制へと改変されていきます。
ヒトの移動(移住、移民、旅行)と、モノの移動(流通)にならんで重要な情報の移動はこの産業資本主義の時代にやはりグローバル化を加速させます。大洋の海底に敷設される海底ケーブルは19世紀に初めて開通し、金融のグローバル化を可能にしました。
ヒト、モノ、そして情報がグローバルなネットワークを構成し、一部に集積(ハブ)しつつ、その他の領域に対して格差を生じさせているのです。格差はパーソナルなスケールではあまり実感されません。共同体のスケールでみれば、地域間や社会集団間の不均衡としてあらわれてきます。しかしその総体を眺めるためには個々の共同体のスケールを包括する環境のスケールで眺める必要があります。かつて東西を結んでいたシルクロードがネットワークであったように、しかしそれよりももっと広大な領域にわたり、かつ高速で緊密にヒト・モノ・情報がやりとりされるネットワークが現代の「環境」を構成しているからです。
(次回へ続く)
『我々はどこから来て、今どこにいるのか? アングロサクソンがなぜ覇権を握ったか』(上・下)エマニュエル・トッド、堀茂樹 訳、文藝春秋、2022年
『2050年 世界人口大減少』ジョン・イビットソン、ダリル・ブリッカー、倉田幸信 訳、文藝春秋、2020年
『エクソダス 移民は世界をどう変えつつあるか』ポール・コリアー、松本裕 訳、みすず書房、2019年
『移民をどう考えるか グローバルに学ぶ入門書』カリド・コーザー、平井和也 訳、勁草書房、2021年
『移民の経済学 雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか』友原章典、中公新書、2020年
『物流の世界史 グローバル化の主役は、どのように「モノ」から「情報」になったのか?』マルク・レヴィンソン、田辺希久子 訳、ダイヤモンド社、2022年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)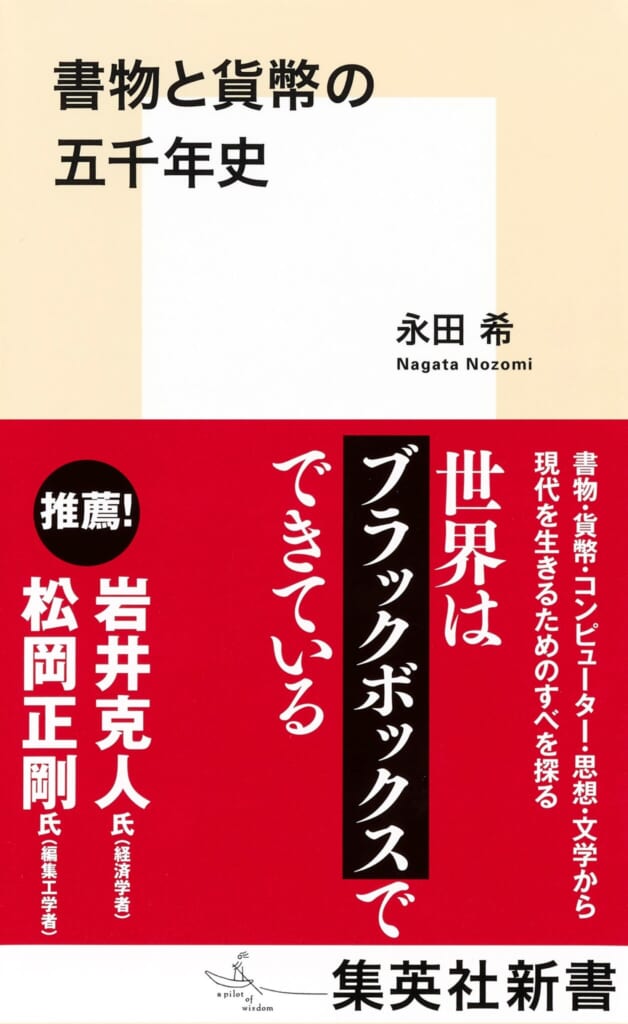










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

