「気候」と3つのスケール
今回、テーマになるのは「気候」です。第5回から第7回は「環境のスケール」で見ることを主軸に書いてきましたが、気候はまさに環境のトピックといえるでしょう。
なお、パーソナルなスケールでいえば、日々の気候はまずメンタルに影響を与えます。どれくらい、また、どのように、その日その日の天候が個人のメンタルに影響を与えるのかには個人差があります。しかし、ある日が晴れていればその日は気分良く過ごせるし、曇っていたり雨模様だったりすれば気持ちは塞ぎがちにります。晴れの日が続けばその期間は調子良く感じられ、雨の日が続けばずっと不調のような気持ちになるでしょう。気圧の昇降で気分障害を感じる人もいます。もっとも、晴れの日があまりにも長く続けば旱魃となり、農作物の生産が減少したり、ダムが渇水して生活用水が足りなくなったりします。逆に雨の日が続けば、日照量の不足でやはり農作物は減り、今度はダムの決壊や河川の氾濫の懸念が生じます。これは共同体のスケールの事象だといえるでしょう。
近年、話題になることが増えた異常な気象は、海面温度の上昇による大気の状態の不安定化が原因だと言われています。これは複数の国を覆う大きな気候団に関わる現象であり、ここまで考えるとあきらかに環境のスケールの話になります。
今回はまず、気候について考えるための基本的な要素(気候因子)、そしてこれらの気候因子の相互作用によってある気候が発生する仕組み(気候システム)を概説し、さまざまな気候変動がこれまでの人類史に及ぼしてきた影響を振り返ります。そして現在、広く議論されている現代的な気候変動の問題として、気候変動を考慮した地政学ともいえる気候安全保障を紹介します。最後には、大富豪として知られるジェフ・ベゾスやビル・ゲイツらが出資していることでも耳目を集めている、地球温暖化問題に取り組むテクノロジーや企業、いわゆるクライメートテック(グリーンテック)を紹介し、彼らが今後どのような役割をになっていくのかを考えます。
気候因子と気候システム 気候とは何か
気候、と一口に言っても、天気、天候、気象などとの違いがよくわからない、というのが普通の感覚ではないでしょうか。これらの語はいずれも大気の状態を指すのですが、そうなると今度は「大気」とは何なのか、そしてその「大気の状態」とは何なのか、ということになります。大気とは、いま読者の皆さんが吸って吐いている空気を含み、読者の皆さんが住んでいる家や国を覆い、地球の地表を包んでいる空気の層のことです。全体として大気圏と呼ばれるこの層は、ご存じの通り、全体で均一な層ではありません。地域によって大気の状態はムラがあり、しかも刻一刻と変化しています。
大気の状態の変化、つまり、大気圏内の各領域の、そのときどきの状態の偏りは何によって生じているのでしょうか。大気の状態や、そのときどきの天候は、温度や湿度、風向きなどで示されます。ある地域のある時点の大気の状態、つまり天候を決めているのは何なのか、これは実は難しい問題です。大気の状態を左右する要因は複数あり、その要因のうちの一部だけを見ても、その結果である天候を特定することができないからです。これが、天気予報がなかなか当たらず、外れる場合がある理由です。
気候因子には、気温、降水量、風、緯度、海抜高度、水陸の分布、海岸からの距離(隔海度)、地形、海流、植生などがあります。これらは地球上の要素ですが、地球の熱は太陽からもたらされているので、地球外の、つまり太陽の状態も気候因子になります。これらの気候因子が互いに結びつき、影響し合うことで気候が生み出されるわけです。このような仕組みは気候システムと呼ばれます。この連載の第5回で取り上げた小氷期、中でも有名なマウンダー極小期などは、太陽の黒点と呼ばれる部分がほぼ消滅し、太陽から地球へのエネルギー供給が減少したことで地球上の気候が寒冷化したと考えられている時期です。
環境のスケールで見れば、地球外にある太陽からの影響、地球の惑星規模の気候システムが気候を左右しています。気候システムは、太陽の活動を含むさまざまな気候因子によって構成されています。共同体のスケールで見れば、各国、各地域の社会は、たとえば寒冷化にともなう不作によって不安定化する場合があります。パーソナルなスケールで見れば、日々の天気の変化にはあまり気がつかないかもしれませんが、社会が不安定になれば、移住を余儀なくされたり、日射量の低下や栄養の欠乏で免疫力が低下して疫病の流行によって健康を害する可能性があります。
人類史と気候
気候の変動と人類史の関わりについて紹介するにあたって、もっとも大きなものは、今から1万数千年前まで続いていたと考えられるヤンガードリアスイベントと呼ばれる寒冷期と、農耕の開始の関係でしょう。数万年以上前に生まれたと考えられるホモ・サピエンスは、それまでは定住をせず狩猟採集生活をしていたと考えられています。人口が増えてそれまでの狩猟採集では食糧をまかないきれなくなり農耕を始めるようになったところにヤンガードリアスイベントが発生し、農耕生活への移行が加速したことで、それ以降の人類が農耕を中心とするようになったという説のほか、仮説は複数あります。1万年を超える時間を遡るため、決定的な証拠が見つからないのは仕方ありませんが、ユーラシア大陸でも、南北アメリカ大陸でも、ほぼ同時多発的に農耕への定着が認められており、全地球的、少なくとも半球規模で共通する原因があったのではないかと考えられています。
農耕の開始と定着は、人類という大きな共同体にかかわる出来事ですが、もう少し細かい国家や文明のようなサイズの共同体のスケールにも影響を与えていたと考えられています。
紀元前二千年紀に勃興したと考えられているエジプト古王朝は、ナイル河の氾濫を天文学と暦により把握することで食糧生産を安定化していたと考えられています。しかしそのナイル河の水位が低下したまま上がらない時期が到来します。これは地球の公転軌道の変化による寒冷化とそれにともなう大気の乾燥が影響していると言われています。この時期は、エジプトにかぎらず、世界四大文明として挙げられるメソポタミア文明やインダス文明、黄河文明でも異常気象を示す記録があり、それぞれの衰退期と重なっています。
また太陽活動が減少した紀元前千年頃には、やはり寒冷化が生じています。この時期は、考古学的に青銅器時代から鉄器時代への移行期と考えられています。「海の民」と呼ばれる集団によって地中海の東岸ではミケーネ王国やヒッタイト王国が略奪にさらされ衰退します。気候変動は緯度によって発生時期がズレることが少なくなく、数百年後、北部のヨーロッパ地域で悪天候が続くようになります。この時期は、スカンジナビア半島近辺に住んでいたゲルマン民族が南下を開始します。このゲルマン民族の移動により、ケルト民族が押し出されるかたちになり、ヨーロッパ各地へと拡散していきました。
気候変動と安全保障
20世紀後半に、ユーラシア大陸のロシアを中心とするソビエト連邦と、アメリカ大陸のアメリカ合衆国とが対立した米ソ冷戦は、それぞれが核兵器を開発して互いを牽制し合う時代になりました。第7回で紹介した地政学で見たとき、ある種の均衡といえる状態の時代です。この時代、地政学に代わる言葉として使われていたのが「安全保障」です。
20世紀末のソ連崩壊以後、安全保障は軍事的なニュアンスを色濃く帯びていくようになります。そもそも安全保障は国(国家、国民)の安全を保障するものでしたが、近年はそのような共同体のスケールを中心とするのではなく、人間の安全保障という、よりパーソナルなスケールを重視するものへとシフトしています。国や軍事の枠組みを離れて安全保障について考えるときに、浮上してくるのが環境です。まさに「環境安全保障」として最初に注目されたのは資源でした。
以前にも触れた通り、世界人口は今後は増加の勢いを失い、やがて減少する可能性が高いと考えられています。このことにより、古典的なマルサス主義は退けられますが、しかし局所的に人口が集中している地域では、食糧やエネルギー、生活必需品が行き渡らなくなる事態が考えられます。生命の維持に必要な物資の不足は、そのまま「人間の安全保障」が保障しようとする「人間の安全」を文字通り危機に晒します。また、紛争も人間の安全をダイレクトに破壊します。20世紀には資源の安全保障が議論されていましたが、ここ20年は「気候安全保障」という言葉が使われるようになってきました。
さきほど瞥見したように、気候変動は人類史上さまざまな文明や国家の衰退や崩壊に影響したと考えられています。ピラミッドやスフィンクスを遺したエジプト古王朝や、高度に発達した天文学で知られるメソポタミア文明は、紀元前二千年紀代に発生した乾燥化の影響で衰退したと考えられています。この時期、いまの中国のある地域では、黄河流域に文明が築かれていましたが、低緯度にあって乾燥化したエジプトやメソポタミアとは違い、高緯度にあったために冷涼湿潤化し、洪水に襲われて衰退したと考えられています。海に近い地域が衰退したことで、より内陸にある長江流域に夏王朝が現れることになります。
王朝や文明の衰退は紀元後からも観測されます。中国では唐王朝が7世紀に成立し、9世紀に衰退(滅亡は907年)しました。現在のメキシコやグアテマラにあたる中央アメリカで紀元前から続いていたマヤ文明は、8世紀に絶頂期を迎え、9世紀から衰退しはじめます。太平洋の東西に位置する両地域で、盛衰がシンクロするように観測されるのは、当時の地球気候が8世紀に温暖化し豊富な農作物が人口増加を促すものの、寒冷で乾燥した気候になることで生じる旱魃が王朝の安定統治を脅かす、と考えられるのです。
もちろん、気候変動は社会の不安定化に直結するものではありません。気候変動などの環境要因が社会の変化に直結するという考え方は環境決定論と呼ばれます。人間はある程度の環境変化にはかなりの柔軟性をもって適応します。環境変動はむしろ、小さな紛争を減らすというデータもあります。これは、環境が変化して生活基盤が揺らいでいるときに、目先の紛争をしている場合ではない、ということで異なる集団が連帯するような場合です。
しかし、このような例は、目先の紛争を休止することで生活基盤を守れるような短期的な変動の場合の話であり、気候変動が長期化し、環境変化が生活基盤を破壊するほど長引くと、今度はかえって紛争に参加する心理的コストが下がるという説もあります。生活基盤を共同体がどの程度までまもるのか、という社会設計によって、似たような規模の環境変化にさらされた場合の行動が異なってくるのです。天災と人災が連動するのかしないのか、環境のスケールと、共同体のスケールと、パーソナルなスケールが重なるテーマです。
歴史上の事件ではなく、現代に目を向けてみるとどうでしょうか。アフリカ大陸のチャド湖は、世界的に巨大な内陸湖であり、ニジェールやナイジェリア、カメルーン、チャドの4カ国にまたがっています。「大きな水域」を意味するチャド湖は、チャド国の水産物の9割以上を供給していましたが、現在はかなりの部分を失い、これまでに2度も完全に干上がったことがあり、21世紀中に消滅してしまう可能性があるとすら言われています。チャド湖は、砂漠化の進行しているサハラ砂漠に近接しており、急激な縮小との関係が指摘されています。水は人々の生活や産業に欠かせない資源であり、チャド湖の縮小にともなって周辺地域の住民の生活水準は低下していると考えられます。生活基盤を失った住民の一部は、チャド湖に接している国のひとつであるナイジェリアの反政府組織ボコハラムに吸収され、ナイジェリアの治安を脅かす一因になっている可能性があるとも考えられています。
環境のスケールでの気候変動という現象が、各地域で暮らす個々人の生活を脅かし、共同体のスケールの安定性が危機に晒される、という各スケールの連動は、現代でも変わりません。むしろ、ここ200年間に加速している温暖化によって、今後ますます3つのスケールの現象は深く結びついていくと考えられます。
クライメートテックの活況
人々の生活のために気候システムを保全したり安定化させたい、という考えが気候安全保障です。気候安全保障の考え方は、各国の統治者たちや、市場の安定から利益を得る経済人たちの間に浸透しました。気候安全保障という用語が学術論文に頻出し始める2000年代後半、オバマ政権だったアメリカはグリーンニューディール政策を打ち出し、1500億ドルを再生可能エネルギーに投資しました。これにより再生可能エネルギー業界はにわかに活気付きますが、短期的に見ればこの施策はバブルを生み出しただけで、投資を受けた多くの事業は倒産しています。イーロン・マスクを現代随一の資産家に押し上げたテスラ社は、グリーンニューディールの投資を受けて成功した数少ない例として知られています。
テスラ社は、石油ではなく電池を搭載した電気自動車を発表し、自動運転機能などでも注目されています。しかしテスラ社は、石油から電気へ、という自動車の動力の転換だけを目指しているのではありません。炭素燃料を使うのは自動車だけでなく、火力発電でも同様です。自動車の動力を電気にしても、その電気が火力発電でつくられたものであれば、炭素排出量は削減されません。そのためテスラ社は太陽光発電の会社を子会社化し、連携しようとしています。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、それ自体が天候の影響を受けやすく、晴れた日や風の強い日には多く発電できるけれど、曇っていたり風がない日は発電できません。このように安定して発電ができないことは再生可能エネルギーの大きな問題のひとつです。テスラ社は、自動車を電化して販売する過程で電池を独自開発していますが、この電池の開発によって、安定供給されない電気を各家庭が蓄電して適宜利用するという仕組みを構想している可能性があります。これまでテスラ社の電気自動車は充電して走るだけでしたが、最近の発表によると、充電した自動車から家庭に電気を供給するという、文字通り「電池としての自動車」へのステップを進めていることが窺えます。
テスラ社は気候安全保障の枠組みのなかで活躍している企業群のなかの目立った稼ぎ頭です。しかし、マイクロソフトのビル・ゲイツ、Amazonのジェフ・ベゾス、中国アリババのジャック・マー、ソフトバンクの孫正義など、著名な億万長者たちが長期的な見通しのもと多額の出資をおこない、現在はグリーンニューディール以来となる活況がクライメートテック業界に訪れています。
人間とモノの移動(流通)ではなく、大気や海流などの、より環境的で見えづらい大きなモノの移動、それこそが気候ではないでしょうか。近代、人間とモノの移動は、自動車や鉄道によって加速し、量的にも爆発的に増大しました。その家族と爆発的な人口の増大は、石炭や石油などの化石燃料(炭素燃料)の大量使用に裏付けられており、これが莫大な温室効果ガスとなり、現在の温暖化を招いている、と考えられています。
かつてオバマ政権でエネルギー省科学次官を務めた経歴を持つ理論物理学者のスティーブン・E・クーニンは、『気候変動の真実』で、温暖化が人為的なものだという現在の主流の考え方に疑念を呈しています。
現在の地球上でさまざまな「異常気象」が観測されていることは、直観的に信じられることです。パーソナルなスケールで、まさに人々が体感していることです。そして、さきに触れた通り、人類は莫大な温室効果ガスを産業革命以来、大気中に排出し続けてきたことから、この気候変動や温暖化は人為的なものだと考えてしまうのも無理のないことだといえます。クーニンは、気温をはじめとするさまざまな観測データをコンピューターで処理する手法の開発にかなり早い段階からかかわっていた人物ですが、その経験から言って、人類が手に入れられるデータはあまりに少ないため、地球規模の気候システムを把握することができないと告白しています。つまり、現在の地球が本当に温暖化しているのかどうか、そして気候変動が起きているとして、その原因が人間の営みによるものなのか、科学では断言できない、というのです。それでも多くの科学者が何らかのデータを元にレポートや報道番組が作成され、その報道を受けた人々が選んだ政治家たちが政策を作っていくことになります。クーニンはこの主張をするたびに、既存のエネルギー企業の御用学者として振る舞っているという批判を受けたと書いています。しかし、クライメートテック業界への投資は石油メジャーのような既存のエネルギー産業からも多くの資金が流れています。逆に、クーニンの主張で彼が得ている利益は特にありません。むしろ損しかしていないでしょう。クーニンは「気候変動などは起きていない」と主張しているわけではありません。盛況なクライメートテック産業が虚業にすぎないと言うのではなく、その根拠になるデータの扱いについて倫理的な指摘をせざるを得なかったのです。
20世紀初頭、イギリスの数学者ルイス・リチャードソンは気象データを計算することで気象予測が可能になると考えました。当時の計算技術では気象は複雑すぎたため、リチャードソンの考え方は「リチャードソンの夢」として知られるようになります。のちにコンピューターが発達し、現在の気象予測はリチャードソンの考え方の延長に実現することになりました。
気象予測の実用化には、コンピューターという高性能な計算機のイノベーションが不可欠だったのです。気候変動とその人為性を疑うクーニンは、コンピューターを用いた気候データのモデル化に初期から携わっていた人物ですが、いまやその運用の仕方があまりに恣意的になっている、と批判しているのです。
パーソナルなスケールでは、気候は日々の天気(気象)としてしか経験されません。気温や湿度、降雨量などの数値化されたデータによって、気候は記録され共同体のスケールで扱えるようになります。「扱えるようになる」ことで、クライメートテックの無数の企業が生まれ、そこに投資がなされるわけです。しかし、データは飽くまでデータであり、気候そのものではありません。環境のスケールは、観測し記録することができ、予測を試みることはできるのですが、まだ正確な予測が可能になるほどのイノベーションはもたらされていないのかもしれません。
環境のスケール
文字通り「数えられるもの(可算的なもの)」である人口の爆発的な増大は、産業革命の時代に始まりました。現在の地球が温暖化しているとして、その気候変動が炭素資源の大量消費に由来しているのだとすれば、クライメートテックが向き合おうとしている状況は産業革命とともに始まっています。人とモノの「移動」は、自動車や鉄道という「イノベーション」によって加速され、それは産業革命の動力になりました。このことは、石炭や石油などの資源を奪い合う地政学、そして安全保障の問題になりました。
ここ数回の連載で扱ってきた、人口学、人間とモノの流通、地政学、そして今回の気候学は、既存のいわゆる「教養」に含められることのないものです。これらを新しい教養と呼んでもいいかもしれません。しかし、これらは単に「新しい」のではなく、既存の教養が無視していたものを扱うものです。それはなぜなのでしょうか。「メタ教養」は、教養そのものではなく、その背後や上部から教養を捉え直す試みです。なぜ既存の教養が、これらを無視していたのか、それは今後の模索のなかで追究されていくでしょう。
次回は逆に、教養(リベラルアーツ)の中核におかれていた「数学」を取り上げます。
参考文献
『気候安全保障の論理 気候変動の地政学リスク』 関山健、日経BP、2023年刊
『クライメートテック 新しい巨大経済圏のメカニズム』宮脇良二 、日経BP、2023年刊
『「人新世」の惑星政治学 ヒトだけを見れば済む時代の終焉』前田幸男、青土社、2023年刊
『気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか?』スティーブン・E・クーニン、 三木 俊哉 訳、日経BP、2022年刊
「宇宙気候学の現状と課題」草野完也
「アフリカにおける気候変動と紛争」華井和代
「気候変動から紛争への経路:アフリカ・サヘルを事例に」華井和代
「気候変動と文明の盛衰」小泉格

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)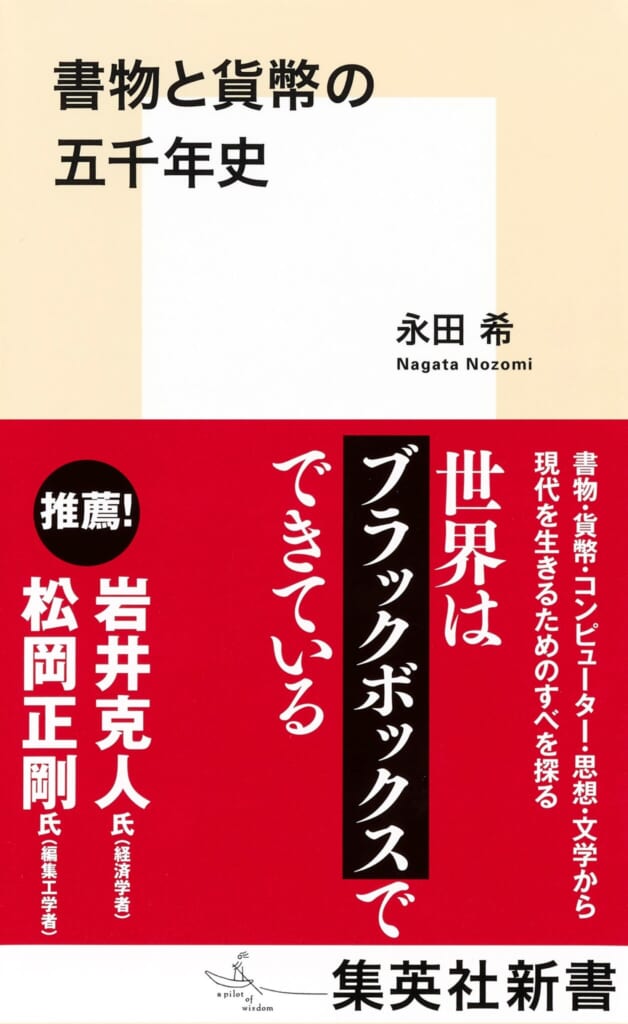










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

