レヴィ=ストロース以後の人類学 デスコラの存在論の四類型
人間が自然と対峙し、自然の脅威を分析し、それに対処する文化を育み、継承する。脅威となる自然を馴致する方法を体系化するのが人間の文明であり、文化や文明を持つことが、人間と自然とのあいだに一線を画すものだ、という考え方があります。この考え方はデカルト以来の西洋の文明観です。
西洋には「思索の体系」としての学問があり、非西洋はその体系から距離がある、つまり「より自然に近い」とみなされました。精神(思索)と、精神と対立するものとしての身体(自然)との二項対立による二元論がこの体系の基礎になっています。人類学は、思索の主体である精神が、非西洋の自然の事物を調査して収集し、学問の体系を発展させていくというプログラムだったのです。
しかし、非近代的な社会を未開とか野蛮とかと呼んでいたジェームズ・フレイザーですら、自分たちとは違う社会に固有の論理があったことを強調しました。西洋の自民族中心主義は相対化の契機も含んでいたのです。
レヴィ=ストロースは、未開とされた社会の、そのなかで暮らしている人々が自分でも気が付かない「構造」を指摘することで、社会のなかで暮らしている人々にとっての「見かけ」と、暮らしている人が自分では気が付かない不可視の「ルール」(構造)があるという立場を取りました。そしてこの「見かけ」と「ルール」の関係は、西洋近代社会にも再帰的に適用可能なのです。
フィリップ・デスコラの存在論の四類型とは、「文化の進化論」でいえば、呪術的な段階のアニミズムとトーテミズムから、近代合理主義を標榜する西洋のナチュラリズムへ、そして両者の中間にアナロジズムがある、という考え方です。デスコラはアニミズムからナチュラリズムへという「文化の進化論」を想定しつつ、四類型を四象限にまとめてみせています。
デスコラの四分類は簡単には理解できないうえに、そのまま採用できるような説得力があるものだ、とは俄に主張しづらいものです。しかし、これまで西洋近代を中心にして先端であると考えてきた従来の人類学の立場を、ナチュラリズムという存在論のいち類型に過ぎないと指摘したことは重要です。ナチュラリズムとは、デカルト的な精神(思索)の類似性を軽視し、逆に、デカルト的な意味での自然(身体)の類似性に注目するという考え方です。これは精神性を軽視する、いわゆる近代科学のことです。
西洋近代社会は単に合理的であるのではなく「心の類似性を軽視して、自然の類似性に着目する合理性」であるということになるからです。合理的であるとはどういうことか、という考え方をデスコラは相対化したのです。デスコラによれば、アニミズムはナチュラリズム(西洋近代)とは反対に、「心の類似性に注目し、自然の類似性は軽視する合理性」を持っているといえます。
アニミズムが文化という言葉を含んでいないのに対して、ナチュラリズムが自然(nature)いう言葉を含んでいるのは、類型を捉えるうえであまり適切ではないようにも思われますが、ともあれデスコラの理論はレヴィ=ストロース以降の、21世紀人類学を切り開いたのでした。
インゴルドとVDC
フランスの現代人類学を代表するのがフィリップ・デスコラだとすれば、デスコラとほぼ同年代でイギリスを拠点に活躍しているのがティム・インゴルドです。上述の通り、やや思弁に偏る傾向が否めないデスコラ流の現代人類学に対して、インゴルドの人類学は、ひとことでいえば「わかりやすい」のが特徴です。
そうはいっても、20世紀以前の人類学が西洋中心主義的であったことを自省し、西洋近代を相対化しようという姿勢はデスコラと共有しています。インゴルドは人類学を「世界に入っていき、人々とともにする哲学である」と定義していると語ります。
ここで「世界」「人々」「哲学」がいずれも人類学にとっては自民族の視点で語られてきたものである、と批判的にいうことは可能です。デスコラ式にいえば、「世界」も「人々」も「哲学」も、ナチュラリズムで捉えられたものでしかないのではないか、ということです。しかしその批判が妥当なものだとしても、インゴルドたち西洋人がわかりやすく人類学をやろうとすればそういうしかありません。
インゴルドは「世界に入っていき、人々とともに哲学をする」ために、相手の言ったことを真面目に受け取ることを重視します。この「真面目に受け取る」ということこそ、現代人類学のもっとも根本的な態度である可能性があります。というのも、フィールドワークで他者の社会に足を踏み込んだとき、現地の人々が言うことを、西洋中心の考え方に照らして、いわば客観的に捉えようとすれば、それは相手の言っていることをどうしても歪めて捉えることになるからです。文化が違うというか、存在論的転回以降の考え方でいうなら「生きている世界が違う」のだから、どんなに気を付けても相手の世界をそのまま受け入れて理解したり翻訳することは不可能なのですが、それにしても歪みをできるだけ減らそうとするならば、相手の話を勝手に解釈しないでひとまず「真面目に受け取る」という態度になるわけです。
存在論的転回以降の現代人類学の論者たちのなかで、ある意味でもっとも異彩を放って目立っているのは、ブラジルのエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロです。エドゥアルドがファーストネームで、そのあとがファミリーネームなのですがカタカナで書くととても長いのでローマ字の頭文字をとってVDCと略記します。
VDCはレヴィ=ストロースと並んで、フランスの現代哲学とりわけジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの理論を重視しています。デスコラの存在論の四類型ではなく、多自然主義(マルチナチュラリズム)や遠近法主義(パースペクティビズム)という概念を提唱しています。多自然主義と遠近法主義は、存在論の四類型のように明確な図式を持って対比されるモデルではなく、インゴルドはもとより、デスコラの方がまだわかりやすいのではないかというくらいVDCの理論はわかりにくいのが特徴です。
そうはいっても、ともに西洋の自民族中心主義から逃れることのできないインゴルドやデスコラとは異なり、西洋化されながらも西洋の自民族中心主義からは常に排除されてきた南米ブラジルという場所性からの提言であることを考えると、西洋ではないのに脱亜入欧を唱えて近代化を推し進めてきた日本の読者には共感できる部分があるのではないかと思います。
もっともVDCが研究しているアマゾニア(アマゾン川流域のこと)の先住民諸集団において、たとえば「ジャガーがビールを飲む」という表現が示す事態は、説明なしにはほとんどの日本人が理解できないでしょう。
VDCが研究した地域の人々は、デスコラのいう意味でのナチュラリズムでいえばヒトとは異なる種であるジャガーを、ある意味で「人間」とみなす、とVDCは主張します。ジャガーは、彼らにとって自分たちを襲い、自分たちを喰らう他者です。ナチュラリズムでいえば、人間とジャガーは別の生物種であることは明確なのですが、逆をいえば、ナチュラリズムを保留したとき、ジャガーをジャガーとして人間から区別する根拠になる体系もまた保留されます。ナチュラリズムではない世界においては、あるいは、ナチュラリズムが西洋近代だけのものではなく、他のナチュラリズムがあるとすれば、ナチュラリズムにおいてジャガーとヒトとして区別されていた生き物が、同じ「人間」というカテゴリーに包括されうるのです。
疫病の人類史
自然と文化を二項対立的に捉えるかどうか、ということを考えるとき、喫緊の問題として現れてくるもののひとつに医療があります。とりわけ近代医療はやはり古代ギリシアのヒポクラテスに起源を持つ西洋医学が中心にあります。個々人の身体は、ヒトにとってもっとも身近な「自然」です。医学は、その身近な「自然」を研究し、その異常として病を捉え、その病を癒そうとします。
しかし、何を病として捉え、何を健康とみなすか、という根本的なレベルに始まり、どのような処置を施すのかという次元に至るまで、健康と病に対するさまざまな文化的な差異があります。たとえば呪術を前提とした世界では、ある種の病は呪いによって引き起こされます。その病を癒せるのは、呪いに長けた者(呪医)たちです。人類最古の図書館といわれるメソポタミアのアッシュルバニパル王の文書館に収められていた粘土板は、その過半数が呪医のためのものだったといわれています。近代医療の観点からは笑止千万な考え方かもしれませんが、そのような世界観で生きている人たちを癒すためには、その文化を前提にしなければなりません。
いままさに病んでいるヒトを癒すだけでなく、ある人々がある状態を病と考える前提になる世界を、どのように作り出してきたのかを考える、ということです。
コロナとワンヘルス
2019年に発生し世界をパンデミックで覆った新型コロナウィルス感染症、いわゆるコロナ禍によって、多くの人々が感染症とその感染経路を意識するようになりました。ヒトからヒトへの感染は、観光や流通といった広い範囲の産業を停滞させ、「ソーシャルディスタンス」を維持して自衛できる人々と、密集した環境で高い感染リスクに晒される人々を分断しました。
コロナに限らず、多くの感染症は人間以外の生物から感染することが知られています。そのため、人間だけの「健康」ではなく、生態系全体の健康を意識する「ワンヘルス」という考え方が昨今提唱されています。
先ほど触れた呪医に限らず、西洋医学の正統的な伝統から離れた文化圏では、いわゆる民間医療が支持されています。近代的な医学の説得力が相対的に弱い社会では、感染拡大を避けるために現地の文化に近代医学の知見を「翻訳」する必要があります。そのためには近代医学とは違う各地域の医療的な営みの文化を理解する必要があります。これは医療人類学と呼ばれます。
人類はこれまでの歴史のなかで、繰り返し大きな感染症(疫病)を経験してきました。その痕跡を遺跡や伝承に探り、何が起きていたのかを研究するのが疫病人類学です。たとえば、さまざまな物資やヒトを西から東、東から西へと運び、文化的に東西に架橋したシルクロードが、同時に疫病を伝搬していたことも指摘されています。たとえば寄生により肝硬変に移行するリスクもある肝吸虫の卵は紀元前の中国、戦国時代の遺跡の遺体から発見されています。肝吸虫はシルクロードに沿って1500キロにわたって発見されており、数千年におよぶ人類と肝吸虫のある種の共棲が認められるのです。ワンヘルスの観点からは、人間だけでなく、肝吸虫の「健康」も無視されないことになります。
機械カニバリズム
ヒトとヒトならざるものの共棲というときに、和気藹々とした平和な共棲が想像される場合は多いものです。しかし、ともすれば人間は侵入者であり、自然が侵入され、破壊され、作り替えられる、という非対称性があるように、その関係は決してのんびりしたものではありません。ときに自然は文字通りに容赦のなく人間社会の破壊を行います。いわゆる自然災害や、先述のパンデミックもそうでしょう。人類は、その圧倒的な環境のスケールと対峙し、時にそれを改変し、ときにその脅威をその場しのぎに対処しようとしてきました。
このようにして、デスコラが指摘し、四つの存在論的類型で相対化しようとした、自然と文化の二項対立は生まれてきたわけです。しかしヒトは、自分たちが生み出した文化の内部に、制御不能な領域を育てつつあります。
それが近年話題にされることが増えてきた人工知能の脅威です。久保明教の『機械カニバリズム』は、人間がするものと考えられてきた将棋という競技に、人工知能がいかに取り入れられるようになってきたのかを論じています。
書名にある「カニバリズム」は、存在論的人類学の旗手のひとりヴィヴェィロス・デ・カストロのキーワードのひとつです。
VDCは、近年の政治学で議論されることの増えた多文化主義を批判します。西洋中心主義を相対化する存在論的人類学は、さまざまな地域の文化を並列させる多文化主義といっけんしたところ似ており、何が違うのかわかりにくい部分があるのは確かです。しかし、デスコラが提示したように、西洋の自文化中心主義は「文化」と「自然」を対照的に捉えてきました。文化を複数とみなしたところで、自然は単一であり、同じ世界に住まう限りは、その環境は共有されているという立場です。単一の自然のなかで、複数の文化が併存している、という世界観です。これはごく当たり前のことのように思われるかもしれませんが、それは私たちが西洋的な自然主義(ナチュラリズム)を前提にしているからです。
VDCは多文化主義に対して多自然主義を提唱します。これは文化と自然の二項対立になっているという点ではデスコラ以前の考え方にも見えますし、多文化主義と自然の関係を単に図式的に転倒させただけにも思われます。しかしVDCの提案を真面目に受け取るとすれば、多自然主義とは、複数の文化がそれぞれに「自然」あるいは「世界」を構築しており、それぞれの文化ごとの自然は、互いに同じものではあり得ない、ということになります。
VDCはキーワードとしてカニバリズムや多自然主義のほかにも無数の概念を提示しています。たとえば観点主義(パースペクティビズム)です。観点(パースペクティブ)とは、以前に少し触れた遠近法における鑑賞者(制作者)の位置を示すものです。遠近法に関連して概説した射影幾何学においては、いわば射影変換のルールにあたる、見えない領域のことです。
西洋的な自然主義は、見えないものについては語らずに、見えるもの(自然)を存在として扱います。その結果として近代から現代に至る科学の体系が作られてきました。
これに対して、VDCが調査したアマゾン(アマゾニア)に住む人々は、見えるものをむしろ信じません。彼らが信じているのは、その奥にある魂という「見えないもの」なのです。
人間は動物を狩り食べます。動物を狩って食べる、という点において、人間はジャガーと同じになります。同じ行為をしているのだから、人間とジャガーは同じ存在です。ジャガーはときに人間を襲うということや、人間とジャガーが異なった見た目をしていることは、「見えるもの」という相対的に瑣末な違いにすぎません。
人が人を食らうというカニバリズムは、西洋においては強烈なタブーとされてきました。人間を食べる人間は、人間社会を脅かす典型的な野蛮人とみなされたのです。しかし、人を食べるジャガーは問題になりません。なぜならジャガーは人ではないからです。しかしアマゾニアでは、ジャガーとヒトは同じものなので、ヒトを喰らうことは、確かに恐ろしいことではありますが、西洋社会のようなタブーにはなり得ないのです。
久保は、ヒトが人工知能に敗北し、人工知能とともに将棋に向かうようになる様子を機械カニバリズムと呼びます。それは、単なるプログラムに過ぎないものを「人工知能」というヒトに類するものとして捉えるからです。アマゾニアの人々が、人とジャガーとを、動物を襲い、喰らうという点で同一視したように、ヒトと人工知能を、将棋をさすという点で同一視するのです。
妖怪の人類学
VDCが批判するデカルト的二元論は、「見えるもの」(身体、他者)を対象にして観点に立つ「見えないもの」(精神、自己)が観察と分析を行う、というものです。不可視の立場にある精神的自己は、自分を「疑い得ないもの」として特権化し、「見えるもの」を「疑う」という懐疑論を展開します。
精神的自己が疑い、観察し、分析した身体的で物質的な他者は、精神的自己によって操作されるようになります。
リベラルアーツつまり「自由技芸」の「自由」とは、この操作する自己の自由です。知的なリベラルアーツに対して、手工的な技術は機械技芸と呼ばれ、中世においては蔑視されていました。
音楽の楽曲を書く作曲家が、それを演奏する人よりも高位にあるとされ、ヒポクラテスの時代から継承されてきた歴史を持ちながら医学において手を動かす外科医がかつては卑しい職業とされ、図面を描く建築家が現場で働く大工たちよりも高い地位にあったのは、知的な営みが手業的な営みよりも高貴なものとされていたからです。
『機械カニバリズム』において、人間がすることとして将棋が捉えられ、人工知能の導入に対して激しい抵抗があったのは、知的な創造をする人間(精神)と、決められた通りに動くだけの人工知能(機械)とを区別する考え方があったのではないでしょうか。
「疑う精神」と「疑われる身体」が、互いに互いを喰らい合う、それが機械カニバリズムの構図です。これに対して、精神と身体がともに疑われる次元を扱ったのが、廣田龍平の『妖怪の誕生』と『<怪奇的で不思議なもの>の人類学』です。廣田は、これまで存在しないことをことさらに強調されてきた妖怪を存在論的人類学の枠組みで耐えようとします。
妖しく怪しいもの、として、人間(見るもの)から捉えがたいとされてきた妖怪。それは超自然的な力を持つ神の零落した姿であるとした柳田國男や、その柳田を批判して神になったり神から零落したりする別のカテゴリーとして捉えた小松和彦とも違うものです。廣田は、妖怪を西洋由来の分析的精神が捉えることのできなかったものとして扱います。そのうえで、妖怪について語る人々の言葉にあらためて目を向け、科学的に見て存在しない妖怪、ではなく、妖怪が存在できる世界、がどのように可能なのかを模索するのです。これは、妖怪を積極的に肯定するということではなく、妖怪の存在を疑っていなかった人々の世界を理解するための方法なのです。
ここにきて、大きな環境のスケールがあって、そのなかに中くらいのスケールの社会や共同体があり、それをさらにもっと小さなパーソナルなスケールが構成している、という単純な入れ子構造は、相互貫入的で複雑な世界観と転換されます。
パーソナルなスケールは、疫病のように世界中を席巻するファクターによって危機に晒され、その精神は人工知能や文化によってカニバリズム的に喰らわれています。共同体は、そのように環境の影響をダイレクトに受けているパーソナルなスケールの存在によって構成されています。文化も人工知能も共同体のスケールで制作されますが、パーソナルなスケールがカニバリズム的に喰らわれるように、共同体のスケールもパーソナルなスケールに喰らわれます。文化やその生産物はけっして静的なものではありえず、常にその構成員や外来者によって作り替えられ、解釈し直されるからです。そして環境のスケールは、西洋由来の自然主義のなかでは大きな自然として、精神によって眺められる「見えるもの」の集合として捉えられますが、VDCの観点主義からは、むしろ「見えないもの」つまり観点(パースペクティブ)の集合となります。環境(世界、自然)こそが「見ている」のです。
かつてユクスキュルは、ノミにはノミの環境世界(環世界、ウンベルト)があると考えました。いま人類は宇宙重力波望遠鏡を手にして、宇宙の果てを観測しようとしています。人間の環世界は、宇宙の果てまで広がろうとしているのです。そのとき、宇宙は「見られるもの」であり、望遠鏡を見ている人間は「見えない」ことになるかもしれません。しかし観点を変えるなら、人間も、重力波望遠鏡も、宇宙の果てにあるブラックホールも、すべてが「見るもの」つまり観点になりえます。次回は、そのような観点がひしめく環境として世界を捉える生物学をご紹介します。
(次回へ続く)
『食人の形而上学 ポスト構造主義的人類学への道』エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ、檜垣立哉 山崎吾郎 訳、洛北出版、2015年
『機械カニバリズム 人間なきあとの人類学へ』久保明教、講談社選書メチエ、2018年
「人類学の存在論的転回と政治哲学における存在論の問題 多文化主義批判と政治的存在論の可能性をめぐって」田村海斗、2022年
「存在論的転回とエスノグラフィー:具体的なものの喚起力について」浜田明範、2018年
『妖怪の誕生 超自然と怪奇的詩人の存在論的歴史人類学』廣田龍平、青土社、2022年
『<怪奇的で不思議なもの>の人類学 妖怪研究の存在論的転回』廣田龍平、青土社、2023年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)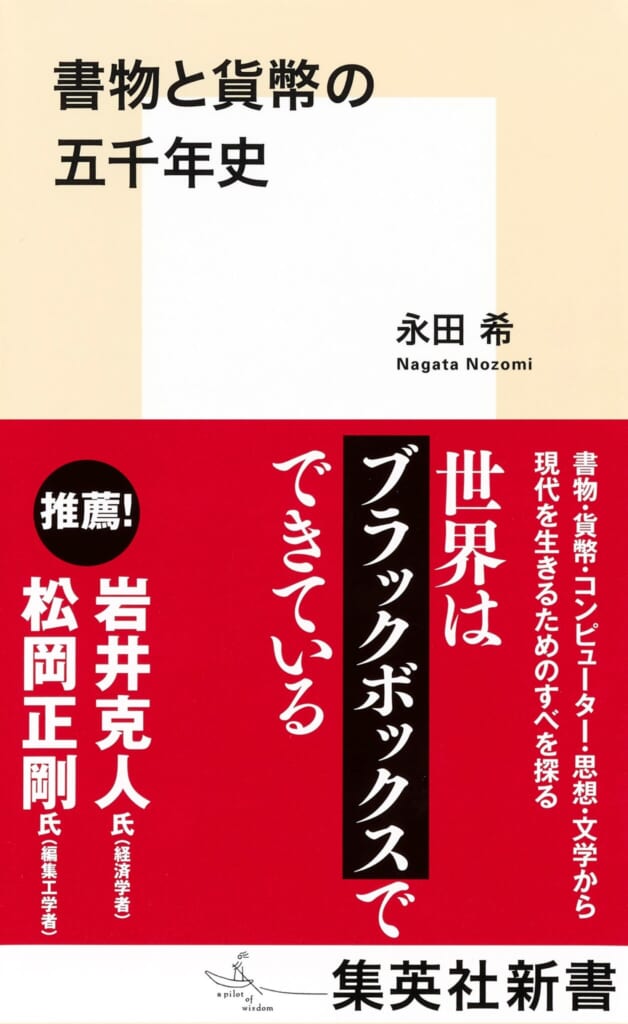










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

