世代を超えて蓄積された変化
進化という概念は、 現代の生物学の教科書では「世代を超えて蓄積された変化」のことを指します。したがって、たとえば目がなくなったり、尻尾がなくなるようないわゆる「退化」も「進化」です。字面の上では気持ち悪いのですが、ダーウィンの考えていた「進化」はこの意味でした。
進化論といえばダーウィンが有名ですが、実は「進化(evolution)」という言葉はダーウィン以前から存在しており、ダーウィンの独創ではありません。いま一般的に理解されており、またダーウィン進化論の用語としては誤っているとみなされる方の「進化」のニュアンスの方が、もともとの用法だったのです。
したがって、ダーウィンの用法を知らない人が進化という言葉を単なる進歩として捉えてしまうのは仕方のないことなのかもしれません。
ダーウィンは「進化」のほかにも、自説とは相性の良くない考え方を取り入れることがありました。とりわけ、無神論的と言われるダーウィンが、神に祈ってまで傾倒することを自らに戒めたのがラマルキズムです。
フランスのジャン=バティスト・ラマルクは、近代的な「生物学(biology)」の概念を作り出した人物です。下級貴族に生まれ、フランス革命期に頭角をあらわしたラマルクは、生物個体が一生のうちに獲得した特性は次の世代にも伝達されると考えました。これを獲得形質といいます。
獲得形質 ラマルクの考え方
ダーウィンは進化論の先駆者であるラマルクを讃えていましたが、しかし獲得形質が遺伝するという仮説を疑っていました。
進化論を考えるときに、◯◯は△△のために進化した、という表現がよく現れます。おそらくもっともよく目にするのが「種の保存のため」です。たとえばキリンの首が長いのは高い場所にある木の葉を食べる「ため」であり、そうすることでキリンという「種」を保存できる「から」だという説明です。
しかし少し考えればわかるように、キリンは自分たちを「キリン」という種として認識していません。ましてや、自分たちが滅びることでキリンという生物種が滅びるということなど考えているはずがないのです。そして、生物個体であるキリンがそう考えているはずがないのと同じくらい当然なことに、キリンの遺伝子もキリンという生物種を保存しようと考えているはずがありません。進化生物学者リチャード・ドーキンスにはベストセラーになった本のタイトルでもある「利己的な遺伝子」という言葉がありますが、ドーキンスはこの言葉を理論でも仮説でもなく、モノの見方として提案しているに過ぎません。しかし、自己を持たない遺伝子を利己的と形容するのは、直感に訴えて「わかったような気持ち」にさせる効果はあるでしょうが、その結果として得られるのが、少し考えればすぐにわかる程度の誤解であるとしたらあまり良い表現ではないのかもしれません。
ダーウィンの考え方からすれば、例えばキリンの首が長いのは、首の長い個体集団が生き延び、首を長くしなかった個体の子孫が生き延びなかったという以上の意味を持ちません。それはキリンの意図も関係ないし、キリンという生物種を保存しようという遺伝子の意図も関係ありません。
ラマルクの進化論における獲得形質の遺伝は、たとえばキリンが高いところの木の葉を食べようと首を伸ばしたことが次の世代にも受け継がれる、というようなものです。
鶏が先か卵が先か、という言い方がありますが、ダーウィン進化論では絶対的に「卵が先」です。鶏以前の鳥が、鶏のひよこが生まれる卵を産む必要があります。鶏以前の鳥がいたとして、その鳥が個体として一生のうちに鶏になるという考え方はないのです。
パーソナルな個体が後天的に獲得した変化は遺伝しません。そして、世代を超えて引き継がれる遺伝子はひとつではなく、さまざまな性質を発現させる遺伝子の集団が引き継がれていきます。その集合のなかのどの遺伝子が発現するかによって、個体の特性、いわば個性の多様性が生じます。同じ遺伝子を引き継いでいるはずの血縁集団で、性格や形質に差が生じるのはこのためです。もちろん、その多様性には突然変異によって前の世代から受け継いだわけではない特性も含まれます。
この「進化」の仕組みはいわば環境のスケールです。この仕組みを内包し、さまざまな個性を発現するのが個体(パーソナルなスケール)であり、それらの個体が集まっているのが共同体のスケールです。
遺伝子の在処
「遺伝子」という言葉は、今では誰でもなんとなくその「存在」を知っています。それは、遺伝子を不可欠の構成要素として組み込んでいる進化論生物学が現代社会のパラダイムの一部になっているからです。しかし、「遺伝子」そのものを見たり触ったりしたことがある人はあまりいません。
そもそも遺伝子は「どこ」にあるのでしょうか。その答えは「細胞のなか」です。遺伝子は、生物の身体を構成している細胞のなかにある細胞核に含まれています。遺伝子は、細胞核のなかの染色体という組織にあります。染色体は通常、細胞核のなかに23対46本あります。
23対46本の染色体のそれぞれのなかに含まれる遺伝子は、タンパク質を生成するための情報を持っています。遺伝子と染色体は、よくDNA(デオキシリボ核酸)と混同されますが、それぞれは微妙に異なっています。
DNAは4種類の塩基から構成されています。これが糸状になり、折り畳まれたものが染色体です。遺伝子とは、この染色体に含まれるDNAのうち、タンパク質の生成に関わるものを指します。
遺伝子は、よく知られているように二重螺旋の構造をしています。この構造において、螺旋のそれぞれは微妙に異なっており、この多様性はアレルと呼ばれます。
まとめると次のようになります。生物のからだは細胞からできており、細胞には細胞核が含まれており、細胞核には染色体が含まれています。染色体はDNAが糸状になり折り畳まれて凝縮されたものであり、そのうちタンパク質の生成に関わる情報を持ったものが遺伝子です。遺伝子は二重螺旋構造で、その多様性がアレルと呼ばれます。進化論が語られるとき、遺伝子の多様性によって生物が世代ごとに変化していくわけですが、その変化は遺伝子のなかのアレルに左右されます。
蛾と人間の「進化」
遺伝について説明するときによく参照される事例に、近代イギリスで観察された、とある蛾の変異があります。オオシモフリエダシャクと呼ばれるこの蛾は、それまでは白っぽい淡色種が多かったのですが、イギリスで工業化が進み、空気が汚染されるとともに暗色種が増えました。空気汚染が問題視されるようになり、空気がきれいになると再び淡色種が増えるようになりました。
なぜこんなことが起きたのかというと、蛾が羽を休める樹木の状態が原因と考えられています。樹木には、表皮に白っぽい地衣類がついていることが多く、淡色種の蛾はその地衣類のうえにとまっているといわゆる保護色になり、鳥類からの捕食を避ける結果となりました。これに対し、空気汚染がすすむと、空気の変化に敏感な地衣類が減ってしまい、黒っぽい樹木のうえで淡色種はかえってめだつようになり個体数を減らしたのです。
興味深いのは、空気汚染が改善されると再び地衣類が樹木を覆い、今度は暗色の蛾の個体が減るようになったことです。
環境の変化に応じて、個体の特徴が変化していくことを「適応変化」と呼びます。これはいわゆる「進化」のイメージを示す良い例なのではないでしょうか。しかし、進化はこれだけではありません。
人間の体質で、お酒に含まれるアルコールや、牛乳に含まれる乳糖を分解できるかどうかという多様性があることはよく知られています。お酒を飲んでも基本的には平気な人もいれば、逆にお酒を飲むとすぐに倒れてしまう人もいます。また、その中間というか、真っ赤になるけど少しは飲める、という人もいます。また牛乳を飲んでも全然平気という人もいれば、お腹を壊してしまう人もいます。アルコールや牛乳への耐性が世代を超えて遺伝することはよく知られています。
さきほどのオオシモフリエダシャクの場合、捕食者に狙われやすくなる要素を持っていると、捕食されて次の個体を残すことができなくなります。このように、個体を死に至らしめる可能性を持つ遺伝子の多様性を「有害なアレル」と呼びます。アルコールや牛乳は、酩酊することで行動が抑制されたり、体調を崩してしまうことがあり、野生状態では個体を命の危険に晒す可能性があります。したがって、アルコールや乳糖を分解できないアレルは「有害なアレル」になりえます。しかしヒトは社会集団を形成しているため、「有害なアレル」を持っていても、その個体は死なずに次の世代へと遺伝子を受け渡していくことができます。
有害なアレル
このように、個体の生存を危険に晒す可能性のある「有害なアレル」を持っていても、自然選択の淘汰をかいくぐるパターンがあります。アレルには、二重構造の2つのうち片方だけで遺伝形質が発現する優性アレルと、二重構造の両方が揃わなければ発現しない劣性アレルがあるため、「有害なアレル」を、発現しないままで個体が保持する場合があります。
「有害なアレル」を持っていても発現しない場合、個体はそのアレルによって命を落とすことはありません。次に、そのアレルが発現しても、たとえばアルコールや乳糖を摂取しなければ、やはりその個体は安全です。問題は、そのアレルが発現している個体が命の危険に直面する場合、この例で言えば、アルコールや乳糖を分解できない個体がアルコールや乳糖を摂取した場合です。野生状態であれば、体調を崩して動けなくなった個体は捕食され、次の世代にこのアレルを伝えられません。自然選択です。しかし、社会性動物であるヒトの場合、ここでケアが介入します。
アルコールや乳糖を摂取して体調を崩す「有害なアレル」を持っていて、実際に体調を崩しても、社会ではケアが行われてその個体が生きながらえる可能性があります。このとき、そのアレルは自然選択を免れます。あるいは、日本のように地形的に大陸から切り離されている地域の場合、そこでは局所的に「有害なアレル」が集団全体に共有されることがあります。有害か否かを問わず、アレルが地形によって分断されることは「地域文化」と呼ばれます。
遺伝分子生物から代謝論へ
アルコールの分解プロセスに欠かせない酵素(ALDH)を体内で作るには、細胞核にある染色体のDNAが必要になります。タンパク質を作る情報に関連するDNAが遺伝子なので、ALDHを作るためのDNAも遺伝子です。
ヒトという種のなかでも、東アジア一帯に多く住むモンゴロイドにはこのALDHを作るための遺伝子のうち、二重螺旋の片側だけ変異している低活性型と、両方とも変異している非活性型の割合が高く、いわゆる「お酒に弱い」人が多いことが知られています。なお、東アジアの一角である日本でも、列島の中央部分にいくほど、代謝の遅い酵素を持つ遺伝型の人が多くなります。一般的に「お酒が弱い」とか「下戸」と呼ばれる人は、アルコールの分解酵素が相対的に少ない低活性型と非活性型、つまり「アルコール代謝が遅い」体質の人たちです。
細胞核内の染色体に含まれるDNAに保存された情報は、RNAに転写されます。RNAは一重の螺旋構造を持つ、DNAと同じ核酸です。
細胞核内のDNAから情報を転写されたRNAは核の外の細胞質に移動し、タンパク質が合成されることになります。A LDHも、その設計図は細胞核内のDNAに保存されているのです。細胞核は「マイクロメートル(μm)」のスケールです(μmは、0.001mmの単位)。この細胞核に含まれる染色体を構成しているDNAはもちろんもっと小さいスケールになります。μmのさらに1/1000の単位であるnm(ナノメートル)で計測されます。
ナノメートルのスケールは、原子が結合する分子のスケールです。
代謝の仕組み
アルコールを人体内で分解するために必要な酵素ALDHは、DNAに保存された情報を転写されたRNAから合成されたアミノ酸で構成される酵素のひとつです。
お酒として飲まれたアルコール(C₂H₆O、エチルアルコール、エタノール)は、胃や小腸で吸収され、血液を経由して大部分は肝臓に送られます。アルコールは肝臓でまずADHという酵素によって分解されます。ADHによる分解で、アルコールはC₂H₄Oつまりアセトアルデヒドとなります。化学式を見ればわかるように、エタノール分子C₂H₆Oから水素Hが2つ減ったものがアセトアルデヒドC₂H₄Oです。
ALDHはアルデヒド脱水素酵素の略称で、アセトアルデヒドを酢酸(CH₃COOH)に分解します。アルコールの分解には、MEOS(ミクロゾームエタノール酸化系、Microsomal ethanol oxidizing system)などの働きもあり、複雑なプロセスになっています。アルコールの分解ひとつとっても、精密工場のような緻密な「工程」が、ヒトの意識を介さずに、いわば勝手に行われることには驚かされずにはいられません。
代謝論のスケール
人体というきわめてパーソナルなスケールに目を凝らしていくと、ナノメートルの分子生物学的スケールが現れてきます。それは、この宇宙にあまねく広がる環境のスケールです。
人体のなかのミクロコスモスと、外的世界つまりマクロコスモスの間には、共同体のスケールがあります。人間社会と自然環境の間にある関係についてカール・マルクスがどのように考えていたのか、それを研究しているのが『人新世の「資本論」』などで知られる斎藤幸平です。
マルクスは産業社会における労働の重要性に注目しました。自然環境から農作物や鉱物資源を得て加工する「労働」は、産業によって資本の増大に役立てられます。資本は自己目的的に増大を続け、その過程で労働が生み出す価値は、資本へと集約されていきます。一般にマルクスは進歩主義的な思想を持っていたとされ、労働者はやがて資本家を打倒することになると主張していたと考えられています。この議論では、労働者と資本家という対立はありますが、環境から労働が農作物や鉱物資源を「搾取」している構造は無視されています。
自然環境を、人間ではないものとして定義すれば、農作物や鉱物資源などが自然環境から労働が搾取する対象になりますが、人間自身も自然に取り巻かれて生きている生物という意味では自然の一部です。労働に充てる時間は、そのほかの生活の営みに使える時間を減らしてしまいます。心身の健康を害するほどの労働が存在するように、労働は労働者自身の肉体からも搾取をしているのです。
斎藤は『大洪水の前に』や『マルクス解体』で、人間と自然環境の双方が、資本による収奪(搾取)によって疲弊していくばかりの状況を、マルクスがどのように論じようとしたのか、またマルクス以降の思想家たちがそのマルクスの模索をどう引き継いだのかを整理しています。
斎藤によれば、マルクスは労働者の身体と自然環境がともに搾取されている状況を「物質代謝(メタボリズム)」と呼びました。メタボリズムは、普通は代謝と訳されます。
斎藤の注目するようなエコロジカルな側面はこれまであまり注目されておらず、マルクスは技術楽観主義的な進歩主義者(プロメテウス主義者)と捉えられてきました。
代謝は、ある集団を構成する要素が新しいものに順次置き換わっていくことを指す「新陳代謝」を意味する場合があります。たとえば人体を細胞の集まりとして考えれば、古くなった細胞が人体外へ排出され、新しい細胞が作られ古い細胞に置き換わっていくのはまさに新陳代謝です。
新陳代謝とは別に、飲食や呼吸によって体内に取り込んだ物質を、人体の維持に必要なものへと変換したり、有害なものを人体に無害なものへと変換するような一連のプロセスが「代謝」です。さきほど触れたアルコールの分解は、そのままでは毒物であるアルコールを水と二酸化炭素に分解する代謝の例です。
普通、代謝は生体内のプロセスを指しますが、マルクスはこれを自然界と人間界の関係に見出します。食品やエネルギーを自然から得る過程で、人間は自然の素材を分解し、組み替えています。人類が自然にとって有害な存在でなければ、食品やエネルギー、さまざまな産業の材料を自然から人間が獲得しても、それは収奪にはならず、いわば正常な「代謝」になるはずです。
しかし人間の文明は周知の通り、自然を破壊し、人間がいなければ維持されていたと思われる自然状態を変化させてきました。物質が代謝せず、自然環境に負担をかけている状態、これがマルクスのいう「物質代謝の亀裂」です。
ヒトやほかの生物は、それぞれの種の誕生から何世代もかけて、たとえば代謝の仕組みを構成してきました。生物学的な代謝はとても精巧な仕組みです。これに対して、現在の人類が自然環境に対して行ったことは、あまりに粗雑で持続性に欠けると言わざるを得ません。生態を観察し分析する生態学(エコロジー)と、人間の経済活動を観察して分析する経済学(エコノミクス)は、人類の存続という根本的なレベルで通底することになるのです。
物質代謝の3つの次元
マルクスは、物質代謝を3つの次元で考えました。
第一の次元は、農業の方法です。作物を作るためには、土壌の栄養素が必要になります。繰り返し農作物を作れば、それだけ土壌の栄養素は農作物へと移動します。農業によって土壌の成分を吸い上げられることを「土壌の疲弊」といいます。
第二の次元は、農作物の移動です。都市化の進む近現代社会では、農作物の多くは人口が密集する都市部に運ばれます。都市部では農業が行われないので、第一の次元で土壌から栄養素が農作物に移動したように、農村部から都市部へと農作物は移動し集積されることになります。
第三の次元は、排泄です。都市部の住人は農作物を食べて排泄をします。農村部の人々も同じように排泄をしますが、その屎尿は農作物にとっての肥料になります。都市部で排泄された屎尿は、農村部のように農地へと還元されずに滞留するか、近隣の河川や海へと廃棄され水産資源にダメージを与えます。
農地への肥料として注目されたグアノ(堆積した海鳥の糞が化石化したもの。肥料の原料になる)や、ハーバーボッシュ法による化学肥料は、第一の次元の一時的な解決に役立ちます。しかし、グアノには採取量の限界がありましたし、ハーバーボッシュ法にも肥料を生成する過程で必要になるエネルギーや、そのエネルギーを作るための二酸化炭素排出量の問題があります。
マルクスは、経済的な富が偏在し、その度合いが増していくことを批判したことで知られています。それは社会的な代謝を論じていたと言えるでしょう。しかしそれだけでなく、土壌の成分、つまり自然の代謝にも関心を払っていたのです。
人類が、長い歴史のなかで進歩してきたのかどうか、それは一概に断言できることではありません。しかし、現代の進化論がいうところの、進歩とは違う意味での「進化」、つまり「変化を蓄積する」という意味でなら、確かに人類は進化してきたと言えるでしょう。
生物学的進化については、遺伝子が変化を蓄積するようになっているため、人類もまた進化してきたのは当然のことでしかありません。しかし文化的な進化の側面では、イノベーションが蓄積し、それによって社会が変化してきていることから、やはり「変化の蓄積」はされているのです。その結果として、社会に格差が生じ、苦しむ人が生まれ続けるという望ましくない現実があり、今後その事態が継続してしまうとしても、「良くなる」という意味ではなく、単に「変化が蓄積する」という意味では進化はしているのです。
(次回へ続く)

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)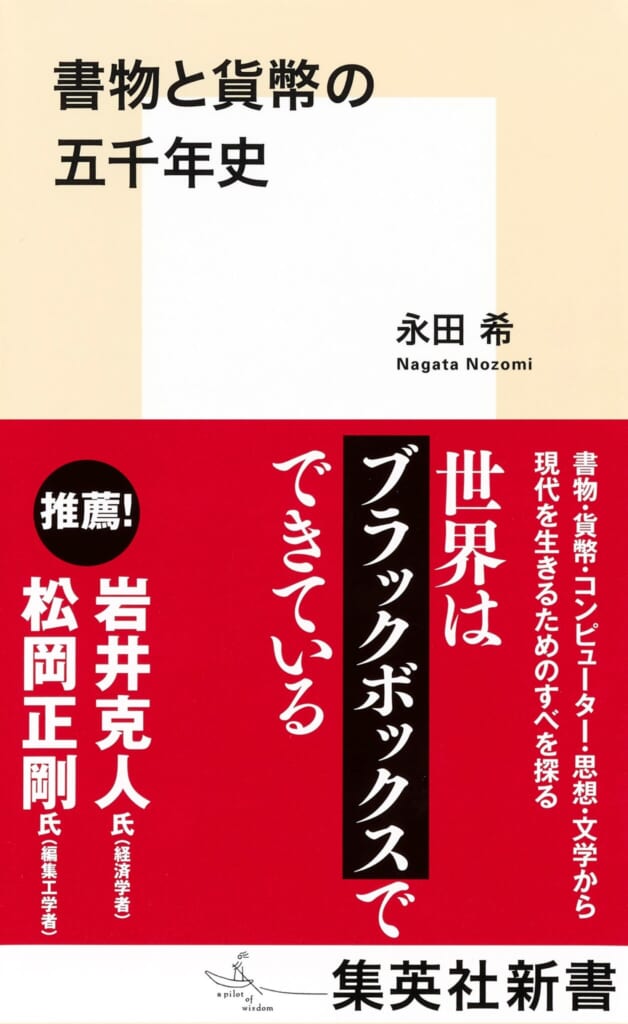










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


