近代的人間と野蛮人
人間と人間でないものを区分する二元論的な考え方は、文化と自然を二分できるという西洋的な自文化中心主義的なものとして批判されるようになってきています。しかし依然として世の中で広く信じられている考え方でもあります。理論家たちの議論と世間とのあいだに乖離があるために、新しい考え方が広まるまでにはタイムラグがあるのです。
人間と人間以外を区別し、文化を自然から分離させる考え方は、人間社会を自然環境から相対的に独立したまとまりとして看做します。文明と野蛮の二分法です。自然という言葉は英語ではnatureと言いますが、これは別の日本語「本質」と同じものです。それが具体的にどのようなものであるかは別にして、「もともとそうであった」という状態、つまり「本来」の姿こそが自然だ、ということです。これに対して、人間があとから付け加える要素は人為的(artificial)と言われます。
デカルト的二元論は、人間である「我」と、それ以外の世界を厳然と区分します。この区分によって、自然で本来的な世界を、人間である「我」が観察し、分析し、操作することが可能になります。本来的な自然を観察し、分析し、操作する「我」が人間なのだとすれば、理想的な人間とは、自分の身体や心理や行動も観察し、分析し、操作しうることになります。なぜならば、人間の身体、心理、行動は世界という自然に属しているからです。自分の身体、心理、行動すら含む自然の世界を観察し、分析し、操作するのが人間であるとすれば、ヒトでありながら自然や世界を観察せず、分析せず、操作しない人々は、人間よりも自然に近いということになります。
人類の文明は、自然を観察、分析することで無数のイノベーションを獲得してきました。道具の発明、火の利用、農耕や牧畜の開始、文字や経済などのコミュニケーション。第二の自然とも言われる、これらのイノベーションは、後世の研究者たちが自己分析的に観察し、分析する対象になります。人類学や社会学、哲学などを含む社会科学や人文科学です。
イノベーションとその利用についての研究は、新しいイノベーションを生み出します。このイノベーションの連鎖は、政治的、経済的な強さに繋がりました。現在、世界を西洋式の生活スタイルが席巻しているのは、西洋にイノベーションを連鎖的に生み出す学問の体系があったからです。この学問の体系に勤勉に取り組み、イノベーションの不断の連鎖を続けていくこと、これこそが近代社会の理想であり、自然から分離された人間の使命だと考えられていました。いまだにこの考え方を素朴に信じている人もとても多いので、「考えられていました」と過去形で書くのは妥当ではないかもしれません。近代が未完のプロジェクトだと言われるのは、この進歩主義的な文明観が完遂されておらず、また完膚なきまでに失敗もしていないからです。
近代西洋の理想の人間像が進歩的で勤勉なイノベーターであるとすれば、そうでない人々はどう見られてきたのでしょうか。彼らは、勤勉ではなく怠惰であり、イノベーティブではなく旧態依然とした生活を是とする人々と看做されました。彼らは良く言えば伝統的な生活をしているわけですが、相対的に自然な状態にいる、つまり人間より動物に近い野蛮人と看做されました。
教育されていない野蛮人とその野蛮な社会は、進歩的な社会によって善導されるべきである、と考えられました。これが「啓蒙」の思想です。リベラルアーツや教養は、「啓蒙」する側のものだったし、今でもこれらを結びつける考え方は根強く支持されています。リベラルで自由な教養人が文明社会を代表し、伝統的な社会に縛られている不自由で暗愚な人々を解放する、という見方です。
自由な教養人の「文化」と、野蛮人たちの「自然」との二項対立は、しかし「野蛮人」とされる人たちの世界に身を置く観点(パースペクティブ)からは全く別の意味を持ちます。
フィリップ・デスコラがナチュラリズムと呼んだ文化と自然を二項対立的なものとして捉える世界観は、観点を持つ「我」の精神と、観点から眺められる世界に属する身体、という二項対立に依拠します。観察し、分析し、操作する「我」の精神と、観察され、分析され、自らは操作しない世界。この「世界」は、わたしたち自身の思索しない部分、ジークムント・フロイト的に言えば無意識の部分を含みます。この「世界」は、意識が操作する指や手足などの身体から、目に見える世界、直接には観測できないので望遠鏡や顕微鏡を使って眺める必要のある世界までが含まれます。
身体やそのほかの自然現象には、合理的に説明することができる仕組みがあります。口から入った食べ物は胃で消化され、その一部の成分は血管を介して脳に伝わり、脳の活動に使われます。太陽光で温められた地面の熱は空気に伝わり、温められた空気は膨張し単位体積あたりの重さが相対的に軽くなるため、上空に移動するいわゆる対流が生じます。このように、人間の身体を含む自然や世界が「仕組み」によって動くことは機械的と呼ばれました。
ダーウィンとフロイトの重要性
人間と動物を比較して、人間には思索する精神があり、動物には精神がないという区別をする考え方があります。人間は機械を操作できますが、動物にはそれができないからです。身体や自然が機械的だとすれば、人間にだけは、その機械をコントロールできる精神があり、人間以外の動物や自然物には精神がなく、観察され操作されるだけの客体である、という主張です。
西洋の思想史においてチャールズ・ダーウィンやフロイトが重要だと看做されるのは、主体であるはずの「精神」や、精神を持つために他の動物と区別されるはずだった人間を、二項対立ではない形で捉えようとしたからです。
フロイトは、精神分析において「精神」もまた仕組みを持つ機械的で分析可能なものとして捉えようとしました。ダーウィンは、人間が動物の一種として系統樹の枝のひとつを構成するだけの種であると指摘したのです。
ダーウィンの進化論には、自然淘汰(natural selection< 自然選択>という原語に忠実な訳語を用いる場合も少なくない)という重要な概念が含まれます。
生物種が環境の変化や多様性に応じて淘汰され、生き残った個体たちが次の世代を残し、これを繰り返した結果、現生の生物種が存在している、という考え方です。この淘汰(選択)の過程を辿って樹形に示したものが系統樹です。ヒトという種も、この自然淘汰を経て現れてきたものに過ぎない、これがダーウィンの主張でした。
神が多様な生物をすべてデザインしたと信じられていた社会において、先天的なデザインを必要とせずに、淘汰の繰り返しのなかでたまたま生き残った個体たちが偶然に生き延びてきた結果があるだけだというダーウィンの主張はかなり過激なものとして受け止められました。
ダーウィンは反発を買っただけでなく、共感した他の学者たちによって曲解されもしました。環境の変化による淘汰を生き延びることは、たまたま新しい環境に適した機能を持っていたという偶然にほかなりません。しかし、生き延びることを「強さ」や「優秀さ」と取り違えてしまった学者たちが、ダーウィンを擁護する立場として発言力を持ってしまったのです。このことは、ダーウィンの母国である当時のイギリスが、世界中に広大な植民地を抱える帝国だったことに関連します。つまり、戦争のような環境の激変、過酷な事象を勝ち残ってきた白人は強い人種であり、白人の近代文明に敗れて支配される植民地の人々は白人に導かれるべき劣等人種である、という考え方です。
自民族中心主義と内集団バイアス
「西洋の自民族中心主義」と書くと他人事のように見えるかもしれません。しかし、心理学の考え方に「内集団バイアス」というものがあります。自民族を中心に考えてしまうのは、西洋に限られる態度ではないのです。
「内集団バイアス」とは、誰であっても、自分が属している集団の内部のメンバー(仲間)については本人の努力や性格によって幸福や成功を手にすると考えがちであることを意味します。また、もし自分の仲間が不幸になったり何かに失敗したときには、その仲間本人の努力や性格の及ばない「仕方のないこと」が原因であると考えがちであることも「内集団バイアス」と呼ばれます。単純に切り詰めて言えば、「内輪褒め」「仲間贔屓」のことです。
これに対して、ヒトは、自分が属していない集団のメンバーに対して、その不幸や失敗の原因を本人の怠惰や生活の問題に求めがちになります。自分が属していない集団のメンバーが幸福だったり、何かに成功したときは、本人の努力や性格を低く見積り、「たまたま運が良かっただけ」と考えてしまうのです。
この傾向は、西洋と非西洋のあいだ、文明人と「未開人」「野蛮人」のあいだに見出されるのみならず、自国人と外国人、男性と女性、人間と動物、大人と子供など、さまざまな「集団」を眺めるときに避けられない傾向です。
社会ダーウィニズムの問題
西洋社会の支配者の集団は、自分たちの経済的な成功は自分たちの努力や勤勉な性向に由来するものであると考えました。近代以降、なぜ西洋社会が現代社会において覇権的な地位を占めるにいたったのかについて、さまざまな仮説が提唱されてきましたが、それは当時の独善的な自民族中心主義を相対化し、その経済的で政治的な優位性がどのような環境に条件づけられたものなのかを吟味しているのです。
さてダーウィンが提唱しはじめた進化論(ダーウィニズム)は、自然環境の変化に適応できなかった種が絶滅し、適応できたものがたまたま存続してきた、と考えます。ここに、個体それぞれの努力や性格が役立つ側面はありません。パーソナルなスケールではなく、環境のスケールで変化は起こります。絶滅するか存続するかは個々の個体の努力や性格でどうにかなるものではないのです。
ダーウィニズムのこの側面を見落として語られたのが、社会ダーウィニズムです。社会という「環境」のなかで生き抜くには、自ら適応していく努力が必要であるという考え方です。何万年という時間的スケールで進行する種の絶滅と存続のせめぎ合いを論じていたダーウィニズムに対して、社会ダーウィニズムはごく短い時間スケールでの議論をして、しかも内集団バイアスの陥穽にはまっていたのでした。
社会ダーウィニズムは、白人エリートの優位性に基礎を与えると期待されました。世界中に植民地を築くほど強大な権勢を手にした西洋人は進歩的であり、その他の地域の「遅れた人々」を善導するべきだ、という主張です。
しかし社会ダーウィニズムは、のちに科学的な根拠が認められないことが明らかになり没落します。いまだに科学的な考え方よりも内集団バイアスの傾きを信じて、社会ダーウィニズムを支持する人が多くいるのは頭の痛いところではありますが、心理学的なバイアスは直感に訴えるため、科学者以外がハマって抜け出しにくくなるのは仕方のないことなのかもしれません。
現代では、このような非科学的な社会ダーウィニズムとは別に、遺伝子というこれもまたダーウィン的な要素に注目する新しい動向が存在します。親から子へと受け継がれていく遺伝子を分析することで、特定の病に対する罹患しづらさ、耐性、性格の傾向、容貌などについて、ある程度コントロールすることが可能になりつつある、少なくともそこに可能性がある、という考え方です。この新しい動向は「新しい優生学」と呼ばれています。
新しい生命により良い人生のための条件を与えようという親心といえばその通りなのですが、これから生まれてくる生命の新しい人生に対して、親の世代の価値観で取捨選択が行われること、また、そもそもそのような取捨選択ができる親が基本的に富裕層であることによって、「新しい優生学」はさまざまな問題を提起しています。
目(眼)に注視する
進化論を語るときに陥りやすい混乱があります。自然淘汰が種全体に関わる、いわば環境のスケールの概念であるのにもかかわらず、個別の個体、つまりパーソナルなスケールの話に当てはめてしまうことです。
現代の生物学は進化論のパラダイムを採用しており、生命の誕生から現代の生態系に至るまでに自然淘汰が常に働いてきたと考えています。これは明確に環境のスケールの話です。進化論において、ヒトという生物種も当然ながら自然淘汰を経てきたとされています。厄介なのは、進化には生物的な側面と、文化的な側面があることです。例えば、ヒトの視覚の機能について、進化論的に説明できる部分があることは、マーク・チャンギージー『ヒトの目、驚異の進化』などで示されています。これは環境のスケールの話です。しかし性的な好みなどを進化論的に説明しようとすると、個体の属する文化圏の違いによるものが大きく、一概には言えなくなってしまうのです。「文化圏の違い」は実はヒトに限ったものではない、という説もありますが、その議論はいったん横に置いておきます。環境のスケールで説明ができる、種全体の傾向に対して、文化的な側面は社会集団という共同体のスケールの話になります。
ひとまず環境のスケールで、ヒトと他の生物種を比較してみましょう。引き続き目(眼)を例にします。
ベストセラーになった『タコの心身問題』の著者で科学哲学者のピーター・ゴドフリー=スミスは、その著書『メタゾアの心身問題』で、海棲の節足動物であるシャコの「目(眼)」を次のように紹介しています。
シャコはひとつの物体を片方の眼の異なる領域で見ることができ、そのため片目だけで奥行きがわかる。また、シャコの眼には一〇種あまりの色の受容体がある(ヒトの眼は通常三種)。
シャコなどの節足動物は、ヒトが属する哺乳類を含む脊索動物とは異なる生物学的分類にあたります。節足動物の「目(眼)」は、一部の例外を除き、たいていは複眼です。複眼は、ひとつひとつレンズを備えた小さな個眼が多数集まって構成されています。
これに対して、ヒトや一部の節足動物(ある種のクモ)の眼は、片方につき一枚のレンズと網膜があり、その構造はカメラと同じになっているため、カメラ眼と言われます。
光センサーの発生
ヒトのカメラ眼やシャコ類の複眼は、もとを辿れば今から数億年前(約5億4200万年前から約4億8830万年前)のカンブリア紀に発生したものと考えられています。最初期の「目(眼)」は、ただ光を感知するだけのセンサーのようなものだったようです。そんな単純な「目(眼)」でも、あるのとないのとでは大違いです。
この頃まで生物たちは、主に他の生物の死骸や微生物を食べる「スカベンジング」をして暮らしていました。生物の個体数が増え、死骸ではなく生体を捕食する種が現れるようになると、獲物を見つけるため、あるいは捕食者から逃れるために光センサーが有用になったのです。
光センサーは、獲物を見つけたり捕食者から身を守るのに役立つだけではなく、体内時計の役割に関わっています。分子生物学者の粂和彦は、ショウジョウバエとヒトは共通して生物時計をもっており、クリプトクロームと呼ばれる同じ遺伝子がその生物時計をリセットすることを発見しました。クリプトクロームは光に反応する光受容体タンパク質です。1日24時間の周期を、生物が日光などの強い光を受けてリセットすることは世の中でもよく知られていますが、その現象はクリプトクロームによるものなのです。
感覚器と行為のフィードバックループ
光センサーや「目(眼)」のような生物の感覚器官は、「自分」の行為を把握して制御するという「行為主体性」と不可分に結びついています。
何かを感覚する→行為する
という、感覚と行為の連関は、感覚したから行為した自分の行為を感覚する、というフィードバックループを生み出します。このループする系(システム)は、いわばデカルト的な二元論の一方をなす「我」の原初の姿なのだとしたらどうでしょうか。自分の身体を含めた「世界」を観察し分析し、操作すること。それは、周囲や自分の行為を感覚し行為することの発展形だと考えてみればどうでしょうか。白人エリートや教養人だけの特権であり、その資格でもあったはずの、世界の観察、分析、操作(は、ヒトという生物種を超えて、遠い親戚であるシャコにすら共有されるものだったことになります。
ゴドフリー=スミスは、視覚による光学的な感知ではなく、電気による感知をする魚類にも言及します。ヒトを含む哺乳類も、周知の通り脳などの神経系は電気的な信号で情報を伝達しています。一部の魚類は、陸上の空気よりも電気を伝達しやすい海中で、複数の個体同士で電気信号をやりとりし、魚群を形成しています。信号をやりとりするためのアンテナのような部位まで持っているのです。
小さな魚が集まって大きな群れとなり、捕食者に対抗する。レオ・レオーニの有名な絵本『スイミー』のもとにもなった、一部の魚類のこの生態は、電気センシングによるものだったのです。目に見えないという性質だけを見れば、まるでWi-Fiを介してスマホでやり取りをするSNSユーザーの「クラスタ」や「界隈」を彷彿とさせます。
神経に直結した電気センシングによって、小魚たちは大きな魚群となり、サメなどの外敵に遭遇したときに、まるで大きなひとつの個体のように全体として動けるのです。そのとき魚群には、ヒトの脳のような神経系の中枢はありません。無政府主義(アナキズム)的に、個々の個体は全体と連絡をとりながら動いているのです。
ゴドフリー=スミスは、『タコの心身問題』『メタゾアの心身問題』の2作を通してタコなどの頭足類を考察の対象にしています。
タコは、いわゆる「頭」にあたる部分にある脳のほかに、「ほぼ脳と言っていい」くらいの大きな神経組織を8本の足それぞれに持っています。中枢の脳から完全に自由とは言わないまでも、かなりの自由度をもったそれぞれの足は、中枢の脳からの指令を待たずにそこそこ勝手に動いています。ヒトに例えれば、持とうと思わずにテーブルの上のグラスを取り、反対の手で頭を掻きむしり、片足で貧乏ゆすりをしながら、もう片足で絨毯を摘むようなものです。こう書いてしまえばどうにかやってできないこともなさそうですが、タコの足はヒトの両手両足(4本)の倍の数(8本)あり、しかも「勝手な動き」なので、脳からの指令なしにこれらが行われるわけです。ヒトで想像しようとしても不可能なくらいにかなり慌ただしい状態です。
もちろん、タコだって中枢の脳が足を完全に自由にしているわけではありません。問題になるのは、頭にある中枢の脳と、それぞれの足にある分散的な「脳」の関係です。タコの専門家のあいだでは、「頭と足」という1+1の脳なのか、頭とそれぞれの足、つまり1+8の脳なのか、という議論がなされてきました。ゴドフリー=スミスは自身の学生からの指摘に着想を得て、ヒトの右脳左脳のように、タコも複数の脳の組み合わせをスイッチングしているのではないか、という刺激的な説を提唱しています。
心身問題と「親戚」
このようにゴドフリー=スミスは、タコの心身の関係を、ヒトの心身問題と交差させて論じています。ヒトとタコとは、ヒトとシャコ、ヒトとショウジョウバエのように、脊索動物と無脊椎動物という、生物学上のかなり遠く離れた生物種です。ヒトとその他の生物を単に同じカテゴリーとして論じてしまうのは、ほとんどタブーと言っていいでしょう。近代科学の基礎にある「分類」という規範に抵触してしまうからです。
ゴドフリー=スミスが、「分類」を重んじる自然科学ではなく、哲学という人文科学の専門家でしかない、という専門性を理由にして、この「混同」を免罪することはできません。
専門性を話題にするのであれば、ゴドフリー=スミスは科学を対象にする哲学の分野、つまり科学哲学の専門家なので、むしろカテゴリーに対しては人一倍敏感であるべきだとすら言えるでしょう。しかし、ゴドフリー=スミスはカテゴリーを「混同」しているわけではありません。
ヒトとタコ、ヒトとシャコを、同じカテゴリーで論じることは可能なのです。我々は、数億年前まで遡れば共通の祖先を持つ、遠い親戚として捉えられるからです。数億年をいったん遡り、そこからまた何億世代分の時間を辿り直せば、ヒトとタコ、ヒトとシャコは、遠いながら親戚同士なのです。何億年、何億世代という環境のスケールを経れば、かなり巨大にはなりますが、「親戚」という共同体のスケールに、我々ヒトとタコ、ヒトとシャコ、ヒトと魚群は「同じカテゴリー」になりえるのです。
ヒトは、親戚同士どころか、親子や兄弟でも喧嘩をするし、ときには右脳と左脳の連携が取れないこともあります。だから、タコやシャコと遠い親戚だからといって、そう簡単に分かり合えはしないでしょう。簡単に分かり合えないどころか、分かり合うは永遠にないかもしれません。しかし、バラバラな感覚と行為を、バラバラな脳でどうにか統御しようと苦労しているという「問題」は、数億世代の隔絶を挟んでもなお、「我々」を同じカテゴリーに包括するのです。
現代の生物学が依拠するパラダイムは進化論であり、進化論は既述のとおり環境のスケールの考え方です。個別の生物個体を研究する際には、とうぜんパーソナルなスケールがクローズアップされ、場合によってはヒト以外の生物種による共同体のスケールが採用されることもあります。
教養は、人類史のなかでヒト同士を分断するものとして機能することもありました。その様子をメタ的に捉えるためには、このように「環境/共同体/パーソナル」の3つのスケールを切り替えながら眺めることが有効なのです。
(次回へ続く)
「集団間差別の発生・発現に関わる心理過程についての 実験的研究」柿本敏克、1997年
『時間の分子生物学 時計と睡眠の遺伝子』粂和彦、講談社学術文庫、2022年
『生物学者のための科学哲学』コスタス・カンプラーキス・トビアス・ウレル 編、 鈴木大地・森元良太・三中信宏・大久保祐作・吉田善哉 訳、勁草書房、2023年
『タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源』ピーター・ゴドフリー=スミス、夏目大 訳、みすず書房、2018年
『メタゾアの心身問題――動物の生活と心の誕生』ピーター・ゴドフリー=スミス、塩﨑香織 訳、みすず書房、2023年
『実力も運のうち 能力主義は正義か?』マイケル・サンデル、 鬼澤忍 訳、 ハヤカワ文庫NF、2023年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)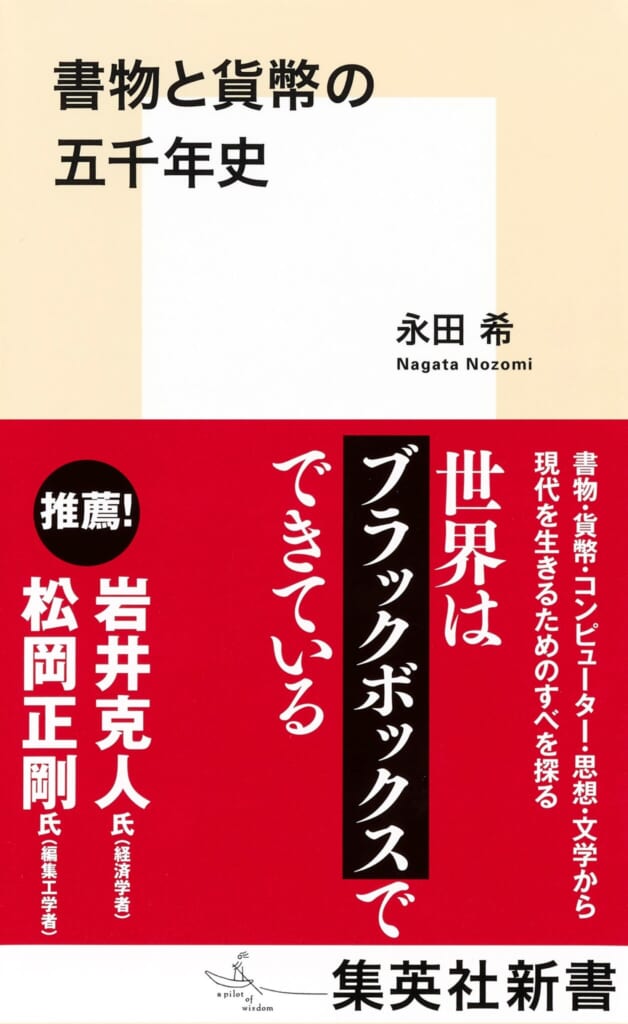










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

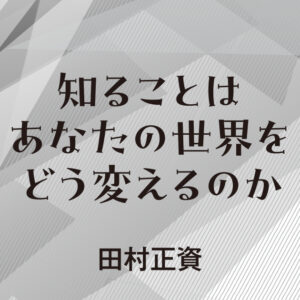
 田村正資
田村正資