情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。
現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日発売の新書『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載。
第1回目は、コンサルティング会社に勤める傍ら2017年に小説『構造素子』(早川書房)でデビューし、今年の7月には、SF小説を書くことで未来の世界を構想するコンサルティング手法「SFプロトタイピング」の理論と実践を記した『未来は予測するものではなく創造するものである−考える自由を取り戻すための<SF思考>』(筑摩書房)を上梓したSF作家・コンサルタントの樋口恭介氏との対談。SFにおける認識の話からSNS、ホラー小説、労働問題までを横断したこの対話は、「ブラックボックス」が溢れた時代に「ブルシットジョブ」(どうでもいい仕事)に飲み込まれないための方法を探る。
(構成:仲俣暁生)
■SFプロトタイピングとリバースエンジニアリング

(樋口恭介 氏)
樋口 永田さんの今回の本、情報技術の歴史をガーッと遡っていく前半の仕掛けは正直、メッセージをうまく掴むことができなくてちょっと謎に感じていたんですが(笑) プラトンやボルヘス(註1)の話が出てくるあたりから、哲学史の正統的な流れに則りつつブラックボックスに取り囲まれた現実を読み解いているんだな、と納得しました。あと、単純にSFが好きというのもあって、とにかくSFの話をたくさんしているのがいいなと思いました(笑) SFというまったく想像上のフィクションを読み解くことが、現在実際に起きている事象を理解することへとダイレクトにつながっていて、その根幹にはプラトンが言っていたような人間が認識できるすべての物体は不完全だという「認識の限界」があり、世界はすべてがブラックボックスなんだよ、という根本的な話に至るところが非常に刺激的でした。
註1:ホルヘ・ルイス・ボルヘス 夢や迷宮、無限と循環、宗教・神といった幻想的な作品で知られる作家。
永田 ありがとうございます。樋口さんのデビュー作『構造素子』を読み返したんですが、組み立てられたものを解体していく「リバースエンジニアリング」という概念がとても印象的でした。こんどの本で情報流通の歴史を超高速で遡ってみたのは、現代社会を構成する様々な事象をブラックボックスとして再発見し、その中身を開けていくこと(リバースエンジニアリングすること)でライフハック的に作り変えていくことを意識してみたんです。
樋口 ウィリアム・ギブスン(註2)の有名な言葉、「未来はすでにここにある。ただ均等に行きわたっていないだけだ」にも通じる話ですね。未来はまだ目に見えていないだけで、実は潜在的にはつねにすでに存在している。目の前にあるブラックボックスに手をつっこんで探ってみれば、いろんな未来が出てくるよ、と。いま永田さんがおっしゃった「リバースエンジニアリング」という言葉は、そういう風に、ブラックボックスに積極的・主体的に関わっていく営みなのだと理解しました。
註2:アメリカのSF作家。1980年代にコンピューター・ネットワークやテクノロジーが人間に与える影響を主題とした作品を多く発表しSFの1ジャンル『サイバー・パンク』の旗手としても知られる。

永田希 氏
永田 今日は様々な事象をブラックボックスとして捉えなおすといったお話を、樋口さんのSFプロトタイピング論に結びつけていけたらな、と思います。
樋口 僕のSFプロトタイピング論は既存のものとは少し変わっていて、かなり「スペキュラティブ(思弁的)」という概念に寄っています。プロトタイピングの思想としては、SFプロトタイピングに近しいものとして「スペキュラティブ・デザイン」(註3)と呼ばれる手法があって、それらはゼロからクリエイトする、今まで世の中に存在しなかったものを存在たらしめる行為なんですが、その考え方からかなり影響を受けています。既に存在している「飽き」のきたものではなく、スペキュラティブな仕方で、見たことのないような面白いものを作り、現実を覆っている「飽き」を破壊していくこと。僕の考えるSFプロトタイピングとは基本的にそのようなものです。でもその一方で、先ほどの「ブラックボックス」の話を聞いていて思ったのは、自分自身の目をスペキュラティブにすることでも現状の閉塞感を打破していくことはできる、ということです。つまり、既にあるものを別の角度から読み解く行為、いわば「批評」によっても新しい現実は作られる。別の目をもって現実から別の現実を取り出すことで、現実を複数化することはできる。そしてそれは、未来を創造する営みと等価であるということです。外部に世界をスペキュラティブに創るのではなく、自分自身をスペキュラティブにすることで、世界を創り替えるということ。言ってしまえば、「SFを作るんじゃなくて、おまえ自身がSFになるんだよ」ってことです(笑) 永田さんの今度の本は、歴史や現代の様々な事象を一度「ブラックボックス」に放り込み、そこから別の側面をどんどん切り出していくので、そういう意味での「批評」であって、広義の「スペキュラティブ・フィクション」ですね。内容に触れていくと、たとえば、僕も大好きなテッド・チャン(註4)の「あなたの人生の物語」(同題の短編集に収録)の話が出てきますが、あれはまさに「自分の目を変える」話だと思います。語り手である女性科学者は自分の娘に訪れるすべての運命を知りつつ、その悲劇を記述することを選びとる。語り手はすべてを知っているから、語り手の中では未来と過去が折り重なっている。それは執筆の体験そのものであり、読書体験そのものであり、あれは自分の人生が「生きられる書物」に変わるという話だと言えます。煎じ詰めると、あらゆる書物に書かれていることは「過去」である。しかしそれは、これから読者によって経験される「未来」でもある。書物を読み解く行為とは、既に終わった過去を追体験することであると同時に、その経験によって別の角度から過去が見えるようになり、その結果主観的には未来がちょっとだけ変わるという、原理的に批評的な行為です。
註3:未来のありえる可能性を提示し、問いを創造するデザインの手法。
註4:中国系アメリカ人のSF作家
永田 批評とフィクションは樋口さんの書評集『すべて名もなき未来』(晶文社)でも軸にされていた考え方ですね。とても共感します。また、「スペキュレイティブ」という語に「投機的」というニュアンスがあるのもとても興味深いと思います。ところで、本を読んでいる間の読者は、主観的には「作品世界」の内にいるわけです。『書物と貨幣の五千年史』でも引用したギブスンの『ニューロマンサー』(註5)における「ジャックイン」の話です。サイバースペースと現実空間との間で行き来が行われるだけだから、真の意味ではジャックインではないとも言える。一方、フィリップ・K・ディック(註:6)の作品では両者の際が混濁していき、そこがいいという話です。でもサイバースペースで流れる時間を「本を読んでいる時間」になぞらえるなら、人はそこでは身体を意識しない状態になっているわけで、主観的時間においては「ジャックイン」(没入)している、と言ってもいいんじゃないかと思うんです。
註5:超巨大電脳ネットワークが世界を覆う近未来を舞台にしたSF。作中では、電脳世界「マトリックス」に意識ごと入り込むことを「ジャックイン」と呼ぶ。
註6:アメリカのSF作家。代表作が数多く映像化され『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』(映画『ブレードランナー』原作)や『トータル・リコール』、『マイノリティ・リポート』などの作品で知られる。
樋口 認知の点からは没入(ジャックイン)していますね。人は複数の世界を同時に認知できないから。
永田 そう、しかも人はその「ジャックイン」の時間を経由してしまうことで、根本的に変わってしまう。パソコンにマルウェアがインストールされたりハックされたりするように変わってしまうんじゃないか、って。
樋口 ミームによって汚染されてしまう、とか。
永田 そう、まさに「汚染」される感じがあると思うんです。
■一貫性のある時間から、断片化した時間へ
樋口 近年は情報技術が発展して可処分時間が少なくなっていくなかで、コンテンツの断片化が起きていますよね。TwitterやTikTokでわずか百何字のツイートとか10秒の動画が繰り返し流れてくるけれど、Twitterの一つのツイートを読んでいる間はそのことしか考えてないし、TikTokの一つの動画を見ている間はその動画のなかに自分の認知が埋没されている、という状態になっている。その瞬間瞬間は別世界へのジャックインを繰り返しながら、世界や時間を認識するようになってきている。
永田 それがまさにデヴィッド・グレーバー(註:7)のいう「ブルシットジョブ」の問題だと思うんです。僕も普通のサラリーマンだったことがありますが、多くのサラリーマンの仕事は誰かが企画したプロジェクトのなかで、淡々と分業体制の歯車として働くことが期待される。なぜこの仕事をやっているのかわからない状態でするのがブルシットジョブの最たるものだけど、そのときに目の前にある仕事がどういうグランドデザイン(全体構想)の基に成立しているのかわかれば、ものすごく楽観的に言えばやりがいが出るんじゃないか。グランドデザインまで遡ってリバースエンジニアリングするのは簡単なことではないし、その結果、大本からしてブルシットだったと判明する可能性もあるわけですが(笑)
註:7 アメリカの人類学者、アナキスト。『ブルシット・ジョブ−クソどうでもいい仕事の理論』は昨年邦訳され日本でも話題に。2020年没。
樋口 それは滅茶苦茶ありますね。大体がそうだと思う。
永田 でも、それに気づくことなく考えることをやめてしまうと、映画『花束みたいな恋をした』(註:8)の主人公の麦みたいに、学生時代は文化に触れたり趣味に没頭する生活をしていたはずが、会社員になるとブルシットジョブで疲れてスマホゲームの「パズドラ」で時間をやり過ごす、まさにブルシットな人生になっていく。すごくポジティブなことを言えば、グランドデザインをする側になれれば、少なくとも当人にとってその仕事はブルシットじゃなくなる。でも凡人は、ただ話がデカいだけで大したことはできないから、結局はブルシットなグランドデザインしかできない。そのときにぶっ飛んだ面白いことを作るのが樋口さんの言う「SFプロトタイピング」だと僕は理解しています。
註8:2021年公開の日本映画。菅田将暉演じる麦と有村架純演じる絹という二人の男女が出会い、ともに暮らすようになるも、仕事に忙殺されすれ違っていくさまを5年のスパンで描く。
樋口 なるほど。
永田 パズドラやTikTokにハマるひとが多いのは、部分最適だからでしょう。憧れるものごとや束の間に集中できる何かに関わる幸せな「断片」に自分を同一化させる、その瞬間だけ、ブルシット人生から離れられているような気持ちになれる。そういう主観的時間を体験しているときに「それって違くね?」と言うのが樋口さんのいう全体最適思考ですよね。でも全体最適はグランドデザインをどこまで捉えていくかによって無限に拡大していく。選択肢が無限にある中で、なにを全体とするかを仮に決めて有限化しないと、とりかかれない。
樋口 そうですね。全体最適的な思考は近代の産物で、耐用年数が切れつつあるというか、少しずつその感覚が崩れてきている気がしています。最近まで、自分のなかにもそうした「全体最適であろうとする意識」がずっとあったんです。でも逆に、あまりにも全体を見ようとするから不安になるのかも、と考えはじめたところです。たとえば、小林泰三の「酔歩する男」(註:9)というホラー小説があります。まあ筋だけ言ってしまうとホラーというより明らかにSFなのですが、この作品がなぜ怖いのか、ということを考えると、それはたぶん、われわれ近代人が、全体性のある世界とか一貫性のある時間みたいな、事象と事象の緊密な結びつきに触れられるのを自明視しているからだと思ったんですね。「酔歩する男」はその結びつきがばらばらになり、自分が知っていたはずの世界が手元から離れてしまうことで恐怖が生まれる、そういうホラーなんです。ところがいまの若い人とかがこれを読むと、僕が初めて読んだときよりもあんまり怖く感じないのではないか、ということを思います。いまはTwitterとかTikTokが当たり前になって、瞬間瞬間の認知が断片に奪われ続ける世界になっている。そこでは新しく情報が生まれても部分が生まれ続けるだけで、統御された全体性みたいなものには全く寄与しない。「全体の認知」がもはや自明視されていなくて、現実って普通にそういうものだよね、みたいな話になってきている気がします。そういえば永田さんの『書物と貨幣の五千年史』のあとがきにも、時間というものを線としてではなく、ランダムアクセス可能な点の集まりとして捉える話が出てきますよね。時間については僕もかねがねそういう感覚をもっているんです。
註:9 1999年に刊行された『玩具修理者』に収められた短編小説。主人公、血沼壮士は大学院時代の友人を名乗る小竹田丈夫という男にバーで話しかけられる。そこで語られたのは菟原手古奈という女性を学生時代に取り合ったこと、そして彼女が死んでしまったことだった。やがて、二人は脳の器官を破壊することでタイムトラベルを試みるようになる。
永田 時間論として「酔歩する男」を読むと、基本的には語り手2人のそれぞれの「生きている時間」をリアルタイムで読んでいく感覚がある。ところが2人が自分の脳をいじり始めたタイミングで物語そのものが個人のそれぞれの「生きている時間」から、誰のものでもない「時間という概念」に移り変わってしまう。つまりそこで本作は「永遠性」の話になるんです。すべての時間(永遠)のなかに、語り手2人の時間(生きる時間)がある、という入れ子構造になっていく。「生きる時間/永遠」の二項対立は僕の本のキーとなる概念です。そこに他者性を採り入れて「自分/他者」の軸を加えた四象限にできる。個人それぞれの生きる時間(主観時間)、個人それぞれの永遠(客観時間)、他者による永遠、他者の生きる時間。「酔歩する男」のオチまでに読者がたどる展開は、こう図式的に捉えてみるとわかりやすいのかな、と。「酔歩する男」では語り手2人それぞれが、相手の「生きる時間」を経験する。つまり、他者の「生きる時間」を経由することで、他者の「永遠」性に到達していく、というのが僕の読みなんです。
樋口 なるほど、そう考えるとすべての書物は「他者の永遠」ですね。
永田 書物もそうだし、恐らく貨幣もそうなんです。「酔歩する男」の主題である脳と時間、記憶モデルもそうですね。右目で「永遠(グランドデザイン)」の世界、いわば常世を見て、左目で「生きられる時間」の世界(現世)を見る、その視差で両方の世界が入り混じっていく感じが大事なのかなと思います。僕の言うブラックボックスは、その視差のことなのかもしれません。
■グランドデザインVSボケ
樋口 この話はさっきのテッド・チャンの話にもつながるかもしれません。たとえば、短編集『息吹』に入っているテッド・チャンの「商人と錬金術師の門」という作品も、書物よりも現前性の高いかたちで、世界そのものであるかのように見えるもの――自分が経験してきた過去のできごと――にふたたび触れることによって「自分の目が変わる」、つまり認知が変わる、という話です。「あなたの人生の物語」も、過ぎ去った時間も別の解像度で見ることで一貫性のレベルを変えていくといいことも見つかったりして、人生捨てたもんじゃないよねという話ですが、その根底には「時間を感覚する人の認知には一貫性がある」という前提がある。それに対して「酔歩する男」はまだ覚えている経験を何度も繰り返すうち、その事象がバラバラになっていきます。「これはいつ・どこで起きたことなんだ?」「これは誰が経験したことなんだ?」「そもそも俺は誰なんだ?」というように、一貫性のある認知や自己同一性が揺らぐことでホラーとして成立する――まあ、ようするに「酔歩する男」という小説はボケの恐怖を書いた話だと思うんです。 ところが、最近読んだ円城塔の「男・右靴・石」(註:10)という短編では、もはや一貫性とかそんなに信じなくてもいいんじゃないですか、別にボケてもいいんじゃないですか、というかわれわれは、そもそも普段から実はボケボケなんじゃないですか、みたいな価値観が提示される。「男・右靴・石」の探偵の思考を追っていくと、論理的に整合性があり、合理的に納得できる一貫性のあるストーリーで仮説を作っていくという行為が、ものすごく馬鹿馬鹿しいことのように思えてくる(笑) 「男・右靴・石」がやっていることは、構造的には「酔歩する男」と同じなのに、かたや恐怖小説として、かたや奇妙なギャグ小説のように読めてしまうという、不思議なことが起きているわけです。なぜこの小説がホラーにならないかと言うと、それはおそらく、世界はそもそも不思議だし、人間はそもそもボケているし、人間は気づかないこと・忘れてしまうこと・思い込みによって解釈してしまうことが多すぎる、ということだと思うのですが、僕の感覚としてはこっちの認識のほうが正しい気がします。小説の中で描かれていることは、エピソードとしては意味不明ですが、僕もかなりボケている人なので、まあ、語り手も含めて登場人物全員の主観がボケボケで当てにならない可能性も思うと、そういうこともありうるよな、と割とすんなり受け入れてしまうところがあります。
註:10 2020年2月に雑誌「MONKEY」で発表された小説。あるホテルの一室から男が消え、右靴と石が残されていた。そこに現れた探偵は、推理をせずにただその状況を事実として確認し、口に出すことしかしない。一方、同行した記者は男が消えたことに対して自説を展開していく。
永田 円城さんの「男・右靴・石」は、いわば「ボケ散らかして終わる」っていう話ですよね。一貫性をちゃんと突き詰めた結果、ボケのところに出てしまった、という。
樋口 そうそう。正直に語ろうとすればするほど一貫性なんてとれなくて、どんどんボケてるみたいに見えちゃう、ということはあると思います。流通している多くの小説で一貫性のあるように見えるところは、たいがい、編集的な情報操作の賜物であり、作家や編集者が底力を出して無理やりがんばっている(笑) 小説って、何日も何ヶ月にもわたって書いていくものなので、そのあいだ自分が考えていることとかどんどん変わっていくんですよね。だから、本当に自分に正直に小説を書いていくとひたすら話は飛ぶし矛盾はするし、一方変わらない思想みたいなのは繰り返されるし、といったようにボケが出てきて、読者はたぶん「なんだこれは?」「作者は狂っているのではないか?」って思う。近代人は基本的にみんな、ボケとボケ以外で考えていて、普通の状態はボケではないと思っているから、ボケが出てくるとびっくりしちゃうわけです。伊藤計劃(註:11)が「つぎはぎという王国から」という短いエッセイ(『伊藤計劃記録II』収録)を書いていて、これは人間の意識とは生物として進化する過程で一貫性のある意識を持っていたほうが生きやすいから、場当たり的な適応の結果として得たものにすぎない、という進化心理学な話なんです。その最後で伊藤計劃も、ボケの話をしているんですよ。「つぎはぎの心が見た、つぎはぎの解釈でしかないのが、実はわれわれが見ている現実なのであって、認知症やアルツハイマーを患った人が病院や施設で暮らさざるを得ないのは、彼らがボケて、われわれが正しく現実を把握しているからではなく、それはある種の現実で、われわれとは異なる現実を持つ人々をいかにして囲い込むかという政治の問題にすぎないのだ」みたいなことを書いている。ボケにはボケの世界観っていうのがあるはずなんです。
註11:日本のSF作家。2007年『虐殺器官』でデビュー。翌年、第2作目長編『ハーモニー』を刊行するも、2009年に逝去。2012年には生前書いていた原稿をもとに円城塔が続きを書く形で共作『屍者の帝国』が発表される。
永田 自分が正気だと思っている人は、自分のことをツッコミだと思いがちだけれども、結局、別の仕方でボケてるにすぎない、みたいな話ですね(笑)
樋口 永田さんが『書物と貨幣の五千年史』で、ブラックボックスの話をしているのも、そういう話なんじゃないかなって。不可視化されたものや断片化されたもののなかで、俺らはボケてるし、これからもボケ続けるぜ! みたいな。 認知がボケたままでもいいと。
永田 はい。それはその通りと言っていいと思います。これは余談ですが、ファーウェイという中国の携帯電話企業が、米中貿易戦争のあおりをくらってグーグルのAndroid OSを入れられなくなったでしょう? その代わりに彼らが作ってすでに実装され始めているOSの名前はHarmonyっていうんですよ。伊藤計劃の『ハーモニー』(註:12)と同じ名前で、それを知ったときは鳥肌が立ちました。もうバージョン2まで出ていて、IoTを視野に入れている。ファーウェイの技術者が本当に伊藤計劃を読んでいてほしいなと思います。
註12: 世界中で戦争と未知のウィルスが蔓延した「大災禍(ザ・メイルストロム)」によって従来の政府機構が瓦解し、新たな統治機構「生府」によってすべての人々が社会のために健康で幸福であることが義務付けられた近未来を舞台にした小説。
樋口 実際に読んでいる可能性はかなり高いですね。しかもディストピアをユートピアとして読んでいる疑惑がある(笑) 『世界SF作家会議』という番組で、『荒潮』という作品を書いている中国のSF作家・陳楸帆(スタンリー・チェン)と喋ったことがあるんです。そのとき彼は、コロナ禍によって粉々になっていく社会をどう統御すればいいかという話の流れで、「伊藤計劃は『ハーモニー』で新しいユートピアを描いて皆が幸せになれる新しい社会を提示してる」と言っていた。それを聞いてかなりビビりました。中国人はけっこう本気で統制された社会をよいものと思っているフシがあるな、と思ったんです。
永田 たしかに、ポスト・コロナで中国が覇権を握った世界として『ハーモニー』を読み直したら、すごく面白いかもしれない。
樋口 中国人はやっぱり全体的な指向性というか、近代の論理的な一貫性を重視している。中国のSFにはスペキュラティブ・フィクションっぽいものは少なくて、ガチのサイエンス・フィクション、科学で社会をイノベートしていくぜ、という小松左京的な感じがメインストリームなんですね。文化的な違いなのかどうかはわかりませんが、その一方で最近の日本のSFは円城塔みたいに、登場人物がみんなボケボケでわけがわからなくなっていたりする(笑)
永田 習近平の「一帯一路」(註:13)は完全にグランドデザインですし、危機の時代に全体主義というのはやはり強い体制なんでしょうね。
註13:習近平が2013年に打ち出した、アジアとアフリカ、ヨーロッパを陸路と海路でつなげることで、貿易を活性化させ経済成長を目指す構想。
■サラリーマンは皆「ホラー的存在になれ」
樋口 会社組織も従業員が1万人を超えると、社長は一人一人の社員の顔まではわからないから、ツリー構造になって中間管理職が生まれてくる。その中間管理職は中間管理職として採用されるから、現場のことはわからないし会社の理念も正直わからない、中間管理だけ一生やらせていただきます、みたいな感じになる。もちろん、現場も現場のことしかわからない。
永田 そうやってどんどん仕事や組織がブルシット化していくと。
樋口 でも会社全体でやっていることはデカいから、情報の流通量もすごく多くて、しかもその情報一つ一つが断片化されている。業務の枝葉些末な部分は、最終的に派遣社員やバイトを使って頑張るしかないけれど、一度そうしてしまうともう単価を上げられないから、永遠にそうするしかない。その構図のなかで、よくわからない情報が生産され続けてももう逃れることができなくなって、人が代替わりするとさらにブラックボックス化が進み、誰にもそのシステムを止められず、なんだかよくわからないまま「辛えなあ」とか思いながら過ごしていく感じになるんです。
永田 すごいリアリティがある話ですね(笑)
樋口 その一方に、情報の処理を自分の身体的レベルにとどめておけば絶対にブルシットジョブは生まれない、という逆説がある。ようするに人間は少なめのほうがいい、小規模生産体制でやればいいという話なんですが、サラリーマン的な視点でいくと、それでいいんじゃないですかね。数人程度のベンチャーが世界的にやばいことをしているみたいなことは普通にあるし、ビジネスにおいては作り手と使い手が分かれているとブルシットジョブ的な再生産モデルになってしまう。作る人は使うし、使いたいものがあれば自分で作る、というのがいいと思うんですよね。
永田 なるほど。「人間は少ない方がいい」って『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』で宇宙の人口を半分にしてしまうサノスとか、『キングスマン』1作目の悪役で地球環境のために世界規模のテロを目論むヴァレンタインみたいな、人類の人口を減らす規模の話かと思いました(笑) 組織を小分けにしていくという話ですよね。
樋口 だから『書物と貨幣の五千年史』をサラリーマンが読んだとしたら、「生産者はブラックボックスを作らない」という教訓を得られると思います。
永田 あるいは、「おまえがブラックボックスになれ」と。
樋口 えっ、どういうことですか。
永田 自分がブラックボックスの外にいて、ブラックボックスを作るんじゃなくて、もう自分ないしは自分たちが、一つの完結性をもったブラックボックスを目指せばいいんじゃないかと。
樋口 たしかに、今度の永田さんの本でも触れられているAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)など、クラウドサービスのビジネスモデルは完全にそれですよね。AIもブラックボックスの中は全部企業秘密で、だけど超便利だからみんな使ってね、みたいなことになっている。だからアクセス障害があると、マジでどうなっているかわからないから、ユーザーはもう途方に暮れて待つしかない(笑) ピーター・ティール(註:14)の『ゼロ・トゥ・ワン――君はゼロから何を生み出せるか』に書いてあることって、ようするに「ボッチ」でいろ、ということだと思うんですよね。誰もいないところに行って、そこでビジネス作ってみんなに教えてあげて自分の村を作る。そういうオンリーワンであり続けるということは、まさに自分をブラックボックス化せよってことですよね。
註14: ピーター・アンドレス・ティール。電子決済サービスPay Palの創業者であり、アメリカのシリコンバレーに大きな影響力を持つ投資家。
永田 なるほど。まさかピーター・ティールも同じことを言っていたとは。
樋口 ピーター・ティールは、「誰にも追いつけない速度で駆け抜けろ」みたいなことを言ってると思うんですね。外部に出て、追いつかれたらさらにその外部に出ろ、と言い続けている。「自分をブラックボックス化せよ」というのもそれと同じで、まず誰にもわからないことをやって、誰かがわかり始めたらまたほかのわかんないことをやれ、というかなり極端な教えを説いている。
永田 そのメソッドをサラリーマンが実践してくれたら面白いですね。部下が一斉にブラックボックス化したら、管理職は辛い気持ちになるかもしれないけれど(笑)
樋口 でも、管理職はいらないという話は90年代ぐらいからずっと言われているじゃないですか。それこそオープンソース・カルチャーの聖典である『伽藍とバザール』なんて、中間管理職みたいなのはもう要らない、自分で作れみたいな話だったでしょう。そういうハッカーカルチャーみたいなものが、やっと普通のビジネスパーソンにも「ああ、いい感じだね」となってきてるのがここ最近で、フレデリック・ラルーの『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』(註:15)などもそういうふうに読まれている。あの本で言われているのは、要するに生産者と消費者が一致する生活協同組合モデルです。そういう共産主義的な思想から出てきた仕組みがビジネスにも役に立つよ、っていうことだと思うんです。最近では超バズワード化しているDX(註:16)も「ユーザーが直感的にやっているうちに業務がうまく回っていくようなモデルを、ミニマルなサイズでバンバン作っていこうぜ」というのが基本的なコンセプトだから、やっぱり根本はハッカーカルチャーなんですよね。DXはいまでは保守的な大企業の中の一時的な流行みたいになっていますが、本質的にはアナーキーな思想だと思います。
註15:社長や上司が細かにマネジメントせずとも、個人個人がルールを理解し目的を持つことで組織が成長するという組織論。
註16:デジタルトランスフォーメーションの略。IT技術によって会社の業務や社会を根本から変革すること。
永田 でも、いま流行しつつあるそうした理想像は、現実とは乖離しているわけですよね。現場のサラリーマンは、そうはいっても管理職の顔をうかがわないと……
樋口 まあ、そういう会社からはみんな辞めていって、潰しちゃえばいいんじゃないですか(笑) みなさんどんどん転職して、自分にとって都合のいい環境に身を置いていくべきだと思います。あるいは最近だと副業が普通に流行っていて、会社勤めは週休3日でやったほうがいいみたいな話があるでしょう。自分がサラリーマンとして働きながら作家としてやっているのもそうだし、いまはUber Eatsとかのギグワークをしている人もたくさんいる。まあそれも搾取ビジネスだと思うので、反資本主義的な観点からすると褒められたものではないけれど、そうやって仕事の流動性が増すこと自体は多分いいことだし、他人から見たら何しているかわからない人が社会にどんどん増えていくのもいいことな気がしますね。
永田 副業は会社側から見たらまさにブラックボックスですね。
樋口 それと同時にホラーでもある、と。僕自身、会社に勤めながら執筆をしているけど、会社からしたらなにをしているかがわからないブラックボックスだし、普段小説読まない会社の人が興味本位で僕の小説読んでみたら、たぶん意味不明だと思うので、かなり「ホラー的存在」だと思うんですよ。
永田 ブラックボックスがあふれた組織で「ブルシットジョブ」に飲み込まれないために、これからのサラリーマンは皆「ホラー的存在になれ」と(笑) そうなったとしたら、だいぶ楽しい社会になりそうです。
次回の更新日は9月27日(月)
農業史研究者の藤原辰史 氏との対談をお届けします。
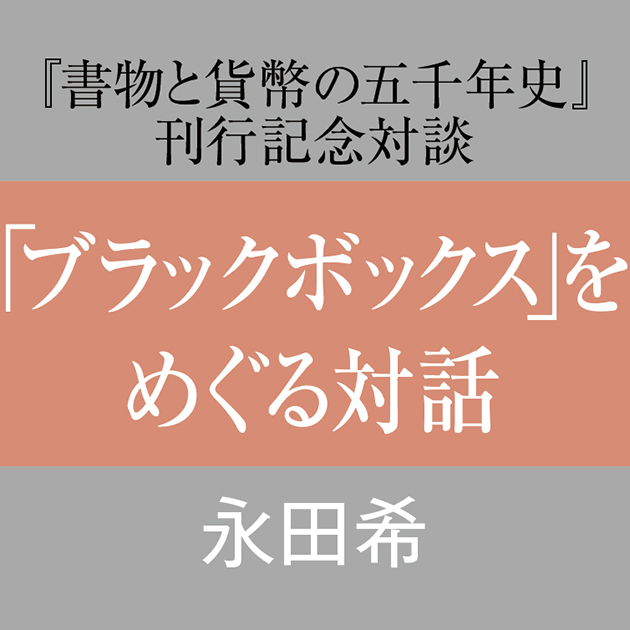
情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。 現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売される『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。
プロフィール

永田希(ながた のぞみ)
著述家、書評家。1979年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ。
書評サイト「Book News」主宰。「週刊金曜日」書評委員。
「ダ・ヴィンチ」ブックウォッチャーの1人として毎月選書と書評を担当。
著書に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス)。
樋口恭介(ひぐちきょうすけ)
SF作家、コンサルタント。外資系コンサルティングファームに勤務する傍ら、スタートアップ企業Anon Inc. にてCSFO(Chief Sci-Fi Officer)を務め、多くのSFプロトタイピング案件を手がける。
単著に長篇『構造素子』 (早川書房)、評論集『すべて名もなき未来』(晶文社)、『未来は予測するものではなく創造するものである』(筑摩書房)。


 永田希×樋口恭介
永田希×樋口恭介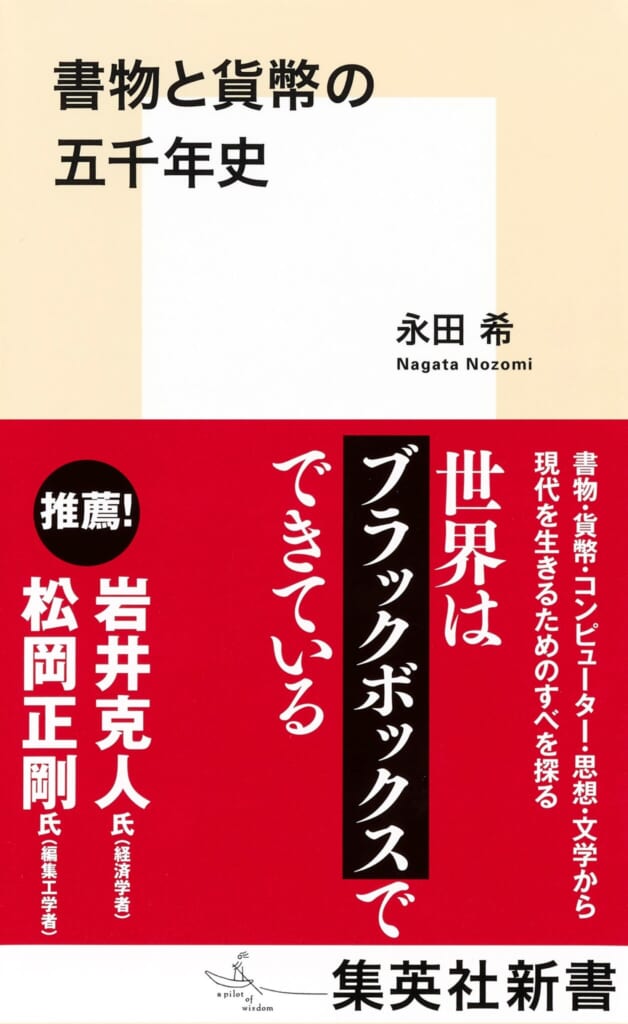










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


