3 日本の「冷たさ」について
とはいえ、東アジアの同世代と付き合っていると、やはり日本の立場については気まずい思いをすることが時々ある。ある日、語学学校で台湾人の女の子から「台湾が日本の植民地だったのはなんで?」とたどたどしいスペイン語で質問を受けた。
こうした質問は、彼女からだけでなく、一緒にバルで飲んだ韓国人のGからも、中国人のFからも言われたことがある。かれらとしては、議論を吹っかけたいわけではなく、おそらく日本のサブカルチャーや日本人の友達を通して日本に親しみを持っている一方で、日本政府や政治家たちの過去の歴史を顧みない強硬な姿勢には違和感があり、その二つの日本の不一致の感覚から、率直な疑問として、こういう言葉が時折出てくるのではないか。
自分でも納得のいく答えをかれらに返せぬまま、日本から持ってきた野坂昭如の短編集『アメリカひじき・火垂るの墓』で「火垂るの墓」を最近読んだ。作中に出てくる戦争中の大人たちの態度、その「冷たさ」の描写が頭に残った。
ぼくよりも下の世代は高畑勲監督のアニメ版のほうから知った人が多いのではないかと思うが、これは、神戸空襲で母を亡くし、父の消息も分からなくなっている状況で、幼い兄妹清太と節子が困窮生活を送り、大人たちは助けてくれず、最後は二人とも衰弱死するという、戦時中から敗戦直後までを描いた物語である。

兄妹は、母を亡くしたあとまず遠戚の家に居候するが、その家のおばさんから日々つらく当たられ住んでいられなくなり、清太は妹と二人だけで防空壕で暮らすことを決意する。その旨をおばさんに伝えると、彼女は「はあ、まあ気イつけてな」と「とってつけたような笑顔うかべ」すぐ家のなかへ入ってしまう。おばさんは、日常的に兄妹に嫌味を言ってはいじめ、子ども二人がどこへいくとも告げずに家を出ようとしても、心配もせず、なぜか愛想笑いだけはする、という、独特な冷たさが描きこまれていると思う。冷水のようなはっきりとした冷たさではなく、それよりは少し「ぬるい」。「冷たい」ことを一瞬感じさせない、相手に追及されないようにする効果を持った、そんな微妙な温度の「冷たさ」だ。
日本のTwitter上ではアニメ『火垂るの墓』の清太と節子が衰弱死したのはかれらの自己責任だ、というような書き込みが見られる。日本人がなぜ外国の人たち、とくにアジアの人たちにあのようなことをしたのか。その答えからそう遠くないところに、原作「火垂るの墓」で描かれたおばさんのような「普通」の大人たちの「冷たさ」があり、それはいまにも通じる問題として、日本社会の見えづらい部分にまだ焼け残っているような気がした。
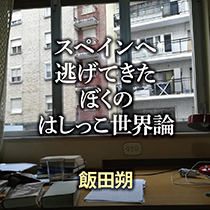
30歳を目前にして日本の息苦しい雰囲気に堪え兼ね、やむなくスペインへ緊急脱出した飯田朔による、母国から遠く離れた自身の日々を描く不定期連載。問題山積みの両国にあって、スペインに感じる「幾分マシな可能性」とは?
プロフィール



 飯田朔
飯田朔









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

