1.「地方移住の民主化」とZ世代
本連載では第5回と第6回にわたって、イケハヤ氏の移住論を取り上げた。『まだ東京で消耗してるの?』(幻冬舎新書)が出版されたのは2016年。イケハヤ氏が移住先で仕掛けたさまざまな取り組みは現在、その多くが行われておらず、その移住について「失敗だった」と見る向きもある。
しかし、個人の動向にブームは影響されない。全体としての「移住ブーム」はいわく言い難い”熱量”をもって生き延びている。いや、生き延びているというより、むしろ日増しに高まっているとさえいえる。「地方移住」について研究している伊藤将人によれば、図書に限っていえば「地方移住」の語が含まれた書籍は2010年代の中頃から2020年代にかけて急増、新聞記事では1970年代以降から現在まで波を描きつつも右肩上がりで記事が増えているという。
伊藤氏はこうしたことを捉えて、「地方移住ブーム」がほぼ30年の間継続して起き続けていることを指摘するが、一つの追い風になったのがコロナ禍だ。「ウィズコロナ」あるいは「アフターコロナ」という言葉に後押しされて、「テレワーク」「リモートワーク」といった働き方が急速に浸透した。大都市にあることが多い会社に通わなくていいのであれば、わざわざゴミゴミした都会(あるいはその周辺の郊外)に住む必要なんてないのではないか?空気もきれいで、食べ物も美味しくて、物価も安い地方に住めばいいのでは?こんな期待感が生まれた。
イケハヤ氏が『まだ東京で消耗してるの?』を書いた2016年は、いくら地方で仕事ができるとはいっても、それを実現できたのは一部の極端に働き方の自由度が高い人だった。単純に言えば、IT関連のベンチャー企業かフリーランス、といったところだろうか。それがコロナ禍という思わぬ出来事から、一般のサラリーマンでも「地方移住」の(理論上は)現実的な道が開けた。いわば、「地方移住の民主化」だ。
そんな民主化の時代を体現するべく生み出された概念が「Z世代」である。
2.地方に<深さ>を求めるZ世代
もはや説明するまでもないかもしれないが、Z世代とは1990年代後半から2010年代前半までに生まれた世代のこと。これからの市場におけるマスゾーンとなる世代で、ほぼ、マーケティングの世界で生み出され流通している言葉だといってよい。タイパやコスパを重視し、他人との競争よりも周囲との協調関係を重視すると共に、環境貢献意識が高い。だいたいこんな特徴を持つ世代らしい。
このZ世代の中でいま、「地方移住」がアツい。
JA共済連は「農業に関する意識・実態調査」を行っているが、2024年の調査では「Z世代の4割超えが地方移住を希望している」とのこと。この調査は10代から50代の男女10,000人に対して行われているが、このうち全体で「地方暮らし」を希望するのが37.4%であったのに対し、Z世代単体で見ると、この数値が45.1%と高かった。さらに驚くのはZ世代の4人に1人が「農業をやってみたい」と答えているらしい。この結果を信じるなら日本の食料自給率の安定性は末長く担保されることになるが、他にも就職意向のある学生の28.1%が「就農の可能性あり」と回答したり、今後、副業や兼業をする意向がある人の半数近く(42.8%)が「農業に携わる可能性あり」と答えている。かくいう筆者も1997年生まれであるがゆえにギリギリZ世代と呼ばれる人間だが、この割合と周囲のギャップにいささか驚いている。見ている世界が違いすぎて、パラレルワールドかと思う。それとも、Z世代は胸のうちに就農体験への熱い想いを秘めているのか。
Z世代と地方でいえば、他にもいろいろな調査がある。
例えば、じゃらんリサーチセンターによる「じゃらん宿泊旅行調査」。ここではZ世代に絞って旅行・宿泊の傾向を調査している。特に興味深いのは、Z世代の旅が「移住検討」のフェーズに入ってきたということ。移住を検討するためにその土地を訪れるZ世代が増えているらしい。それだけでなく、体験型の観光や地元の人との触れあいなど、彼らの旅は他の世代に比べて地元・地域への密着度合いが高いという。
調査の再分析では以下のように述べられている。
コロナ禍の影響を受け、地域・地方への関心が世の中全体で高まる中、特にZ世代は地域の魅力や生活環境を体験し地元の人々との交流を求める傾向が見られた。
先ほどのJA共済連の調査結果ともリンクするかもしれない。これまでのバスツアー的な大衆観光から、体験やふれあいを重視する観光へ、そしてその果てには「移住」がある。地方への<深さ>が増していて、それが数字に現れている。
ちなみに、ここまで読んで「Z世代だから、という特徴なの?」と思う人がいるに違いない。私も、もはや高齢者の話のネタになりつつある「Z世代は〜〜だから」語りを繰り返すつもりはない。『Z世代化する社会』(舟津昌平、東洋経済新報社)では、「Z世代の特徴」といわれているものが、Z世代だけでなく、徐々に社会全体に広がりつつあることが指摘されている。その通りだと思う。別に1990年代後半以降に生まれたから、コスパとかタイパとかを気にしているわけではなく、時代的な変化をいち早く受けたのがZ世代だというのに過ぎない。その意味では「Z世代」が世代としてある特徴を持っているのは確かだろうが、それは他の世代と比べて異質なものだとはいえず、現代社会の一側面を色濃く表しているのに過ぎない。
「地方移住」についても全年代で興味関心が広がっている話題ではあるが、それがZ世代ではより顕著に、具体的にいえば<深さ>を求める形で広がっている、ということを指摘しておきたい。
3.ポルノグラフィ化する地方と、消費するZ世代
でも、Z世代はなぜそのような<深さ>を求めるのだろうか。
先ほどのじゃらんリサーチセンターはこう述べる。
①オンラインやリモートなど学び方、働き方が柔軟になったことで移住含め地域がより身近な存在となった。
②Z世代の三大都市圏居住率は年々高まり約6割で地域を知る機会に乏しいこと。
③地域に居を構え地域活性に向き合う若手への注目など、コロナによって「地域」というものを強く意識する機会が増えたこと。
さらっと読むとなんとなくわかった気になるのだが、よくよく見ていくと、わからないところが出てくる。単純に考えて①では「地域が身近になった」と言っているのだが、②では「地域を知る機会が乏しい(地域が遠くなった)」と言っている。そして③ではやはり「地域を意識するようになった(身近になった)」と続く。
Z世代にとって地域とか地方が遠いんだか近いんだかよくわからない。
よく考えてみると、この謎はこう読み解ける。つまり、「実態としての地域は知らない人が増えた(②)が、メディアを介した情報としては「地方」を見る機会が増えた(①、③)」ということだ。「地域活性に向き合う若手」を見るのは、だいたいマスメディアやSNSの発信によってである。TikTokを開けば、海がきれいなどこかの地方に移住した人の穏やかな日々が発信され続けている(だいたい同じ画角)。
実際としては見る機会が少なくなっているのに、メディアを介した「情報」としては触れる機会が増えている。
このメカニズムについて、社会学者の貞包英之が興味深いことを述べている。貞包氏は社会学者のゴーラーの議論を用いながら、現代において「地方」は「ポルノグラフィ化」していると述べた。ポルノグラフィとはなにか。イギリスの社会学者ジェフリー・ゴーラーによると、社会にタブーが産まれるとき、それを補うために生じるのがポルノグラフィだという。「たとえば19世紀には性が隠されていくことに逆行して、性を過剰に表現する文学や絵画、写真が発展する。他方、20世紀には死が扇情的に描かれる。医学の進歩や社会の変化によって死が日常生活から遠ざけられるなかで、それをグロテスクに表現する『死のポルノグラフィ』が映画や大衆文学で人気を集めるというのである」と貞包氏は説明する。
つまり、「地方」が現実世界からリアリティを持って失われれば失われるほど、それを補うために、逆説的に「地方」が召喚されることになる。しかも「ポルノグラフィ」という言葉からも想像が付く通り、少しばかり過激な形で。
こうして考えれば、Z世代の中で地方へ<深さ>を求める感情が高まっていることは簡単に説明がつく。先ほどの話によれば、Z世代の6割は三大都市圏に居住する。地方では少子高齢化が猛烈な勢いで進んでいることは周知の通りだ。他の世代に比べても、地方を知る人数が相対的に少ないのがZ世代なわけである。だからこそ、反動的に地方への意欲が深まるのではないか。
いわば、Z世代の中で「地方」は「ポルノグラフィ」として消費される存在になっているのではないか。
4.二極化する地方の「語り」はZ世代的環境の中で激化する
地方が「ポルノ」として消費されている、なんて書くとあまりにも大袈裟すぎるのではないか?と言われそうだ。確かにそうである。第一、私自身も二拠点生活をしており、そこに地方に対する一種の理想像の投影のようなものがないかといわれれば怪しい。しかも「地方のポルノ消費」を断罪する姿の背後には「あるべき地方移住」という考え方が潜んでいると思うが、そうやって地方への関わり方を一つの正解に落とし込むこと自体、ひどく狭い考え方である。
さらには、そうやって最初は憧れを抱きながら地方に入ってみて、だんだんと現実を知った上で本当にそこにコミットしていく人だっているはずだ。その意味ではこうした「ポルノ消費」が悪いことだとはまったくいえない。むしろ「地方消滅」が叫ばれる現在において、一筋の希望の光であるとさえいえる。
ただ、ここで私が留保したいのは、こうした「地方の消費」に含まれる危険性である。
先ほども引用した貞包氏が指摘していることに注目したい。ここでは、「地方」の存在が希薄になるにつれて召喚される「地方」についての議論が、「地方移住は素晴らしい!」という礼賛論か「地方なんて消滅する、オワコンだ」という否定論に両極化することが述べられている。簡単にいえば「地方」に関する話がエンタメ化する、ということだ。
実際、「地方」に関する語りを見ていくと不思議な現象が起こっている。「地方消滅」という議論と同時に「地方創生」「地方移住」ブームが起こっているのだ。一種の分裂状態だ。この問題はもはやネットメディアの大好物ともいえる話題であり、「地方は〇〇年後に消滅します」という記事の隣に「地方移住して幸せになった夫婦」の記事が掲載されるというカオスぶりである。
ここに、Z世代地方移住論の脆弱性が浮かび上がる。今はまだ、地方移住に対してZ世代たちはポジティブだ。しかし、もしその需要がエンタメ的なものだった場合、なにかをきっかけにその論調は大きく「地方の否定」へと急旋回する可能性がある。より地方への<深さ>を求めるZ世代だからこそ、よりその分裂が深いものになってしまうのではないか。
さらに「Z世代と親和性が高い」と言われているSNSによって、その対立は深くなるかもしれない。すでによく知られた話だが、SNS上のアルゴリズムによって、各人のスマホにはそれぞれの趣味嗜好に適合したコンテンツばかりが表示されるようになる。現代の政治状況が顕著に表しているが、こうしたSNSの構造上の仕組みによってさまざまなところで平行線の対立が深まっている。その余波は「地方」の語りへも波及するかもしれない。
もちろん、これは「仮定」の話だ。けれども、実際にすでに「地方消滅」―「地方移住」論争が勃発している。それが、より強固な形で起きてもおかしくない。私が見ている範囲であれば、現状ではZ世代による「地方」の語りは今はかなり肯定的な側面で語られている。そこには「Z世代は環境配慮意識が高い」的な「Z世代ジャーナリズム」の強い力も働いているし、SNSの使用も「地方とダイレクトでつながれる」という意味でかなり好意的に扱われている。しかし、ひとたびSNSが悪い方向に作用し、さらに人々が「Z世代ジャーナリズム」に飽きてきたころ、より厄介な、地方に対する二極化した語りの対立が発生するかもしれない。
5.「場所の消費」問題と「その場所を知っていること」
こんなことを書きながら思った。
これって逆も然りでは?と。つまり、「地方」に対する両極の語りが生まれているように、「東京」に対しても両極の語りが生まれている。Z世代による「東京礼賛」はあまり見ないが、「東京ほど暮らしやすい街はない」という人と、「東京は人間の住むところではない」という人の論争は、特にネット媒体が好むものであり、いまでもこの議論は延々と量産され続けている(筆者もその量産に手を貸している一人かもしれない)。もはやこうした議論で重要なのは、東京の都市としてのポテンシャルを云々することではなく、ただただそれを議論し続けることだ。もちろん、議論と言っても高尚なものではなく、SNSやヤフコメで一言物申す、という意味だ。まさに「ネタ」となっている。つまり「東京」も消費されているのだ。「地方」の反対語が「東京」ではないのだが、その語られ方を見ると「地方」と「東京」は驚くほど似ている。これらをまとめて、「場所の消費」問題と呼んでおこう。
でも、こうなるとこれまで話してきたことと矛盾が生じる。なぜなら、人々は東京を中心とする三大都市圏に集中して住むようになっているはずだからだ。単純に「住んでいる=知っている」だとすれば、「東京の消費」は起こりようがない。
しかし、そもそもだ。「地方を知っている」とか「東京を知っている」とはなんなのだろう。「知る」とはなんなのだろう。住んでいれば知っているのだろう。「東京を知っている人」って誰だろう。
その最有力候補は、東京について詳しい地理学者だ。地理学者はさまざまな統計データを用いて東京の地理を隅々まで調べている。だから、彼らは「東京を知っている」。しかし、それは本当に「東京を知っている」ことになるのか?
この意味での「場所を知る」ことに反旗を翻したのが、地理学に革命をもたらしたといわれるイーフー・トゥアンである。彼はそれまでの地理学がデータの集計などに基づく客観的なものに終始していたことを批判し、より根本的に人間と場所・空間の関わりや、人間の空間に対する知覚についての知見を深めた。
「場所の消費」問題を考えるときに出てくる「その場所を知っているかどうか問題」は、トゥアンの議論を参考にすると解決の糸口が見えてきそうだ。
そこで、次回はトゥアンの議論を使いながら、もう少しこの問題について考察を深めてみることにしよう。
(次回へ続く)

東京における再開発ラッシュやそれに伴う反対運動、新しい商業施設への批判、いまだに報じられる地方移住ブーム……なぜ人々は都会に住みにくさを感じるのか。全国のチェーンストアや東京の商業施設の取材・研究を続けているライター、谷頭和希がその理由を探求する。
プロフィール

たにがしら かずき チェーンストア研究家・ライター。1997年生まれ。早稲田大学文化構想学部卒業、早稲田大学教育学術院国語教育専攻修士課程修了。「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 第三期」に参加し宇川直宏賞を受賞。著作に『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』 (集英社新書)、『ブックオフから考える 「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』(青弓社)。


 谷頭和希
谷頭和希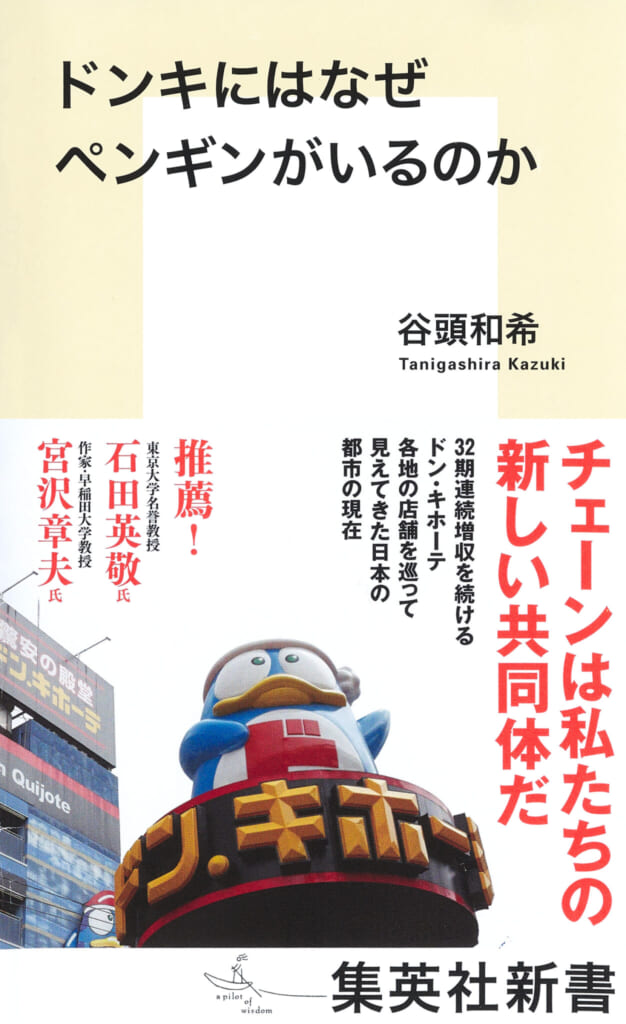










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


