「対テロ戦争」という言葉で
パンドラの箱を開いたのはブッシュ
――内田先生は、最近の欧米の論調などをいろいろ御覧になったりしていてどう感じていますか。
内田 僕はニューヨーク・タイムズの電子版と、あとフランスのリベラシオンを取っているだけなんですけれども、ニューヨーク・タイムズの論調は「とにかく即時停戦を」ということを訴えていますし、子供たちが殺されている映像も、病院や大学が爆破されている映像も出しています。宗教施設や教育施設や医療機関を攻撃するのは、どう見ても戦時国際法違反です。それを毎日やっているんだから、これを容認するのは主義主張の問題じゃなくて、人道的に許し難いことだと思います。これを傍観していてロシアのウクライナ侵略を批判することができるわけはない。
中田 あっと言う間に今、ロシア・ウクライナ戦争の死者数を超えちゃいましたからね。数週間で。
山本 今、3万人超えたそうですね。
内田 ウクライナの場合はまがりなりにも正規軍同士の戦いですけれど、ガザでは非戦闘員がためらいなく殺されている。イスラエル政府の高官がパレスチナ人のことを「ヒューマンアニマルだ」と言っていて、僕は驚愕しました。本当に分からないんですよ。イスラエルの人たちは、一体何をしようとしているんですか。
中田 本当に皆殺しにしようとしている。
内田 民族虐殺をした後に、国際社会でイスラエルがどう遇されるか、イスラエル国民が世界でどういう待遇を受けることになるのか、それについて見通しがあるんですか。
中田 いや、別に普通に……パンドラの箱を開いたのはジョージ・W・ブッシュだと思いますけどね。対テロ戦争というのを始めてしまって、あれが全世界に広まってしまいましたから。
ロシアもそれに乗って、「対テロ戦争だから、チェチェンでどれだけ殺してもいい」という話になって。「対テロ戦争と言えば、相手を全てテロリストにしてしまって許される」というふうになってしまったのは、やっぱりあそこからだと思います。対テロ戦争という言葉を使ったこと自体がはじまりです。
内田 それまでは国民国家が非国家アクターを相手に戦争をするということはなかったわけですね。
中田 というか、その前はむしろ「パルチザン」とか、むしろ良い意味だった。「テロリスト」とは呼ばれなかった。左翼が強かったときは「独立の闘士」的な言葉であったりして。内田先生の時代でも、テロリストってあまり使わず、「ゲリラ」って言われていましたよね。

内田 そうでした。「ゲリラ」って言葉を使っていましたね、確かに。テロリストというのは、僕らの時代だと、本当にそれこそボリス・サヴィンコフ(*ロシアの革命家、1879-1925。政治家の暗殺に関与、『蒼ざめた馬』などの著書がある)の用例の方が標準的でした。一人で道端に立って、権力者が来ると「一人一殺」で相討ちになる。日本でしたら、大久保利通を暗殺した島田一郎とか、大隈重信を暗殺しようとした来島恒喜(くるしま つねき)とか、そういう一人で行動するのが「テロリスト」でしたから、準軍隊組織を持って、ミサイルを飛ばすような軍事力を持つ非国家アクターを「テロリスト」と呼ぶ習慣はなかったと思います。そういう戦闘集団のことは「ゲリラ」と呼んでいましたよね。
中田 ですよね。ゲリラには、少なくとも昔だと、「造反有理」(*「反逆には道理がある」という意味の中国語。毛沢東が使い、70年安保など日本の学生運動でも用いられた)じゃないけど、それなりの理由があるという。
内田 基本的には左翼ですよね、ゲリラというのは。
中田 そうですね、そういう感じだったので、「テロリスト」というと、戦争じゃなくて、「犯罪」として語ってしまう。
内田 そうですね。反米闘争を「政治の言語」ではなく、「犯罪の言語」で語るようにシフトしたのが、ブッシュの「対テロ戦争」なわけですか。なるほど。
中田 「犯罪だから悪い」という話になって、それで終わり。警察や軍隊がそれを使うのはまだいいんですが、知識人が乗ってしまったのが現在の状況です。一般市民までそれに乗ってしまうようになったら、もうおしまいです。
内田 「テロリスト」という言葉は、政治的な文脈では使うことを控えるべきだということですね。
中田 「テロとの戦争」という曖昧な言葉を使ってしまうのは本当にまずい、というふうに私は思っています。
ただ、私はもともと「テロリスト」という言葉は使わない。あるいはそれだったら、「国家も全部テロリストである」というふうに、中立的に使うべきです。
もともと近代西洋諸語のテロという言葉は先ず、フランス革命での国家による反体制派に対する弾圧、恐怖政治を指すものであり、それから人民による国家への抵抗、暗殺にも転用されるようになったものですから。昔だったら本当に「国家が暴力装置だ」っていうのは当たり前でしたけれども。(清水隆雄「テロリズムの定義 国際犯罪化への試み」『レファレンス』675号2005年10月39ー41頁参照)
昔だったら本当に「国家が暴力装置だ」っていうのは当たり前でしたんですけどね。
内田 僕は「非国家アクター」という政治学の用語でいいと思うんですけどね。たしかに今の国際政治は「国民国家」という政治単位が基礎的ですけれども、「国民国家を形成しない政治的なアクター」というのが現に存在して、国際政治にコミットしている。そうである以上は、「非国家アクター」という呼称の方が中立的で適切と思います。
中田 それがもう区別があまりなくなってきて。
習近平がタリバン政権のアフガニスタンを国家承認
中田 非常に象徴的なことがありました。おととい、習近平がタリバンの大使の信任状を受け取ったんです。信任状を受け取るって、外交的には国家承認と同じことですから。たとえば日本では、天皇陛下が大使などから信任状を受け取るまでは、実は外交ってできないんですね、本当は。
内田 そうなんですか。
中田 だから、一人一人ではそもそも受けないんですよ。何人か集めて、全員そろってやってきて、信任状を受け取って初めてそこで大使になるんです。だから信任状を受け取ってしまうと実質的に国家承認と全く変わらないんです、実は。1、2カ月前に、中国の大使が信任状をタリバンの元首に進呈したんです。これがあって今回、習近平が写真つきで、タリバンの大使から信任状を受け取っていますので、本当にどうでもよくなってきているんです。国家承認とか、国連とか。
内田 じゃあ今回、タリバン政権は中国から国家として承認されたわけですか。
中田 そういうことですよね。中国が初めての国なんですね。今アフガニスタンは、前あったアフガニスタンの共和国政府が任命した大使が、いまだに一応大使館にいるところと、現タリバン政権から派遣されて旗を掲げているところと、2つあるんですよ。
でも、その中でも信任状を出したのは、今回の中国が初めてだった。なし崩し的にどんどんそっちに動いていって。
実はソマリアもそうなってきているんです。ソマリアは3つに分かれているんですが、その中で一番安全なのがソマリランドというところで、台湾がそれを国家承認したんですよね。それまで1つもしてなかったんですけど。
だから、どんどん今増えてきています。アフリカで、ロシアによってクーデターが起きた国々が、みんな今までの秩序を崩していますので、非国家主体が、なし崩し的にどんどん国家になりつつある。
内田 最終的には国連に加盟できるかどうかがハードルになるんですか。
中田 それがもうどうでもよくなってきている。「国連に加盟したら何かいいことがあるのか?」「しなくても何も困らない」というふうになってきている。それよりも「グローバルサウスから仲間にしてもらったほうがいい」というふうに。
内田 国民国家の液状化が本当に進行しているということですね。
中田 本当に進んでいます。一番はっきり分かる例がタリバンで。そういう動きに拍車をかけているのが、今回の「パレスチナが国家なのか、国家じゃないのか」という。
山本 イギリスは一応認めるみたいなことを言っていましたね。
中田 本当に何をやっているのか。今、スーナク首相ですよね。
内田 パレスチナを今、国家として承認している国というのはどれぐらいあるんですか。
中田 もう百何か国あります。
内田 そんなにあるんですか。
中田 逆に言うと、イスラエルを国家として承認していない国がけっこうあるんですよ、まだ。当然ですけどね。今オブザーバー扱いかな。日本も「パレスチナ大統領」という言葉を使い始めているんです、この数年間で。
内田 PLO(パレスチナ解放機構)の東京事務所ができたのは1970年代でしたからね。
中田 ずいぶん前からあるんですけど、たしか大統領という言葉は使ってなかった。たしかここ1年ぐらいで使い始めた気がします。ただそれがまた逆行しつつありますので。
内田 話を戻しますけれど、この後ガザの問題はどうなるんでしょう?
中田 解決しません。当分このまま。
内田 かわいそうですね。このままずっとパレスチナの人たちは死に続けていくわけですか……。

プロフィール

(うちだ たつる)
1950年東京都生まれ。思想家・武道家。東京大学文学部仏文科卒、東京都立大学人文科学研究科博士課程中退。凱風館館長。神戸女学院大学名誉教授、芸術文化観光専門職大学客員教授。専門はフランス文学・哲学。著書に『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)『日本辺境論』(新潮新書)『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。共著に『世界「最終」戦争論 近代の終焉を超えて』『アジア辺境論 これが日本の生きる道』『新世界秩序と日本の未来』(いずれも集英社新書・姜尚中氏との共著)『一神教と国家 イスラーム、キリスト教、ユダヤ教』(集英社新書・中田考氏との共著)等多数。

(なかた・こう)
1960年岡山県生まれ。イスラーム学者。東京大学文学部卒業後、カイロ大学大学院文学部哲学科博士課程修了(哲学博士)。在サウジアラビア日本国大使館専門調査員、山口大学教育学部准教授、日本学術振興会カイロ研究連絡センター所長、同志社大学神学部教授、同志社大学客員教授を経て、イブン・ハルドゥーン大学客員教授。著書に『イスラーム 生と死と聖戦』『イスラーム入門』(集英社新書)、『一神教と国家』(内田樹との共著、集英社新書)、『カリフ制再興』(書肆心水)、『タリバン 復権の真実』 (ベスト新書)、『どうせ死ぬ この世は遊び 人は皆 1日1講義1ヶ月で心が軽くなる考えかた』(実業之日本社)、『神論』(作品社)他多数。

(やまもと なおき)
1989年岡山県生まれ。専門はスーフィズム、トルコ地域研究。広島大学附属福山高等学校、同志社大学神学部卒業、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了。博士(地域研究)。トルコのイブン・ハルドゥーン大学文明対話研究科助教を経て、国立マルマラ大学大学院トルコ学研究科アジア言語・文化専攻助教。著書に『スーフィズムとは何か イスラーム神秘主義の修行道』(集英社新書)、内田樹、中田考との共著『一神教と帝国』(集英社新書)。主な訳書に『フトゥーワ――イスラームの騎士道精神』(作品社、2017年)、『ナーブルスィー神秘哲学集成』(作品社、2018年)等、世阿弥『風姿花伝』トルコ語訳(Ithaki出版、2023年)、『竹取物語』トルコ語訳(Ketebe出版、2023年)、ドナルド・キーン『古典の愉しみ(The Pleasures of Japanese Literature)』トルコ語訳(ヴァクフ銀行出版、2023年)等がある。


 内田樹×中田考×山本直輝
内田樹×中田考×山本直輝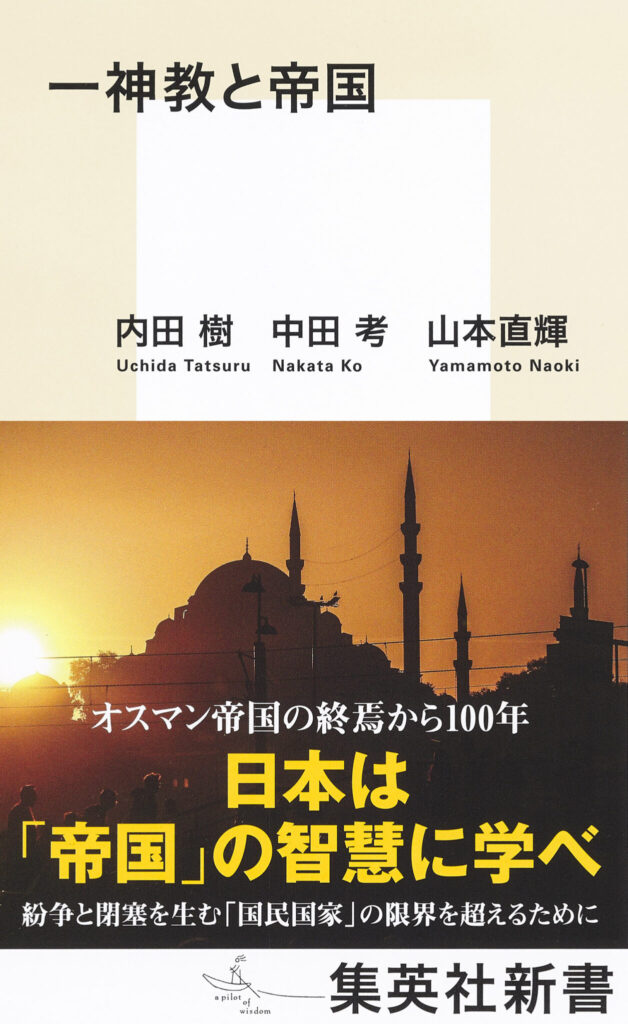












 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

