少年犯罪や犯罪被害者遺族等を取材してきたノンフィクションライターのもとへ、ある日、見知らぬ人物から手紙が届きました。
それは何の罪もない人の命を奪った、長期受刑者からの手紙でした。
加害者は己の罪と向き合い、問いを投げかけます。「償い」「謝罪」「反省」「更生」「贖罪」--。
著者の応答からは、現在の裁判・法制度の問題点も浮かび上がります。
さまざまな矛盾と答えのない問いの狭間で、「贖罪」をめぐって二人が考え続けた記録が、『贖罪 殺人は償えるのか』(集英社新書)です。
本書の刊行を記念し、著者の藤井誠二さん、ゲストに哲学・倫理学がご専門の古田徹也さんをお招きした対談を企画しました。
昨年9月刊『謝罪論 謝るとは何をすることなのか』において、謝罪という行為の全体像に迫った古田さんにとっては、殺人という罪を犯した者の「贖罪」はどのように捉えることができるのか。
決して許されぬ罪を背負った者が「罪を償う」ことについて、二人が真摯に語り合います。今回は、対談の後編となります。
※2024年8月26日、本屋B&Bで行われたイベントを採録したものです。

贖罪に逢ったと思ったら、その贖罪を否定し
古田 『贖罪』で印象に残った言葉として、藤井さんが『臨済録』を引用されていた部分があります。
「仏に逢うては仏を殺し、祖に逢うては祖を殺し、羅漢に逢うては羅漢を殺し、父母に逢うては父母を殺し、親眷に逢うては親眷を殺して、始めて解脱を得、物と拘らず、透脱自在なり」(286頁)
この言葉の、「仏」とある部分を、藤井さんは「贖罪」と読み替えて、「贖罪に逢ったと思ったら、その贖罪を否定し」と表現されています。
加害者が刑期を務め上げる。あるいは、10年間欠かさず被害者遺族に謝罪の手紙を送り続けたり、線香を上げ続けたりする。そういうことにはもちろん重要な意味があるのだけれど、それで「贖罪ができた」「謝罪が完了した」と思ってはいけないということですね。
藤井 そうですね。加害者が少年院や刑務所にいる間は、そうした贖罪につながるようなイメージ的行為や思考を続けていくことは可能かもしれません。刑務所などは、純粋培養的な環境ですからね。でもそれが、社会に出た後だとどうか。社会に出た後も、贖罪の行為を続けていくのは、なかなか難しいと思います。
私自身が取材をした例だと、刑務所から被害者遺族宛に謝罪の手紙を書く受刑者は少ないけれど存在はします。しかし、出所してからも手紙を出し続けたり、被害者遺族に直接謝罪に赴く例は、ほとんど無いですね。加害者の親も、裁判などでは、「子どもと一緒に一生償います」とよく言うのですが、きちんと履行している例は皆無でしょう。その場限りの「謝罪」は耳にタコができるほど聞いてきました。
古田 それはやはり、自分の犯した罪を自覚し、理解をすればするほど、罪の深さに気づき、むしろ謝罪や贖罪をすることが難しくなるということでしょうか?
藤井 そういう側面もあると思います。たとえ刑事施設の中で謝罪の気持ちを深めていくことができてもそれは脳内のことであって、実際に行為にうつすことや、被害者や被害者遺族が望むことにリアルに対応できるかという問題とは別です。
古田 出所してから贖罪の行為に消極的になる加害者は、単に己の罪から逃げているだけとはかぎらない。むしろ、自分の犯した罪に対する理解が深まることにより、自分が謝罪をすることが被害者遺族に対する二次加害になるのではないか、ということを考えるようになっている場合もあると思います。
藤井 私が手紙のやり取りを続けた加害者・水原は、最初の謝罪の手紙を遺族に出した後にコンタクトを拒否され、とりわけそれを懸念していました。しかし、それを「二次被害」だととらえることができた感性は加害者の変化の芽生えだったのだと思います。『贖罪』の中で、『0からの風』という映画を紹介しましたが、その映画の中で被害者遺族である主人公が、「加害者の自分探しや、自分自身を許すために、遺族は存在するわけじゃない」というセリフがあった。水原も刑務所内でこの映画を観たそうなのですが、このセリフのことを手紙に書いたら、彼もいたくショックを受けていましたね。
加害者側が反省して、「自分はなぜこういうことをしてしまったのだろう?」と自問をしても、被害者遺族から、「自分探しのために、謝罪をしているんだろう」と言われてしまう。遺族の立場からしたら当然の反応なのですが。しかし、そうなると何をすればいいのか分からなくなって、思考を放棄して逃避してしまう加害者がほとんどです。そういった被害者の思想を刑務所では学ぶことができませんし、刑務官も被害者と接したことがないからわからないのです。

被害者が忘れ去られないようにするために
古田 今回、『贖罪』という本から私が受け取ったのは、加害者にとって、悩み続けるのが真の贖罪なのではない、ということです。そうではなくて、被害者が忘れ去られないようにすること、そのために自分に何ができるかを模索し、実際に試み続けること、そこに贖罪の内実があるというメッセージです。
もちろん、被害者がこの世界から忘れ去られないように努力することは、加害者でなくともできます。亡くなってしまった被害者が、実際にどう生きていたのか、何を願っていたのか、といったことを想起し、共有することはできる。しかし、加害者しか想起できないこと、語れないことがある。酷く辛い事柄ですが、亡くなる直前の被害者はどういう様子だったのか、どれほど苦しんで亡くなったのか、殺された理由や背景は何だったのか、といったことです。
そうしたことを、残りの人生を懸けて想起し続ける責任が、命を奪ってしまった者にはある。それが贖罪のすべてではないけれど、加害者がやらなければならないこととしてあると思います。
藤井 私は、長年凶悪犯罪を取材してきた者として、加害者による「贖罪」なんてものは、成立しないんじゃないか、という思いがまず前提としてあります。これはもう、当事者以外の論者によって、一人ひとり全然考え方の違う問題ではあるんですけどね。人によっては、「贖罪の可能性はゼロではない」という人もいれば、もう最初から、そんなのはまったくありえない、成立しないんだ、という人もいる。当事者の中にも百人百様の意見があるし、それは何年経とうが変わらない被害者もいれば、変化がある方もいて、動態的です。
「被害者を生き返らせることが唯一の贖罪だ」という人が殺人や傷害致死事件の遺族には多いのはたしかです。でも、それは不可能ですよね。ということは、贖罪なんていうものは、そもそも成立しないというのが論理的に帰結してしまう。被害者遺族からそう言われると、加害者の側は大体委縮しますね。これはもう何をやっても駄目だ。自分は一生、他人から恨み続けられるしかない、と自暴自棄になったり、日常に埋没して考えることをやめてしまう。ですから刑事施設にいる間も社会に出てからもある種の「強度」が必要で、それをどう維持していけるかがスタートだと思いますね。
でも、そうしたジレンマがありながら、水原は今は立ち止まらないで、考え続けている。そういうことは、やっぱりすごく大事だと思う。彼と文通をしていて、私もすごく苦しかったんです。私が被害者の立場にあるわけではないのに、なんとなく私が水原を責めているみたいになったシチュエーションもあった。水原にとっては、己の罪に向き合うことは私のどんな問いかけにも黙さず答えることだと考えているふしがあって、それが苦行みたいになっていたと思います。
古田 そうですね。
藤井 今後も水原が苦行のように、己の罪に向き合っていくのか。それが被害者遺族に対する謝罪につながるのか。それ自体は、私には分かりません。
古田 大事なのは、なぜ「謝罪」や「贖罪」という行為には一般的な答えが存在しないのか、それを理解することですよね。それがないと、ただの諦めになってしまう。この『贖罪』という本をよく読めば、なぜ謝罪や贖罪が百人百様のものなのかということが、よく見えてくると思います。
藤井 水原との対話で印象的だったのは、彼が最初刑務所に収監された時に、贖罪や謝罪というものに、定型があると思っていたということです。最初は、水原も刑期を務め上げることが、贖罪なんだと思っていた。ただ、それではいけないと彼は読書などを通じて気がついた。
その気づきを、今後どこまで深めていけるかということが、重要だと思います。彼とは今も、文通を続けています。この『贖罪』についても、世間でどう読まれたかも、今後、彼に報告しようと思っています。そのようにして、水原が己の罪と向き合うことは、今後も続いていくのだと思います。

プロフィール

藤井誠二 (ふじい・せいじ)
1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。少年犯罪について長年にわたって取材・執筆活動をしている。著書に『人を殺してみたかった―愛知県豊川市主婦殺人事件』『少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い』『殺された側の論理―犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』『黙秘の壁―名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか』、共著に『死刑のある国ニッポン』(森達也との対談)など多数。
古田徹也(ふるた・てつや)
1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学教育学部准教授、専修大学文学部准教授を経て、現職。専攻は、哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』で第41回サントリー学芸賞受賞。その他の著書に、『それは私がしたことなのか』『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』『不道徳的倫理学講義』『はじめてのウィトゲンシュタイン』『いつもの言葉を哲学する』『このゲームにはゴールがない』『謝罪論』など。訳書に、ウィトゲンシュタイン『ラスト・ライティングス』など。


 古田徹也×藤井誠二
古田徹也×藤井誠二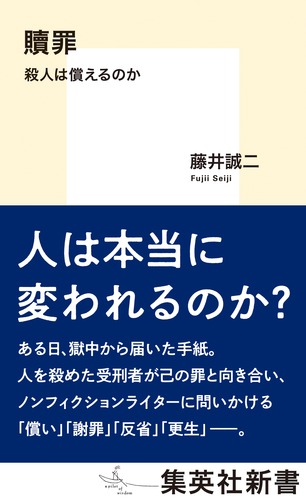










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


