■年をとるとなぜ新しいテクノロジーを遠ざけるようになるのか
明治末期、1890年代。電話が登場して間もない頃、高齢層の中には、これを「身も知らぬ奇体なエレキ」と呼び、触れることを嫌がる人もいたという。
当時は、家電製品が日常生活に普及する以前である。まだせいぜい白熱灯くらいしかなかった時代。その矢先に、仕組みもわからない装置が突然、大声で話しかけてくるのだから、戸惑うのも無理はない。相手の顔も見えず、電線を通して声だけが届く。日常に突如現れた電話は、明らかに「奇異なテクノロジー」だった。
20世紀になると電化製品が急速に普及する時代となり、20世紀終盤になると今度は家庭用の情報機器の時代が訪れる。21世紀は、個人向けの情報機器の時代である。
我々はもはや、明治の高齢者のように新しいものに怯えることはない。だが、次から次へと現れる新しい技術やサービスに対して戸惑う感覚自体は、あまり変わっていない。
そもそも新しい技術は、若年層をメインターゲットに設計されていることが多い。老眼が進み、小さな文字が読みにくくなる中高年世代は、それだけで疎外されていると感じることが増えてくる。
そして、そもそも率先して新しいものを取り入れようという意欲が薄くなっている場合も多い。このように年を重ねるごとに「新しい技術についていけない」という思いが生まれてくるのは、なぜだろう。
僕の父親は、かつて新しい技術に積極的だった。80年代初頭、まだ「おもちゃ」とも思われていたコンピューターを、僕に買い与えた。そして、そのコンピューターで父親も将棋のゲームをしたりしていた。
それから25年ほどが経ち、父親の定年退職の時期に、MacのノートPCをプレゼントした。ちょうどブログが流行り始めた時期だった。サラリーマン時代には、ワープロ専用機を仕事で使っていた父親はすぐにブログに夢中になった。ただ、ブログを書く以外のサービスには、関心を示さず、利用しなかった。60代半ばを超える頃からテクノロジー全般への関心も低下し、むしろ、それへの悪口の方が多くなった。
一方、母親はノートPCだけでなく、旅先でiPadを使ってGoogleマップで道を調べたりするし、それどころかスマホやiPadを使い動画編集をこなしテロップやBGMをつけた作品をSNSで友人と共有して楽しんでいる。そもそも、新しい技術に対応できるかどうかは、年齢だけでなく、個人差に大きく左右される。
■新しいテクノロジーを自分には不要と思うメカニズム
老いは、あるとき突然、突きつけられる。
『はじめての老い』を書いた編集者の伊藤ガビンは、知人を乗せての運転中、「ガビンさんて、バックモニター見ないんすね」と指摘され、動揺のあまりタイヤを側溝に踏み外してしまったという。動揺したのは、知人の指摘によって自覚していない自らの「老い」に気づいたからだ。
伊藤は80年代のパソコン雑誌出身。ゲームデザインやデジタルアート制作に関わり、大学でメディア論を教える立場にもある。間違いなく「テクノロジー側」の人間だ。しかし、いつの間にか、バックモニターという自動車の新しい技術を取り入れることを自ら拒んでいた。
人には「新機能を覚えるのが楽しい」と感じるタイプと、「負担」と感じるタイプがある。伊藤は明らかに前者だったはずだが、知らぬ間に「新しいテクノロジーについていけていない」側面を持つようになっていた。そしてそれまで気にしていなかった老いを、意識するようになった。
老いは一般に、小さな字が読めなくなったり、反応が鈍くなったりと、能力の低下として捉えられる。だが、「変化しない」ことこそがむしろ老いの特徴だと伊藤は捉える。『はじめての老い』で語られるのは、年齢とともに新しい技術が「苦手になる」という話ではなく、「こっちの方が便利だし早い」という自身の判断基準を頑なに守っているうちに、周囲の環境とのズレが大きくなっていくのだという話である。
この話で思い出したのは、パワーウィンドウやパワーステアリングが登場した当初のこと。1980年代末のことだが、むしろ運転好きの人々からは「必要ない」と拒否反応があった。だが数年後には、すべての車に搭載され、異論は聞かれなくなった。これ以前にも、マニュアルからオートマへの変化、馬車から自動車への変化の頃にも同じ議論は繰り返されただろう。
ちなみに僕自身も、車の運転ではバックモニターを使わない派だ。一時期使っていたこともあったが、結局、モニターを見ても振り返って目視確認もする。苦手という自覚はないが、二度手間になるので、次に車を買い換えたときには、バックモニターなしのモデルを選んだ。やはり自覚がないまま、新しいテクノロジーを取り入れない理由を自ら生みだしていた。
もちろん新しいテクノロジーとの付き合い方として、「必要なものだけを取り入れる」という取捨選択をすることもできる。自ら選び取り、あえて距離を取る。過剰に情報を選ばされる時代に、これこそが有効な生存戦略だと前面に打ち出したくもなるが、それはそれでなかなか難しい。
スマホのアプリを利用していると、じきにアップデートの通知がくる。特に不便もないのでパスして「このバージョンを使い続ける」という選択肢を選ぶこともできるが、いつかOSのバージョンとの齟齬が生まれて、突然、使えなくなる日が来る。結局、スマホを全部最新型に買い換えた方が早いということになる。そうなるくらいだったら、あらかじめアップデートをその都度判断するよりも、全部を自動アップデートに委ねる方がよかったということになってしまう。
■一度身についたやり方は簡単には消せない
変化のサイクルがめまぐるしい社会において、新しい技術への戸惑いは、年齢の問題だけではない。一度身についたやり方を捨てること自体の難しさが、新しい環境を受けとめることの難しさと結びついている。
自転車の乗り方から子どもの頃に覚えた1人あやとりまで、一度、身体で覚えたものは、一度それをは忘れたとしても、すぐに習得し直すことができる。
この人間の能力を、行動科学者のエムレ・ソイヤーは著書『経験バイアス』で「経験」と呼ぶ。「経験」は、単なる知識ではなく、感覚や情景と結びついて記憶され、反射的に再生できるもの。そして、「それほど努力せずに思い出したり結びつけたりすることができる」ものでもある。
実際に自転車の運転や水泳のように一度身に付いたものは、ほとんど意識せずに引き出すことができる。そして、右足の後に左足を出すなどと考えることなく、歩いたり走ったりするのも同じである。
これらは、無意識に行うことができるから、人は歩いているときに、まったく関係ない仕事のアイデアについて考えることができる。
しかし、その「経験」が障害にもなることもある。一度、経験として身についた身体的な習性は、むしろ簡単に書き換えることができなくなるのだ。
ソイヤーは『経験バイアス』のなかで、「左右逆転自転車」の実験を紹介している。
これはYouTubeチャンネル「Smarter Every Day」で行われたもので、ハンドルを左に切ると右に進むように改造された自転車に乗る試みだ。普通の自転車に慣れた人にとって、この操作は極めて困難だった。一度染みついた操縦感覚は、そう簡単にはリセットできない。
しかし実験者は、訓練の末に逆転自転車に乗れるようになった。ただ、その代わりに今度は普通の自転車に乗れなくなってしまった。新しいスキルを身につけるには、古いスキルを完全に上書きしなければならない。これが、単なる知識の更新ではなく、「経験の上書き」の難しさを物語っている。
新しいテクノロジーへの適応も同じである。iPhoneからAndroidのスマホに機種交換するときに、それまで身についたiPhoneの操作の技術は、むしろ邪魔になる。音量を上げるつもりがつい癖で電源を落とすボタンに触れてしまう。しかも、この操作は無意識で行うものなので、同じことを何度も繰り返してまう。
過去の機種の操作にまつわる記憶を脳内から全部消去できればいいのだが、リセットすることは、ソイヤーの言うとおりに難しい。そもそも、人は、すでに身についているスキルを自ら手放すということに合理的な理由を見つけることですら困難だ。すでに得たスキルを活かしたまま、次の仕事に取りかかりたい。だがこれからの時代は、新しいことの習得の前に、これまでの経験を捨てろといわれるようになるかもしれない。それだけ、根本的なルールが大きく変わっていくと普通の人は、次のスキルが身につくかどうか確証もない状態で、過去のスキルを捨てろと要求されてそれを拒むだろう。
■普及する方式は性能の優劣で決まらない
1951年生まれの高橋源一郎は、1980年代半ばから、いち早くパソコン(アミーガ)と富士通のワープロのユーザーだった*。これは、導入が相当に早かったケースである。
高橋が愛用していたのは、親指シフト式と呼ばれる独自のキー配列だった。日本語をローマ字入力すれば「K+A=か」と二度打ちが必要だが、かな文字入力なら一回で済む。さらに親指シフトは、日本語に最適化されており、英字タイプライター由来のQWERTY配列よりも合理的だった。
親指シフトは、ワープロ専用機の時代には広く普及した。しかしパソコン時代に入り、国産メーカーの独自規格が衰退する中で廃れていった。高橋は、慣れ親しんだ親指シフトから別方式に移行できず、メーカーサポート終了後も使い続けた結果、WindowsやMacという主流環境から取り残されることになる。
誰よりも早くデジタルを取り入れた高橋が、結果的に時代に取り残されてしまった。一度身についた入力法は、「経験」として身体的、無意識的に刻み込まれるため、後から変更するのは難しいということをよく示している事例である。これはむしろ年齢とは関係のない話だ。
どんなに慣れたやり方があっても、社会全体が新しい規格に動いてしまえば、それに合わせるしかない。そもそも、なぜ高橋は親指シフトを使い続けたのか。それは単純に「そちらのほうが優れていた」からだ。テクノロジーの歴史は、「劣ったものから優れたものへ」という一方向の進化ではない。むしろ、性能や使い勝手に優れた技術が敗れ、劣ったものが生き残ることも多い。
キーボード配列においても、QWERTY式は決して合理的な設計ではなかったが、普及の偶然に恵まれ、長い時間をかけて定着した。ビデオカセット戦争では、画質・コンパクトさに優れたベータマックスが、早期の普及スピードと録画時間の長さでVHSに敗れた。1990年代、MacユーザーはWindowsを「取って付けたような、洗練を欠くOS」と嘲笑していたが、周辺機器メーカーやソフトウェア企業は次々とWindows版開発を優先し、最終的にシェア争いではWindows陣営が圧勝した。
「ビデオはベータ」「入力方式は親指シフト」「パソコンはMac」。これらを自分の選択肢として歩んできた人は、むしろ技術に関心が高く、造詣も深いエリート・ユーザーだったはずだ。間違いなく家庭用ゲーム機の選択は、任天堂ではなくセガだっただろう。高橋源一郎と同じだ。性能の優れた方式を選んだとしても、それがスタンダードになるわけではない。むしろ滅びていく陣営になるケースが多い。
新しいものに飛びつく人たちを「アーリー・アダプター」とも呼ぶが、必ずしも情報社会で勝利を収めるのは、こうした目利きたちだとは限らない。むしろ、広く世間に普及したものにしか飛びかないレイト・マジョリティとして生きるほうが選択肢を間違わずに済むのだ。ただ、「アーリー・アダプター」的な人たちは、趣味として「レイト・マジョリティ」的な生き方を絶対に選びたくないだろうが。
*『還暦からの電脳事始』高橋源一郎
■手書きの作家たちのデジタルに移行した時期
かつて、手書きで文章を書くことになれた物書きは、それを捨て、ワープロやコンピューターに切り替えることに苦労したはずだ。小説の書き方の手書きからデジタルへの転換期は、おおよそ、1980年代末から1990年代前半にかけての10年の間。個人差はあるが、1960年生まれ前後世代に分岐点がありそうだ。誰がどのような環境で小説を書いていたかに触れてみると、村上春樹(1949年生まれ)は、小説家デビュー(1979年)から『ノルウェイの森』までは、400字詰め原稿用紙に万年筆を使って小説を書いていたが、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)のころに富士通のワープロを使うようになった。ほぼ同年代の高橋源一郎に比べるとやや遅いが、それでも他の作家と比べて少し早い。そして『ねじまき鳥クロニクル』(1994年)のころからMacを使うようになったという。年齢にすると40歳前後で手書きからデジタルに転向し、40代半ばでワープロ専用機からパソコンに切り替えた。
春樹よりも下の世代で、原稿用紙アンド手書き派を公言するのは、林真理子(1954年生まれ)、泉麻人(1956年生まれ)、坪内祐三(1958〜2020年)、中森明夫(1960年生まれ)ら。この世代は、ものを書く仕事でプロになって、およそ10年ほどが経ってデジタル化の波が来た世代。十分になれた手書きの方を選んだのだろう。
新しい道具を取り入れるかどうかの選択が、単なる好みではなく、その時期をいくつで迎えたか、どのくらいのキャリアを積んでいたかなどと結びつく。もちろん、プロとして身につけた技術を守った方が、効率もいいし、人気作家がひっきりなしの締め切りに追われる中、やり方を変えるのは難しい。
村上春樹よりも遙か上の世代で、80年代の前半に誰より早くワープロを取り入れた作家が曽野綾子(1931年生まれ)。彼女は弱視ゆえに早くからワープロを取り入れたという。原稿用紙に書く手書きの文字よりも、モニターの文字の方が見やすかったのだ。石原慎太郎(1932年生まれ)は、曽野綾子の自宅まで見学しに行き、自分もその導入を決めた。字の汚いことを自覚していた石原は、当初カセットテープに小説を吹き込んだこともある。ワープロが登場するとそれを導入した。石原は、東芝のワープロ専用機「ルポ」を愛用し、生涯、使い続けた。ワープロ専用機は、2000年頃からメーカーが撤退し、事実上消滅した商品だが、作家としての石原は、その消滅後も個人的なサポートを受け、それを使い続けた。死後公開された彼の遺品の中にもそのワープロが含まれていた。
80年代前半にワープロは、オフィス機器として普及する。当時は、小説の執筆に使うとの想定はメーカーにもなかった。主な利用法は、ビジネス文書の作成、それも主に清書用だった。これでいきなり文章を打つというやり方は、後から考えられたもの。作家たちのワープロ導入も、その多くは清書用だったはずだ。それが次第にワープロの画面上でものを考え、書きながら小説やエッセイを考えるのが当たり前になった。ちなみに僕は、1995年から編集者の仕事をしているが、テキストに関しては、原稿用紙の手書き原稿を入稿したり、作家とやりとりをしたことは一度もない。概ねこの頃には誰もが電子メールを使ってやりとりをする時代になっていたということだ。
■トフラーの外した予言と情報社会で身につけるべき能力
ワープロやパソコンでも、どのやり方、何の方式、機種が次のスタンダードとして普及するかは、必ずしも合理性や性能の優劣だけでは決まらない。それでも変化の時代には、何かしらの選択を行い、新しい状況に対応しなければならない。
未来学者アルビン・トフラーは、著書『未来の衝撃』(1983年)でこう書いている。
「社会やテクノロジーが絶えず変化し、グローバル化していく世界で、過去の経験にずっとしがみついていると、長年のうちに、そうとは気づかぬまま、こうした面での「非識学者」になってしまうおそれがある」
社会の変化があまりに速く、求められる知識や技能の水準が絶えず引き上げられる世界では、以前は通用していた経験もあっという間に役に立たなくなる。「非識学者」とは、文字の読み書きのできない者のことを指すがその「非識学者」のラインは常に引き上げられ、誰しもがいつの間にかラインを下回る社会が到来するという。
トフラーが当時想定していたのは、コンピューターが家庭に普及し、誰もがコンピューター言語、具体的には、FORTRANやCOBOLを習得していることが当たり前になる世界だった。つまり、読み書き、そろばんなどの能力同様、プログラミング言語が万人の基本スキルになると考えていたのである。
この点に関して、トフラーの予測は結果的に外れた。確かに、コンピューターは社会の隅々にまで普及した。しかし、日常生活において必要とされたのは、プログラミング能力ではなかった。代わりに発達したのは、マウス操作やタッチパネルといった直感的なインターフェースだった。これによって、専門知識がなくても、誰もがコンピューターを使える世界が実現した。言い換えれば、機械の側が人間に合わせて歩み寄ったのである。もちろん、それを可能にしたのは、コンピューター技術者たちの努力、そして使いやすい商品が生き残る「市場のメカニズム」による選別の力だった。
ちなみに、トフラーは適当に未来を語っていたわけではない。むしろ、多くの分野で的確な予測を行った。1980年の『第三の波』では、自宅でのリモートワークの普及や、家電・自動車のネットワーク化といった未来像を描き、それらは現実のものとなった。
現代では、プログラミングの知識こそ必須ではないが、絶え間ない技術変化への対応は「事実上」求められている。かつては駅員が切符を手渡し、はさみでパチンと切って改札を通ったが、いまやICカードやスマホ決済が当たり前になった。その利用には、モバイルSuicaやPASMOをスマホに登録し、チャージを管理するという新しい作法が求められる。
もしこれらの操作に対応できなければ、現代社会では「非識学者」、または「機械音痴」とみなされかねない。まだ窓口で切符を買うことも可能だが、その行為自体が「時代遅れ」と見なされつつある。みどりの窓口が消えつつあるのと同様、廃止されるのも時間の問題である。
■テクノロジーの受け入れにおける「35歳」の壁
テレビが普及して間もない頃に、「一億総白痴化」という警鐘が世間に広く知られたことがある。これを発言したのは評論家・大宅壮一である。大宅が匿名コラムで使った言葉は「一億白痴化」。そこに「総」を加えたのは、作家の松本清張だった。どちらもテレビという新しいメディアが、国民の知的レベルを下げる可能性についての言及だが、当時の大宅が50代で松本は40代後半だったことは、考察に値するテーマだろう。もしも子どもの頃にテレビに親しんだ世代であれば、テレビに対する感覚はまったく違っていたはずだ。
新しいテクノロジーが登場したとき、その人が何歳だったかは、その受け止め方に大きな影響を与える。この現象を法則化したのが、イギリスのSF作家ダグラス・アダムスである。彼は「ダグラス・アダムスの法則」として、次の三箇条を記している。
「1.生まれたときに世の中にあったものは、普通で当たり前で、世界を動かす自然の一部である」
「2.15歳から35歳の間に発明されたものは、刺激的で革命的と感じ、その分野でキャリアを積むこともできる」
「3.35歳を過ぎてから登場してきたものは、自然の秩序に反するものである」
アダムスがこの法則を紹介したのは、1999年8月にイギリスの新聞『The Sunday Times』紙に寄稿したエッセイの中だった。背景には、当時の著名ジャーナリストが「インターネットなんて1950年代のハムラジオのような一時的な流行に過ぎない」*と語ったことへの反論があった。アダムスは、こうした無理解に対して皮肉を込め、自らの法則を紹介したのである。
ダグラス・アダムス自身は1952年生まれ。つまり、彼がこの法則を書いたのは40代後半、インターネットに初めて触れたのも35歳を過ぎてからだっただろう。アダムスはあえて、世間は誰しも「自分の若者時代を超えて登場した新しいテクノロジー」に距離を置きがちだと笑い飛ばしている。だが、この法則は単なる皮肉に留まらず、深い説得力を持っているようにも思える。
これを自分の人生に置き換えてみるとそれがよくわかる。
1973年生まれ世代には冷蔵庫もカラーテレビも「自然の一部」だった。15歳前後は、80年代の半ば。ちょうど、ビデオデッキやワープロ専用機、パソコンが普及した時代。これらの機器、その周辺文化、例えばレンタルビデオや8ビットのゲーム機などは自分の世代特有の文化で、それらに夢中になり、できることならそれに関わる仕事に就きたいと思っていた。僕が選んだその後の職業は、コンピューター雑誌の編集、その周辺のビジネスの取材、20代の頃に普及したインターネットでものを書くライターという方向に進むので、アダムスの法則はピタリと当てはまっている。
一方、アダムスの法則によると、35歳を超えて登場したテクノロジーは「自然の秩序に反するもの」として受け入れにくくなる。iPhoneの登場が、2008年。ちょうど35歳の頃にそれが誕生した。35歳の分水嶺の、よく解釈すれば、ぎりぎり間に合ったテクノロジーはスマホということになる。同時期にSNSが普及し、音楽や動画のサブスクリプションサービスが生まれてきた。どれも、ぎりぎり間に合ったかどうかというタイミングだ。
*「遠藤諭のプログラミング+日記」で紹介されている。「ダグラス・アダムスの法則をキミは知っているか?」*https://ascii.jp/elem/000/004/213/4213879/
■就職氷河期とインターネット老人会
1970年代前半生まれの団塊ジュニア世代、及び、その5、6歳下までは、就職氷河期世代としても知られている。
社会に出ようというタイミングでバブル崩壊に直面し、長い不況期に突入した。そのため、非正規雇用の割合が他の世代に比べて高い。
この世代の就職活動期と、インターネットの登場期はちょうど重なっていた。とはいえ、まだ履歴書は手書きで提出するのが常識で、就職案内の資料請求も郵送が当たり前だった。「インターネット」は、履歴書の「特技」や「趣味」欄に書いてアピールするものだった。
面接でインターネットについて聞かれたとき、通り一遍の説明以上のことが話せるように、パソコンを持っている知人に頼んで、実際にインターネットを触らせてもらう──そんな時代だった。
ただし、1995年初頭の時点では、まだ誰もが自由にネットにアクセスできたわけではない。
ウェブブラウジングに必要なソフト「Mosaic」(モザイク)は、店頭で売られているものではなかった。手に入れるには、インターネットのFTPサーバーに接続するか、パソコン通信の「倉庫部屋」のような場所に入り込むか、あるいはハッカーの知り合いを頼るしかなかった。雑誌の付録などで「Netscape Navigator」などのブラウザーが手に入るようになるのは、1995年の半ば以降である。
当時、ウェブサイトは「ホームページ」と呼ばれ、掲示板(BBS)が主要なコミュニケーション手段だった。その後、2000年代前半になると、テキスト中心のウェブサイトを生成する日記的なサービス──すなわちブログが広まり、さらにSNSへと発展していく。
この時代、インターネットの世界には、まだ初期から参加していた技術オタクたちの姿が見え隠れしていた。そして『電車男』に象徴されるように、無邪気な善意や集合知への信頼が、かろうじて信じられていた時代である。
とはいえ、こうした話を延々と続けると、いまではすぐに「インターネット老人会」と揶揄されてしまうので、このあたりで区切っておこう。
驚くべきことは、この「インターネット老人会」と呼ばれる中心世代が、いまやITツールやデジタルスキルの再教育、すなわち「リスキリング」の対象とみなされている点だろう。
かつては「デジタルに明るい世代」と自覚し、それを武器にしてきた世代のはずが、気づけば、新しいテクノロジーに適応できていない世代とみなされている。黎明期の知識にとどまり、その話題ばかりを繰り返しているうちに、「新しい波に付いていけない」存在に見られるようになったということ。
かつてはデジタル機器に強い若者世代と目されてきた世代が、時代が一巡した今、その知識は古び、適応を求められる側へと回る。老いとテクノロジーを巡る関係性は、常に順繰りに入れ替わっていく。そして、そこからは誰も逃れられない。下の世代もすぐに「インターネット老人会」の第2、3世代を形成するようになるだろう。
(次回へつづく)

20年前は「ゲーム脳」、今は「スマホ脳」。これらの流行語に象徴されるように、あたらしい技術やメディアが浸透する過程では多くの批判が噴出する。あるいは生活を便利なはずの最新機器の使いづらさに、我々は日々悩まされている。 なぜ私たちは新しいテクノロジーが生まれると、それに振り回され、挙句、恐れてしまうのか。消費文化について執筆活動を続けてきたライターの速水健朗が、「テクノフォビア」=「機械ぎらい」をキーワードに、人間とテクノロジーの関係を分析する。
プロフィール

(はやみずけんろう)
ライター・編集者。ラーメンやショッピングモールなどの歴史から現代の消費社会について執筆する。おもな著書に『ラーメンと愛国』(講談社現代新書)『1995年』(ちくま新書)『東京どこに住む?』『フード左翼とフード右翼』(朝日新書)などがある。


 速水健朗
速水健朗





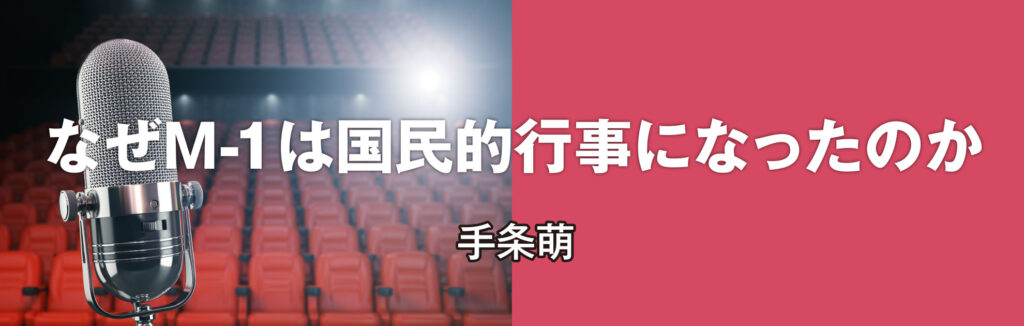



 佐藤喬×谷川嘉浩
佐藤喬×谷川嘉浩



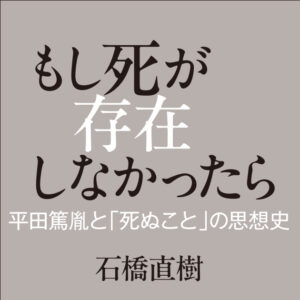
 石橋直樹
石橋直樹