日本のアスリートはなぜ自らの言葉で発言できないのか?
武田 サッカーの長谷部誠さんが『心を整える。』という本を出して(2011年)、ベストセラーになりました。とりわけあれ以降、スポーツ選手が、そのメンタルや生き抜くためのメソッドを語る本が数多く出版されるようになりました。本人たちの希望というより、出版界の仕業なのでしょう。たとえば、長友佑都選手が猛スピードで左サイドバックを駆け上げっていくことって、自分の仕事のやり方にはあまり関係ないと思うんですが、アスリートが語るメソッド本って、大きな書店ではビジネス書と一緒に並んでいたりします。そのメソッドをビジネスにつなげるごちゃごちゃ感。世界的に活躍するスポーツ選手の感覚、体や精神の整え方が、我々の実生活といったいどこまでリンクするんだろう、という疑問があります。
西村 たぶんこれも、出版社や放送局と、それを求める読者や視聴者の「鶏と卵」の関係なんでしょうが、アスリートに人生訓を求めたりビジネス系のウェブサイトで組織論を語ったりすることって、あれは競技に対してむしろ失礼な行為なんじゃないかとも思うんですけどね。
武田 成功者の言葉を聞いて真似をすると自分も成功するんじゃないか、と思わせる。ずっと続いてきた手口ですよね。戦国武将と同じ扱い。秀吉の処世術、信長の戦略みたいなものと同じ消費のされ方というか。でも、選手の言葉で大切なのは、アスリートアクティビズムのほうですよね。その点は、この本でも、山本敦久さんや平尾剛さんがお話されていたと思うんですが。
西村 おふたりとも言及していますね。
武田 世界で活躍するアスリートたちは、日本で暮らしている我々よりも広い世界を見て、多くの人種と接し、様々な社会状況を知っているわけじゃないですか。そうであるならば、その見聞を生かして、たとえば、日本の部活動のココがおかしいとか、メディアでのスポーツの消費のされ方はおかしい、と言える場面やチャンスがたくさんあるはず。でも、そういう発信に積極的な選手はめったに出てこないですね。東京オリンピックが強引に開催された時も「おかしいと思う」と声をあげたアスリートはほとんどいなかった。
西村 山口さんはこの本の中でも「アスリートの能力と社会人としての成長は必ずしも同じように伸びていくわけではないから、スポーツで能力を発揮しているからといって社会人として何も言わない、と選手たちを責めるのは、今の日本の環境では酷かもしれない」とおっしゃっていて、まあそれは確かにそうだなとも思うんですよ。
じゃあ、なぜ日本の選手たちがテニスの大坂なおみさんや、F1のルイス・ハミルトンのような人権に関する発言や行動をしないのかというと、ひとつは取材する側がそういう話をしないからでしょうね。目の前の競技に関係ないから聞かない、聞いてはいけないという姿勢にも原因があると思います。活字メディアも放送メディアもおしなべて、類型的な常套句の「感動をありがとう」「勇気をもらう・与える」という分かりやすい物語の中に話を押し込めてしまう。
森田浩之さんが『スポーツニュースは恐い』等の著書で、ディスコース・アナリシスという手法で「スポーツニュースはオヤジ的な世界観でできている」、つまり日本のスポーツニュースが想定している日本人の姿は「年功序列の会社社会の中で努力を積み重ね、ガイジンとの交流が苦手な私たち」という類型的で20世紀的な読者・視聴者像が、アスリートの活躍によってカタルシスを得るさまを投影していることを解きほぐしています。だから今もその延長線上で、人生に活かせるだとか感動をありがとうという物語にスポーツが絡め取られて収束していく。
武田 東京オリンピックでは、サッカー日本代表の女子チームがピッチに片膝をついて人種差別に抗議をしました。それを、メディア側がきちんと報じていたかどうか。それを踏まえた上で、メディアが言葉にすることは、もっとできるはずですよね。
西村 僕は日本メディアのスポーツ取材をすべて見ているわけでは当然ないし、どちらかといえばモータースポーツという狭い世界をずっと見てきたわけですが、モータースポーツに限らずほかのスポーツの取材も少し見ていて思うのは、取材する側が何も聞こうとしないだけでなく、選手をマネジメントする人たちにも「こういう話題には触れないでくださいね」という無言の要求みたいなものがあって、それがある種の「抑える力」として働いているようにも思うんですよ。
だから、去年のサッカーのワールドカップの時でも、ヨーロッパの選手やチームがカタールの人権抑圧状況に対して様々なアクションを起こそうとしていた一方で、日本の選手や関係者がそれをどう見ていたのかはまったく伝わってこなかった。JFA会長の田嶋さんの「今はサッカーに集中するときだ」という薄っぺらい言葉だけが大会直前に流れてきましたけれども、各国の選手たちやチームの行動を日本の選手たちはどう思っていたのか、どんなふうに捉えていたのかということは、何もわからないままでしたよね。その場で選手たちに聞いたら、ひょっとしたら話してくれたかもしれないとも思うんですが、メディア側のフィルタリングなのか、そこは何も日本には伝わりませんでした。
武田 たとえば政治の世界でも、総理番や官房長官番として朝から晩まで一緒にいる記者が、総理や官房長官に厳しく問わなければいけない場面でも、彼らを守るかのようなヌルい質問をする。これと似ているのかもしれません。海外の主力選手に張り付いて行動していると、その記者が一番欲しいのは独占インタビューなどになるから、距離の近さを保ちたい。その距離を遠ざけるような質問はしたくなくなるわけですよね。
西村 でも、必ずしも距離が遠ざかるとは限らないですよね。
武田 そうですね。むしろ、腹を割って話してくれるかもしれない。
西村 なかには、そういうことを積極的に言いたい選手もいるんですよ。僕が今まで取材してきた中でも「オレ、ルイス・ハミルトンってすっげえ尊敬してるんですよ。人権に関することとか積極的に発言するのはとても大事だと思うんですけど、なんで日本では誰もそういうことを聞いてこないし記事にならないんですか。おかしいじゃないですか」と、訴えてくる選手もいるんですね。だからそこは本当に人それぞれだと思うし、さっきも言ったようにメディアが聞かない、聞いたとしてもそれを放送しないし記事にしないという二重のフィルタリングが作用しているのかもしれないなと思いますね。
武田 2030年の冬季オリンピック招致に関して、スピードスケートの小平奈緒さんが、引退会見で、札幌五輪の招致運動について「(参加を要望されたけれど)いったん置いているところ」と言ったら、まるで招致反対の筆頭のように祭り上げられ方をしたことがありました。ああやって、一気に取り上げられる状況があると、「発言するのはやめておこうかな」と思ってしまうのかもしれません。
日本スポーツ界の中枢はスポーツウォッシングを知らない
武田 そういえば、アスリートがオリンピックで金メダルを獲ると、なぜか首相が電話をかけてくるじゃないですか。あれ、いらないですよね。もし自分がアスリートだったら、あの電話は断りたいです。
西村 「すみません、今は競技に集中したいんで」って。
武田 水泳や柔道だったら、その後に団体戦があるかもしれないし、なくても、勝利を分かち合いたい人は他にいるでしょう。なんでだろう、って思うんです。
西村 選手が競技団体や協会に慮って、断れない面もあるのかもしれないですけどね。
その話で思い出したんですが、しばらく前にJOCのある集まりに呼ばれて、スポーツウォッシングについて話す機会があったんですよ。話をする相手は日本国内のいろんな競技団体で仕事をしている人たちで、世界の組織と仕事をする場合に備えて国際感覚を養ってもらうためのレクチャーみたいなことの一環だったんですけど、話をする前に「皆さんの中で、スポーツウォッシングについてご存知だった方はいますか」って訊ねたら、30人弱ぐらいいた中で手を上げたのがひとりだけだったんですよ。
武田 えっ、それは情けないですね。日本のスポーツ界の中枢にいる人たちなのに。
西村 で、逆の質問で「スポーツウォッシングという言葉を知らなかった人」って聞くと、8割ぐらいの人が手を上げたんですね。この言葉を知らなかった人がそんなにいたのかということには、正直びっくりしました。知っていたのはサッカー協会の方で、カタールの一件があったので知っていますとおっしゃっていました。
武田 それだけ様々なスポーツ協会の人がスポーツウォッシングという言葉を知らなかったのであれば、この問題が浸透するまで、まだまだ時間がかかりそうですね。

西村 その時に話したのは、この本に書いたことの概要と、あとは今日ずっと話をしてきたように、今の日本の環境では、選手たちはほとんどそういう発言をしないし、メディアの側も発言を求めたりはしないけれども、その風潮もやがて変わってゆくでしょう、と。多数になるかどうかはともかくとしても、発言する選手は今後出てくるでしょう。その時に、炎上や反発が起こったとしても、選手たちを守ることができるのは皆さんなんですよ、皆さんが選手たちを守ってあげなければいけないと思うんです、という話をしたんですが、興味深く聞いてくださっていたようなので、ある程度は伝わったのかなと思うんですけどね。
その話をしている時に、「選手が(人権などに関する)発言をしたいとなったら、やっぱり協会のトップに話を聞きに行きますよね」みたいなことをおっしゃる人もいるんですよ。そこで協会の会長が「選手にそんな発言をさせちゃダメだろう」って言ったりすると上からの圧力が働くんだろうけれども、そうじゃなくて、あなたたちはその競技界の中間管理職として上を見るのか下を見るのか。あなたたちが守るべきは、上司の機嫌じゃなくて選手ですよね、という話をしたんだけれども、だからといって実際にそういう場になったら、競技界の人たちがどう動くのかは、わからないですけれどもね。
武田 かつて選手として名を馳せた人がスポーツ協会の会長をやると、部活の先輩後輩のような関係性がずっと続く、という話もよく聞きます。2013年に発覚した女子柔道強化選手への暴力問題がまさにそうでしたが、あのような環境では現役プレイヤーたちが声を上げることは難しい。厳しい部活動の延長線上のような人間関係が、オリンピック招致や運営まで、ずっと地続きになっているんじゃないかと思ってしまいます。
西村 2030年の招致を断念した札幌オリンピックでもそうなんですが、やりたいと言っているのはあくまでも準備委員会や組織委員会で、たとえば北海道新聞がアンケートを取ると、いらないという回答が大半だったりするわけですよね。なのに止まらない。札幌の場合はもう止まらざるを得ないでしょうが、大阪万博でも今まさに同じような状態になっているわけで、あれ、いったいどうするんでしょうね。
武田 万博が、なかなか賛同を得られないのは、オリンピックのときに有効だった魔法の言葉、「アスリートはがんばっているんだから!」が使えないからではないかと思います。「建設現場の人たちはがんばっているんだから!」と言っても、共感はなかなか得られにくいですよね。
オリンピックにしても、アスリートたち自身がほぼ何も言わない中で、彼らの気持ちを勝手に代弁して、「このときのために、彼らは4年間ずっとがんばってきたんだ。なのに、今さら中止なんて無責任じゃないか」みたいなことを、大声で主張する人たちがいたじゃないですか。あれは何なんでしょうね。
西村 アスリートたちはそこにピークを合わせてやってきたわけだから、自分が誰よりも強い、速い、世界で一番なんだ、ということをその場で証明したい、という気持ちも、もちろんわかるんですよ。ただ、「だからといってこれでいいのか……」という逡巡や葛藤も、彼ら彼女らの中にはきっとあったはずだと思うんですよね。
そこでさっきの話に戻ってしまうんだけど、アスリート自身は自分たちを取り巻く周囲の環境を考えて口を慎むし、メディアもそこを拾い上げないままで進んでいって、結局のところ目立ったのが、外の人たちの「アスリートはがんばっているんだ!」という大きい声だとか、アスリートファーストというよくわからない標語。そこに回収されてしまって、アスリートたち自身がそのとき実際に何を考えていたのかはわからないし、最後まで伝わらないままなんですよね。
武田 彼ら彼女らが何を考えていたのか。絶対に葛藤があったはずです。
西村 東京オリンピックのときは、そういうものが何も伝わらない違和感が非常にありましたよね。
プロフィール

西村章(にしむら あきら)
1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。


 西村章
西村章
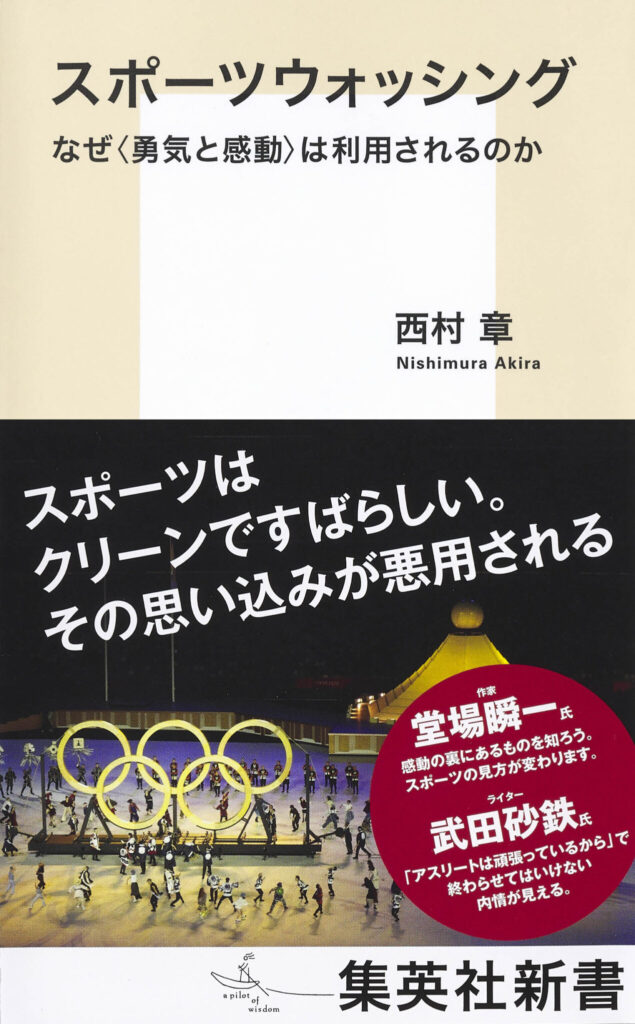












 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


