■「細い」ではなく「危ない」…やせ願望のリアル
この連載では「生活習慣病の改善と予防のために減量を科学的に理解して実践する」ことを追求しています。実践するにはまず、減量の必要があるかどうか、自らの体型や病気の有無の確認が必要だと、これまでに述べてきました。
しかし現実には、実際に減量が必要な人よりも、「自分が太いと思っているかどうか」ということが、ダイエットの有無に強く影響することが複数の研究で報告されています。
たとえば、順天堂大学の研究グループによる2023年実施の調査では、18~29歳の女性5,905名のうちBMI(体格指数。体重÷身長÷身長。第2回参照)が18.5未満の「低体重」(医学用語です)に分類される人は約23.5%であることと、そのうちの約30%にダイエット経験があることが報告されています(※1)。
BMIが18.5以下とは、たとえば身長が160cmの場合、体重は約47.4kg以下であることを意味します。この体重でもなおダイエットを経験しているというのは、栄養面、健康面から見て医学的に危険な行為であり、さらにその人数が低体重の人の30%にのぼるという事実には驚きを隠せません。
また、本連載で紹介している「糖尿病や肥満症の患者さんを対象とした糖尿病治療薬や減量目的の新薬」の誤った用い方に対しては、国や自治体、各医学会などから警告が発せられています。
さらに日本肥満学会はつい先日(2025年4月17日)、根拠が乏しいやみくもな「やせ願望」に警鐘をならす医学的な見解を発表しました。
これらはいずれも、体型、体重に関わる医学的、社会的な最新ニュースでもあるため、今回、減量の実践法を紹介する前に触れておきます。
■低体重は憧れではなく「症候群」…肥満学会が警告
まず、前述の日本肥満学会の発表はこうです。過度な痩身願望によって、低体重や低栄養による健康障害を「女性の低体重・低栄養症候群(FUS:Female Underweight/Undernutrition Syndrome)」として新たに定義する案を発表しました。この情報は多くのメディアで報道されたので、耳にした人も多いでしょう。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」令和5(2023)年版によると、日本の成人女性(20歳以上)におけるBMIが18.5未満の「低体重」の割合は12.0%です。とくに20~30歳代の女性では、20.2%に達しています。
また、その割合は、OECD(経済協力開発機構:現在、ヨーロッパ諸国・日・米を含め38カ国の先進国が加盟する国際機関)加盟国や先進国の中で最も高いことが、厚生労働省や内閣府、国際共同研究(NCD Risk Factor Collaboration)などの複数のデータで示されています。
同学会はそうした現状を危惧し、「やせていることが美しい」という価値観がネットを中心に広く浸透していることを指摘し、健康上の問題を具体的に警告しました。
同症候群の症状には、骨密度の低下、月経周期の異常、不妊、妊娠合併症、貧血、筋力低下、抑うつや不安などの精神・神経症状、代謝異常、徐脈、低血圧、摂食障害などがあります。現時点での対象は18歳以上で閉経前までの女性ですが、今後は対象年齢などの拡大も検討されています 。
現段階では、新たな病名や制度が公的に決定したわけではなく、名称や診断基準は今後、定義・運用していくという医学的・社会的な問題提起です。しかし将来的には、メタボリックシンドロームのように広く認識され用いられる概念になると思われます。
■その薬は本当に医療? 「GLP-1ダイエット」は危険
第1回・第2回で述べたように、「GLP-1受容体作動薬」「GIP/GLP-1受容体作動薬」の新薬は糖尿病や肥満症の患者さんを対象に、体重減少と血糖値改善において画期的な効果を発揮しています。そのため世界中の医療界でニーズが高く、経済界にも影響が及んでいます。
そうした社会現象を背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつあるという見かたがあります。
ただし、新薬の世界的な売り上げのすべてが、病気の治療目的で医療機関において適切に処方された結果というわけではありません。
「GLP-1受容体作動薬」「GIP/GLP-1受容体作動薬」とは、医学や薬学の専門用語です。ところがいまや、美容目的のダイエット外来クリニックや、一般の「美容のためにやせたい人」のあいだで「GLP-1ダイエット」と呼ばれ、「週に1回の注射で劇的にやせられる夢の薬」といった情報が広まっています。
これらの薬を肥満症の治療目的で処方するには厳格な施設基準があります(第2回参照)。一部の基幹病院に設置の専門的な肥満外来でしか処方できないほど、厳密に管理される薬剤です。
それにもかかわらず、専門的な体制を欠いた自由診療の美容クリニックやオンライン診断などで安易に処方されている現状は、医師として看過できない深刻な問題です。
同薬は、俗に「やせ薬」とも呼ばれ、美容ダイエットを目的とする自由診療や通信販売で高額(公的医療保険適用の自己負担額の数倍とか)にて流通しています。世界的な大ヒットの背景には、欧米や日本でのこうした適応外の購買が大きな割合を占めていると推定されています。
このような需要の急増で同薬は品薄になり、2023年の夏から秋にかけては、製薬会社による限定出荷に陥りました。すると、本来、同薬を必要とする2型糖尿病の患者さんに行き渡らない事態が発生し、厚生労働省、製薬会社、日本医師会、日本糖尿病学会が公式に自由診療による適応外処方に警告を発する事態となりました。
これは治療の現場にとって、極めて切実な問題です。現在は供給が回復していますが、今後も複数の新薬の市場投入が公表されており、同様の事態の再発が懸念されます。
また、厚生労働省・消費者庁・国民生活センターなどの公的機関が公式に、医療関係者と一般の人向きにそれぞれ、注意喚起をくり返し発信しています。
美容医療の広告規制は毎年更新、強化されていますが、「それらの警告を知らないまま、広告だけ見て減量効果を信じ、自由診療で高い薬を購入してしまった」「オンライン診療で体調が悪化したと伝えても、返品はできないと言われた」などという一般の人の後悔談は後を絶ちません。
さらに医療としての問題にとどまらず、薬の定期購入システムや高額な解約金など、費用にまつわるトラブルも多発しています。
病院やクリニックによる広告の表現や掲出方法には法的な規制が設けられています。オンライン広告も同様です。しかし、わたしが確認しただけでも規制に違反する広告はいくつも見受けられます。
こうした医療広告の表現や読み取りかたについては、京都大学大学院健康増進・行動学分野准教授の田近亜蘭医師の著書『その医療情報は本当か』(集英社新書)にて、一般の人にもわかりやすく詳述されているので紹介しておきます。
■意識喪失、けいれん、急性すい炎…「やせ薬」で健康を失う
その問題に加えて、やせ薬と呼ばれる薬による副作用が、世界的に深刻な社会問題となっています。肥満症や糖尿病ではない人がダイエット目的でこれらの薬の服用を続けた場合、健康への影響はどうなのでしょうか。
第2回で述べたように、当クリニックで「GLP-1受容体作動薬」を用いる患者さんの約20%が吐き気、胃部不快感、嘔吐(おうと)、下痢、便秘などの消化器系の症状を訴えています。この頻度は、ほかの多くの薬と比べても「突出して高い」のです。そのため、専門医の管理のもとで、患者さんのメリットとリスクを考えて用量を調整しながら、慎重に用いなければなりません。
処方の対象外にもかかわらず、「やせ薬を飲みたい」「GLP-1ダイエットをしたい」と希望する人の中には、日ごろからダイエットのために食事や水分を過剰に制限している、また、BMIが18.5~25の「普通体重」や、先述の18.5未満の「低体重」に分類される人であるケースも少なくありません。
そのような人が自由診療の通信販売などで入手した同薬を注射や内服した場合、重度の低血糖で意識を失う、けいれん、昏倒、後遺症が残る、さらに、常用や長期使用をすると、すい臓(血糖値を安定させるインスリンを分泌する臓器)に負担がかかって急性すい炎による激しい腹痛や背中痛に襲われるなど、予期しない重篤な症状に見舞われる危険性があるのです。
今回の新薬にかかわらず、糖尿病の治療薬では、何年も前から同じ事象がありました。日本糖尿病学会ではたびたび、「病気ではない人が糖尿病治療薬を服用することの危険性」について公式に警鐘を鳴らしてきました。
ダイエットをしたいからといって、自分に必要がない薬を入手し、副作用について考えなく服用する……その選択は、自分で自分の健康を危険にさらす無謀な行為です。副作用を軽視し、自己判断で薬を使えば、本来は避けられたはずの新たな健康リスクを自らまねくことになりかねません。副作用の代償は、美しさではなく、かけがえのない健康の喪失です。
わたしが考える減量の目的は、「高齢期までも長く健康に過ごすこと」にあります。
これらの薬がどのように作用して血糖値の抑制や体重・内臓脂肪の減少をもたらしているのか、それは最近明らかになった食欲のメカニズム、腸内細菌、ストレス、神経の働き、睡眠のありようなどと密接に関係しています。これからは、そうした科学的な知見を理解しながら実践する、見た目重視ではない「健康重視の減量」の時代であるとわたしは考えています。
■肥満や糖尿病への偏見…「自己責任論」からの脱却
これまで、「食欲や食事の内容、量をコントロールできる人は理性的で、食べ過ぎて太るのは怠惰だからだ」といった見方がされてきました。しかしその観点はいま、減量効果を持つ新薬開発の研究成果を根拠のひとつとして、大きく見直されています。
従来の観点は「体重スティグマ」「肥満スティグマ」「糖尿病スティグマ」などと呼ばれます。スティグマとは、「偏見」や「差別的な見方」のことですが、もともとは罪人に焼き印や刺青を入れて社会的に区別することが語源です。たとえば、病気や体型など、本人の特徴に対して「自己管理ができていない人」「だらしない人」といったマイナスのレッテルを貼られ、周囲から不当に扱われてしまう——それがスティグマです。
アメリカでは糖尿病学会が2015年の診療ガイドラインから「スティグマ解消」を明記し、複数の学会が声明や政策を打ち出して実施しています。
また、WHO(世界保健機関) は2023年に「肥満の予防と管理のための保健サービス提供枠組み」を発表しました。2025年にはWHOヨーロッパが医療従事者への専門教育をはじめ、肥満や糖尿病を「自己責任」ではなく「支援が必要な慢性疾患」であることを認識する啓発キャンペーンを推進しています。
日本でも、日本医療政策機構が2024年、「肥満症対策に求められる6つの提言」を発表し、肥満や糖尿病に対するスティグマの解消を重要な柱に挙げています。とくに、「偏ったボディイメージ」や「肥満=自己責任」という考えからの脱却を提唱しています。
地域の活動例では、千葉市・千葉大学・製薬会社のノボ・ノルディスクファーマが連携協定を締結し、肥満や肥満症に関する認識不足や誤解によるスティグマの解消に取り組んでいます。
また、日本糖尿病学会・JADEC(日本糖尿病協会:2024年6月にアドボカシー活動推進団体として英字に改称)は合同で2019年11月に「アドボカシー委員会」を設置し、「糖尿病であることを隠さずにいられる社会づくりを目指して」を発表しました。アドボカシーとは、「病気や差別、貧困などの問題に直面する人の治療の権利を守り、改善すること」で、患者さんが糖尿病を理由に不利益をこうむることがない社会を目指した活動を続けています。
また、同会と同協会は現在、「糖尿病」という名称の変更を検討中です。すでに報道はされていますが、国際的な「ダイアベティス」(diabetesのカタカナ表記)を用いる案が浮上しています。
変更提案の理由は、以前から、「尿」という文字の印象や「甘いものの過剰摂取による病気」という誤解が、患者さんへのスティグマを助長するなどの懸念にあります。
過去には、「痴呆症→認知症」「精神分裂病→統合失調症」など、差別解消のための病名変更が実施されてきました。
ただし、ダイアベティスという英語はわかりにくい、なじみがないなど病名変更への慎重論もあります。今後、1~2年をかけて患者さんや医療関係者から意見を収集、行政手続きを含む正式変更を目指しています。
病気や障害に対するスティグマは、肥満症や糖尿病に限らず、精神疾患や感染症などにも広く見られ、こうした偏見をなくそうとする社会的な取り組みが続けられています。
医師や医療関係者はもちろんのこと、われわれ一人ひとりを含む社会全体がこの問題に正面から向き合う必要があります。
肥満や糖尿病は決して「自己責任」だけで語れるものではありません。生活環境や遺伝的要因、ストレスなど、さまざまな背景が関係しています。しかしながら、「努力が足りないから太る」「だらしないから病気になる」といった偏った見方は、患者さんを深く傷つけ、必要な支援から遠ざける要因になります。
医療の現場で感じるのは、患者さんはまず、「家族や職場の上司、同僚、友人、近所の人たちが病気について理解してくれているか」に直面するということです。「身近な人による理解」が、慢性疾患によるストレスを軽減し、治療への前向きな姿勢や再発の予防に大きく影響するのです。
肥満症、糖尿病、脂質異常症、高血圧症は誰でもかかる可能性がとても高い病気です。これからの治療において大切なのは、薬や治療法の進歩だけではなく、患者さんを取り巻く社会のまなざしがより温かくなることです。スティグマをなくし、誰もが安心して治療を受けられる社会を目指していきましょう。
■ピンピンコロリの現実は突然死
周知のとおり、日本は、平均寿命も健康寿命もいずれも世界で上位になっています。健康寿命とは厚生労働省の定義では「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の平均」のことです。
しかし、平均寿命から健康寿命を差し引いた年数、つまり要介護や寝たきりを含み、自立した生活ができない年数といえば、2019年のWHO発表によると日本は世界で33位となっています(「差」については現時点で2019年が最新のデータ)。
また、厚生労働省が公表した「令和4(2022)年簡易生命表の概況」と、「健康寿命の令和4年値について」では、次のようになっています。なお、平均寿命は毎年公表され、健康寿命は3年に1回公表されるので、ここでは2022年の数値を取り上げます(引き算が合わないのは四捨五入の影響)。
・平均寿命:女性87.09歳、男性81.05歳
・健康寿命:女性75.45歳、男性72.57歳
・その差 :女性11.63歳、男性8.49歳
平均して「その差」の年数が、自立した生活が困難と推定されるわけです。患者さんでも医療者でも、「ピンピンコロリで逝きたい」という人はとても多いのですが、それは「この差を縮めたい。要介護や寝たきりを避けたい」という思いにほかならないでしょう。
患者さんから、「ピンピンコロリを実現するには、生活習慣病の治療や予防をしないで、血液ドロドロのまま高齢期を過ごすべきでは? 血液がサラサラだとコロリと逝けないですよね」と聞かれることがあります。
いろいろな考え方があるとは思いますが、医学的にはそうではありません。実際には、「ピンピン」とは健康寿命の状態であり、「コロリ」とは突然死のことです。
WHOの定義では、「突然死」とは、発病から24時間以内に内因的な原因で亡くなることを指します。
日本でも突然死は身近な問題であり、その主な原因は「心原性突然死(心臓突然死)」と「脳卒中」です。
『心臓突然死の予知と予防法のガイドライン(2010年改訂版)』(日本循環器学会など関連学会による合同研究班)によると、心臓突然死は、「急性の症状が発症した後、1時間以内に突然意識喪失を来たす心臓に起因する内因死」と定義されています。心臓の病気が原因で発作や症状が現れてから1時間以内に起こる、予期せぬ死亡ということです。
日本では、突然死の発症数は年間およそ5万人と推定され、その多くは心筋梗塞や重度の不整脈(心室細動など)が引き金であるといいます。実際、同学会の報告によれば、日本における突然死のうち大部分が心原性とされています。
脳卒中も突然死の原因の1つですが、いくつかの調査によれば心臓の病気ほど多くはなく、突然死全体のうち約10~20%と報告されています(※2・※3・※4・※5)。
ただ、くも膜下出血や脳出血、重度の脳梗塞(とくに脳幹梗塞)では急激に意識を失い、呼吸が止まることがあります。こうした状態では、窒息感や激しい胸痛や頭痛などの苦痛を伴うケースがあることや、現実として突然死は予測不可能であるため、完全に「ピンピン」な状態から苦痛を伴わない「コロリ」はまれなのです。
このように突然死とは、ことばの響きからは突然に起こるように思うかもしれませんが、実はその背景には「動脈硬化」をまねく「生活習慣病」が深く関係しています。
第6回と第7回で述べたように、肥満症、脂質異常症、糖尿病、高血圧症が原因で血液がドロドロの状態であり、心筋梗塞や脳卒中を引き起こした可能性が高いのです。実際、突然死の多くが、これらの生活習慣病と関連しているという報告もあります(※5)。
そして厚生労働省の「国民健康・栄養調査」の2022(令和4)年版から推計すると、日本人の40歳以上の約半数が、生活習慣病のいずれかを有しており、動脈硬化が進行していると考えられています。だからこそ、体重過多の場合は減量が必要になるのです。
■わたしが伝えたいのは「セルフケア✕医療でピンピンスーッ」
前回までにこれらの生活習慣病は、体のどこかが痛むわけではなく、血液検査などをしないと気づかないうちにじわじわと進行することを伝えました。しかし放置すると、全身の血管、神経、多くの臓器に不調と合併症が現れ、つらい症状に悩むことになります。亡くなる直前まで元気そうに見えていたとしても、実は闘病中だったという事例はとても多いのです。
また、「ピンピン」の状態を長く保つには、血管や内臓の健康だけではなく、感染症やケガに対する免疫、筋力、また認知機能の維持、うつや孤立の防止、医療をはじめとする社会とのつながりなど、幅広い活動が必要です。
そして「コロリ」とは、単に「瞬間的、突然に亡くなること」ではなく、自立した日常生活を送りながら寿命を全うすること、それが多くの人が望む姿ではないでしょうか。
すると、ピンピンコロリを実現するには、生活習慣病の予防・改善を実践してできるだけ長く自分らしく生きる視点を持つことが大きな要因となるはずです。そうした現実からわたしは医師として、「コロリ」ということばのとらえかたには違和感を覚えています。
そこで提案したいのは「ピンピンスーッ」という表現です。これはわたしの造語です。ピンピンとは「できるだけ自立して活動的に過ごす高齢期」であり、スーッとは「年齢に応じて少しずつ活力が落ちていくものの、穏やかに、自然に歩んでいく」という意味合いです。
それには、現時点で明らかになっている適切な科学情報に耳を傾け、医療のみに過度に頼ることなく、自ら生活習慣病を改善・予防することが第一の選択ではないでしょうか。
そして医療者が目指すのは、患者さんの苦痛を抑えながら、QOL(生活の質)を支えることです。
ピンピンスーッとは、一人ひとりのセルフケアと医療の積み重ねによって実現していく生きかただと、わたしは考えます。
次回に続きます。
※1 Murofushi Y, Yamaguchi S, Kadoya H, Otsuka H, Ogura K, Kaga H, et al.
Multidimensional background examination of young underweight Japanese women: focusing on their dieting experiences. Front Public Health. 2023;11:1130252.
※2豊田章宏. 全国労災病院データからみた急死例の検討. 日本職業・災害医学会会誌. 2014;62(1):57-62.
※3 林千治,豊嶋英樹. 新潟県における突然死 : 虚血性心疾患の占める割合と突然死発症に関連する要因. 新潟医学会雑誌. 1995;109(6):263–267.
※4 岩本 廣満, 清原 裕, 藤島 正敏.日本内科学会.講座:突然死-突然死の実態とその病態生理. 日本内科学会雑誌. 1998;87(1):58–64.
※5 清原裕.変貌する生活習慣病の現状と課題:久山町研究.第50回日本人間ドック学会誌.2009年;24(Suppl):1169–1173.
構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。
プロフィール
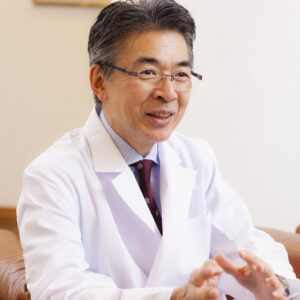
大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。


 福田正博
福田正博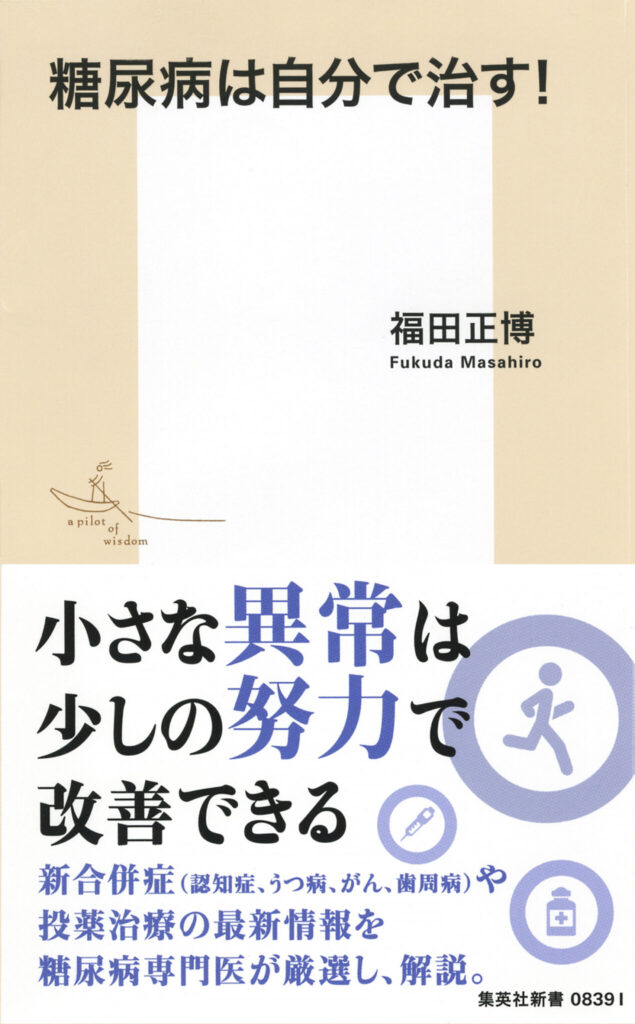










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


