
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第3回 隠岐さや香 未来世代の「自由」を殺さないために
科学史の研究者で、科学アカデミーについて研究してきた名古屋大学教授の隠岐さや香さん。日本学術会議の連携会員でもあり、2014~2015年に行われた「日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議」では委員として提言も行っている。今回の日本学術会議の会員任命拒否問題について、科学アカデミーの歴史を手がかりに寄稿して頂いた。
「学問の自由」とアカデミー
菅首相が6人の会員の任命拒否を行い、その理由が明らかにされなかったとき私は驚いた。まるで、前近代的な歴史的事例を目の当たりにしているかのような感覚に陥ったからである。
私は18世紀のフランスに存在した科学アカデミーの歴史について研究をし続けている。当時の科学アカデミーは優れた才能を持つ学者を集めた組織であり、研究発表の場であると同時に、国家の科学・技術的な問題に関する諮問を受ける場であった。その歴史において、フランス国王が説明もなく、アカデミー会員により優先順第1位とされた候補者を任命しないことがあった。その話を真っ先に思いだしたのである。後になって、その行動が日本学術会議法という同組織の根拠となる法に照らし合わせても違法とみなされうると知って納得した。
この問題は即座に「学問の自由」(academic freedom)が侵害されたとの反応を呼んだ。米英仏独のメディアでもそのような扱いを受け、国内でも様々な学協会が声明を出した。この声明について調査中の埴淵知哉氏(東北大学)によると、2020年11月6日の時点で686件の声明が確認されたという[1]。また、作家、芸術家など表現の仕事に携わる方々からも活発な議論提起があった。しかし、世論調査ではそもそも首相の行動の何が問題なのかわからないという反応も多かった。
その状況を追い風としたかのように、政府与党は学術会議に関するプロジェクトチームを立ち上げ、2ヶ月という恐るべきスピードで改革を提案するに至った。3年ほどかけて国立の組織から非政府組織になってほしいという[2]。要求の内容はともかく、改革要請の経緯が異常である。しかも任命拒否の理由についてはまだ説明がない(2020年12月18日現在)。
こうした事態を受けて、ひとまずやっておかねばならないのは「学問の自由」とアカデミー組織の関係について説明することだと私は考えた。なぜなら、それを理解しないと、日本の戦後社会を築いた人々が私たちに何を伝えようとしたのかもわからなくなるからである。このままでは、先人が世界から受け取り、作り上げたものが台無しになってしまうのではないか。このような危機感を抱いたことから、私は本記事を執筆することになった。
国際通念におけるアカデミー
日本学術会議は学術が関わる国際会議においては、「ナショナル・アカデミー」の一つとみなされている。すなわち、日本を代表するアカデミーということである。たとえばインターアカデミーパートナーシップ(IAP)や国際学術会議(ISC)のような各国のアカデミーや学術団体の代表が集まる場には学術会議が参加している。
アカデミーとはもとの古い理念を辿れば、学問のための自由な個人による会合のことである。英語圏では一般的に「学術協会」(learned societies)と呼ばれることもある。その本質は、地位や身分や国籍の違いなどを一旦留保して、自由に知を求める個人として集う場を作るということにある。そのため、身分制の時代であっても、敢えて対等に近い対話をするための作法やルールが模索されてきた。また、専門学会と違って複数の分野を集めていることにも特徴がある。
歴史的経緯を踏まえれば、自由に人が集うアカデミー的、あるいは学術協会的な活動が先にあり、後から専門的な学会が発展したと捉える方がよいだろう。特に19世紀以降、西欧と北米においては大学が研究の場となり、業績発表の場は専門学会に移った。もとのアカデミーはといえば、学術研究をもとにした知見を社会に発信する場となっていった。
日本で最初のアカデミーは民間組織として立ち上がった明六社である。明六社のメンバーは福澤諭吉、津田真道、森有礼といった、日本の明治維新で活躍した錚々たる人々である。日本の「近代化」のための知識人グループとして知られるこの団体が主に教育や経済、道徳について語り合う「アカデミー」の一種であったことは一般にはあまり知られていない。だが、明六社が後に日本のアカデミーである東京学士会院(後に帝国学士院、戦後に日本学士院 The Japan Academyと改称)の母体となったことからもそれは明らかである。
学者が自由闊達に議論する「学術協会」の設立というのが当初の目的であり、創立に当たって森有礼はアメリカの識者から助言を得てもいた。その精神は、津田真道が「たとえ政府の命といえども、無理なることはこれを拒む権あることを知らしめ、自主自由の気象をわが人民に陶鋳する[教えて導くこと]は、我輩のおおいに望むところ」[3]と述べたとおりであった。
他方、日本学術会議は、第二次世界大戦における学者の戦争協力に対する反省をもとに誕生した。GHQの助言を得て戦後の新しい学術体制を作る動きがあり、民主主義社会のための新しいアカデミーとして学術会議が誕生したのである[4]。
初期の学術会議は「学者の国会」を目指したことでも知られる。現在のように業績に優れた学者を現職会員が推薦するという形ではなく、日本中の研究者が選挙で会員を選ぶ方式だったのである。これは他の国のアカデミーにはない特徴であり、いわば実験だった。
このことにより、日本学術会議が他のアカデミーとは違い、政治的な組織だったと捉える人もいる。だが、それは早計だろう。というのも、「学者の国会」を自称してきたのはパリの科学アカデミーでも同じだからだ。実態はともかく、理想としてはそれを掲げたのである。これが偶然の一致とは考えられない。戦後の先人達は他の国のアカデミーが掲げる理念を知った上で、よりそれに即した理想を追求しようとしたのではないだろうか。たしかに選挙制自体は1984年の法改正により廃止されてしまった。だが、その試行錯誤の歴史は貴重な経験であったと私は考えている。
ヨーロッパにおける「学問の自由」とアカデミー
日本の社会と「学問の自由」とのつきあいはいささか日が浅いといえる。1889年の大日本帝国憲法には学問の自由に関する規定はなかった。手本とした1850年のプロイセンの憲法20条には「学問の自由」があったのだが、それは受け継がなかったのである[5]。一方で、1886年に発布の帝国大学令第一条には「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」[6]との言葉が見られる。すなわち、国家に必須とされる学術と技芸を教え、探求するのが帝国大学の役目とされていた。そこに見て取れるのは露骨な実利主義の精神である。
戦後日本国憲法に書き込まれた「学問の自由」はアメリカの影響と言われる。だが、意外なことに、アメリカの憲法には学問の自由の規定はないらしい。教育関連法に記載のあるイギリスやフランス、憲法に記載のあるドイツとは違うのである。
これにはアメリカならではの事情もあるようだ。まず、同国は18世紀末にイギリスから独立した国であり、個人の「自由」がしっかりと憲法で保障されている。また、貴族のような特権階級を持たない平等な国という前提がある。そのため、研究者や大学教員という一部の層だけに特別な自由を法律に明記するのは、エリート主義的として敬遠される土壌がある。
しかし、その一方でアメリカでは市場原理があまりにも浸透したがゆえに、教育や研究に対するその弊害が露わになる機会も多かった。それで逆説的にも「学問の自由」についての議論がむしろ蓄積されてきたようである。戦後の日本に受け継がれたのはそのようにして育まれた理念の部分であった。
アメリカでも「学問の自由」の考え方には何種類かあるのだが、ここではそれを「表現の自由」の親戚のようなものとみなす考え方を紹介する[7]。まず、民主主義的社会には表現の自由があり、本来、政治的な発言によってみだりに解雇されたり、排斥されたりしてはいけない。それでも多くの仕事では、たとえば一年のうちに売り上げ目標を達成するといった特定の目的に逆らう発言の自由は実質上許されず、多くの人が大なり小なり自由を侵害されながら生きている。それゆえ、このような現実が際限なく人々の自由を蝕むことがないように、歯止めとして「学問の自由」を保障された職業があるというのである。その職業に就く彼ら彼女らは、いわば社会全体が享受できる自由の度合いを下支えするために、意見を発信し続ける役割を担っていることになる。要は「学問の自由」を尊重することが、めぐりめぐって最終的には民主主義社会を守ることだという考え方である。
大学における「学問の自由」と軍事研究
日本学術会議は2017年に、大学が「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究」に関わる場合、その適切さについて学内で倫理的な審査を行うことが望ましいと主張した[8]。これをもって学術会議が軍事研究をする「学問の自由」を抑圧したと批判する人々がいる。また、軍事研究を受け入れない日本の大学は世界の常識をわかっていない、と訳知り顔に説く人もいる。
だが、私からすれば、それこそ視野が狭いというものである。そもそも軍事研究が「学問の自由」で守られるべきかどうかというのは、通常の軍隊を持つ国でも十分に議論の対象となる問題なのだ。
有名な例をあげよう。カナダのマギル大学では、ヴェトナム戦争のあった1960年代以降、一部の研究室が軍から資金提供を受けて燃料気化爆弾(サーモバリック爆弾)の開発に協力してきた。資金提供者には自国の軍や私企業だけでなく、米軍も含まれる。開発は秘密裏に行われていたが、1980年代に入り、同大の学生新聞記者が教授たちとカナダ軍の契約書類を見つけたことで学内に知れ渡った。そして、学生達と一部の教員を中心に大学内での軍事研究に対する抗議運動が広がりをみせた。
抗議運動の担い手達は、大学という場において、学生やスタッフである自分たちに秘密で人間に多くの害を与える兵器研究がなされていたことを許しがたいと考えた。抗議運動は4年間にわたって盛り上がりを見せ、最終的には、大学当局が軍事研究に対する事前の倫理審査を課す方針を打ち出すに至った[9]。同大学には今でも軍事研究反対の考えを受け継ぐ団体が存在しており、学生新聞には関連する記事が掲載される[10]。
ここで興味深いのは、北米の学生と教員たちが実に強烈な反対運動を展開したという事実である。北米は歴史的に見ても、大学を巻き込んだ軍事研究が非常に盛んな地域だった。原爆開発を成功体験として、巨額の資金が軍を経由して国家から大学に投下される流れが定着してきたからである。しかし、それに歯止めをかけたいという市民感情もしっかりと存在している。
いくら「学問の自由」があるとはいっても、それは人権への配慮抜きには成り立たない。なぜなら、民主主義の社会において、他者の自由を侵害する自由は許されないからである。そのため現代では、自然科学・医学分野の多くの研究において、安全性や人権への配慮がなされているかどうか、計画の段階で事前の倫理審査を行うことが定着している。近年は更に、社会科学系分野、即ち文系にもその波が押し寄せつつある。
要するに現代的な基準では、倫理的観点抜きで守られる研究の自由はあり得ない。従って倫理審査を経ないのであれば、いかなる研究も「学問の自由」により守られるべきではないだろう。しかも軍事転用しやすい研究の場合、軍需産業や軍事的組織という強力な出資者がいるため、わざわざ大学で「守られ」なくても研究できてしまう。
実際の所、日本政府も軍事研究の場は特に大学でなくてもよいと捉え、一部の民間企業に任せてきた経緯がある。さすがに直接的な破壊を担う狭義の軍事技術に関しては消極的な開発姿勢であったが、戦闘機の部品開発のようなそれ以外の軍事技術については官民の垣根を越えた軍事技術育成の努力がなされ、外国からは一時期高い評価を得ていたのであった[11]。
そのような形で日本社会では、いわば倫理的な議論も社会的合意も不充分なまま、なし崩し的に民間企業と大学との間で研究開発における役割分業を進めてきた。それが2010年代に入り急に防衛省の発出した文書で「デュアルユース」(軍民両用)技術をキーワードに大学との連携が言及されるようになり、2015年には防衛省の資金により大学でも関連研究を行えるという「安全保障技術研究推進制度」が始まったのである。しかし、そこには倫理的な問題の検討もなければ、経済的な側面の検討すら十分ではない様子が窺えた。何より、通常の科学・技術・イノベーション政策であれば関与があるはずの内閣府や文部科学省、経済産業省で具体的な議論がなされた形跡はなく[12]、突然研究資金の提案がなされたのであった。
要するに、戦後の科学者は「もう二度とこのような悲劇を繰り返したくない」と思い、軍事研究を行うまいとした。だが、大学の外の民間企業では可能であり、一定の歯止めはかけられながらもそれはなされている[13]。しかし政府はそこで留まらず、大学でもやろうと声をかけ出した。それを受けて「そうだ!やろう!」となるか、「いや、これ以上はもうやるべきでない」となるかで関係者の反応が分かれている状況にある。
私は「いや、これ以上はもうやるべきでない」の立場である。その理由は、経済的リスクと倫理的なリスクが大きいと感じるかだ。
経済的リスクであるが、軍事研究には基本的にお金がかかり、経済には負担となりやすい。冷戦期の米国が軍事費の膨張に苦しんだことは有名である。冷戦後に諸国が軍事研究のデュアルユースといいだした一番の理由は、各国における国防予算の縮小である。軍事研究が民間の市場にも利益があるという言い方をしないと国費を投入しづらい世界情勢になったのだ[14]。
そもそも、科学の発見という観点からすれば、その応用先として軍事研究と民生研究の明確な境目などあるはずがない。たとえば、純粋に科学的なウィルスの研究ですら、やり方によっては生物兵器開発のヒントになりうる。それで論文が公開停止になった例もある。
しかし、研究内容には軍事/民事の境目がなくても、「研究のやり方」には歴然とした違いがある。敢えて違いを設けてきたという方がよいかもしれない。科学は基本的に公開され、万人に広く共有されるべきものである(そのために現在、EUが世界を巻き込んで、あらゆる科学論文を公開にする政策を進めている)。それに対し、軍事研究はそれが戦略的に重要であればあるほど、徹底した機密性が求められる。ある研究によると、この文化の違いは、実際に巨大な官民軍事産業セクターを持ち、デュアルユース政策を進めたフランスにとってすら困難な課題として映っているようだ。そうした文化の違いがある場合、双方が自然に丁度よい形で折り合うことはなく、主流となった側が自らの目的を達するため、他の立場の人々の目標設定を支配する結果に終わりやすいという[15]。要は、相当な工夫をしない限りは、軍事・非軍事セクターそれぞれが目標を共有し、効果的に協力することは難しいということだ。
先に書いたように、現在の大学は厳しい倫理的基準を設けて研究活動を行っている。その今までの制度を大きく変えてまで、軍事研究を受け容れる利があるとは言いがたい。仮に資金難にあえぐ大学がそれで一瞬潤うとしても、そこでなされる研究が日本全体の経済的活性化につながるとも考えづらい。1990年代から現代までの経緯を見る限り、日本はアメリカに比べても格段に国費を投じてのイノベーション振興が不得手な国であるからだ。
さて、ここまでは実利的な側面を書いてきたが、軍事研究が日本の大学で仮に一般化するとして、最も大きく損なわれるのは、先人が世界に発信してきた理念である。実は、日本の研究者に伝わってきた軍事研究禁止の発想は外国にも共鳴する人々を生んできた。ドイツには民生研究のみに関わる(つまり軍事研究に関わらない)とする「市民条項」(Zivilklausel)を採用している大学が多いのである。この市民条項は日本から広がったものであったという。
2015年、ドイツのフィリップ大学マールブルクで、イナゴの空間認知能力についての研究が米国の国防総省から資金提供を受けていると発覚した。同大は市民条項を採用していたため、メディアや学生組織からの批判を浴びたという。また、この前後の時期に市民条項を採用する大学数が激増した。その多くは大学当局ではなく、学生団体の要求によるものだという[16]。若い世代が未来の学問の向かうべき方向について意思表明をしたのだ。
防衛のためとはいえ、あるところで人間をより危険に晒すための研究が行われるのなら、社会の中の別のところで、その発展をできる限り留めようとする意志が働くのは自然なことだろう。たとえるなら、車にアクセルとブレーキ両方がなければ危険であるのと同じことだ。
「もう二度とこの悲惨な戦争を繰り返したくない」と願った戦後日本の研究者の思いは、決して内向きの理想論などではない。それは未来への責任を切実に噛みしめた世代の声であった。だからこそ、似たような痛みを知った遠い国の人々、それも「学問の自由」を最初に憲法に書き込んだ地の人々にも受け継がれている。
今の日本の大学が大手を振って軍事研究を受け容れる場合、その研究活動に混乱が生まれるだけでは済まない。それは日本から世界に受け継がれた先人の思いを踏みにじってまで、不確かな経済的リスクを冒す愚行となる可能性が高いのである。
おわりに
「学問の自由」とは、考えることで、ものごとをよい方向に変えていけるという希望のための条件である。そして、未来世代の「自由」を殺さないための勇気を示す基盤でもある。私はそのように考えている。
言うまでもないが、この世の営みは全てがカネの論理で動くのでもなく、全てが上司のいいなりになるのでもなく、ましてや同時代の一部地域の人に気に入られるかということだけで決まるわけでもない。数百年前の抑圧的な身分社会を生きる人々ですらそう考えていた。そして、時には文字通り命をかけて、国境を越えた自由な議論の空間を作りあげてきた。
彼ら彼女らが行く先を照らしてくれたから、今がある。そのおかげで、今の社会はより自由になったはずではなかったか。
私は、その灯火を受け継ぎ、次に伝えていかなければならないと思っている。
[1] 正確には、2019年時点の日本学術会議協力学術研究団体のうち、11月6日までに単独もしくは共同(連合含む)で声明を出した学会が686団体あったとのこと。その後も声名は出続けているためこれより増えている。
[2] 自由民主党政務調査会内閣第2部会政策決定におけるアカデミアの役割に関する検討PT「日本学術会議の改革に向けた提言」2020年12月9日https://www.jimin.jp/news/policy/200957.html
同提案では外国のアカデミー、特に全米科学アカデミー(NAS)のような組織を作るための改革が主張されているがNASの組織構造を充分には踏襲していない。NASの組織構造については次を参照。Constitution and By-Laws of the National Academy of Sciences, Adopted January 1864, URL: http://www.nasonline.org/about-nas/leadership/governing-documents/constitution-and-bylaws.pdf.
改革に関する日本学術会議の考えは次を参照。日本学術会議幹事会「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて(中間報告)」2020年12月16日 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo305-tyukanhoukoku.pdf
[3] 山室信一・中野目徹校注『明六雑誌』上、岩波文庫、1999年、75頁。
[4] より詳細に述べると、戦前の日本は帝国学士院とは別に、主に理工系研究者の連絡・交流を担う学術研究会議という組織を1920年に作っている。両者は共に国際的なアカデミーの連合会議に代表者を派遣していた。ただし学術研究会議は第二次世界大戦期に科学者動員の中心的組織となった。たとえば次の文献を参照。青木洋「第二次世界大戦中の科学動員と学術研究会議の研究班」『社会経済史学』72-1(2006年9月)。戦後、学術研究会議の戦争協力に対する反省から学術会議が生まれた。
[5] 大浜啓吉「学問の自由とは何か」『科学』2016年10月号、1049-1055頁。
[6] 帝国大学令(明治十九年三月二日勅令第三号:https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318050.htm
[7] Stanley Fish, Versions of Academic Freedom: From Professionalism to Revolution, University of Chicago Press, 2014は「学問の自由」につい5種類の分類を行っている。(1)「ただの仕事」派、(2)「公共善のため」派、(3)「学術共同体の例外性」派、(4)「批判としての学問の自由」派、(5)「革命としての学問の自由」派である。紙幅の関係で本稿では主に(2)を紹介している。
[8] http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gunjianzen/index.html
[9] Alexandre Vidal, « Recherche militaire dans les universités. Quelle est la place de l’éthique ? Le développement de technologies de l’armement à l’Université McGill », Éthique publique, vol. 12, n° 1 | 2010, 123-138.
[10] http://mcgilltribune.com/sustainable-peace-for-a-sustainable-future/
[11] R. J. Samuels, “Rich Nation, Strong Army”: National Security and the Technological Transformation of Japan, Cornell University Press, 1994.
[12] 夏目賢一「デュアルユース技術研究の大学への期待と外交問題」『科学技術社会論研究』第16号(2018)、202頁。
[13] 安全保障技術研究推進制度には伝統的に防衛産業を担ってきた企業含め、民間企業、公的研究機関等の研究者からの応募があり順調に採択されている。
[14] 関連して、防衛技術の高度化により開発費が膨らみ、ますます効率よく技術開発をしなければならなくなったことも指摘できる。装備品等を一国で研究開発をすることも難しくなり、複数国で共同開発する風潮がある。ただし日本は比較的一国だけで防衛装備を賄おうとする傾向が残っている。ジョン・パーマ「日本の防衛産業は今後如何にあるべきか?」『防衛研究所紀要』第12巻第2・3合併号(2010年3月)、115-145頁。
[15] Valérie Mérindol and David W. Versailles, “Dual-use as Knowledge-Oriented Policy: France during the 1990-2000s”, International Journal of Technology Management · March 2010. DOI: 10.1504/IJTM.2010.031919
[16] German National Academy of Sciences Leopoldina and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), “Joint Committee on the Handling of Security-Relevant Research”, progress report of 1 October 2018, Halle (Saale), p. 30. ドイツと、デンマークの一部の大学で採用されている市民条項については次の記事を参照。https://www.insidehighered.com/news/2018/09/14/german-universities-pacifism-challenged-new-government-efforts
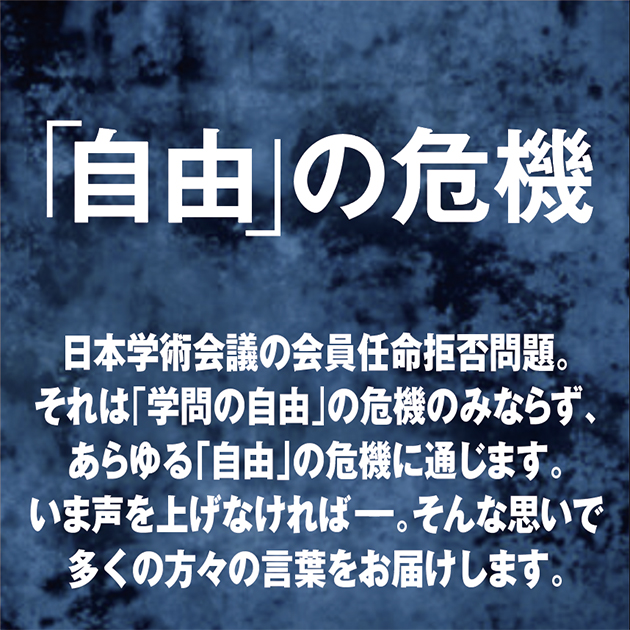
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

1975年東京生まれ。名古屋大学教授。専門は科学史。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。博士(学術)。広島大学大学院准教授を経て現職。『科学アカデミーと「有用な科学」―フォントネルの夢からコンドルセのユートピアへ―』(名古屋大学出版会)、『文系と理系はなぜ分かれたのか』(星海社)など。


 隠岐さや香(おきさやか)
隠岐さや香(おきさやか)









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

