
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第4回 前川喜平 教育から「自由」が奪われ続けている
文部科学行政の中枢で、権力による介入を目の当たりにしてきた元文部科学官僚の前川喜平さんに、日本学術会議の会員任命拒否問題についてお話を伺いました。学術会議への権力介入と通底する問題として、教育の現場でも「自由」が奪われて続けていると指摘します。その流れに決定的な影響を与えたと見るのが、2006年、第1次安倍政権下で行われた教育基本法の改正です。前川さんには、この法改正がもたらした負の影響や教育行政の現状について論じて頂きました。最後には、これからを生きる子どもたちに向けて、大きく後退しつつある「自由」の中でたくましく生きるための知恵も。これは、私たちが「自由」を守るためにも、心に留めておかなければならない、切実なメッセージです。
人事に介入する政権
日本学術会議の任命拒否の報道に接したとき、ついにここまで来たか、という感じがしました。
現在、官僚の人事は完全に官邸に握られているし、そのほかの一定の独立性をもった機関にも次々と官邸の政治的な支配が及んでいる、そういう状況です。たとえば、人事院などはもともと独立性をもった機関なのですが、東京高検の黒川弘務検事長(当時)の定年に関して国家公務員法を適用するなどという解釈変更を官邸に飲まされてしまった。2020年2月、人事院の松尾恵美子給与局長は「現在まで同じ解釈」と答弁しましたが、1週間後にその答弁を撤回。さらにその1週間後、一宮なほみ人事院総裁は、法務省と人事院の間で事前に解釈変更の文書確認が行われていたと答弁しましたが、これは虚偽答弁だとしか思えない。
なぜ私がそう思うのか、少し込み入っていますが、ご説明しましょう。
2020年1月31日、政府は国家公務員法を適用して、黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を閣議決定しました。
森まさこ法務大臣は、2月10日の国会で、国家公務員法の定年延長の規定は1981年の法改正時から検察官にも適用されていた旨の答弁をしました。この説明に対し山尾志桜里議員が、1981年の法改正時に、検察官に定年延長は適用されないと政府が答弁していたことを指摘。森大臣はそれを「承知していない」と答弁しました。過去の政府見解を知らなかったわけですね。
一方2月12日には、人事院の松尾局長が、検察官に勤務延長が適用されないという法解釈について「現在までも、特に議論はなかったので、同じ解釈を引き継いでいる」と答弁しました。
森大臣と松尾局長は正反対の答弁をしたのですが、1981年の法改正以来、法解釈が変わっていないという点だけは一致していました。
ところが2月13日の国会で、安倍首相は「今般、検察官の勤務延長に、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と答弁した。つまり、閣議決定の前に法解釈を変更してあったのだと説明したわけです。
2月19日の国会で「なぜ解釈変更を説明しなかったのか」と問われた森大臣は「問われなかったから」とはぐらかしました。また松尾局長は、2月12日に「現在まで」と言ったのは「1月22日まで」という意味だったと苦しい釈明をし、「なぜ間違えたのか」と問われると「つい言い間違えた」と、唖然とするような答弁をしました。
閣議決定の前に解釈変更を行ったという「ストーリー」を補強するため、政府が引っ張り出したのが一宮なほみ人事院総裁です。2月26日の国会で「いつ法務省と協議したのか」という自民党議員の質問に対し、一宮総裁は「1月22日に、人事院事務総長が法務事務次官から、法解釈が示された文書を受領した」「1月24日に、異議がない旨の文書を作成し、人事院事務総長が法務事務次官に直接渡した」と答弁しました。これらの文書には日付がありませんでした。事務方トップ同士で日付のない文書で直接協議するなどという事務処理は、およそ行政の常識を逸脱しています。
もしこの一宮総裁の答弁が本当なら、森大臣も松尾局長も、2月12日以前の答弁で解釈変更をしたと説明していたはずです。しかし彼女たちは、解釈は変わっていないと答弁していた。解釈変更をしたと言い始めたのは、2月13日の安倍首相の答弁の後です。つまり、この「解釈変更」は2月12日の夜に行われたとしか考えられません。したがって、一宮総裁の、法務省と人事院の間で1月に解釈変更の文書確認が行われていたという答弁は虚偽答弁だと断じざるを得ない。この一事で、人事院の独立性が失われたことは明らかです。
もっと遡れば、内閣法制局も行政府の法の番人という位置づけだったのですが、官邸は2013年に同局の長官の首をすげ替えて、集団的自衛権を認める人を長官にもってきた。法制局長官は内部登用という従来の慣例を破り、内閣法制局での勤務経験のない外務官僚の小松一郎氏を長官にして、集団的自衛権を容認する安保法案にお墨付きを与えさせた。
その他、NHKの経営委員、さらには最高裁判所の裁判官もかなり恣意的な任命がなされている。私が経験したことでいえば、2016年の文化功労者選考分科会の委員二人の差し替え指示です。それまでは文部科学省で人選した候補者が拒否されることはなかったのですが、そのときは杉田和博官房副長官(当時)から差し替えを求められた。一人の学者が「安全保障関連法に反対する学者の会」に入っていて、もう一人の文化人は、政権批判的なことを雑誌で何度か発言するなど、政権の方針に反対する言動があったというのが理由でした。
教育行政でいえば、第2次安倍政権発足以来、教育再生実行会議という教育改革の審議機関が内閣官房に置かれていますが、この委員は、安倍さんと当時文科大臣だった下村博文さんのお友達しかいなくて、多様性や公平性というものはまったくない。
そうやって行政府やNHKなどの人事が次々と官邸の意のままになってきた経緯があり、それがついに学術会議にまで及んだということです。学術会議は法律上独立性が担保されているのだから、その人事に介入するのは明らかに法律違反です。学術会議の独立性は憲法が保障する学問の自由に基づくものですから、その独立性を侵す法律違反は憲法違反にほかならない。
教育基本法改正、負の影響
学問や文化というものは、人類が何千年にもわたって自由な精神の上に築き上げたものです。現在の学校教育も、そうした学問や文化にのっとってその内容が決まる。学習指導要領の策定にしても教科書検定にしても、学問や文化の蓄積の上でなされなければならず、それに反することはやってはいけない。しかし、時としてそういう事態が生じます。
たとえば、2006年から2007年にかけての教科書検定で、高校日本史の教科書で、沖縄戦におけるいわゆる集団自決についての記述について、それまで認めていた表現を突然認めなくなったということがあった。沖縄戦で起こったいわゆる集団自決に対して、従来は「日本軍による強制」という表現が認められていたのに、強制や軍命という言葉を使うことを突然認めなくなったのです。日本軍による強制というのは、歴史学の世界で検証された事実として認められていたものなのに、その事実を曲げてしまった。
この検定内容が明らかになったのは2007年の春でしたが、それを知った沖縄県民はこの歴史の歪曲にたいへん怒り、同年9月29日にこの教科書検定の撤回を求める県民大会が開かれ、11万人もの人が集まった。この検定について文科省はいまだ撤回していないので、撤回せよという運動はいまも続いています。
私はこのとき文部科学省の中にいましたが直接の担当ではなかったので、どういう力が働いてこういう検定方針の変更が起きたのかの経緯はわかりません。具体的に何があったのかは想像するしかないのですが、この突然の検定方針変更がひどく不自然だったことは確かです。これには、おそらく2006年の第1次安倍政権の成立と教育基本法の改正が影響していると思います。
2006年は、第1次安倍政権の成立と教育基本法の改正が行われたという意味で、日本の教育が右傾化する一つのエポックメーキングな──良くない意味でのエポックですが──年で、ここからむき出しの政治が教育の中身に手を突っ込んでくることが起こり始めました。
教育基本法改正という政府の方針を初めて公にしたのは、2001年の通常国会での森喜朗首相の施政方針演説ですが、それ以前に中曽根康弘元首相が教育基本法の改正に意欲を燃やしていた。中曽根さんにとって、教育基本法の改正は憲法改正の露払いというか前段階という位置づけでした。中曽根さんは個人より国家が大事だと考えていた人ですから、それを明確にした憲法にするためにはまず教育基本法を変えなければいけないと思っていた。そうした中曽根さんや森さんの圧力が自民党の内部に脈々とあり、小泉内閣のときに教育基本法の改正の具体的なプロセスが始まって、法律改正まで行ったのが第1次安倍政権、という流れです。
教育基本法の改正で特に問題なのは、同法旧10条では「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」と規定していたのが、新16条では、「国民全体に対し直接に責任を負つて」に代わって「この法律及び他の法律の定めるところにより」という文言が入ったことです。
実は削られた「国民全体に対し直接に責任を負つて」の「直接に」という言葉が大事だったのです。もしこれが「間接に」であれば、国民が代表者である国会議員を選び、国会議員の中から総理大臣が選ばれ、総理大臣が文部科学大臣を選任する。国民から信任されている文部科学大臣なのだから、文部科学大臣がいったとおりに教育することは間接的に国民に対して責任を負っていることになってしまう。
しかしそうではなく、教える者と学ぶ者との関係は直接であり、それゆえ教師は目の前の児童・生徒に対して直接責任を負っているのだという、その直接性を担保するための教育行政の仕組みとして、戦後設けられたのが公選制の教育委員会です。住民から直接選挙で選ばれる教育委員会が教育行政を行うことで、首長、そして文部科学省(当時は文部省)からも独立しているという極めて独立性の高い地方教育行政制度だったのです。
「学問の自由」はすべての人がもつ人権
もう一つ問題なのは、旧10条では第1項の教育と第2項の教育行政の2つの条文に分かれていたのが、改正後の16条では一つの条文になって、教育と教育行政を峻別する考え方がなくなってしまったことです。これは従来の文部科学省の考えで、国公立学校における教育は教育行政に含まれる、つまり、教育行政の方が上位概念で、教育行政の中に教育が含まれるという考えです。言い換えれば、公務員である公立学校の教員が行っている教育は教育行政で、教育行政の中に学校教育があるのだ、と。この文科省の考え方は改正前から一貫しています。
この教育基本法の旧10条が新16条に変更されたことは、教育行政にとって大きなインパクトがあったのですが、辛うじて「不当な支配に服することなく」という言葉が残ったのは、不幸中の幸いでした。しかし、「この法律及び他の法律の定めるところにより」という、法律の根拠さえあれば政治が教育にいくらでも介入できるかのように読める条文が入ってしまった。実際、教育の内容、教育の実践に、国なり自治体なりが口を出すというのは法律の根拠がある限りは不当な支配にはならないというのが、改正したときの文科省の言い分です。
しかし私個人は、「不当な支配に服することなく」というのは、法律の根拠があったとしても不当な支配はできないのだと読むべきであって、「不当な支配に服することなく」というのは憲法から導かれる考え方なのだと思っている。なぜかといえば、教育の自主性が認められなければいけないからです。なぜ教育の自主性が認められなければいけないかといえば、学問の自由に基づいているからだ、というのが私の理解です。
学問の自由というのは、大学の先生だけの自由ではない。学問の自由は基本的人権であるから、すべての人がもっている当然の権利である。また学問というものも、難しい論文を書いたり難しい実験をしたりすることだけではない。現に、1872(明治5 )年に福沢諭吉が『学問のすゝめ』を書き、その中で「いろは四十七文字を習ひ、手紙の文言、帳合の仕方、算盤の稽古、天秤の取扱等」も学問だといっている。同じ年に明治政府が学制を発布して、その学制発布に際して太政官が布告した被仰出書という国民に対して学校に行きなさいと呼びかけている文章があり、その中に「學問ハ身ヲ立ルノ財本」という言葉がある。学ぶということは、職業に就いて身を立てていく元手(財本)であるから学校へ行きなさい、と。つまり、もともとの「学問」は学ぶことすべてを表していて、いまでいう「学習」という意味も含み込む言葉なのです。
だから私は学問の自由というのは、すべての人の基本的人権であって、それゆえアカデミズム、大学の先生だけではなく、小学校の先生、中学校の先生、もっといえば小学生も中学生も学問の自由をもっている。そもそも学ぶということは自由な行為なのだということです。
教育の自由そのものを規定した条文は、日本国憲法にはありません。明治憲法にはそもそも教育に関する条文がありませんでした。ところが、明治憲法発布前に市井の人たちによってつくられた私擬憲法の一つ「五日市憲法草案」の中には、「子弟ノ教育ニ於テ其学科及教授ハ自由ナル者トス」と、教育の自由を保障する条文があったのです。自由民権運動の先進性を感じますね。
教育から自由が奪われ続けている
このように、教育に関していえば、徐々に自由が奪われていく状況がずっと続いている。この状況の背後にあるのは、新自由主義と国家主義だと思っています。効率と有用性を優先して生産性を競わせるという新自由主義的な考えが世界的に広がってきていることと、個人よりも国家が大事だという国家主義的な価値観を植え付けようとする動き、その2つが同時進行している。
まず新自由主義についていえば、憲法上自由権といわれるものを大きく分けると、精神的自由権と経済的自由権に分けられます。たとえば、憲法19条の思想・良心の自由、20条の信教の自由、21条の言論・出版その他表現の自由、23条の学問の自由、これらは精神的な自由です。一方、職業選択の自由、財産権などは経済的な自由です。このうち経済的自由権のほうを最大限に保障して、公共の福祉という理念で制約することを極力避けて自由に経済活動させる、これが新自由主義の根本にあると思います。新自由主義の人たちは、経済的自由にはものすごく関心をもつけれど、精神的自由にはほとんど関心がない。一方で、精神的自由、心の自由を重んじるのが本来の自由主義、リベラリズムです。
精神的自由と経済的自由とを比べたときにどちらが大事なのかといったときに、私は圧倒的に精神的自由だと思っています。学生のときに憲法を教えてくださった芦部信喜さんがアメリカから学んできた理論に「二重の基準論」というのがあります。憲法上の自由権の制約が合憲であるか否かというのを判断するときに、経済的自由権と精神的自由権については、同じ考え方を当てはめるべきではない。経済的自由権のほうは、政策的に幅広く制限することができる。しかし、精神的自由権の制約については、極めて厳密に考えなければならない、と。精神的自由は最大限に保障されなければならず、公共の福祉という曖昧な概念で制限してはならない。他者の人権を守るためにどうしても制約せざるを得ない場合にしか制限できない。これが二重の基準論です。
これはアメリカの憲法判例で形づくられてきた考え方で、私もこれは非常に妥当な考え方だと思います。新自由主義的な人たちは、自分の金なのだから自分が使うのは勝手だろう、税金というのは国家による収奪であると思っていて、とにかく税金を払わないように考える。しかし、たくさん稼いでいる人や多くの資産をもっている人からはたくさん税金を徴収するというのが福祉国家の在り方です。20世紀に至ってようやく人類はそういうところまで進歩して、社会権というものを人権として打ち立てた。だから、貧しい人の生存権を保障するために豊かな人の経済的自由を制限するのは必要なことなのです。ところがいまの日本では、経済的自由の制限が取り払われる一方で、精神的自由がどんどん締めつけられるという逆の方向になっている。
その新自由主義と国家主義がなぜ結びつくのかといえば、新自由主義は必然的に国家主義を求めているからだと思います。新自由主義が前提としている人間像というのは、自分の利害しか考えない、お金で評価できる利益しか関心がないという人間です。そうした利己的な人間像を前提にしていると、自分以外の人間は競争相手にしかならない。お互い市場で争っているライバルだということになると、自分たち自身では社会の秩序をつくることができずに、国家という強い権力・権威が上から与えないと社会の秩序が得られないことになってしまう。そういう意味で、新自由主義と国家主義は非常に親和性が高い。
しかし、独立した個人が手をつなぎ合って市民となり、市民が対話や熟議の中から市民社会をつくっていく。これが本来の人間社会のあるべき姿ではないかと思います。民主主義の一番根っこにあるのは話し合いで、話し合いながらお互いルールをつくっていく。その前提にあるのは自由な個人です。自由な個人であることで、賢明な市民になり、その賢明な市民が市民社会をつくっていく。そういう市民像は、新自由主義からは出てこないし、国家主義からも出てこない。
私は学生時代にエーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』を読んで、こういう自由からの逃走が広範に起こることによってファシズムが生まれるのだと学びました。最近見直されている「自発的隷従」という言葉も「自由からの逃走」とほぼ同義だと思います。本来自由であるはずなのに、自ら大きな権威に付き従おうとする。そうした世俗の権威にすがろうとする考え方が国家主義を呼び込み、それがいま広範に広がっているのだと思います。
子どもたちへ−−まず、大人を疑うこと
教育の自由をめぐる問題で考えなければならないのが、上からの規範を押しつける、道徳の教科化です。自由を摘み取ってしまうような道徳教育が、強力に学校教育の中に組み込まれている。私は文科省で道徳の教科化が進行しているときにちょうど、その担当の局長でした。だから、お前がいえた義理かといわれるかと思いますが、道徳の教科化の議論をしている中で、「いや、これはまずいな」と思いつつも、政治の力でどんどん流されていってしまったことで、いまでも慚愧の念に駆られています。
私が局長だった2014年には、道徳の教科化はまだ議論をしている最中でしたが、最終的に2018年度から小学校、2019年度から中学校で制度として道徳の教科化が始まった。道徳の教科化がそれまでと何が違うかというと、検定教科書を必ず使って授業せよと、教科書が指定されていることです。それまでも道徳の時間はありましたが、教材は何を使ってもよかった。
それからもう一つ大きいのは、学習成果を評価しないというのが以前の道徳で、現在の道徳は新たに評価制度が導入されている。道徳の教科化の前段階として、当時の下村文科大臣の下で、文部科学省自身が『私たちの道徳』という指導資料、いわば国定教科書のようなものをつくったのですが、私はそのときの担当局長でした。といっても、内容にはほとんど口出しできなかった。有識者会議をつくってそこで議論したのですが、そのメンバーには下村さんのお気に入りで、日本の保守政治を裏から操っているといわれる日本会議系の人も入っていた。そういう場でつくられたものが道徳科の検定教科書の模範例になった。
この「国定教科書」の中に「うばわれた自由」という読み物がありました。その後つくられた小学校の検定教科書でも、数社が同じ読み物を載せています。封建時代のヨーロッパが舞台で、森の番人のガリューが、決まりを破って勝手に狩りをしたジェラール王子を咎めたために、牢屋に入れられてしまう。その王子は、王になってからもわがままに振る舞ったため、裏切られて投獄される。牢屋でガリューに再会した王子は、自らのわがままを反省する──。単にわがままはいけないというだけの教訓になっていて、自由とは何であるか、人類はいかに苦労しながら自由を勝ち取ってきたかという自由の価値については何も触れられていない。こんな教科書で自由を教えられる子どもたちは不幸です。
精神の自由をもつというのは、裏を返せば、疑うということです。どんな偉い人のいうことでも鵜呑みにしない。私が中学生、高校生の前で話す機会があるときに、必ず中高生に向かっていっているのは、「大人を信じるな」と。まず、自分を信じなさい。自分を信じる人間というのは自分に対する疑いをもてる人間です。自分が考えていることが100パーセント正しいなどと思っているのは思い上がりで、いろいろな人と対話する中で自分の考えを変えていくということは当然あり得る。そのときに、ここまでは自分が確かだと考えていることがあれば自信をもてる。誰かがいっていることをそのまま鵜呑みにしたら、本当の自信にはならない。だから、先生のいうことでもお父さんお母さんのいうことでも、頭から信じずに、一旦は疑いなさい、と。
ですから、もし若い人たちに学術会議問題で起きたような政治の介入がいかに危険なことであるのかを伝えようと思ったら、このままいけばどんどん国民の自由が奪われていくから反対しなさいと、頭ごなしにいうのではなく、まずその人に疑問を抱かせるように語りかけることが大事なのです。その意味では、大変なバッシングを受けましたが、ゆとり教育というのは、学習する子どもたち自身の中に疑問を生じさせて、なぜだろう、どうなっているのだろうという気持ちをもつことを大事にしていたことは見直されてもいい。
これからもいろいろな形で政治が教育に介入してくる場面が出てくると思います。滅私奉公を求める道徳教育、過去の侵略戦争や植民地支配を正当化する歴史教育、周辺国の軍事的脅威を強調する公民教育、正しい知識を与えることを否定する性教育などです。そのときに、教師であれ、生徒であれ、保護者であれ、市民であれ、これはおかしいのではないかときちんと声を上げて、その疑問をできるだけ多くの人たちと共有できるようにしていくことがとても大切であり、また、そこに希望をもちたいと思っています。
構成:増子信一
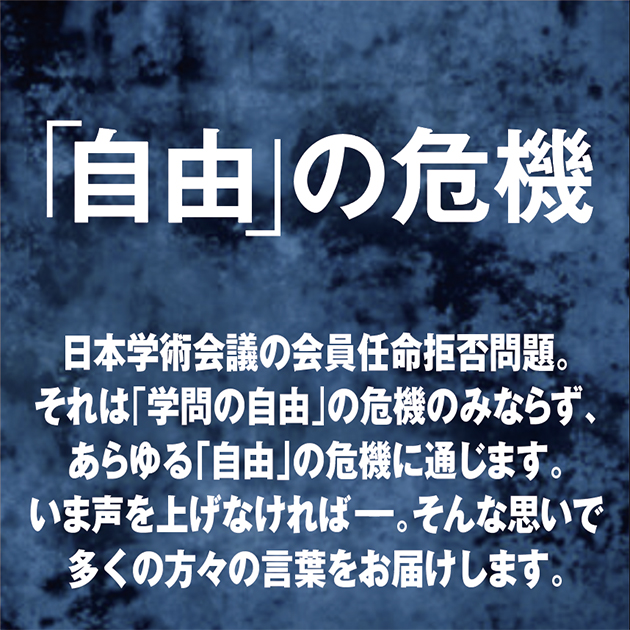
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

1955年生まれ。現代教育行政研究会代表、元文部科学事務次官。東京大学法学部卒業後、旧文部省入省。初等中等教育局長などを経て2016年事務次官。2017年1月、天下り斡旋問題で辞任。現在は執筆活動や全国で講演を行いながら、自主夜間中学での指導にも当たる。主な著書に、『面従腹背』(毎日新聞出版)、『これからの日本、これからの教育』(ちくま新書/寺脇研氏との共著)などがある。


 前川喜平(まえかわきへい)
前川喜平(まえかわきへい)









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

