分断と衝突を繰り返すアメリカ。今や国民の多くが「数年以内に内戦が起こる」との恐怖を抱いている。そうした時代の変化に伴い、民主主義と国民国家の在りかたに向き合ってきたアメリカ文学も、大きな分岐点を迎えている。
本連載ではアメリカ文学研究者・翻訳家で早稲田大学文学学術院教授の都甲幸治が、分断と衝突の時代において「アメリカ文学の新古典」になりうる作品と作家を紹介していく。
第2回目はSF作家、ケン・リュウの「紙の動物園」(『紙の動物園 ケン・リュウ第一短編集』ハヤカワ文庫SF 収録)。幼いころ中国から移住してきたリュウが、アメリカ戯曲の傑作「ガラスの動物園」にオマージュを捧げた「紙の動物園」で起こした、アメリカ文学の価値転換に迫る。
最近、中国からやってきた中国文学科の博士課程の学生を指導している。というと、まるで僕が、中国語がペラペラで、アメリカ文学も中国文学もいける、みたいな感じがするが、そんなことは全然ない。何年か前、中国語入門の本を一、二冊やり切ったが結局、ごくごく簡単な挨拶ができるようになっただけだった。
それで、中国からの留学生に頼んでもう少し中国語を勉強しようとしたのだが、あまりにも発音の種類が膨大で、しかもそこに四声(中国語の声調)が掛け算される、ということを発見してしまい、なんだか心が折れた。それで今のところそれっきりになっている。
じゃあ何を指導しているか、と言うと、普通に英語圏の文学である。なんだそりゃ、とおっしゃるかもしれない。お気持ちはわかる。もちろん単に英語圏の文学というわけではない。ある程度の年齢で中国からイギリスやアメリカといった英語圏に移住し、その後、英語で書く力を獲得して、今は小説家として活躍している作家たちの作品を学生と一緒に読んでいるのだ。
なんで中国文学科の学生がそういうものを学ぶのか。正直言って、最初は僕もそう思った。けれども、中国文学科の先生と話していて分かった。どうやら中国文学の世界では、物事の分類方法が英文科とは違うんですね。
英米文学の世界だと、けっこう分類が細かい。イギリス文学、アイルランド文学、アメリカ文学は全て違う専攻であり、国や歴史が異なるので、それぞれ担当教員も異なる。少なくともある程度の人数がいる大学では、イギリス文学とアメリカ文学の先生は分かれている。したがって学生も分かれているし、人間関係も研究する国ごとによって異なる。
けれども中国文学の世界はそうではない。そもそも日本に巨大な中国文学学科を維持している大学などない。ということは、数人で中国数千年の歴史をカバーしているのだ。怖い。あれだけ広大で、あれだけ歴史が長い国の文学を。つまり、現代担当の人が五百年や千年くらいは平気で教える、ということですね。アメリカが独立してから二五〇年くらいしか経っていないのに。ずっと現代アメリカ文学を教えてきた僕にとってはゾッとする数字である。
しかも中国には昔から、華人と言われる移民たちがいた。彼らは世界中に出て行き、中国文化を保ちながらも現地の文化に馴染み、さらには現地語でものを書いたりしてきた。そしてなんと、中国文学科の人たちは華人文学も中国文学だと思っているのだ。たとえそれが、中国語以外で書かれていても、である。
そんなの当たり前だろう、とあなたは思うかもしれない。けれども、パッと日本文学と言われて、英語で書かれたアメリカ在住の日系人の文学を思い浮かべる人がどれだけいるだろうか。
さて、話を戻そう。僕が指導しているのは武漢出身のKさんである。彼はむちゃくちゃにインテリで、好きな作家はプルースト、でも最近はアイルランドのウィリアム・トレヴァーに惹かれている、という。加えて、壺井栄の『二四の瞳』を中国語訳した。正直言ってすごい人だ。と同時に、なんで中国文学専攻なのかわからない。
もともと彼は、中国のかなり古い時代の文学を研究していたそうだ。だが途中で好きに生きることに決めて、英語圏の現代華人文学に突然、専攻を変えたらしい。いや、自分らしく生きるのは大事だけど、指導教員としては心配である。
彼が興味を持っているのがイーユン・リーやケン・リュウ、シャオルー・グオなどで、こうした英語圏の華人作家たちを扱った博論を書きたい、と言われた。平静を装いながら、そうですか、とは言ったものの、心の中ではかなり驚いた。イーユン・リーはアメリカの中国系作家で、ケン・リュウはアメリカのSF作家、そしてシャオルー・グオはイギリスの映画監督、かつ前衛小説家である。
正直言って、英文科的な価値観ではこの三人は全然違う。なにしろ、ジャンルも国も違うのだ。だから一緒に扱おう、なんて人に今まで会ったことがない。というか、そんなことが可能だなんて思ったこともなかった。でもまあ、中国文学科の先生がオーケーなら、いいんじゃないの、と思ったら、何だか急に力が抜けて楽になった。
Kさんの持論がすごい。確かに伝統的には、国や言語ごとに文学を分けて考えてきたかもしれない。でも読者にしたら、そんなこと関係ない。いい作品かそうじゃない作品しかないんじゃないですか。
しかも作家たちだってそうだ。自分たちがいいと思う世界中の作品を自由に読んで、その感動から自分なりのものを育てていく。だったら、そんな細かい分類なんてどうでもいいでしょう。僕より幅広く世界の文学を読んでいる人にそう言われて、なんとなく説得されてしまった。と同時に、今まで自分が狭い考えに閉じ込められていたことに気づいた。Kさん、ありがとう。
さて、というわけでケン・リュウの『紙の動物園』である。Kさんに勧められて読み出したのだが、いやあ、こんなに面白い小説ってあるんですね。ここ数年で読んだ中でもトップクラスに良い。もちろん僕も最近は劉慈欣の『三体』など、中国SFが日本でもアメリカでも流行っているということは聞いていた。だから興味はあったのだ。でも実際に読んでみて、こんなにすごかったのか、と驚いた。
語り手は白人の父親と中国人の母親を持つ少年である。父親はカタログで母親を選び、アメリカに呼び寄せた。香港出身で英語が堪能、というふれこみだったが、実際には田舎の農民で、英語はハローとグッドバイしか話せない。
けれども彼女には特殊な能力があった。包装紙を巧みに折って様々な動物を作り上げ、それらに命を吹き込むことができるのだ。彼女が作った折り紙の虎は唸りながら、語り手の手にじゃれつき、水牛はたまった水の中を転がる。そうした折り紙の動物とともに育った息子にとって、紙でできたそれらが生きているのは当たり前だった。
けれども数年が経ち、語り手が近所の子供と遊ぶようになると、それが特殊なことだと徐々に気づき始める。友達のマークが持ってきたスター・ウォーズのフィギュアを、折り紙のトラが壊してしまう。するとマークは怒り狂い、虎を二つに引き千切り丸めて、語り手に投げつける。「ほら、くだらなくて安っぽい中国製のクズを食らえ」(17ページ)というマークの言葉は、語り手の心に確実に大きな傷をつける。
自分のお母さんは変なんだ、と思うようになった語り手は、母親に中国語で語りかけられても答えないようになる。そして、母親が作った中華料理を食べることを拒む。最後には母親が作ってくれた折り紙の動物たちを靴箱に入れ、蓋をテープで閉じて、屋根裏部屋の隅に押し込む。何とか息子と喋ろうとして母親が話す英語の訛りや文法上の間違いを、語り手は執拗に直す。しまいには母親は息子の前で一切口をきけなくなってしまう。
そのころには、父親も中国の農民の娘をコネチカット州に連れて来たこと自体が間違いだったと考えるようになる。そして台所で中国語の歌を歌っている母親を見て語り手は思う。「ぼくらはなにひとつ共有しているものがなかった。母さんは月からきた人間みたいなものだった」(21ページ)。つまり母親は、残りの家族と完全に断絶してしまったのだ。そうした孤独に耐えられなかったのか、彼女は四十歳になる前に癌になり、そのまま息を引き取る。
やがて語り手には恋人ができた。彼女は折り紙の動物を見て「あなたのお母さんって、すばらしいアーティストだったんだ」(25ページ)と言う。そこが転機だったのだろうか。ある日、折り紙の虎が動いていることに語り手は気づく。実はその日は、年に一回だけ祖先の魂が帰ってくる清明節だったのだ。
語り手は母親が中国語で残した手紙を持って、中国人観光客のもとを訪れる。そして母親の言葉を翻訳してもらう。そこには、折り紙の魔法の由来や、アメリカの生活で彼女がどれだけ孤独だったか、そして、中国語で話しかける母親に息子が一切答えてくれなくなったとき、改めてすべてを失ったような気がしたことが書かれていた。そのとき息子は母親と、ようやく遅すぎる再会を果たしたのだ。
『紙の動物園』という題名はもちろん、1940年代から80年代に活躍したアメリカの劇作家、テネシー・ウィリアムズの名作戯曲『ガラスの動物園』へのオマージュである。ウィリアムズの作品では、語り手の妹は足が悪く、どんな仕事も続かずに家に引きこもり、ガラスでできた動物たちを集めていた。彼女の孤独に一瞬だけ恋という光が差すのだが、それはもろくも崩れ去る、という悲しい物語である。
精神的な美しさを秘めた女性が周囲に理解されない、という点でこの二作品は共通している。けれども違う部分ももちろんある。もっとも異なるのは『紙の動物園』ではアメリカの人種主義が扱われている、ということだ。
人種主義とは何か。中国人は本質的にこうで、それは未来永劫変わらない。だからこそ、我々アメリカの白人と彼等は違う、理解不能な存在である、という信念のことである。そしてこうした人種主義を基にして人種差別が起こる。
『紙の動物園』でも、語り手は激しい人種差別の対象となる。母親の不思議な世界をそのまま受け入れていた幼いころは良かった。しかし徐々に物心がついて来ると、彼は近所の人々の差別的な視点に晒される。「混血ってけっしてうまくいかないみたいよ。あの子は発育不全っぽい、吊り目でしょ、しらっちゃけた顔でしょ。まるでチビの化け物」(14ページ)。こんな言葉が彼の耳にも届く。
もちろん、こんな心ない人たちの意見など無視すればいいのかもしれない。けれども語り手はそうした偏見をはじき飛せるほどの力を持たない。むしろ彼らの差別意識を自分で内面化してしまうのだ。さらに彼は自分自身の中国人の部分を否定し、ついには母親の存在そのものを否定する。白人の有色人への差別感情に一体化するあまり、自分をこの世に生み出し、こんなにも愛してくれた母親を無視し、いないことにしてしまう。
彼が行う、母親が中国語を使うことの禁止と、中国訛りの英語への執拗な攻撃は、アメリカ合衆国で多くの人々が受け入れている価値観である。移民の国アメリカでは、英語をネイティブ並みに身につけ、できるだけ語彙を増やして、複雑で抽象的な話を正確な英語できるようになることが、そのまま社会的上昇へと繋がる。反対に、不完全な英語を使う者は、何年アメリカにいようが、異質な人間とみなされ続けるのだ。
だからこそケン・リュウは、「紙の動物園」が二つの文化の間の摩擦を描いている、という書評が出たときに怒りを表明した。
「母親も父親もアメリカ人なんです――母親がアメリカ人ではないと言うことは、暗に白人こそがアメリカ人である、と言うことになりますし、移民というアメリカ人の経験を周縁的なものとすることになってしまいます。そうした経験こそがアメリカという物語の中心にあるのに。そこにあるのは「文化的な衝突」なんかではありません。(中略)純粋で単純な人種主義です」(Grimdark Magazine interview)
そして自分自身が中国系アメリカ人と呼ばれることも彼は拒否する。なぜなら、世界中のどこかからの移民であることそのものが、アメリカ人であるということなのだから。「アメリカはもともと、さまざまな土地から来た人が集まってできたメルティングポットで、そうした人々が自らの伝統を語り、それらをアメリカに織り込んでいくことでアメリカのストーリーが生まれてきた。だからぼくは、自分はアメリカ人作家で、中国の伝統をアメリカという“織物”に編み込んでいる作家だと考えているよ」(Wired interview)。
アメリカ文学史において、彼の考えは革命的なものだ。これまでずっとアメリカ文学において、白人の、そして多くの場合男性が書いた作品こそが中心的なものだ、と考えられてきた。そしてそこに女性作家たちや黒人、アジア系、ヒスパニック系といったマイノリティたちの作品が付け加わるという構図である。
だがケン・リュウの言葉は、その大前提を覆している。確かにネイティヴ・アメリカン以外の全てのアメリカ人は、北米大陸の外からやって来た。ならばむしろ、移民の経験を持つ者こそがメインストリームであり、したがって『紙の動物園』の母親の経験こそが、アメリカ文学の主流となり得るのではないか。
このように考えるケン・リュウとはどういう人物なのか。1976年、中華人民共和国の蘭州で生まれ、11歳のとき、両親とともにアメリカ合衆国へ渡った。カリフォルニア州パロアルトで育ち、その後コネチカット州のウォーターフォードに移住、ハーバード大学で英文学を学ぶ。
同時にコンピュータサイエンスの授業も取っていたおかげで、卒業後はマイクロソフトでプログラマーとなった。のちにロースクールを卒業し、弁護士として7年間働く。そして特許訴訟関係のコンサルタントとなる。2012年に『紙の動物園』でヒューゴー賞、ネビュラ賞、世界幻想文学大賞の短編部門を受賞した。三冠は史上初である。
加えて、中国SFの翻訳者としても知られている。有名なところでは、劉慈欣『三体』の第一部と第三部を訳した。最近では、老子の『道徳経』を翻訳したらしい。趣味は古いタイプライターの収集と修理である。
彼の経歴を見ていると、あまりにも豪華すぎてクラクラする。中国語も英語も完璧だし、作家で、プログラマーで、なおかつ弁護士で、書いた作品はいきなり大きな賞をいくつも立て続けに取ってしまう。
しかもその作品は頭の良さだけに頼っているわけではない。『紙の動物園』に出てくる母親の感情の揺れに読者はいつしか巻き込まれる。母親も悲しいし、母親を拒まなければならなかった息子も悲しい。だからこそ、息を吹き返した紙の動物たちが美しく思える。
彼はこうした物語をどうやって思いついたのか。もちろん、幼いころから折り紙には興味を持っていたようだ。それに加えて、彼はこう考えた。「愛のおかげで世界に命が宿る」という比喩表現がある。ならば、そうした比喩を実態化してみたらどうだろう。母親の愛の力で折り紙の動物が動き出すとしたら。
抽象的な比喩も、ケン・リュウの作品というフィルターを通せば、目に見え、手で触れられる実態として読者の前に現れる。身近な比喩だからこそ、読者はその作品の世界に容易に入っていけるだろう。こうした、比喩を実体化させる、という手法こそが、ケン・リュウにとってのSFなのだ。
年に一度、死者の魂が帰ってくる、という信仰は日本も中国も共通している。ケン・リュウのこの作品を読んでいて、僕は日本のお盆のことを思ってしまった。そうしたアジア的な感覚が、ケン・リュウの手でアメリカ文学のど真ん中に登場し、しかも単にエキゾチックなだけではないものとして十分に機能している。
彼の作品を読んでいると、アメリカ文学の在り方が確実に変化を遂げつつあることを感じる。これこそが、アメリカ文学の21世紀的な在り方なのだろう。そうしてその変化は僕には、確実に良いものだと思える。

分断と衝突を繰り返すアメリカ。今や国民の多くが「数年以内に内戦が起こる」との恐怖を抱いている。そうした時代の変化に伴い、民主主義と国民国家の在りかたに向き合ってきたアメリカ文学も、大きな分岐点を迎えている。 本連載ではアメリカ文学研究者・翻訳家の都甲幸治が、分断と衝突の時代において「アメリカ文学の新古典」になりうる作品と作家を紹介していく。
プロフィール

とこう こうじ
1969年、福岡県生まれ。翻訳家・アメリカ文学研究者、早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院総合文化研究科表象文化論専攻修士課程修了。翻訳家を経て、同大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻(北米)博士課程修了。著書に『教養としてのアメリカ短篇小説』(NHK出版)、『生き延びるための世界文学――21世紀の24冊』(新潮社)、『狂喜の読み屋』(共和国)、『「街小説」読みくらべ』(立東舎)、『世界文学の21世紀』(Pヴァイン)、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社)など、訳書にチャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』(河出文庫)、『郵便局』(光文社古典新訳文庫)、ドン・デリーロ『ホワイト・ノイズ』(水声社、共訳)ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(新潮社、共訳)など、共著に『ノーベル文学賞のすべて』(立東舎)、『引き裂かれた世界の文学案内――境界から響く声たち』(大修館書店)など。


 都甲幸治
都甲幸治









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

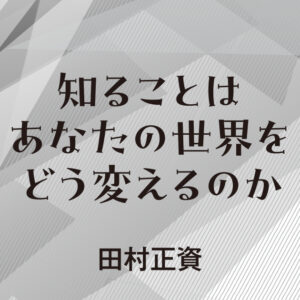
 田村正資
田村正資