マッキンダーの「新しい地理学」
今回のテーマは「地理」です。地理は、国のような大きな共同体にとってチェスの盤面のような役割を担います。イギリスの名門大学オックスフォードに地理学院を創設し、その初代院長になったハルフォード・マッキンダーは、世界的な地理情勢が国際秩序に与える影響を分析し、近代地政学の開祖となりました。
もっとも、マッキンダー自身は「地政学」という言葉を使わず「新しい地理学」と自分の理論を呼んでいました。では、マッキンダー以前の「古い地理学」とはなんだったのでしょうか。今回は、地理をめぐる古い理論を振り返り、マッキンダー以降の新しい理論を捉え直すことで、環境のスケールで世界を眺める視座をより確かなものにしたいと思います。
さて、ひとことで「地理学」と言っても、そこには大きく分けて次の3つの種類があります。
・地誌学 chorography
・地勢学 topography
・狭義の地理学 geography
地誌学とは、土地ごとの特色を列挙する「地誌」をめぐる学究です。たとえば、アメリカのシェールオイルの代表的な生産地域として知られているバッケンを地誌学的に記述すると次のようになります。
バッケンは、ノースダコタ州を中心にモンタナ州やカナダの一部に広がる産地です。この地域は、かつては農業が主な産業でしたが、2000年代に入ってシェールガスやシェールオイルの生産が急増しました。この地域には、先住民の居留地やノルウェー系やドイツ系の移民のコミュニティなどが存在します。
地勢学は、地形の高低や傾斜、山や谷、川などの土地の形成を扱う分野です。そして狭義の地理学は、天体観測や数学を含めて地球を記述することを目指すものといわれました。広義の「地理学」はこれら3つの総称なのです。
この「古い地理学」に対して、19世紀から20世紀を生きたマッキンダーが唱えた「新しい地理学」はどのようなものだったのでしょうか。マッキンダーの理論は、別名「ハートランド理論」と呼ばれます。ハートランドとは、簡単に言えばユーラシア大陸、とりわけ現在のロシアにあたる地域を指します。マッキンダーは、自分も国会議員をつとめたイギリス帝国のような海洋帝国の権力(シーパワー)が、ユーラシア大陸の陸地の権力(ランドパワー)と拮抗することを説きました。
マッキンダーの理論の興味深い点は、単に静的な地形やその特色を論じたのではなく、当時まさに「新しく」勃興しつつあった鉄道や自動車などのテクノロジーと地理を結びつけ、その結果として各地域の政治的軍事的な権力(パワー)がどのように変化するかを考えようとしたところにあります。
ハウスホーファーとドゥーギン
マッキンダーの理論は、彼の精力的な活動にもかかわらず、生前にはあまり重用されませんでした。しかし、その理論は、第一次世界大戦でイギリスと対峙したドイツの理論家カール・ハウスホーファーによって発展的に引き継がれ、悪名高い第三帝国の侵略の指針となりました。ちなみに地政学(geo-politics)という呼称はマッキンダーが提唱したものではなく、ハウスホーファーによって広められたのです。
鉄道や自動車によって陸地の権力(ランドパワー)が強大化し、海洋帝国の権力(シーパワー)に拮抗するという考え方は、第二次世界大戦後の冷戦時代にも引き継がれていきます。
第一次世界大戦後に成立したソヴィエト連邦は、その成立前からマッキンダーに警戒され、第二次世界大戦においてはドイツから侵略を受けました。このため地政学は、ソ連においては敵国の思想としてタブー視されました。近年のロシアで支持を集めつつあるアレクサンドル・ドゥーギンは一万部以上のヒットとなった著作『Основы геополитики』(地政学の基礎)において、マッキンダー以来の地政学を紹介しつつ、ロシアを中心とする独自の地政学理論を開陳しています。
さて、陸地の権力(ランドパワー)の興隆を論じたマッキンダーに対して、海洋国家の権力(シーパワー)を論じた理論家としてはアメリカのアルフレッド・セイヤー・マハンがいます。マッキンダーは近代において新興技術だった自動車や鉄道を地理や国際政治に結びつけましたが、20世紀には空軍(エアパワー)に注目するアレクサンダー・ゼヴァスキーが現れます。21世紀になると、宇宙空間を視野に入れたスペースパワー理論(宇宙地政学)が登場してきます。
批判地政学
ハートランド理論から宇宙地政学にいたる、政治や戦争の戦略思想とその基盤となる地理を組み合わせるタイプの議論は、いわば古典的な地政学です。これに対し、そもそも地政学的な議論で使われる概念や各地域に対する先入観を研究する「批判地政学」が提唱されるようになってきました。「批判地政学」は、古い地理学の「地誌学」に最新の人文系の知見を導入するものだといえるでしょう。
近年、「地政学」を書名に冠する書籍が話題になることが増えており、ニュース解説でも用いられるようになりました。しかし、そこには批判地政学的な視点の欠落が目立ちます。地政学はそもそも個々人の生活の次元(パーソナルなスケール)から乖離し、世界各地をマクロでグローバルな視点から捉えようとするものです。そのような巨視的で戦略的な視座からしか語れないこともあるのですが、地政学の研究者たちのあいだからも、そのようなメガロマニアック(誇大妄想)な地政学の本性について「SF的」と揶揄する向きもあります。虚構的想像力と現実主義との緊張はそれ自体がたいへんに興味深いテーマではありますが、今回は一旦横に置いておきます。虚実の乖離が問題にされるとき、その間隙に架橋するのが批判地政学です。批判地政学はジャック・デリダやミシェル・フーコーらの20世紀に流行した現代思想を取り入れています。これはこれで胡散臭く感じられているようですが、しかしデリダやフーコーこそ、一般に「現実」と言われているものにひそむ虚構的なものの力を批判的に論じた思想家たちでした。
批判地政学はもっぱらアメリカで展開されており、デリダやフーコーといったいわゆるフレンチ・セオリー(フランス現代思想)が流行したことと無縁ではありません。批判地政学とは別に、哲学思想の地政学のようなものも必要なのかもしれません。それはさておき、批判地政学を代表する理論家であるジェラルド・トールは、マッキンダーの理論を批判的に再解釈する一方で、自身が専門としている中東欧の紛争地帯がどのような用語で語られてきており、その言葉の使い方が国際政治においてどのように機能してきたかを論じています。 批判地政学は、たとえば「バルカン半島」という固有名詞の使われ方を分析し、そのニュアンスを解き明かそうとしますが、そもそも古典的な地政学が前提としてきた一般的な概念「領土」や「パワー」などを捉え直そうとします。アメリカの政治地理学者ジョン・アグニューは「領土の罠」を提唱しています。一般に国際政治や戦争は、定義上、国と国のあいだで発生し展開すると考えられています。国と国を隔てるのは、近世以降は国と国の境、つまり国境であると考えるのが現在では一般的です。しかしそれ以前は地図が普及していなかったこともあり、国の概念はそもそも曖昧であり、政治的な主体や戦争で戦う勢力は、諸侯や君主、あるいは都市など様々に定義されていました。
領土を再考する「領土の罠」
地図の上に国境が引かれ、国境によって切り出された空間を領土と呼ぶようになるのは人類史においてここ最近の話なのです。問題は、地図の上では単なる線でしかない国境は実際には面としての広がりがあり、地下資源や領空のような、地図の上に二次元的に画定するのが直観的に困難なレイヤーにも関わってくるところです。国境があることで世界は色分け可能になり、国ごとに色分けされた世界地図によって世界はいくつかの国の集合体として把握しやすくなります。しかし言うまでもなく、世界は、国と国だけによって構成されるものではありません。たとえばクルド人のように、国家間の領域の境界が、民族の居住地を分割してしまっている場合があります。
ある国家の領土のなかに少数民族として包含される人々がいる場合、国家間の境界つまり国境をめぐる紛争が、民族間の対立よりも大きくクローズアップされがちです。たとえば、ロシアによるウクライナ侵攻の背景を考えてみましょう。
ウクライナの国内には、ウクライナ語ではなくロシア語を話すロシア系住民が住んでいました。ウクライナとロシアのあいだにはソ連以前から続く確執があり、ロシアのウクライナ侵攻はこの民族対立を抜きにして語ることはできません。しかし、実際にウクライナとロシアのあいだのこの微妙な関係が世界的に広く知られるようになったのは、ロシアによるウクライナ侵攻以後のことなのです。
ある領域が国境によって境界づけられるとき、つまりある色で国が塗り潰されるとき、その一色の内実のグラデーションやムラは相対的に重要ではないものとして軽視されてしまいがちであり、アグニューはこれを「領土の罠」と呼びました。ふたたびウクライナの例でこれを語り直すならば、ソ連からウクライナが独立したとき、ウクライナの国境に囲まれた領域、つまり「ウクライナの領土」はウクライナ一色に染め上げられ、その内側のグラデーション、たとえばロシア系住民の多寡やそこで繰り広げられている生活は相対的に軽視されることになります。なぜこれが「罠」なのかというと、領土問題が一見解決されようとするとき、その「解決」のために無視されていた、この「相対的に軽視されていた問題」が噴出してくるからです。これは具体的には、ウクライナ内のロシア系住民の他にも、日本におけるアイヌや沖縄で起きていること、イスラエルにおけるパレスチナなど、文字通り枚挙にいとまがありません。 このような「領土の罠」は、国と国、民族のような共同体のスケールが、大地という環境のスケールに境界線を画定しようとすることで生じます。共同体のスケールの問題と環境のスケールが重なり合うのは、このようないわゆる民族問題に限りません。
『新しい世界の資源地図』
アメリカの経済アナリスト、ダニエル・ヤーギンは2020年に『新しい世界の資源地図』(邦訳2022年、黒輪篤嗣訳、東洋経済新報社)を発表しました。ヤーギンはこの本のなかで、資源をめぐる各国の綱引きを多角的に活写しています。
シェール革命によってアメリカ合衆国がロシアやサウジアラビアと並ぶエネルギー資源国になったこと、ロシアがEUと中国に天然ガスを提供するために採用している外交的な態度、イランやイラク、サウジアラビアなどの中東アジアの産油国の各政府が米露との距離感のなかでどう立ち回ってきたか。
マッキンダーは、鉄道や自動車によってユーラシア大陸の陸地の力が脅威になると論じましたが、それは石炭や石油などの化石燃料の需要が増すことも意味しています。これはランドパワーに拮抗するシーパワーや、新興のエアパワー、スペースパワーにとっても同様で、軍事的にも経済的にも、エネルギーを確保することが死活問題であることは敢えて言うまでもありません。
言うまでもないような、当たり前で身近すぎる物事だからこそ、エネルギーは生活のなかで無意識に忘却されてしまうものではないでしょうか。現在、アメリカ合衆国は石油算出量でサウジアラビアを抜いて世界第一位になりました。21世紀になってから開発された技術によって、シェールと呼ばれる種類の岩石から天然ガスや石油を抽出できるようになった、いわゆる「シェール革命」です。シェールガスやシェールオイルの採掘は水質汚染などの環境負荷が高いと危惧する声もあるのですが、皮肉なことにシェール革命の発端のひとつは、人口増大にともなう資源の枯渇というエネルギー問題意識の高まりにあった、とヤーギンは書いています。
第 5回でご紹介したように、現在は世界人口は減少に転じると考えられていますが、少し前は人口は増加を続け、人類文明は資源枯渇という壁にぶつかると考えられていたのです。
資源と環境
もし世界が、動かない国境によって整然と区画され、国境の囲いのなかにそれぞれの国の人口が留まり、互いに資源を融通させることのない、静的な状態であったなら、移民問題もエネルギー問題も起きていなかったでしょう。実際には、国境は地図の上に描かれているほどしっかりとはしておらず、日々、数えきれない人々がさまざまな方法で国境を越えて移動しています。そして、平面的な地図のような世界ではなく、各国の地下にはエネルギー資源が埋蔵されていることがあり、それを抽出する技術が登場することで国と国のパワーバランスも変わっていきます。 天然ガスと石油にだけ注目すれば、それは地下資源の分布という、地図上に描きやすそうな世界観で捉えられる問題に思えるかもしれません。実際にシェール革命のようなイノベーションがあったわけですが、それはそれとして、より複雑なのはこれらの化石資源に代わる再生可能エネルギーへの乗り換えが近年目指されているということです。
3つのオートテック
ガソリンで走る自動車から電池を積んで電気で走る自動車へのシフトが、ヨーロッパを中心に進んでいます。電気自動車に乗るかどうかという個人的な判断や、電気自動車を利用するという経験は、文字通りパーソナルなスケールのことです。
全人類が乗っている自動車のうち、何割がいつまでに電気自動車に取って代わられるのか、現時点でもさまざまな議論が噴出しており、見通しは定まっていません。自家用車だけでなく、トラックなどの事業用自動車も電気自動車にシフトするとなると、現在の石油の主な用途である動力用の燃料の需要が無くなってしまうことになります。
あるいは、ガソリン車から電気自動車へのシフトだけではなく、Uberや Lyftのような新しい自動車利用のスタイルが普及することによって、各家庭が自家用車を持つ社会が過去のものになる可能性があります。さらに、人工知能やセンサーの発達、そして法規制の変化によって、今後は自動運転の一般化が実現する可能性もあります。
これまで石油の需要を押し上げていた自動車の燃料が、これら3つのオートテックの発達によって、その消費量を減らしていくとすれば、世界地図に描かれるエネルギー埋蔵量の意味はこれまでとはさらに異なったものになるでしょう。
資源と「移動」
ヤーギンの『新しい世界の資源地図』においてロシアの天然ガスが扱われているパートでは、ソ連時代からのものを含む、ロシアとヨーロッパや中国を繋ぐいくつかのパイプラインが重要な役割を担います。ウクライナ侵攻によって注目され、それまで知らなかった人たちにも知られることになったノルドストリームや、中国へ天然ガスを供給する「シベリアの力」などがその代表的なものです。
天然ガスのパイプラインは、国と国とを隔てる国境という「横線」に対して、それらを越えて国と国を繋ぐ「縦線」であるということができます。前回、人や物資が「移動」する「道」に注目しましたが、エネルギーが「移動」する「道」としてパイプラインを捉え、共同体のスケールと環境のスケールで眺めてみることが重要です。つまり、各国やパイプラインに関わる企業という共同体のスケール。そしてなぜその場所をパイプラインが通っているのかという地勢学的な理由、その場所をパイプラインが通っていることが国際情勢に果たす役割、という環境のスケール。
パイプラインだけではなく、石油や液化天然ガス(LNG)を運搬するタンカーの航路もまた、国と国の境界線をまたぐ「縦線」を描きます。陸地の地図だけでは見えない、海底の地形や地質学的な特性によって航路は定まります。
地理や資源というと、「〇〇の北東部には油田がある」といったように単純に地図の上に描かれただけの、ダイナミズムのない静的な「単なる情報」だと考えてしまいたくなるものです。しかし資源は技術によって生産量が変わるものであり、諸勢力の地政学的なバランスによってその「移動」が変動します。そして、その変動はガソリン車から電気自動車への移行や、あるいは戦争のように、パーソナルなスケールで体験できる現象を生み出すのです。 今回は、地図の上に描かれている土地、領土、国境、そして国境をまたぐパイプラインや航路のような「縦線」を論じました。次回は、これらの上空に展開する「気候」を扱います。
(次回に続く)
参考文献
『地政学 ―地理と戦略―』コリン・S・グレイ、ジェフリー・スローン、奥山 真司 訳、五月書房新社
『新しい世界の資源地図 エネルギー・気候変動・国家の衝突』ダニエル・ヤーギン、 黒輪 篤嗣 訳、東洋経済新報社、2022年
「境界、領域、「領土の罠」─概念の理解のために――」
山﨑 孝史、2016年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)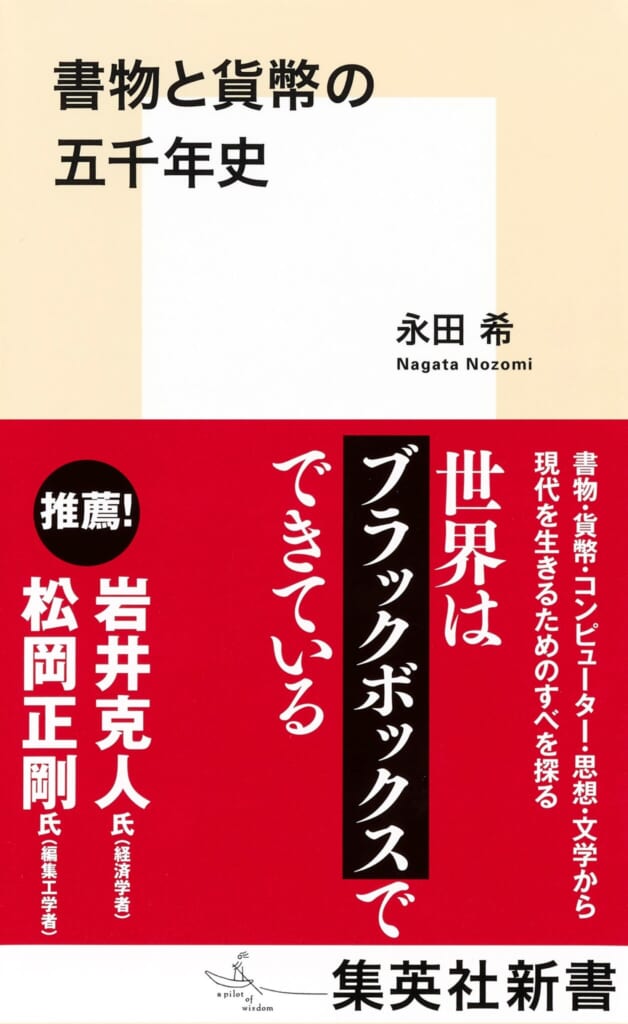










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


