バルセロナの独自性と多様性
二つめは、「多様性の器」という要素。この映画では新たな時代を象徴する舞台になるのが、パリやロンドン、またスペインの首都マドリードではなくバルセロナなのである。
映画の中でバルセロナはその独特な深みのある青空が映され、カラフルな配色の建物、グザヴィエがモンジュイックの丘やサグラダファミリア教会の塔に上がる場面など、留学中の若者の心境をどことなく反映した、宙に浮いた場所として描かれる。そういう街で、アクの強い各国の若者たちがゴチャゴチャと動きまわり、バルセロナは若者たちを包む箱庭のようだ。
これも最近見返して気がついたのだが、『スパニッシュ・アパートメント』の原題“L’Auberge espagnol”や英語題“Euro Pudding”には、各国の多様な若者が集まる「ごった煮」のような意味合いが込められている。カタルーニャのバルセロナというと、独自の言語や文化を持ち、それゆえにスペイン中央政府と長年あつれきがある、といった印象を受けがちだが、そういう独自性の強い場所が同時に「多様性の器」のように描かれるありかたは面白い。

「この世界が嫌なら、私たちで変えていこう」というプラカードを持って歩く女性(国際女性デーの午後)
『スパニッシュ・アパートメント』がいま見返すと面白い二つの面のうち、前者の「EUへの期待感」は、映画から15年後のいま窮地にあるといえる。加盟国間の経済格差や大量の難民への対応、イギリスの離脱や極右勢力の拡大など様々な問題があって、EUの未来に「期待する」という感覚が失われかけているからだ。例えば、2015年にドイツで製作されベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞した映画『ヴィクトリア』では、ベルリンを舞台にスペイン人の若い女性と無職のドイツ人青年たちの出会いが描かれるが、同じEUの若者たちの交流を描きながらも、『スパニッシュ・アパートメント』とは真逆の悲惨な展開が主人公らを襲う物語になっており、時代の変化を感じさせられる。
とはいえ、もう一方の側面「多様性の器としてのカタルーニャ」は、いまカタルーニャ自体が独立の問題に揺れながらも、未来への一定の可能性を秘めているんじゃないか。
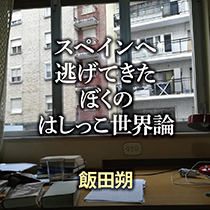
30歳を目前にして日本の息苦しい雰囲気に堪え兼ね、やむなくスペインへ緊急脱出した飯田朔による、母国から遠く離れた自身の日々を描く不定期連載。問題山積みの両国にあって、スペインに感じる「幾分マシな可能性」とは?
プロフィール



 飯田朔
飯田朔









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

