サラマンカにいながら、スペイン関係の日本の書籍をいくつか読んでいるのだが、工藤律子『ルポ 雇用なしを生きる』(2016年、岩波書店)に、カタルーニャについて興味深いことが書かれていた。この本は、2008年からのスペイン大不況を生きる中で、スペインの人々が試行錯誤しつつ作り出してきた様々な形の「もうひとつの経済」を紹介している。工藤によると、バルセロナのある地区では、移民が多いという事情を抱え、また地域の交流が少なくなっていたが、住民たちがみずからの手で「時間銀行」という制度を活用し、既存の貨幣を介在させずに様々な背景をもつ人々が互いの生活を支えあうことが可能になっているという。時間銀行とは、地域の人々が何か自分が得意とする作業を他人に無料で提供し、そのかわり自分もまた他人から無料で何かを提供してもらえるしくみだ。こうした試みはスペインのほかの都市でも行われているが、その中でもカタルーニャはより先進的な地域として紹介されている。

バルでサッカー観戦
2001年に『スパニッシュ・アパートメント』が作られたとき、バルセロナの「多様性」はEUへの期待感とともにやや楽観的に映画内で描かれていたと思う。そこから2008年からの不況を経て、独立問題が沸点に達した現在にいたり、ヨーロッパも世界も、日本もだいぶ雰囲気が変わってしまった。そうしたいまこの映画を見直すと、カタルーニャの「多様性の器」としての側面は、ヨーロッパというより、いま様々な問題で揺れる世界の不寛容なありかたをどうにか打開するための、ひとつのヒントとして捉えるほうが合っているように感じられた。『スパニッシュ・アパートメント』でグザヴィエが経験する、「いろいろな背景・個性をもったやつらと一緒に生活するのは楽しい」という素朴な感覚は、時間銀行のような地域の試みを通して、人々が互いの長所をいかして支えあう様子にも通じている。
『スパニッシュ・アパートメント』で描かれた、「ごった煮」のテーマは、中学生のぼくには明るい未来への指標のようなものだったけれど、30手前でスペインへ逃げてきた自分には、ひどいことばかりの世の中をマシにするための、小さな、しかしひとつの重要な手がかりに思えている。
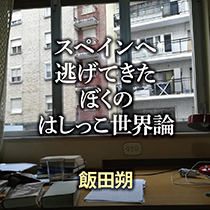
30歳を目前にして日本の息苦しい雰囲気に堪え兼ね、やむなくスペインへ緊急脱出した飯田朔による、母国から遠く離れた自身の日々を描く不定期連載。問題山積みの両国にあって、スペインに感じる「幾分マシな可能性」とは?
プロフィール



 飯田朔
飯田朔









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

