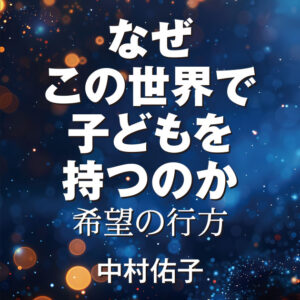プロフィール

三宅香帆
みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。
プラスをSNSでも
Instagram, Youtube, Facebook, X.com


 三宅香帆
三宅香帆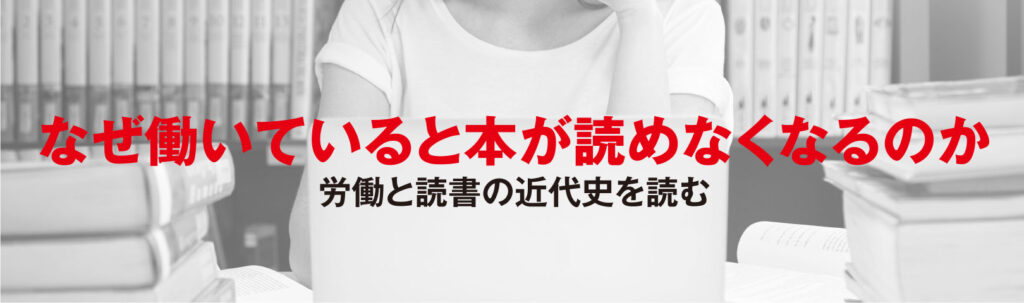








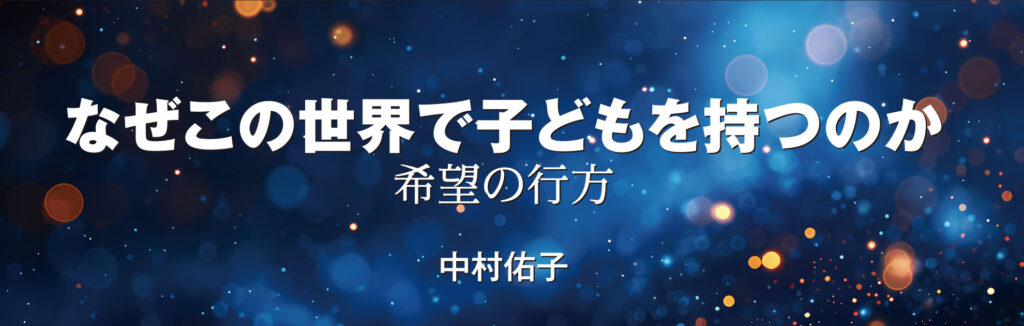

 内田 樹×青木 理
内田 樹×青木 理