昨年(2024年)10月7日にハマスが越境攻撃をしかけたことに端を発するイスラエル軍によるガザへの報復攻撃では、6月に入った時点で、3万6000人超の死者が出る未曽有の事態になっている。死者のうち1万5000人は子供だ。
だが欧米主要国政府は「テロとの戦いだ」「自衛権だ」としてイスラエルを擁護し、アメリカはイスラエルに軍事援助も続けている。
刻々と状況が悪化するガザの問題の本質を、『自壊する欧米 ガザ危機が問うダブルスタンダード』を共著で出したばかりの内藤正典氏と三牧聖子氏が同志社大学のセミナーで語った。
最終回(全3回)の今回は参加者からの質問に両氏が答える。
*この記事は2024年5月17日に行われた同志社大学セミナー「グローバル・ジャスティス」第72回を編集したものです。データや数字はその時点のもの。5月後半の事態について加筆修正があります。
構成=稲垣收 写真(人物)=内藤サトル
日本人は欧米のダブルスタンダードをどう考えるべきか?
Q イスラエルの攻撃を決して「ジェノサイド(虐殺)」と呼ばず、ハマスの攻撃だけを非難する、こうした欧米のダブルスタンダードを、私たちはいったいどう受け止めて、今後考えていけばいいのでしょう?
三牧 アメリカの度が過ぎたイスラエル擁護を批判することとともに、なぜアメリカ政府がそのようなイスラエル政策をとっているのか、その政治的・社会的背景を理解することも、長期的にその改善を求める上で大事だと思います。
まず政治。アメリカには、イスラエルの利益を守るような対外政策をとるよう、米政府や議会に働きかけ、選挙では資金集めでも多大な影響力を発揮する「イスラエル・ロビー」として知られる存在があります。選挙が迫るいま、議員にとってはさらに重要性を増しています。
もっとも、こうしたお金や選挙はすべてではない。実利的な結びつきにとどまらない、思想的・観念的なイスラエルとの結びつきも作用しています。たとえば歴史。アメリカ合衆国の歴史は、ヨーロッパから移り住んだ移民たちによる植民地の建設に始まりました。こうした歴史を持つアメリカには、ヨルダン川西岸で進むイスラエルによる入植に、自分たちの建国の歴史との類似性を見出し、正当化したり、美化する思考が強くあります。17世紀の北米大陸にも、現代のヨルダン川西岸にも先住民がいたわけですが、そうした土地をまっさらな「無主の地」、あるいは神が自分たちに与えた「約束の地」とみなして、暴力的な入植を進めたわけです。自分たちにとって都合の悪い建国の暴力には目を向けない。アメリカとイスラエルの思考の類似性、さらには共犯関係があります。
内藤先生が、ヨーロッパの極右勢力の動向について説明されましたが(第2回参照)、アメリカにも近い状況がある。これまで極めてマイノリティ蔑視的な発言をして、ユダヤ人差別的な言動も見せ、ホロコースト否定論のようなことを言っていた人物までもが、こうした局面で前面に出てきて、「イスラエルを守れ、ユダヤ人を守れ」と言っている。彼らの主張を真に受けることはできません。今、最も差別したい相手=イスラム教徒に対して、ユダヤ人擁護論を戦略的に使っているだけで、状況が変われば再びユダヤ人や他のマイノリティ差別を始めるでしょう。
第1回でご紹介したように、10・7以降のアメリカでは、連邦議会の委員会が開催した公聴会に、パレスチナ連帯デモが起きている大学の学長が呼ばれ、「キャンパス内で反ユダヤ主義を許容している」と尋問されるという異常事態が起こってきました。大学への攻撃が強まっている背景には、差別や多様性の問題に取り組む牙城である大学の力を、今回の問題を利用して弱めておきたいという保守政治家の意図があります。アメリカの大学には、人種平等を求めた公民権運動やベトナム戦争反対運動などの拠点として、政治や社会を変え、戦争を終わらせたりする力になってきた伝統がある。保守政治家たちは、大学を拠点とする社会変革の芽を摘もうとしているのです。

命の重さがなぜこれほど違うのか?
Q 本書の帯に「もう、殺すな!」と書かれていますが、お二方がそこに込めた思いは?
三牧 帯の「もう、殺すな!」ということばには、あらゆる人が殺されてはならないはずが、実際には殺されてはいけない人、殺されることが許容される人のダブルスタンダードがあることへの怒りをこめました。
10・7の犠牲者も、ホロコーストの犠牲者も、本当に痛ましい犠牲です。けれども、残念ながら10・7以降、イスラエルは、ホロコーストというユダヤ人の集合的な犠牲の経験を、ホロコーストの加害者でも何でもなく、罪もまったくないパレスチナの人に犠牲を押しつける「武器」として利用してきました。つまり、「自分たちユダヤ人は、過去にホロコーストという甚大な被害を受けた」ことを理由に、「そうした犠牲の上に打ち立てられたイスラエルが、安全のためにとる軍事行動は正当だ」とガザでの軍事行動を正当化し、さらには「イスラエルの軍事行動を批判する人は、反ユダヤ主義であり、ユダヤ人が虐殺されることを容認している」という飛躍した論理まで展開してきました。
たとえばバイデン大統領にもこうした態度は見られます。彼は、「シオニストであるためにユダヤ教徒である必要はない」「(自分はカトリックだが)シオニストだ」と公言してきました。その一方で、リベラルな民主党の大統領として、トランプ前大統領の差別的な態度を批判してきた人でもあります。しかし、10・7以降のバイデン大統領は、「ガザ保健省が出している数字(犠牲者数)は信用できない」などと発言し、パレスチナ側の犠牲者数に疑問を呈したりしてきました。もし一国の大統領がこういう発言をホロコーストに関してしたら、絶対許されないでしょう。なのに、パレスチナ人に関しては、簡単に犠牲者の数に疑問を呈し、しかもアメリカ社会の側もそれを許容する。ガザでの軍事行動が始まってから100日目の節目の演説でも、バイデン大統領はパレスチナ側の犠牲者には言及すらしませんでした。
大学キャンパスでのパレスチナ連帯デモに関しても、バイデン大統領は批判的です。「平和的な抗議は権利だが、今起こっている学生デモは過激化し、さらには反ユダヤ主義的な傾向を見せている」というのが、大統領の見立てです。ユダヤ人学生の中には、パレスチナ連帯が叫ばれるキャンパスで不安を感じる人もいます。しかし、ではなぜ、ガザでこれだけのパレスチナ人が殺され、ジェノサイドの様相を呈していることに心を痛めるムスリム学生の心は考慮されないのか。ガザの人道危機に心を痛め、軍事行動の停止を求める学生はムスリムにはとどまりません。ユダヤ人学生だって心を痛めている人はたくさんいる。それにもかかわらず、「パレスチナ連帯デモが、ユダヤ人学生に脅威を与えている」ということばかりを強調する。こうした態度の背後には、ユダヤ系献金者など政治の事情もありますが、バイデン自身の人種差別や宗教差別もあるといわざるを得ない。
もちろんユダヤ人の命も大切です。守られねばならない。しかし、現在のアメリカでは、「ユダヤ人の命を守れ」という主張が、「ガザでの軍事行動に反対するイスラム教徒や学生を黙らせろ」「それに連帯するやつらも黙らせろ」という主張になってしまっている。ある集団の命を守れ、という主張が、他の集団の命が奪われている現状を肯定する、そんなおかしい事態になっているのです。「殺すな!」という主張は、守られるべき命と、そうではない命を勝手に選別し、等しく尊ばれるべき命に重みをつける態度に抗い、あらゆる命を守れ!という主張です。
内藤 この問題に関してしばしば「ユダヤ教徒とイスラム教徒の深い宗教の対立だ」とか「ユダヤ人とアラブ人の民族対立だ」と言われますが、そうではありません。欧米の側が、自分たちの責任問題をすり替えて、中東側に押しつけているところがあるのです。
たとえばイスラム教徒がユダヤ教由来の名前をつけることがよくあるのです。ソロモンをアラビア語にするとスレイマンです。「スレイマン何々さん」という名のアラブ人はたくさんいます。ダビデもそうです。同志社大学では、トルコの前首相のダウトオールさんを招待したことがありますが、ダウトというのはダビデ、オールは英語のson=息子なので「ダビデの息子」という意味です。そういう名前が普通にイスラム教徒の名前についている。それからイーサー、これはイエスです。マリアム、メリアムさんという女性もよくいますが、これはマリアです。「イスラム教徒はユダヤ教徒やキリスト教徒を根源的に嫌っている」というのが事実なら、そんな名前をつけるはずがありません。

それからもう一つ、この「もう、殺すな!」という言葉に込めた意味ですが、つい2年前、アフガニスタンで20年も占領統治を続けた米軍とNATO軍が撤退しましたよね。あのときに「タリバンが戻ってきて、女子教育や、女性の人権がこれでもうダメになる」という批判が欧米諸国から噴出しました。もちろん私はタリバンを支持しませんが、「じゃあ、そうなることがわかっていたのに、なぜ撤退したのか?」と思いました。
そもそもその前の段階で、なぜ20年間も「コラテラルダメージ(副次的犠牲)だ」と言って一般市民を殺し続けてきたのか? 欧米から「避けられない犠牲」と呼ばれる犠牲者の中には、女性も本当にたくさんいたわけです。人を殺しておいてから「人権、人権」と言ってみても遅いのです。たとえば欧米社会で、これだけの犠牲者数の殺りくが行われたとしたら、彼らももっと何とかしたでしょう。しかし、そういうことが中東とか、イスラム世界やアフリカで起きても、今まで全く無視してきたわけです。
それなのに今回、イスラエルがからんだ途端に、それが表に出てくる。ある意味、そこにもうダブルスタンダードの根源というのを私は感じてしまうのです。私はずっと中東を見てきましたから。
もちろん女性の人権、LGBTQの人たちの人権も大事です。でも人権が大事なら、まずは「殺すな!」ということです。殺してしまってからそんなことを議論しても意味がない。そこはやはりこの本で、一番訴えたかった点ですね。
プロフィール

(ないとう まさのり)
1956年東京都生まれ。同志社大学大学院教授。一橋大学名誉教授。中東研究、欧州の移民社会研究。『限界の現代史』『プロパガンダ戦争』(集英社新書)、『トルコ』(岩波新書)他多数。

(みまき せいこ)
1981年生まれ。同志社大学大学院准教授。米国政治外交史、国際関係論。
著書に『Z世代のアメリカ』(NHK出版新書)等、共著に『私たちが声を上げるとき』(集英社新書)がある。


 内藤正典×三牧聖子
内藤正典×三牧聖子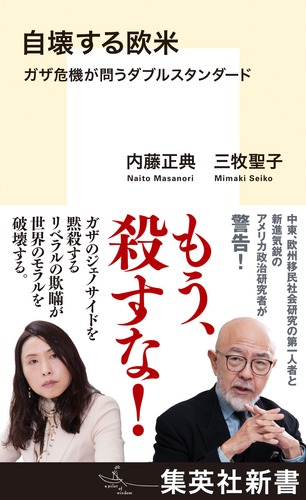
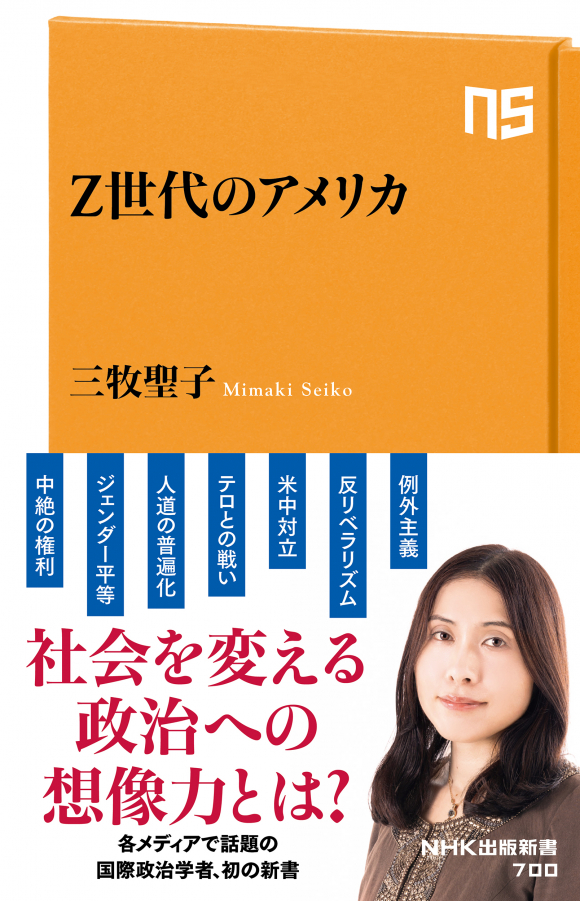











 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


