ブライアン・イーノと無神論者のための教会
いずれにせよ、京都を舞台とするからといって、必ずしも伝統的な史跡を選ぶことはない。すでに触れたように、2022年と2023年の「AMBIENT KYOTO」は別の選択をした。

左は「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」、右は「AMBIENT KYOTO 2023」開催中
今年初めに死去した原広司の手になる京都駅ビルを出て、山田守設計の京都タワーの脇を抜ける。いずれも建設当時に大きな景観論争を引き起こした――しかし今日では多かれ少なかれ市民にも訪問者にも受け入れられているように思われる――2つの近代建築を後にして烏丸通を北上すると、やがて左手に東本願寺が見えてくる。この京都を代表する寺院のひとつの広大な敷地の手前にこじんまりと構えているのが、京都中央信用金庫 旧厚生センターだ。
1930年竣工のこの近代建築は、当初は不動貯蓄銀行七条支店として建てられたもので、同行の支店を数多く手がけた関根要太郎の設計による。装飾的なユーゲント・シュティールの影響下に出発しつつもモダニズムの作風を示すようになったこの建築家は、ここでは凹凸のないシンプルな外壁を基調に、アーチ窓と四つ葉飾りの窓によって独特のタッチを加えている。
巨大な仏教寺院の傍らに位置するこの金融機関所有の建物を丸ごと用いて、ブライアン・イーノは、宗教と同じ力を世俗の資格で行使する芸術という彼の近年の着想に改めてかたちを与えようとした。「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」開催中の2022年夏にウェブ掲載されたあるインタビューで、イーノは自らと宗教との関りを振り返っている(※4)。同展の背景をなす思索を明らかにしてくれるのはもちろん、それを超えた興味深い内容を備えており、少々紹介するに値するだろう(※5)。
(※4:Brian Eno, “World Enough, and Time,” conversation with Martin Wroe, High Profiles, 1 November 2022.)
(※5:なお今日のイーノは、単に著名なアーティストであるにとどまらず、ヨーロッパを代表する公共知識人の顔をもつに至っている。本稿とはまた別の関心から、筆者は以前、彼と人類学者デヴィッド・グレーバーの実に刺激的な対談を日本語訳する機会を得た。「クソどうでもよくない仕事を求めて」片岡大右訳、『tattva』3号、2021年。「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」に寄せられた著名人コメントで桑原茂一が言及している「scenius」の概念――天才(genius)は孤立した存在ではなく、多くの関係者からなるシーン(scene)のなかで、初めて大きな事業をなすことができる――についても、この対談で語られている。)

ブライアン・イーノ《Light Boxes》
カトリック教徒として育ったものの、10代半ばに「女の子たちとデートできるようにプラグマティックな無神論者になった」というイーノは、今世紀に入ってからもリチャード・ドーキンス『悪魔に仕える牧師―なぜ科学は「神」を必要としないのか―』(原著2004年、日本語版は垂水雄二訳、ハヤカワ書房、2004年)を読むなど、神の不在という信念を新たにしてきた。
しかし彼はそうした考察の過程で、人間がつくり上げた虚構という意味では、宗教と芸術は似通ったものだと考えるようになった。
わたしは、宗教とは芸術のひとつのかたち、ただし、自らが芸術であることにまだ気づいていない、そんな芸術の一形態なのではないかと考え始めました。芸術としての自覚がないというのは、宗教は自らの真実に固執しているからです。宗教以外の芸術はそんなことはしない――他の芸術は必然的に、柔軟に変わりゆくものなのです。
(Brian Eno, “World Enough, and Time,” conversation with Martin Wroe, High Profiles, 1 November 2022.)
すでに1978年のニューヨーク移住以後に、無神論者イーノはゴスペル音楽に夢中になり、奇妙な思いにとらわれたのだという。「どうして自分は、信じてもいない存在を称えるこの音楽を愛するなんてことができているのだろう?」音楽を聴くために教会に通い詰めるなか、彼が出した結論はこうだ。「わたしは神を信じない。けれど宗教の力を信じている。わたしは宗教が行っている多くの事柄を好んでいるんだ。」
神の実在を信じないとしても、他の芸術と並ぶ強力なフィクションとしての宗教の力は信じることができる。教会が発揮する力は、イーノによれば、「人びとの経験をつなぎ合わせ、自分たちは何かより大きな存在の一部だという感覚を与えること」にあるのだという。そうすれば、「つねに自分が自分の人生の中心にいなければならないという負担をすべてのひとに負わせずに済む」
そこからさらに進んで、彼は「身を委ねる surrender」ことの重要性を説く。
わたしの考えでは、身を委ねることは受動的な行為ではありません。それは、自分ではコントロールできない何ものかの一部分になるという決断です。動物たちや、「原始的」と呼ばれる人びとに関して、つねに称賛の的となるのは、まさに身を委ねることに長けているというこの点です。彼らは、どのようなときには自分の持ち場を守るべきであり、どのようなときには流れに身を任せるべきかをわきまえている。わたしたちはこの後者があまり得意ではない。わたしたちはいつも、「ここには問題がある。どうしたら直せるだろう?」と考えてしまう。「ここには問題がある。どうしたら害を受けることなしにその流れに身を任せ、流れのなかで浮遊することができるか?」といった考え方はしないのです。
わたしたちは身を委ねることの予行演習をつねにしておく必要があると思うのです。
(同前)
イーノは続けて、「単独の原子化された自我であることをやめ、なんらかの流れの一部となること」が人間にとっていかに本質的かを強調し、だからこそ、トランプ流の「MAGA(米国を再び偉大に)」のようなものでさえもが多くの人びとを惹きつけたのだとして、長年この点を軽視してきた左派の過ちを指摘している。
「それでは、人びとが宗教に求めるものと芸術に求めるものは同じもの――つまり身を委ねることにほかならないのでしょうか?」このインタビュアーの問いにイーノは肯定で答え、だからこそ「宗教とは芸術の一形態だと考えるに至ったのです」と述べる。インタビュアーはそれを受け、イーノがデヴィッド・バーンと共作した2008年のアルバム『Everything That Happens Will Happen Today』に言及し、イーノが同作を「無神論者のためのゴスペル」と表現していたことを振り返りながら、「これは一部の人びとが「超越的」な音楽と呼ぶものかもしれません」と指摘するのだった。

ブライアン・イーノ《77 Million Paintings》
「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」展に戻ろう。そこでの主要な展示のひとつ、会場1階の《77 Million Paintings》は、アルゴリズムにしたがい自動生成される夥しい組み合わせの光の絵画が暗闇に浮かび上がるのを、訪問者がソファに腰掛け、音響に包まれながら見上げるという趣向のインスタレーションだ。2006年にラフォーレ・ミュージアム原宿で初公開されたのち世界各地で展示され、英国では元教会のアートスペースを会場としたこともある(2010年、ブライトンのファブリカ・ギャラリーにて)。
こうしてみると、この京都の展覧会でのイーノの試みは、東本願寺の広大な敷地の近傍に、暫定的な「無神論者のための教会」を設けてみることだったと言えるかもしれない。
プロフィール

片岡大右(かたおか・だいすけ)
1974年生まれ。批評家。専門は社会思想史・フランス文学。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。単著に『隠遁者,野生人,蛮人――反文明的形象の系譜と近代』(知泉書館)、『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』(集英社新書)、『批評と生きること 「十番目のミューズ」の未来』(晶文社)。共著に『共和国か宗教か、それとも』(白水社)、『古井由吉 文学の奇蹟』(河出書房新社)、『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』(水声社)、訳書にデヴィッド・グレーバー『民主主義の非西洋起源について』(以文社)、フランシス・デュピュイ=デリ、トマ・デリ『アナーキーのこと』(左右社)がある。


 片岡大右
片岡大右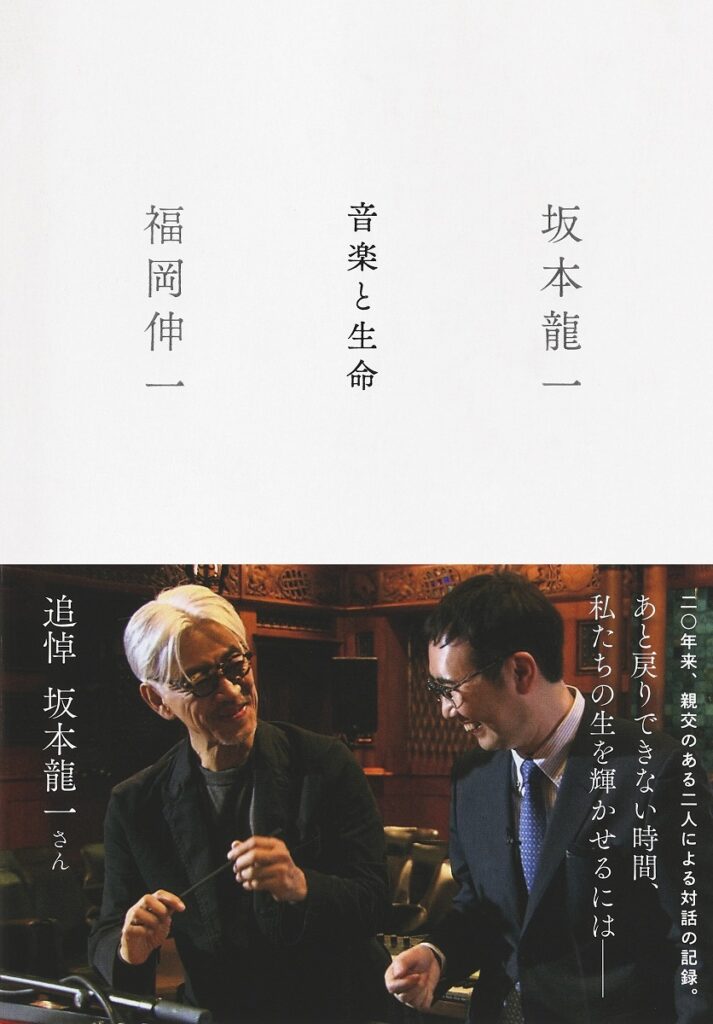
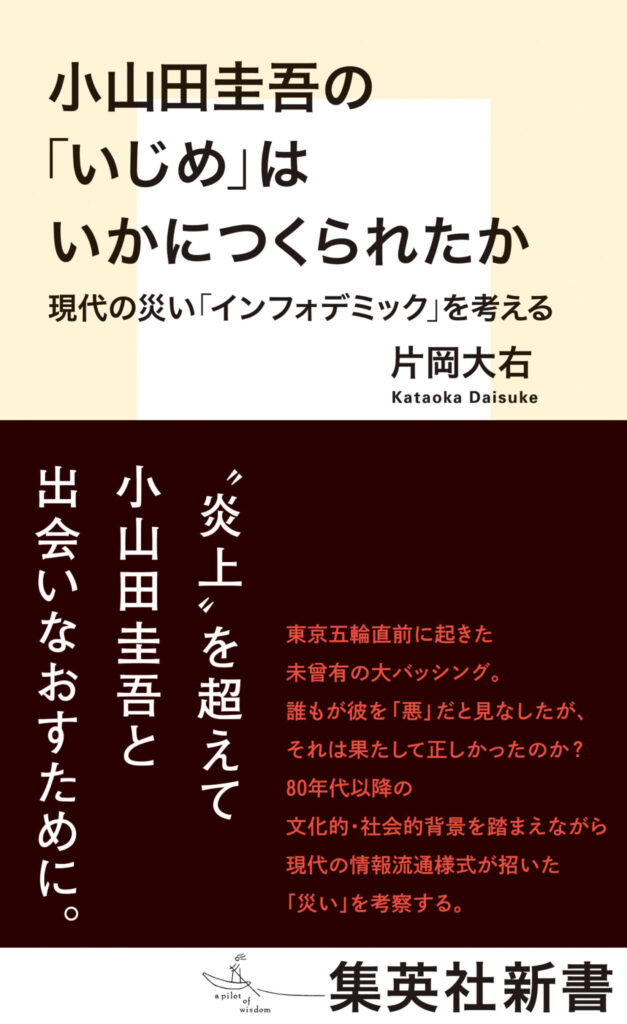










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


