追記――小山田圭吾のいる文化的風景
2021年夏、東京オリンピック・パラリンピック開会式の作曲担当として発表された小山田圭吾をめぐる大炎上のあと、筆者はこの一件をその歴史的背景や「いじめ問題」をめぐる社会学的考察にまで踏み込んで調査し、2023年2月、集英社新書から『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』のタイトルのもとに出版した。元になったのは、2021年12月から翌年1月にかけて岩波書店のnoteに公開されて広く読まれた、「長い呪いのあとで小山田圭吾と出会いなおす」と題する連載記事だ。
2022年以降、小山田は炎上の規模を思えば例外的なテンポで信頼を回復し、以後数年のあいだに、国内外でいくつもの意義深い活動を展開してきた。その背景には、この一件の「インフォデミック」的性格が多少とも周知されたことがあるのに違いない。今日の小山田がかつてと変わらぬ活動を展開しているのを――いやそればかりか、中国ツアーの成功に見られるように、いっそうその活動の範囲を拡大しているのを見るのは、心から嬉しいことだ。
そうして小山田の活動再開を喜びながらも、筆者はこのところ、坂本龍一をめぐる一連の仕事を発表してきた。
2023年3月に没したこの世界的音楽家は、21世紀に入ってから、YMOの他の2人、細野晴臣および高橋幸宏ともども小山田との親交を深め、2021年の炎上後も、彼が発表した謝罪と経緯説明の文章に言及して励ましのメッセージを公表していた。癌療養により出演休止中のレギュラー番組「RADIO SAKAMOTO」の2023年元日の回には代理のナビゲーターに小山田を指名するなど、坂本は彼の活動再開を力強く後押ししていたのだった。
坂本の死後、生前から準備されていたいくつもの企画が実現を見た。筆者はそのうち、中国・成都での坂本龍一展「一音一時」、高谷史郎と共作したシアターピース「TIME」の東京公演(新国立劇場)、両者を踏まえた東京都現代美術館での展覧会「音を視る 時を聴く」について、複数の文章を書くことができた。
文芸誌『文學界』2025年8月号に掲載された「時間という公然の謎を生きる――坂本龍一と時間の問い」は、これらすべてに触れつつ、1980年代の活動や発言から1999年のオペラ《LIFE》を経て最晩年に至るまでの坂本の思想と芸術を、時間の主題のもとに論じたものだ。
しかし坂本没後の一連の企画のうち、筆者が上記すべてに勝るとも劣らない深い印象を受けていながら、これまで言及する機会を逃していたものがあった。それが今回取り上げた「AMBIENT KYOTO 2023」への出品作、《async – immersion 2023》にほかならない。本稿では、同展のみならず、その前身として2022年に開催されたブライアン・イーノ展、今年春から初夏にかけて二条城を舞台に展開されたアンゼルム・キーファー展――前掲写真のキャプションに記したように、坂本が所有していた作品を含む――といった、最近数年間に京都で開催されたいくつかの展覧会とコンサートを取り上げながら、このかつての首都の現在について若干の考察を試みた。
そこでは小山田圭吾は、論及される何人かのアーティストのひとりであるにすぎない。それにまた、議論の文脈は筆者の集英社新書のものとはまったく異なったものであるので、同書とは独立したエッセイとして読むことができる。筆者としては、まさにそのことが――というのはつまり、小山田について、2021年夏の炎上を考慮に入れることなく、他のアーティストと同じひとりのアーティストとして論じることができるというこの事実が――、同書を世に問うた意義のひとつの証しではないかと考えている。
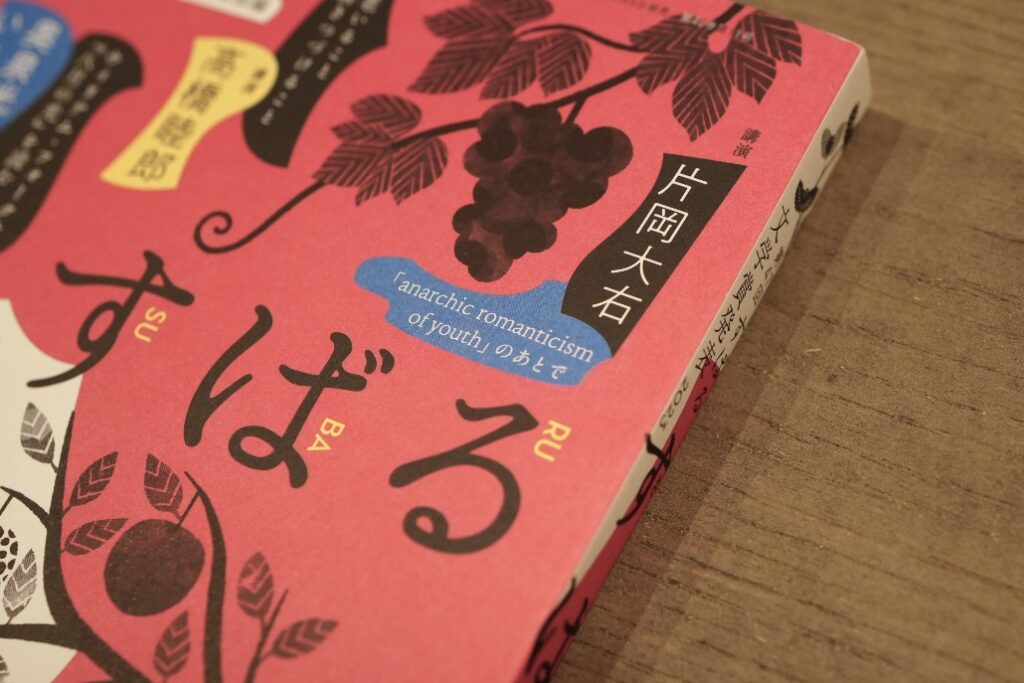
以前『すばる』誌への寄稿「「anarchic romanticism of youth」のあとで――小山田圭吾という芸術家の「炎上」をめぐる考察」(2023年11月号)で言及したように、すでに『ミュージック・マガジン』誌は、アルバム『夢中夢』の発売を機にコーネリアス特集を組んだ2023年7月号において、編集長による巻末の「後記」で筆者の著書に触れ、それが「1冊にわたって騒動を調査し、できるだけ公平を期して紐解いていく内容」を持つものであると評価したうえで、特集本文においてはもはや炎上それ自体を主題とすることなく、もっぱら小山田の音楽的創造に焦点を合わせていた。このような評価はまったく本望というほかない。ともあれこうして、小山田圭吾は再び、わたしたちの文化的風景のなかに帰ってきたのだ。
追記への追記――ヘラルボニーの企画を受けて
本稿脱稿後の7月23日、コーネリアスの楽曲「Glow Within」が配信開始され、翌24日から銀座・HERALBONY LABORATORY GINZAにて、同じタイトルを冠した展覧会「Glow Within -Corneliusと13人の作家の声-」が始まった(8月11日まで)。
「福祉×アート」を掲げる岩手発のスタートアップ企業、ヘラルボニーは、知的障害のあるアーティストたちとの共同作業を小山田圭吾に提案した。2022年冬の発案時には社内でも賛否両論があったというこの企画だが、展覧会が開催されたこの2025年夏の反響は、おおむね好意的なものだったように思われる。とはいえ――当然のことだろうが――不満や失望の声がまったく聞かれなかったわけではない。

こうしたリスク含みの企画を実現に――さらには成功に導いた、ヘラルボニー共同代表の松田崇弥・文登両氏をはじめとする関係者の熱意と手腕、そして繊細な配慮には頭が下がる。なにより、大炎上とその背景をなす小山田圭吾の失敗や過ちを超えたところで、小山田の音楽的・芸術的感性と方法が、障害のある人びとの内側から生まれ育ってくるものを作品化するというヘラルボニーの構想といかに親和的なものであるかを確信して企画を進めてきたことが、手に取るように伝わってくるのが嬉しい。
先ほどの「追記」では小山田の通常の活動再開を喜んでいると述べたけれども、筆者自身、こうした点については著書のなかで触れ、さらにその後、上述の文芸誌への寄稿「「anarchic romanticism of youth」のあとで」のなかで、議論をいっそう展開したことがある。
「いわゆる「健常者」だけが社会を構成しているのではなく、わたしたちの社会は実際には、多くの人びとにとっての「ふつう」とは別の「ふつう」を生きる人びとを含み込んでできあがっているという事実」――筆者はそこで、小山田のなかには少年時代から一貫して、このことをめぐる好奇心や興味があったのだろうと記した。そしてこうした関心のもつ危うさ――それは多数派から少数派に向けられる一方的で暴力的な眼差しにつながりかねず、「いじめ」の出発点にもなりうる――を認めながらも、そこには「ふつう」の問いなおしと再編につながる要素を見出すこともできるのだと示唆して、こうした両義性を、大江健三郎の再読――この作家は、障害をもって生まれた息子の殺害可能性を作品化したのちに当の息子との生活に真摯に向き合い、そこでなお生じる葛藤を含め、小説で取り上げてきた――などを交えつつ考察している。本稿の主旨から外れるためここでの再述は差し控えるが、ご関心の向きにはぜひともお読みいただきたい。
※ 写真はすべて筆者による
プロフィール

片岡大右(かたおか・だいすけ)
1974年生まれ。批評家。専門は社会思想史・フランス文学。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。単著に『隠遁者,野生人,蛮人――反文明的形象の系譜と近代』(知泉書館)、『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』(集英社新書)、『批評と生きること 「十番目のミューズ」の未来』(晶文社)。共著に『共和国か宗教か、それとも』(白水社)、『古井由吉 文学の奇蹟』(河出書房新社)、『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』(水声社)、訳書にデヴィッド・グレーバー『民主主義の非西洋起源について』(以文社)、フランシス・デュピュイ=デリ、トマ・デリ『アナーキーのこと』(左右社)がある。


 片岡大右
片岡大右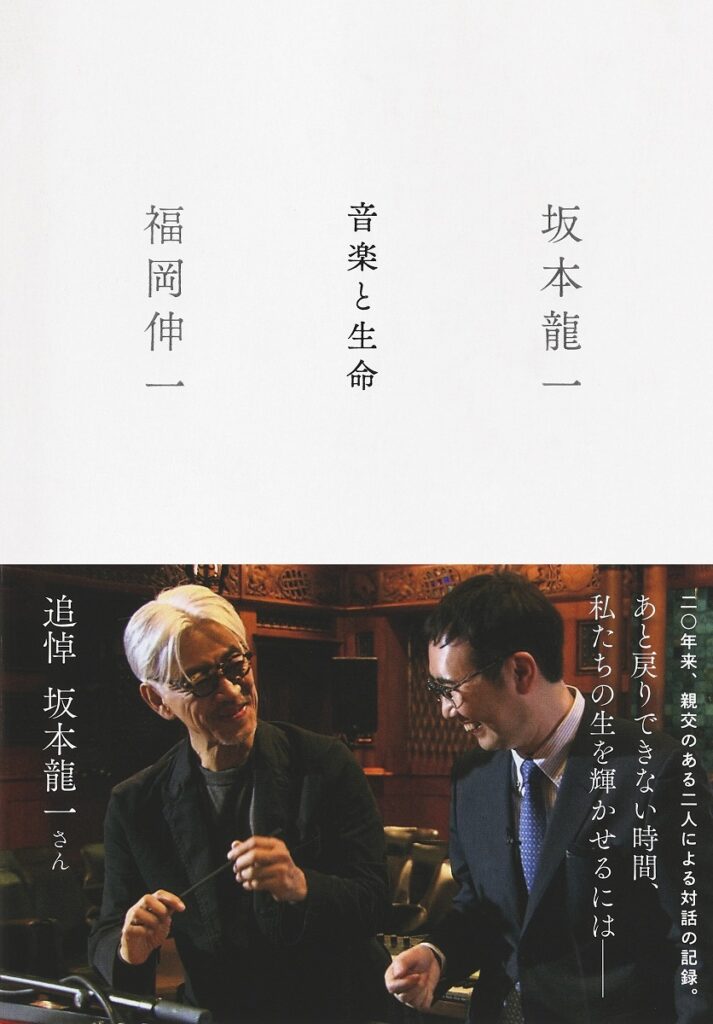
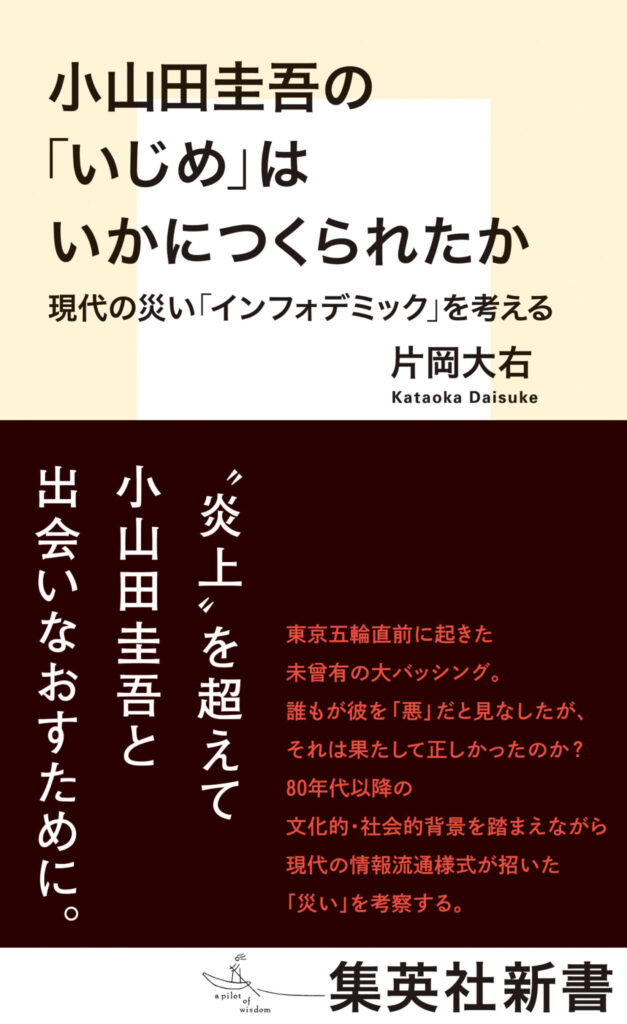










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


