これまで、脳と腸をつなぐ経路には、①自律神経などの神経系(第2回参照)、②内分泌(ホルモン)系(第3回・第4回)、③免疫系(第5回・第6回)があることを伝えてきました。
今回は、その経路を元気づける役割がある「腸内細菌」について見ていきましょう。ここ数年、腸内細菌や腸内フローラ(後述)の遺伝子解析(DNA解析、ゲノム解析ともいう)が急進歩中で、その種類や働きについて国内外から多くの研究結果が報告されています。
「腸活」「腸内フローラ」「腸内環境」「短鎖脂肪酸」「酪酸」といった言葉も社会に定着しつつあるようですが、いまの時点で何がどこまでわかっているのか、脳との関連についてエビデンスが明確になっているポイントを紹介します。
■「善玉・悪玉・日和見」の考えかたはすでに古い
ヒトの腸には1,000種類以上の細菌が棲(す)んでおり、その総重量は1kg以上あると言われます。まず、腸内細菌の実態を確認しておきましょう。
腸内細菌には各々のテリトリーがあり、この様子が草むらや花畑のように見えることから、「腸内細菌叢(そう)」、もしくは「腸内フローラ」(本記事ではこれで統一します)と呼ばれています。
これらの言葉はすでに知られていますが、自分の体に細菌がそれほどに棲みついているとは、なかなかイメージがしにくいのではないでしょうか。
腸内フローラは幼児期以降に個人差が大きくなり、その組み合わせによって特有の働きを示すようになります。これまで腸内細菌は、「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」に分類され、人体への影響について説明がなされてきました。しかし近ごろでは、先述のとおり、細菌の遺伝子解析の進展で、腸内細菌に対する考えかたが変わってきています。
腸内細菌の分類は、生物学では「門―綱―目―科―属―種」となります。たとえば、クロストリジウム属という細菌群には、「腸管免疫寛容」(第6回)などに重要な免疫細胞のひとつ「Tレグ(制御性T細胞)」の変化(分化。成熟すること)を助ける「短鎖脂肪酸」(後述)を産み出す菌がいます。
その一方で、クロストリジウム属の中でもクロストリジウム・ディフィシルという菌は抗生剤を服用するなどによって、腸内フローラのバランスが乱れると、偽膜性腸炎といった酷い下痢を伴う腸炎を起こすことがあります。
つまりは、「この細菌は善玉菌で、こっちは悪玉菌、これらは日和見菌だ」というようなとらえかたでは、腸内フローラの実態に合わないことがわかってきました。そこでこの連載でも善玉などの言葉は用いません。
■腸内フローラは遺伝と環境により個人差が大きい
腸内細菌がどういう要因でほかの菌と組み合わさってフローラをつくるのかは、遺伝的要因と、食事や睡眠、運動など環境要因の双方に影響されます。そのため、腸内フローラのありようは、同じ環境で育ってきた一卵性双生児でも個人差があることがわかっています。
また、便の遺伝子検査でどのような腸内細菌が存在するのかは、先述の分類の「種」までわかってきたものの、それらの菌がどこに、どのぐらいの割合で、どのような菌と隣り合っているのかまでは明らかになっていません。
たとえると、日本に住む田中さんの存在は判明しているけれど、田中さんが日本のどこに住んでいて、ご近所さんは誰なのか、どういう会社やグループでどのような仕事をしているのかといった詳しい情報までは把握しきれていない状況です。

余談ですが、細胞内でエネルギーを産生している細胞小器官(細胞内にある特定の機能を持つ構造物の総称)のひとつに、「ミトコンドリア」があります。ミトコンドリアはもともとは細菌だったとも言われます。生き物に寄生してエネルギーを供給するうちに、細胞の一部に組み込まれた可能性が指摘されていて、ミトコンドリア遺伝子と呼ばれる独立した遺伝子を持っています。
このように、需要と供給が成り立てば、異物であるはずの細菌すら体内に取り込んで利用するところが生きものの面白いところです。
実際、「脳腸相関と免疫系」(第5回・第6回参照)でも述べたように、腸内フローラは、免疫細胞たちに異物や侵入者として見なされず、攻撃されず、良き隣人として共存しています。
ただし、個体が生存するにあたり、細菌との共存は必須ではないという説もあります。その根拠は、1940年代に実施の、作成された無菌動物が繁殖して次世代を生むことが可能であったという報告にあります。
とはいえ、無菌動物の生育には栄養も含めた徹底的な管理が必要であり、細菌と共存しない状態で、自然条件下での生存が可能かどうかはわかっていません。たとえば、無菌動物は肥満になりにくいことなどが報告されています。逆に言えば、腸内細菌は、宿主(しゅくしゅ)が食べものからエネルギーを獲得する活動を助けているとも考えられます。
果たして、ヒトと共存する腸内細菌の具体的な組み合わせはどういうものなのか、腸内フローラの効果については現在進行中の研究や検査方法の発展が期待されています。
■腸内細菌が出す物質「短鎖脂肪酸」に注目
さて、細菌とは生物です。腸内細菌の場合は腸の中で生きていて、ヒトが食べたものの残りかす(食物繊維や脂など)などをエサにし、代謝して(消化、吸収して活動に必要なエネルギーや物質に変化させること)、物質を排出しています。それを「代謝物質」や「代謝産物」といいます。
その代謝産物がビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、ビオチン、ビタミンK2、葉酸)をつくり、食物繊維を分解し、そして酪酸や酢酸、プロピオン酸といった「短鎖脂肪酸」をつくっています。
短鎖脂肪酸は腸活の要などと言われて注目が集まっていますが、その実態は、われわれが食べたものから腸内細菌がつくり出す物質であるわけです。
この短鎖脂肪酸の大部分は腸管の粘膜組織から吸収されて、上皮細胞の増殖や粘液の分泌に使われるほか、大腸の粘膜を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を促進する、免疫反応をコントロールするといったさまざまな作用があります
ただし、代謝産物を産み出すのはあくまで腸内細菌の生命活動です。その影響といえば、現時点では短鎖脂肪酸のようにヒトにとって有益なタイプもあれば、有害な細菌、また、バランスのありようによって有害になるタイプもあります。
そして、最近の研究では腸内細菌の一部は、ヒトの健康を一定に保つ(恒常性・ホメオスタシス)ように働く一方で、病気の発症や増悪(ぞうあく)に関わることも明らかになっています。
たとえば、炎症性腸疾患や過敏性腸症候群といった腸の病気、糖尿病や高血圧といった生活習慣病、アトピー性皮膚炎や喘息(ぜんそく)などの自己免疫系の病気、また、アルツハイマーやパーキンソン病、うつ病といった精神・神経系の病気にも腸内細菌が関係していることが報告されています(※1)。
■腸内細菌は「神経系・内分泌系・免疫系」経由で脳腸に働く
では、腸内細菌はどのようにして、腸と脳の間を取り持っているのでしょうか。
実は、これまで述べてきた神経系、内分泌系(ホルモン)、免疫系の脳と腸の双方向ネットワークのさまざまな場面で働いています。そこで最近では、「腸内細菌-脳-腸相関」という考えかたも広がっています。
しかし、腸内細菌が脳へ直接に働きかけているわけではありません。腸で産生された代謝物質は腸管から一部が吸収されて血液中に入り、全身の活動に影響します。つまり、内分泌系のホルモンや免疫系のサイトカイン(第3・第5回参照)と似た働きかたをすると考えられます。
細菌が血液中に入れば敗血症(はいけつしょう)、脳やせき髄に入れば脳炎や髄膜炎(ずいまくえん)といった、いずれも命にかかわる重とくな感染症を起こします。
このため、腸内細菌は、先述の短鎖脂肪酸などの代謝産物によって、神経系、内分泌系、免疫系を経由して脳や腸に働きかけています。この点も人体の巧妙なしくみのひとつでしょう。
■神経系
短鎖脂肪酸が幸せホルモン「セロトニン」の分泌を促す
次に、神経系、内分泌系、免疫系のそれぞれにおける腸内細菌の役割を確認していきましょう。なかなか勤勉で優秀な細菌たちの働きぶりが見えてくるでしょう。
腸には神経が網のように広がっています。特に注目したい「腸管神経系」という神経ネットワークが発達しているため、腸は、脳の指令がなくてもある程度、独自の活動ができるということは第2回で詳説しました。腸管神経系は腸の蠕動運動など消化に関する働きを担っています。
そして腸内細菌は、その代謝産物が神経に、とりわけ「自律神経」に働きかけることが知られています。
腸内細菌と自律神経について説明するにあたり、患者さんからの質問が多い「セロトニン」について触れておきます。セロトニンとは「幸せホルモン」とも呼ばれますが、その正体は、ホルモンではなく神経伝達物質のひとつであり、神経に働くことは第3回でも少し触れました。
セロトニンは、食事からとる「トリプトファン」という必須アミノ酸を材料としてつくられます。この時に短鎖脂肪酸やビタミン(ビタミンB6やナイアシン、葉酸など)を必要としますが、それらをつくっているのが腸内細菌なのです(※2)。
・セロトニンは脳で2%、ほかは腸でつくられる
セロトニンは意欲や睡眠、感情の安定などに働く物質です。うつ病などの治療薬として「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibito: SSRI)」という薬にも活用されていることで知られます。ただし、脳で働くセロトニンは全身の約2%といわれ、この分は脳内の細胞でつくられています。
一方、ほかの90%以上のセロトニンは主に小腸の細胞(クロム親和性細胞・EC細胞)でつくられ、約90%が腸管、8~10%が血液中の血小板に取り込まれ、止血などに働くといわれます。
腸管でこれほど産生しているなら、トリプトファンや短鎖脂肪酸やビタミン類の材料となる食物繊維をたくさんとれば相対的に脳のセロトニンも増え、気分が安定してメンタルに良いのでは、と考えられるかもしれません。
しかし、実際には小腸でつくられたセロトニンは、血液中の物質がむやみに脳に入ることを防ぐしくみの「血液脳関門(blood-brain barrier:BBB 脳の毛細血管の細胞の働きによるとされる)」によって、脳に移動することはできません。
なぜなら、体内のセロトニンが増えすぎると、イライラや不安、興奮といった「精神症状」、手足が勝手に動く・逆に体がこわばる「運動症状」、そして発汗や発熱、頻脈、下痢といった「自律神経症状」が起こる「セロトニン症候群」になる可能性があるからです。
セロトニンは脳のほか、運動神経や自律神経でも働いているので、過剰になるとこうした症状が現れるのです。また、セロトニン症候群はこのほか、腸や膵(すい)臓などにできる腫瘍(しゅよう)が、セロトニンを分泌した場合にも起こります。
こうしたことから、腸でつくられた大量のセロトニンが脳に流れ込むことは、脳にとっては避けたい状況といえます。
・腸内細菌がセロトニンの生成を調節している
そこで脳は、セロトニンの材料となるトリプトファンを多少加工した「5-HTP(5ヒドロキシトリプトファン)」という物質とビタミン類などを取り込んで、自家生産・自家消費に徹しているのです。
つまり腸内細菌は、代謝産物の短鎖脂肪酸やビタミンの産生を通じて脳や腸でのセロトニンの生成を調節し、間接的に脳や運動神経、自律神経に影響を与えているのです。
とりわけセロトニンを生成している小腸のEC細胞は、セロトニンをメッセンジャーとして腸の組織や内腔(ないくう)の状態を腸管神経系に伝え、蠕動運動のコントールなどを担っています(※3)。
このことを裏付けるように、腸内細菌がいない無菌マウスの腸ではセロトニンの量が減少し、蠕動運動が低下するために便秘のマウスが多いという研究結果があります。
また、セロトニンは腸のセロトニン受容体に働きますが、中でも「5-HT3」(セロトニンが作用する受容体)に働くと、下痢、腹痛、嘔吐(おうと)といった消化管の症状を起すことがわかっています。
そのため、脳のセロトニンの利用率を高める先述の抗うつ剤・SSRIとは反対に、腸のセロトニンの過剰な影響を低下させる「セロトニン(5-HT3)受容体拮抗薬」が、吐き気止めや、下痢や腹痛などを起こす過敏性腸症候群の治療薬として活用されています。
■内分泌(ホルモン)系
やせ・食欲抑制・ストレスの各ホルモンに短鎖脂肪酸が作用する
ストレスがあると、脳の視床下部(ししょうかぶ)や下垂体(かすいたい)といった内分泌系の司令塔からホルモンが分泌されます。中でも、視床下部から放出される「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」(第3回)は、腸に影響する代表的なホルモンで、胃の蠕動運動を低下させ、一方で腸の蠕動運動を促し、知覚を過敏にします。
また、腸管にもホルモンを分泌する「腸管内分泌細胞」が何種類も存在し、そこから分泌されたホルモンをまとめて「消化管ホルモン」と呼びます。それぞれの消化菅ホルモンは、胃酸や腸液、膵(すい)液、胆汁(たんじゅう)などの消化液の分泌を調整しています。
どう調整しているかというと、自律神経などに作用して、脳に「おなかがへったよ~」と空腹を伝えたり、脳から「食べ物が届いたよ」という伝達を受けて消化液の分泌を促したりしています。
そして腸内細菌は、この内分泌系においても代謝産物を通じて、ホルモンの生成や蠕動運動などの消化活動に影響を与えています。
・話題の「やせ薬」の正体は
例として、「やせホルモン」と呼ばれる「GLP-1(glucagon-like peptide-1)」や、腸管の蠕動運動と栄養の吸収に関係する「ペプチドYY(PYY)」という2つの消化管ホルモンを紹介しておきましょう。いずれも、主に小腸の細胞(L細胞)でつくられています。
この2つのホルモンは、腸内細菌の代謝産物である短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸、プロピオン酸など)が、小腸の細胞上にある受容体(GPR41、GPR43)を活性化することで生成されます。特にGPR41は酪酸とプロピオン酸により、GPR43は酢酸によってパワーアップされ、実際に、GPR41を欠損させたマウスではGLP-1およびペプチドYYの量が減少することも報告されています(※4、※5)。
GLP-1の働きは栄養の消化・吸収にとって非常に重要です。このホルモンは膵臓から出る「インスリン」というホルモンの分泌を促すからです。
インスリンとは、血液中のブドウ糖(血糖)を肝臓や筋肉などの細胞に取り込むことを促進させるホルモンであり、体内では唯一、血糖値を直接低下させるように働きます。食事をして血糖値が上昇すると、GLP-1が膵臓に「インスリンを出して!」と指令を出します。するとインスリンが分泌されて、血糖値が低下するのです。
インスリンの分泌量が少ない、あるいは働きかたが悪くて血液中のブドウ糖濃度が高くなると、糖尿病の原因となります。そのため、GLP-1の働きを模した「GLP-1受容体作動薬」が糖尿病の治療薬として活用されています。
中でも、2023年4月に日本で使用開始となった2型糖尿病治療の新薬「マンジャロ」(一般名:チルゼパチド)は「やせ薬」と呼ばれ、欧米で爆発的に売れていること、また、日本ではダイエット目的に自由診療で販売されて品薄状態が続き、肝心の医療機関では入手困難に陥ったことがニュースになっています。
また、2024年2月に日本で使用開始となる肥満症治療の新薬「ウゴービ」(一般名:セマグルチド)も同様の状況です。いずれも、適切な使用をお願いしたいところです。
「話題のやせ薬の正体は何?」と聞かれると、「小腸でつくられてインスリンの分泌を促す消化管ホルモン・GLP-1の働きを活用した、GLP-1受容体作動薬」という答えになります。
GLP-1の働きは多様ですが、満腹になると迷走神経を刺激して、脳に「もうおなかいっぱいだよ」と伝達し、食欲を抑える作用もあります。つまり脳腸相関というよりも、「腸脳相関」に働くホルモンだと言えるでしょう。
また、ペプチドYYは、蠕動運動を抑制し、食べものを腸管に長くとどめて栄養の吸収を助けます。
これらのホルモンの働きにより、腸内細菌が食べものからエネルギーを獲得する活動を助けているということが想像されます。
・ストレスホルモンで腸内フローラが乱れる
さらに、第3回で述べたように、ストレスがあると、「視床下部―脳下垂体―副腎の軸(HPA軸)」を通じて、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンや、俗称ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」の分泌が増加します。
コルチゾールには、次の項目で述べる免疫の機能を抑える働きもあるため、長期にわたって体内のコルチゾールの濃度が高い状態が続くと、腸内フローラのバランスが乱れ、炎症性腸疾患や過敏性腸症候群といった腸の病気をはじめ、全身の病気にも影響する可能性があります(※1)。
■免疫系
免疫細胞の成熟には短鎖脂肪酸が必要
前回(第6回)に、こう伝えました。腸は食べものや細菌、ウイルスなどの異物と常に接する場所であり、さまざまなリスクと向き合っています。その中心となって働くのが免疫系です。そして腸には体全体の50%超の免疫細胞が存在し、「腸管免疫」という独自の免疫系が発達していることから、「腸は人体最大の免疫器官」と言われます。
脳は神経系や内分泌系を介して腸に情報を伝達しますが、免疫細胞はサイトカインと呼ばれる物質を使って、神経やホルモンから脳に情報を伝えています。
そして腸内細菌は、短鎖脂肪酸などの代謝産物によって、免疫系の発達にも働いているのです。
腸内細菌がいない無菌マウスではリンパ組織が未熟であること、リンパ球の減少などがみられること、一方、通常環境で育ったマウスに腸内細菌を定着させるとそれが回復するという報告があり、免疫系の発達における腸内細菌の役割を裏付けています。
・酪酸が免疫細胞Tレグを産む刺激になる
このほか、先に述べた免疫の過剰反応を抑制するTレグが、活動できる形に成熟・増殖するためには、短鎖脂肪酸、中でも「酪酸」が働くこと、その酪酸はTレグの遺伝子の発現を誘導していると報告されています。
また、短鎖脂肪酸の受容体を持たないマウスでは、脳の免疫細胞である「ミクログリア」(第6回)の成熟に異常が出るため、短鎖脂肪酸は免疫系の成熟に必要であり、腸内細菌はTレグを発現させる歯車のひとつであると考えられます。
ほかにも、短鎖脂肪酸の一種の「酢酸」には腸の粘膜の傷を治す作用があり、腸のバリア機能の維持に役立ちます。さらに酢酸は、有害な細菌やウイルスが腸から侵入するのを阻止する抗体「免疫グロブリン(IgA)」(第6回)の産生を高めます。
こうしたことから、短鎖脂肪酸などの腸内細菌の代謝産物が少なくなると、腸管のバリア機能が弱まり、感染症にかかる可能性が高まります。
また、腸管バリア機能の低下に伴って、腸内細菌由来の内毒素(Lipopolysaccharide:LPS リポ多糖)が血液へ多く流れ込みます。すると脂肪組織の慢性炎症を誘発し、耐糖能異常を起こして糖尿病を発症する可能性が報告されています(※6)。
腸内細菌は神経系、内分泌系、免疫系とつかず離れずの絶妙な関係を保ちつつ、脳腸相関のバランスを維持しているわけです。そして実のところ、その種類や量、フローラのありようによって、われわれの体にとっては味方にも敵にも、薬にも毒にもなるのです。
では、腸内細菌と上手に付き合っていくにはどうしたらよいのでしょうか。次回に続きます。
参考
(※1)Vijay A, Valdes AM. Role of the gut microbiome in chronic diseases: a narrative review. Eur J Clin Nutr. 2022;76(4):489-501.
(※2)Yano JM, Yu K, Donaldson GP, Shastri GG, Ann P, Ma L, et al. Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. Cell. 2015;161(2):264-76.
(※3)Bellono NW, Bayrer JR, Leitch DB, Castro J, Zhang C, O’Donnell TA, et al. Enterochromaffin Cells Are Gut Chemosensors that Couple to Sensory Neural Pathways. Cell. 2017;170(1):185-98.e16.
(※4)Kim MH, Kang SG, Park JH, Yanagisawa M, Kim CH. Short-chain fatty acids activate GPR41 and GPR43 on intestinal epithelial cells to promote inflammatory responses in mice. Gastroenterology. 2013;145(2):396-406.e1-10.
(※5)Tazoe H, Otomo Y, Kaji I, Tanaka R, Karaki SI, Kuwahara A. Roles of short-chain fatty acids receptors, GPR41 and GPR43 on colonic functions. J Physiol Pharmacol. 2008;59 Suppl 2:251-62.
(※6)Winer DA, Winer S, Dranse HJ, Lam TK. Immunologic impact of the intestine in metabolic disease. J Clin Invest. 2017;127(1):33-42.
構成:阪河朝美・藤原 椋/ユンブル

「腸は第二の脳」という言葉が知られてきたが、最近の研究でそのメカニズムが医学的に説明できるようになってきた。そのエビデンスをもとに、ストレス関連消化管疾患の治療に、精神神経系疾患のうつ病や不安障害ケアの心理療法「認知行動療法」を取り入れる治療が始まっている。同治療法の研究者である消化器病専門医の著者によるこの研究成果と治療法、セルフケア法を一般に分かりやすく伝える。
プロフィール
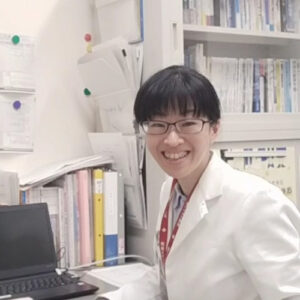
菊池志乃
きくち・しの 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター助教。京都大学大学院医学研究科・健康増進・行動学分野・客員研究員。医学博士。消化器病専門医。消化器内視鏡専門医。京都大学大学院医学研究科博士課程医学専攻修了。高知大学・医学部医学科卒。岸和田徳洲会病院、天理よろづ相談所病院、高槻赤十字病院、京都大学医学部付属病院、京都大学大学院医学研究科特定助教を歴任。専門は過敏性腸症候群と認知行動療法。2022年、日本初の過敏性腸症候群に対する集団認知行動療法の大規模ランダム化比較試験を実施し、有効性を報告した。現在、名古屋市立大学にて過敏性腸症候群の臨床試験を実施中(https://suciri.localinfo.jp/)。


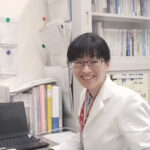 菊池志乃
菊池志乃









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



