
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第6回 津田大介 「自由」を守るのは、対話を通して生まれるシティズンシップ
日本学術会議の会員任命拒否が報じられた時、ぜひお話を伺わなければならないと思った方がいます。「あいちトリエンナーレ2019」※で「表現の自由」の問題に直面した津田大介さんです。一つの企画展を巡って、脅迫行為やメディアの報道合戦などが繰り広げられ、異様な様相を呈しました。その渦中で思ったこと、学術会議問題と共通する点、そして、これから予想される事態についてお話し頂きました。
※2019年8月1日、「情の時代」をテーマに30の国・地域から93組のアーティストが参加する「あいちトリエンナーレ2019」が開幕した。その前日の7月31日、企画展「表現の不自由展・その後」の《平和の少女像》を含む展示内容が新聞で報道されると事務局への抗議の電話が殺到。その後もテロを予告する脅迫FAXなどが届き、8月3日、「表現の不自由展・その後」の中止を決定。9月26日には文化庁が「あいちトリエンナーレ2019」への補助金(約7800万円)全額不交付を決定(その後、約6700万円に減額して交付)。「表現の不自由展・その後」は10月8日に再開、同月14日に閉幕。総来場者数は過去最高の67万5939人を記録した。
「あいちトリエンナーレ」と同質の問題
今回の学術会議の任命拒否のニュースが耳に入ったとき、正直、驚きはありませんでした。というのも、僕が芸術監督を務めた、あいちトリエンナーレ2019(以下、「あいトリ」)において、文化庁による補助金の不交付という事態をすでに経験していたからです。
あいトリの補助金に関しては、複数の文化政策や芸術の専門家が委員となって、補助金を支払うのは適正かどうかということを判断し、それによって一度は補助金が支払われることが内定していたんです。それが何らかの理由によって覆るということは前例がなかったし、覆ったことに関して、交付を決めた専門家の委員の人たちへの報告もなかった。そして、文化庁長官はこの件に関しての決裁をしていないという。では、誰がこの不交付を決裁したのかというと、文化庁の高級官僚ということになるのですが、その具体的な名前はわからないし、決裁の議事録も残っていない。
こうしたブラックボックスの中で、突然、決まっていたものが覆されるというのは、今回の任命拒否とよく似ています。元々安倍前政権時代から文化芸術分野に対するさまざまな介入はあったのです。あいトリで大騒動になった「表現の不自由展・その後」は第2次安倍政権誕生後、公立美術館で展示拒否される作品が増えていることを受けての企画でしたし、数年前国際交流基金に、あるアジアを舞台とした文化交流企画を持って行ったことがあったのですが、担当の職員さんから「企画はとてもいいと思うんですが、いまのうちではできません。ここ数年(第2次安倍政権になってから)韓国や中国がらみの企画はほぼ全て却下されるようになってしまったんです」と。その人は「我々にできることは、政権とトップが変わって状況が変わるのを待つことしかないんです」と悔しそうに言っていました。安倍前首相はオリンピックに合わせてそのものズバリ「日本博」という国威発揚系の企画を進め、文化庁から予算をとっていきましたが、そのように陰ではかなり露骨な介入が進んでいたということです。人事を通じて組織のあり方に圧力をかけ、内容に干渉することを主導していたのは前政権で官房長官を務めていた菅義偉現首相です。そうした流れから考えるに、現政権が文化芸術の次に手を突っ込もうとしているのは学術であり、学術会議の任命拒否問題はあくまで入口に過ぎません。本命は科学研究費(科研費)の領域だろう、と自分は思っています。
現に、その萌芽のようなものはすでに数年前にありました。安倍前首相の肝煎りで自民党議員になった杉田水脈議員が、一部のジェンダー研究やフェミニズム研究が「慰安婦問題」を「反日活動」に利用したという理由を立て、そうした研究に科研費を使う審査のあり方を問題視するような発言を国会やブログ、ツイッターなどでしていたんですね。学問の自由を謳っている憲法を擁護する義務がある国会議員がその自由を侵すようなことを積極的にしているわけです。国会議員の劣化はここまで来たのか、と思わざるを得ません。
しかし、こうしたことは決して日本だけで起きている話ではない。世界的に見れば、ハンガリーのヴィクトール・オルバン政権は、ジェンダー研究をする学科を廃止し、ポーランドのアンジェイ・ドゥダ大統領は、LGBTQへの激しい嫌悪を公言している。このように、権威主義的あるいはポピュリスティックな政権というのは、政府にとって都合が悪いこと、あるいはジェンダーの問題に対して非常に抑圧的になっていく。権威主義政権で芸術や学術への抑圧が起きることはある種の必然ですが、順調に権威主義化が進んでいる日本で特定の分野を狙い撃ちした芸術や学術に対して抑圧が進んでいくことは明らかですよね。今回の任命拒否問題はそのように大きな構図から読み解くべきものだと思います。
この10年で社会が大きく変質している
先ほど、学術会議の任命拒否問題はあいトリの補助金不交付と同質な部分があるといいましたが、もう一つ、「表現の不自由展・その後」の中止に関わる「表現の自由」の問題があります。
まず言っておかなければならないのは、表現の自由というのは無制限に認められているものではなくて、限界があるということです。一番分かりやすい例は、混雑した劇場の中で誰かが「火事だ!」と叫ぶと、みんな混乱して、将棋倒しになって死人が出るかもしれない。それは表現の自由としては認められない。つまり、他人の生命や健康を害するような場合や人間としての尊厳を傷つける場合には表現の自由は制限される、というのが一般的な法解釈です。そして、ある表現が他人の人格権を傷つけたり、他人が攻撃される危険性を増やす場合も表現の自由が制約されることがあります。表現の自由という人権と、人格権や生存権などの人権が衝突するので調整が必要になるということです。その意味でヘイトスピーチは表現の自由には含まれないとされる国が多い。
表現の自由には限界がある。しかし、ここ何年かは、そうした表現の自由の限界を越ええていないような作品でも、公立美術館で撤去されたり、あるいは展示が認められなかったりという事例が頻発していた。端的にいえば、第2次安倍政権になってからこの傾向が顕著になったのです。そうした状況の中で、公立美術館で展示不許可になった作品を集めた展示を行うことは、問題提起として意味がある。そう思って、2015年に東京・江古田の「ギャラリー古藤」で開かれた「表現の不自由展」を公立美術館で展示しようというのが「表現の不自由展・その後」の企画趣旨でした。
「表現の自由」に限界があるのは自明ではあるけれど、その限界のラインを越えて過剰な忖度が公立美術館で行われている。これは表現の自由を、美術側が自ら手放すようなことではないか、という問題意識がそこにはありました。
もう一つ言えるのは、「表現の不自由展・その後」は、10年前だったら何も問題にならなかった企画だろうということです。5年前でも、まだトランプ政権が誕生する前で、ネットもまだ現在のような社会的な力を得ていなかったので、抗議は殺到しただろうけれど、なんとか耐えられたのではないか。それが2019年という時点では、一旦中止に追い込まれてしまった。これは、この5年、10年で我々の社会が大きく変質してしまったということの現れだと思います。
この変質にはマクロな点とミクロな点があり、マクロな点というのは、ポピュリスティックな大衆煽動がネットによってカジュアル化したということです。憎悪をあおるような煽動を政治家が率先して行うようになった。そのツールとしてツイッターというのが非常に力をもってしまったことが大きい。
一方のミクロな状況としては、おそらく、そこが今回の学術会議の問題と通底していると思いますが、人事を通じた介入です。それは現首相が官房長官時代からずっとやっていることで、人事を通じた介入によって、政権の意に反することや批判的なことをいう人に対して報復する。現に、ふるさと納税の問題点を指摘して、当時の菅官房長官に左遷させられた官僚もいた。その他にも、いろいろな現場で同様のことが耳に入ってくる。
前述の国際交流基金の話も同じです。アジアの企画で少しでも社会的なテーマであると全部没になってしまうわけですから。これは異常な状況です。現代アートや文化交流企画は社会的なものをテーマにすることが多く、そもそも政治的なものと無関係ではいられない。しかし、そういう企画は助成を得られないので、企画を持ってきても実現できない。
それが構造化すると、直接圧力をかけなくても、こんな企画を上げてもどうせ上で潰されるからというので、現場の人間が忖度をするんですよね。上で潰されるような企画を上げたら自分の出世にも響くし、そうやってみんながどんどん隷従していくしかなくなる。学術会議で行われたようなことは、実は学術会議だけで起きているのではなく、すでに日本のさまざまなパブリックな組織で起きているんです。7年8カ月の長期政権が日本社会をそう変えてきたのだということの意味を考えなくてはいけないし、ここから目をそらしてはいけません。学術会議のことだけを反対して終わるのではなく、もっと広い領域に根を張っている問題と捉えることが肝要です。
急速に権威主義化する政権
今回の学術会議の問題に関して、政府の介入が問題だとは思わない人が4割を超えている(毎日新聞世論調査・2020年11月7日実施)というのは、一言でいえば、一般の人にとって遠い問題だからでしょう。なぜなら、実際に学術の現場でどういうことが行われているのかが正しく伝えられていないし、それを知る機会もない。翻れば、我々メディアの責任がすごく大きい。だから、そこは丁寧に説明していくしかないんだろうなと。
そう思う一方で、僕自身、今回の学術会議の問題を冷やかに見ている部分もあります。一つには、「不自由展・その後」が最初の三日間で中止になったとき、怒ってくれた人もたくさんいましたが、これは美術の素人に監督を任せた結果だとか、覚悟が足りなかった、これによって表現の自由が狭められた、というような批判もあった。しかし、僕はこの中止によって表現の自由が狭められたという理解はまったく間違っていると思います。先にも言ったように、可視化されていなかっただけで表現の自由はこの10年でかなり狭められていたわけです。あいトリは、そうした状況へのカウンターであり、問題提起であり、結果として政府の虎の尾を踏んだわけです。バカ正直に真正面から行きすぎたんだという批判はありえるかもしれませんが、それだったら逆に、「迂回しながら戦えば、多少でも状況は改善したんですか?」と聞きたいですね。
実際、すでに2019年8月2日の時点で当時の菅官房長官が、定例記者会見で補助金不交付を匂わせるような発言をしているわけです。おそらくそのときに政府は不交付を決めていた。そこから今回の学術会議の任命拒否までは完全に地続きであり、その先には科研費への介入が待っている。僕は当事者ですから激烈だったあいトリ最初の3日間でそのことを予想できた。同じように予想できる人はたくさんいたと思うのですが、当時の学術界の反応は鈍かったですし、他の文化・芸術の側からも大きな反対のうねりは感じられませんでした。できるだけ自分のところに火の粉がかからないようにしていたと思います。
それが、翌月の9月26日に文化庁が補助金の不交付を決定したことで、一気に状況が変わり、大きな声が上がるようになります。これって結局補助金不交付という、かなり乱暴なことを政府がやったからそこで初めて危機感をもって動いた人たちが多かったということですよね。加えて言えば、そのときも学術界からはあまり大きな反応はなかった。いま学術会議の任命拒否問題で反対している学者の人たちには、せめて不交付問題のときにあの問題に関心をもってほしかったというのが本音です。
しかし、2019年の段階では自分たちは大丈夫だと考えていた学術関係の人も結構いたのではないかと思います。実は任命拒否の問題が起きる直前、たまたまある会議で僕がある学者に「いずれ政府は科研費にまで手を突っ込んでくるのではないですか」という話をしたら、「科研費は、基本的には専門家同士のピアレビュー(査読)によって決められていくので大丈夫だ。なぜかといえば、政治家はその分野の専門家ではないので、そもそも正しく評価をすることができないからだ」という答えが返ってきたんですよね。しかし、その見立ては間違っていたように思います。急速に権威主義的になっているいまの政治を信頼し過ぎていたのではないかと思います。
同様に、日本のメディアの弱さも露呈しました。もちろん、問題意識を感じて政府を批判した報道もありましたが、それ以上に、政府の言っていること、要するに、自民党の政調会長はこういうことをいった、官房長官はこういったということを報道しているだけのメディアも多かった。むしろ、海外のメディアのほうが、これは科学や学術に対する現政権の露骨な介入だと、この問題の核心を衝いた報道をしていました。日本でも、もっとそういうふうにシンプルに言い切る報道がされないと、多くの人は見出しだけ見て判断してしまうことになる。政府の側もそのことをよく分かっているから、学術会議は税金の無駄遣いだといった方向に論点をずらしていくわけです。
「あいトリ」を支えたシティズンシップ
あいトリの問題の話に戻しましょう。現代美術というのは、安心・安全で、人々を癒やし、きれいといってもらえるような作品だけが並ぶわけではありません。作家が生きている以上、当然、いま世の中で起きていることにインスパイアされた作品が出てくる。
そして、あいトリのような都市型芸術祭というのは、「情の時代」のような大きなテーマを設定して、その主題にのっとった作品を展示するというのがあるべき姿です。実際、ヨーロッパではそういう歴史として発展してきた。日本でも、社会的なメッセージ性の強い作品が集まるドイツの「ドクメンタ」に展示されるような、テーマを大きく掲げた現代美術の作品を創るとなれば、その中には当然、いまの社会や政治に対する批判を含む作品も入ってくる。事実、あいトリ2019は政治的・社会的な作品を集めた国際芸術祭としては日本でも出色のものだという評価を得て、あれだけの騒動があったにもかかわらず、観客数は最高動員を記録しました。
怪我の功名ですが、あのような騒動があったために、かえって現代美術のアーティストと、観客、市民との距離が近くなったんです。会期中多くのアーティストが会場にいて、観客と芸術祭のあり方について議論していた。あのような関係をアカデミシャンと一般市民の間で築いてほしいと思うんです。自分たちのコミュニティの中だけで分かっていて、国民は分かってないと言っているだけでは政府に押し切られて終わってしまう。本当の意味で、アカデミズムというのはどのように市民の生活を支えるものであるのかを、自らが問う必要があるのではないでしょうか。
アカデミックな研究の中には、我々の生活にすぐに役に立つものではないけれど、100年先、1000年先を見据えた射程の長い研究もある。歴史的な射程が長いという特徴は、美術とも共通しています。アーティストも、存命中に評価されるかどうかよりも、その作品が美術館に収蔵されて、100年後、200年後、1000年後にも見られるということを前提に作品を創っている。1000年後の未来のために自分たちはいまやっているのだということの意味を理解してもらうためには、一般市民の人たちと交流する機会を積極的につくっていかなければならないと思うんです。以前とは異なり、いま、自分たちの創造力を守ってくれるのは、政府ではなく、やはり一般の市民である。ここから始めないといけない。
あいトリのときも、実際に力強く支えてくれたのはボランティアの人たちで、彼ら、彼女らのシティズンシップが非常に大きな力を発揮しました。開催前も開催後も、僕は毎日のようにボランティアの人たちと一緒に食事をし、議論も盛んに交わしました。そういう濃厚な体験をしたことで、ボランティアの人たちも、名古屋だけでなく、日本各地のアーティストの展示を見に行ったり、他のボランティアやアーティストとさまざまな交流をしたり、そうした中で観客とアーティストの新しい関係も生まれた。僕はそれこそがシティズンシップだと思っているんです。そういうシティズンシップの高い人たちのコミュニティがどんどん強くなり広がっていけば、学術会議の件についても、何が問題なのかが理解されていくと思います。
そういう意味で、僕は悲観していません。現に、学術会議以上にテクニカルで難しい問題だと思われる検察庁法改正でも、ミュージシャン、漫画家、俳優といった広範な人たちが反対の声を上げて廃案に追い込むことができたわけですし。任命拒否問題はあくまで入口に過ぎません。これから長い戦いをしていかなければならないわけですから、中長期的な視野に立って守りを固めていくことが重要です。
そのためには、アカデミズムの中の人が先頭に立って、おかしなことはおかしいとはっきり言い、自分たちのやっていることにはこういう意味があるのだということを丁寧に市民社会に対してコミュニケーションしていく。そこが、今後の鍵になっていくと思います。
構成:増子信一
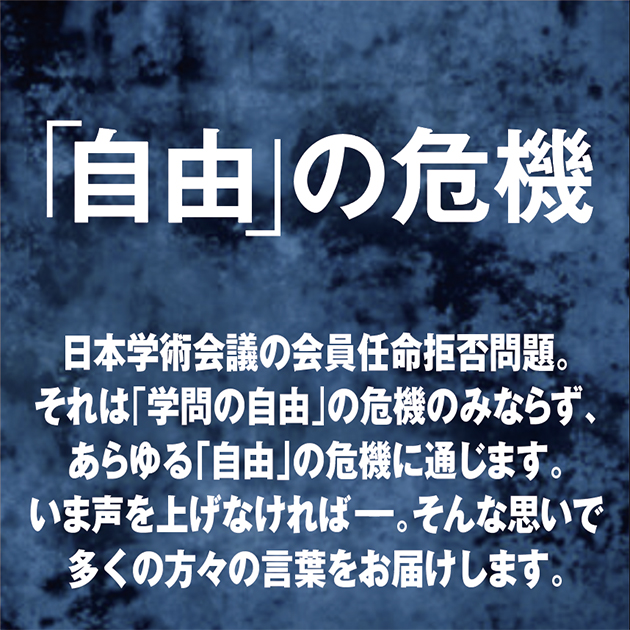
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

1973年生まれ。東京都出身。ジャーナリスト、メディア・アクティビスト。メディアとジャーナリズム、著作権、コンテンツビジネス、表現の自由などを専門分野として執筆活動を行う。主な著書に『情報戦争を生き抜く』(朝日新書)、『ウェブで政治を動かす!』(朝日新書)、『動員の革命』(中公新書ラクレ)などがある。週刊有料メールマガジン「メディアの現場」を配信中。


 津田大介
津田大介









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

