
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第7回 杉田敦 大学の自治は「自由」の砦
これまでの論考でも触れられているように、今回の日本学術会議の会員任命拒否の背景に、軍事研究をめぐる問題があるという見方があります。学術会議は、2017年3月に「軍事的安全保障研究に関する声明」(以下「声明」)を公表しました。そのことが、今回の政府の人事介入に影響を与えたのではないかという見方です。そこで、この「声明」を審議した「日本学術会議安全保障と学術に関する検討委員会」の委員長を務めた政治学者の杉田敦さんに、一連の問題について伺いました。
政府による弾圧は今回が初めてではない
事実経過から言うと、まず、2016年の学術会議の会員補欠人事の際に、すでに政府の人事介入がありました。つまり、軍事研究についての審議開始より前に介入が始まったのですから、「声明」が介入の直接のきっかけということではありません。2016年に、学術会議が推薦予定の補欠候補の一部について、官邸が「難色」を示した。学術会議としては、それに応えて推薦候補を差し替えることはできないので推薦を見送った──これは報道されている通りです。その際、私を含む役員の一部は、こうした不当な介入について、ただちに表に出すべきだと主張しましたが、それは当時の会長らによって阻まれました。
第二次安倍内閣以降、内閣法制局しかり、検察庁しかり、もろもろの組織に対して人事権を振りかざして官邸にとって都合のいいものにするような動きがしばしばありましたが、そうした流れの一環として学術会議に対しても介入が始まったのだろうと思います。
翌17年には会員(210名)の半数改選が行われました。この際にも、選考の途中段階で候補者の何人かについて、官邸側から「難色」を示されたが、説明の結果、「では会長に任せましょう」と言われたと、当時の会長はわれわれ役員に説明しました。「難色」の具体的な内容や、「説明」の内容は、われわれ役員も聞かされていません。結果的には、この時は、学術会議の推薦名簿通りに任命されました。
そこまでは、私は役員だったのですが、その後は会員の任期が切れました。2018年の補欠人事でまた同じような介入が起こったらしいということについては、間接的に聞いてはいました。そして今回の6人の任命拒否に至ったわけです。
そもそも学術会議が創設されたのは、戦争中の科学者の軍事研究動員に対する反省に基づくものです。先の大戦末期には、初期段階とはいえ物理学者が核開発の研究までやらされていた。科学者が軍事研究に関与することで戦争被害が甚大になるという問題について、日本の科学者も無縁ではなかったのです。逆にいえば、科学者が協力しなければ戦争がエスカレートすることをある程度防止できるのではないか。そういう発想で1949年に学術会議はつくられました。翌50年には、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を出し、67年には、同じ文言を含む「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」を公表している。
そのほか、原子力や生命科学の分野などでも、学術会議は政府にとって耳の痛いことをも、時には言ってきました。そうした中で、政府は何度も日本学術会議法を修正して、括弧付きの制度「改革」を行ってきましたが、そうした「改革」の動機が、学術会議の牙を抜こうということにあったのは確かでしょう。会員推薦についても、選挙制から学会推薦へ、そして会員・連携会員らによる推薦を元にした学術会議内部の選考方式へと何度も変更されました。しかし、それでもなかなか思うようにならない、ということで、ついに露骨な人事介入を始めたのかもしれません。そして介入がついに任命拒否にまで至った背景に、軍事研究について学術会議が示した見解について、政府・自民党などの中に不満があったということはあるのかもしれません。
「防衛」研究を認めれば、軍事研究の全面解禁になる
次に、2017年の「声明」に至る、軍事研究をめぐる審議経過についてお話しましょう。
2015年に防衛省が「安全保障技術研究推進制度」を新設しました。それまで、軍事研究、兵器開発は、防衛省の内部や企業を中心に行われてきた。ところが、それだけでは足りないということで、大学も動員すべく、基礎研究という形で研究費を出せるようなスキームをつくったわけです。
これを受けて、学界の一部には、同調する動きも出てきました。学術会議の内部でも、「防衛」研究なら問題ないのではないかといった形で、それまで学術会議が示してきた、そしてそもそも学術会議成立の主要な理由であった軍事研究への慎重な姿勢を変更しようとする意見も、先ほどから言及している元会長など、ごく一部には存在しました。
しかし、わざわざ「侵略」研究といって研究する人などいませんから、「防衛」研究を認めることは、実質的に軍事研究をすべて認めることを意味します。私は委員会が発足する以前の学術会議の総会において、すでに次のような趣旨の発言をしていました。
世界史上はじめて国家間の戦争が否定された1928年の「不戦条約」(パリ不戦条約、ケロッグ゠ブリアン協定)により、いわゆる戦争というものは違法とされた。しかし、各国は戦争そのものをあきらめたわけではなく、名前を変えることで対応した。つまり、自分たちのやっていることは戦争と呼ばずに、「自衛」や「侵略の排除」と言い換え、宣戦布告もしなくなった。自衛権という概念も、近年では非常に濫用されている。アメリカに至っては、9・11の同時多発テロの首謀者がアフガニスタンに逃げ込んだというだけで、個別的自衛権の行使名目でアフガニスタンを攻撃した。集団的自衛権という概念は無論のこと、個別的自衛権の概念でさえそのぐらい拡大解釈されている、と。
そもそも、「自衛」とはどこまでなのか、ということは自明ではまったくありません。集団的自衛権行使の是非をめぐって国論が二分したことは、記憶に新しいところです。さらに、「自衛」のためなら軍事的手段を用いていいのかといったことについても、意見が分かれます。実際に、学術会議の内部でも、安全保障についてはいわゆる「人間の安全保障」しか認められず、軍事的なものそのものが否定されるべきだといった議論もそれなりにありました。
そうした中で、学術会議が、「自衛」概念を定義したりすることは、不可能であるばかりか、学者の共同体というそもそもの性格からして不適切です。たとえば、学術会議の会員は集団的自衛権を容認しなければならない、というようなことでいいのか。あるいは逆に、自衛隊も違憲だという人しか会員になれない、ということでいいのか、という問題です。われわれは、それではおかしいと考えました。どういう政治的な意見の人でも会員になれる。それが当たり前ではないでしょうか。ちなみに、もしも昨年の任命拒否の際に、政府がこの点に介入してきたとすれば、それは大きな問題になります。したがって、委員会審議においては、「防衛」や「自衛」の定義を学術会議としてするようなことはしませんでした。
では、何を議論したのか。それは、学術の健全な発展に対して、軍事研究がどのような影響を及ぼすか。この一点です。言い換えれば、「学問の自由」の問題です。学問の自由の保障という観点から、軍事研究をどうとらえるべきか、ということです。
これに対して、そうした議論も「政治的」ではないか、という議論もあるかもしれません。言葉の広い意味においてはそうでしょう。しかし、学術会議は、学術の健全な発展を図ることを目的とするものです。したがって、その目的を実現するために、学術の世界と政府とのあるべき関係を考えるというのは、当然のことです。これは、他の政治的な問題一般についての議論とは性格が違います。
もう一つ、よくある意見として、あらゆる技術は「デュアル・ユース」(軍民両用)だから、何が軍事研究かは特定できず、したがって、議論には意味がない、というものがあります。確かに、ダイナマイトをはじめとして、技術が色々な用途に使えることは最初から明らかです。しかし、委員会審議でも明らかになりましたが、アメリカなど軍事研究が盛んなところでも、軍事研究と民生研究とは区別されています。
なぜかというと、分けないと機密が守れないからです。民生研究の場合には、研究成果は論文として公開されるのが原則です。他の学者がそれを読んで検証し、さらに発展させて行くわけです。ところが、軍事研究の場合には機密重視のため、成果の発表が制約される。機密性の保持が何より重要という点で、民生研究とは対照的なのです。
さらに、軍事研究においては研究テーマを選択する上での研究者の自律性が失われやすいという特徴があります。政府が国策的に、「今はこの研究が大事だ」と決めて、科学者に研究させるのですから。これについて、委員会でも、それは厚労省などほかの役所の委託研究でも同様ではないかという意見もありました。しかし、政府による強制の度合いが、他の場合とは異なる。国の意向で、ある軍事研究を進めている途中で、それまで研究に携わってきた人が、ある日、自分はこの研究をもうこれ以上やりたくないと言うことができるでしょうか。できるわけがありません。それは歴史が証明しています。
また、財政との関係でも、軍事的な領域は特権化されがちです。どこの国でも、財政的に厳しくなっても、なかなか軍事予算は削減できない。研究資金についても、軍事的なものが広がって行くと、ある特定の領域にだけ研究費が出て、軍事に役立ちそうにないと見なされた分野の研究はできなくなって行く。
要するに、軍事研究というのは究極の「国策」研究であり、研究をこれに紐付けるということは、学者がそれぞれ自律的に研究テーマを決め、その成果を公表して、学者共同体の中で共有して研究を発展させるという回路を壊すおそれがある、ということです。
これに加えて大事なことは、「声明」をどう受け止めるかは、あくまで各大学などの研究機関に委ねられている点です。各大学等は「大学の自治」を保障されており、それぞれの大学の中でどのような研究がどのように行われるかについて決める権利があるからです。
この「声明」を出した結果、多くの大学が、これを真剣に受け止め、防衛省の技術研究には応募しないという方針を決めました。しかし、これは学術会議が強制したことではもちろんありませんし、学術会議にはそんな権限はありません。
「声明」が軍事研究について警鐘を鳴らしたことをもって、学術会議自体が学問の自由を否定している、などと述べている人もいますが、誤解です。先ほどから申し上げているように、学術会議が言っているのは、軍事研究が学術の健全な発展を阻害しかねないという意見です。
それをどう受け止めるかは、まさに「大学の自治」を担う各大学の問題です。アメリカなどでは、軍事研究を精力的にやっている大学は、機密保持のために一般のキャンパスとは別なキャンパスで軍事研究を行っている。日本の大学のような狭いところでそれができるのかということも含めて、各大学はそれぞれの見識で判断することになります。
「学問の自由」は個人のためだけにあるのではない
いま、「学問の自由」と「大学の自治」が非常に大事だと言いましたが、今回の任命拒否事件で、これらの概念が日本では浸透していないことに気づかされました。これらの概念は、近代以前に成立した学問共同体の自律性を背景としています。中世ヨーロッパで、教師と学生による一種のギルド(同業組合)として大学は生まれた。そうした同業組合的な組織は自律性をもっており、誰をメンバーにするかは中で決めるのが原則です。職人として誰がふさわしいかは職人の親方たちが決めるということ。大学についても同じですし、学術会議のようなアカデミーについても、基本的な考え方は同じです。
ところが、今回の任命拒否を正当化しようと、菅首相は学術会議の会員推薦には「国民の理解」が必要だとした。さらに、憲法15条の公務員選定権を持ち出して、会員が特別職の公務員である以上、政府に決める権利があるなどと主張しています。これは、日本学術会議法の規定に反し違法ですし、「学問の自由」をふみにじるものであると共に、学問の世界というのはギルド的な、人事の自律性がなければ成り立たないという国際的な常識にも反しています。
今回の任命拒否を許せば、政府は次には国立大学の学長の任命拒否を仕掛けてくるのではないかという危惧もあります。さらには、税金を支出している以上、大学教授の任命についても、「国民の理解」が必要だなどと言い出しかねない。実際、それを支持するような意見が世論の一部にあります。
なぜ、学者の共同体について、中世の「特権」のようなものを認めるべきなのか。それは、政府にとって都合が悪いようなことを言い出した学者を政府が弾圧し、結果として学問の発展が妨げられ、社会に不利益が及んだりしたような事例がたくさんあったからです。
そしてなぜ、学問の自由は学者個人の権利というよりも、学者共同体の集団的な権利と考えられるべきか。それは、学者個人というものは弱いので、団結しなければ闘えないからです。公権力による介入と闘うためには、大学のような場所で一緒になって、自治を確立しなければならないのです。学術会議のようなアカデミーも同様で、一人で政府に対して意見を言うことはできないので、一緒になってやるわけです。
日本では中世ヨーロッパのような同業組合的な、別の言い方をすれば、国家とも市場とも区別される市民社会的なものについての歴史がほとんどないせいか、そういう集団的な権利はなかなか理解されません。現在の日本人にとって身近な組織モデルは企業か官僚制の二つしかない。したがって、学術会議も官僚制なのか、それとも企業なのか、はっきりしろと迫られるという話になっています。税金で運用しているのなら官僚組織だから、国の方針に従え、もしも国の方針とは別にやりたいのなら、自分で金を集めろ、という話。どちらでもない形態が重要なのだ、ということはなかなか理解を得られません。
「声明」の審議の際に、学者の中からも、軍事研究を認めないのは個人の学問の自由を奪うといった批判がありました。実際、歴史を繙けば、学術会議ができた直後でも、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明文を出すことに反対する人たちが結構いたことが分かりました。その反対派の人たちが言うには、実は研究の自由が一番あったのは戦争中だ、なぜなら軍からいくらでも資金が出たからで、潤沢にお金があれば自由に研究できるのに、それを学術会議や大学が止めるのはおかしい、と。
しかし先ほどから言っているように、軍事研究はどうしても学問の世界への政府の過度の介入を招き、しかも高度の機密性を求められるので、「学問の自由」は侵害されてしまうわけです。
このあたりの論点について、憲法学者の蟻川恒正さんとお話をしたことがあります。私が、「学問の自由」を学者の共同体全体の自律性としてとらえることは、憲法学において一般的なのかと伺ったところ、その考えは正当だが、従来の憲法学では、基本的には、個人の自由を守るために大学などの自律性が必要だという形で、個人の権利に重点を置いて論じられている、とのことでした。その上で、今回の事件をきっかけに、「学問の自由」をより実質的に守るためには、「大学の自治」、あるいは学術会議のようなアカデミーの自治の重要性をより強調して論じる必要があると思うようになった、とおっしゃっていました。
ここに大きなポイントがあると思います。学術全体が健全な発展をするためには何が必要なのか。すべてはそこから考えられるべきです。先ほど触れた戦後すぐの学者たちの述懐のように、個人としては、軍事研究でも何でも研究費さえ獲得できれば自分の研究ができるかもしれません。それを「自由」と思うかもしれません。しかし、研究の国家統制が進んで行けば、ミクロな「自由」と引き換えに、マクロなレベルで「自由」を失って行くことになる。ここのところを、ぜひ理解すべきです。
政治学者の松下圭一さんは、自治体という、個人と国家の中間にあるものを、個人が国家に対抗して行くための、一種の自由の砦と考えていました。砂粒のような個人が国家と直接対峙することはできないから、自治体において連帯することによって国家と闘うということです。大学のような自治的な研究機関、そして学術会議のようなアカデミーも、同じような意味でとらえられるべきです。
社会の多元性を確保するために
もちろん、政府は、一応、形式的には民主的に選出されており、したがって政府の意見は一定の正統性をもっています。何でもかんでも政府の言うことに反対すればいい、ということではありません。その意味で、私も、政府と学問とが常に対抗関係にあるということまで言っているわけではない。しかし、政府にとって耳が痛いようなことを言う存在が社会の中にないと、一つの方向に暴走してしまうおそれがあります。
長期的に見れば、そうした異なった考え方を社会の中に維持しておくことが多元的な社会を維持していくことになる。今回の学術会議の問題が、そのことを改めて考えるきっかけになれば、と思っています。
構成:増子信一
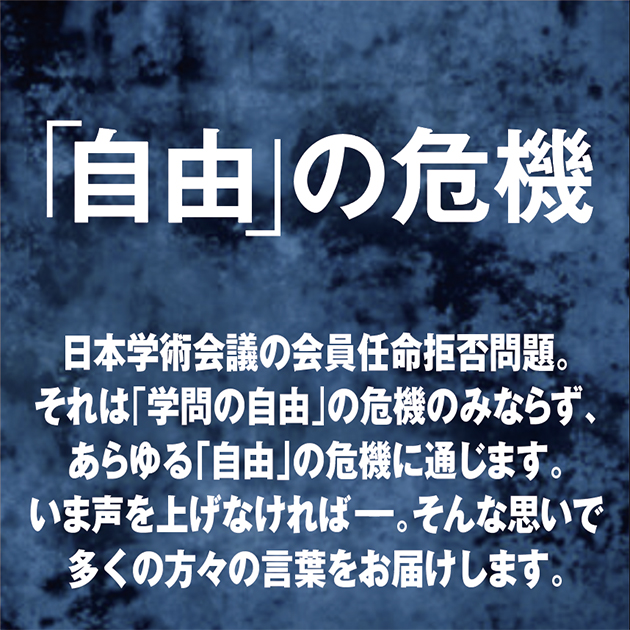
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール
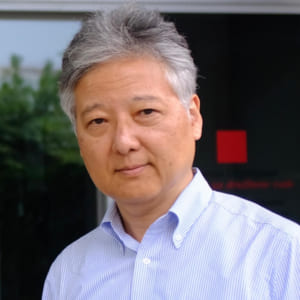
1959年生まれ。政治学者。東京大学法学部卒業後、東京大学助手、新潟大学助教授などを経て、法政大学法学部教授。専門は政治理論。著書に『権力の系譜学』『権力』『デモクラシーの論じ方』『政治への想像力』『境界線の政治学 増補版』『政治的思考』『両義性のポリティーク』。編著に『丸山眞男セレクション』など。


 杉田敦
杉田敦









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

