
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第8回 鈴木大裕 新自由主義時代の「富国強兵」教育
2021年4月に入り、菅政権は“子育てや教育に一体的に取り組む”ための組織として、「子ども庁」の新設を発表しました。そしてさらに14日には、義務教育を文部科学省から「こども庁」に移管して、内閣府の下に置くことが政府内で検討されていると報じられ、それが国家権力による教育への政治介入にあたるのではないかとの懸念が高まっています。
今回は「新自由主義」をキーワードに、注目の教育研究者・鈴木大裕氏に、近年の日本の教育動向について分析して頂きました。本ウェブ企画の発端となった日本学術会議会員の任命拒否問題のみならず、憲法改正、道徳の教科化による愛国教育、「学力向上」というスローガンの意味、そして国をあげて取り組む「グローバル人材」の育成……。一見バラバラの動きのようで、実はこれら全てが根底では繋がっている、と鈴木氏は指摘します。
自民党政権下で進められてきた教育改革の真の目的とは何なのでしょうか。それは教育に、そして子どもたちに何をもたらすことになるのでしょうか。今だからこそ、少しでも多くの方々に読んでいただきたい論考です。
教育を通して強くて豊かな国をつくるのだ。教員が何を教え、子どもたちが何を学ぶのかは国家が決める。激化する国際競争を勝ち抜くために、国が必要としているグローバル人材を育成するのだ。余計なことは考えるな。教育を通して愛国心と郷土愛を培い、国が示す学力の向上に励めばそれで良い……。
それが菅政権の本音なのではないだろうか。「戦後レジーム」――。安倍前首相は、憲法や教育基本法など、日本が占領時代に作られた様々な制度とその精神をそう呼び、「戦後レジームからの脱却」を掲げた。その安倍前首相を官房長官時代に支えたのが現・菅義偉首相であり、前政権からの路線はそのまま継承されている。本稿では、日本学術会議会員の任命拒否問題をきっかけに、「戦後レジームからの脱却」という名の下に進められる教育への政治介入と新自由主義時代の「富国強兵」教育について考えてみたい。
「檻の中のライオン」が暴れている
弁護士の楾大樹氏は、著書『檻の中のライオン[1]』の中で、国家権力を「ライオン」、憲法を「檻」にたとえ、国家権力とそれを制限する憲法の関係を、わかりやすく伝えている。まず、私たち一人ひとりには、生まれながらにして基本的人権がある。そして、個性豊かな私たちが、お互いを尊重しながら一つの社会で共存していくために国が必要となる。大事なのは、もともと「個人のために国家がある」わけで、かつて戦争への道を突き進んだ日本がそうであったように「国家のために個人がある」わけではないということだ。だから、皆が健康で幸せに暮らせるよう、ライオンには皆の権利を守りつつ国を治めてもらわねばならない。そこで必要となるのが、権力を手にしたライオンの暴走を封じ込める「檻」であり、その役割をはたすのが憲法だ。
しかし今、日本では「檻の中のライオン」が暴れている。2020年10月1日、日本学術会議によって推薦された新会員候補105人のうち、6人の任命を菅首相が拒否したことが、会員選出人事における自律性・独立性を保障する日本学術会議法に反するだけでなく、憲法で保障されている学問の自由(第23条)をも侵害すると大問題になった。
多くの識者が指摘しているように、これを独立した問題として捉えることは到底できない。特定秘密保護法の成立(2013年)、集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法の成立(2015年)、文化審議会文化功労者選考分科会委員の官邸による差し替え指示(2016年)、「あいちトリエンナーレ2019」に対する文化庁の補助金不交付問題(結局は減額で決着)、検察庁法改正案(2020年に国会に提出され、世論の反対を背景に見送り)といった一連の動きの中に位置づけられるものだ。そしてこれらの先にあるのは、自民党内で長年にわたって議論されてきた憲法の改正なのだろう。しかし、主権者である国民が訴えるならまだしも、閉じ込められているライオン自らが檻の不都合を訴えるのはおかしな話だ。
それと同じ構図が、日本学術会議会員の任命拒否事件にも見られる。藤谷道夫慶應義塾大学教授は、真の民主主義とは「多数決を捨てること」だと主張する。「現代の民主主義はロゴス(言葉、論理)主義であるべきです。論理に従って議論し、たとえ少数派であってもより正しく合理的な方が勝つ。数ではありません。議会は、そのためにあります。拙速に多数決で決めて間違うより、じっくり考えて正しい道を選んだ方がいい。多数決が正しいなら、天動説が正しかったことになります[2]」。
政治思想史を専門とする獨協大学の網谷壮介氏は、これを「民主主義の可謬性[3]」という言葉で説明する。民主主義は判断を間違える可能性がある。だから多数決で自動的に決めるのではなく、少数の異論にも傾聴し、議論する。理由も説明せずに権力を行使することこそが民主主義に反しているのだ。同時に、間違える可能性があるからこそ、学問が必要なのだろう。その意味で、憲法がライオンにとっての「檻」であるように、日本学術会議はライオンの檻の看守でもある。自ら檻の不都合を訴えて憲法の改正を試みたのと同様に、国民から頼まれてもいないのに檻の看守を変えようとした……。それが日本学術会議会員の任命拒否問題の構図だ。
「個人のための教育」から「お国のための教育」へ
日本学術会議が政治からの独立性を保障されている背景には、政治によって科学が戦争に利用された歴史がある。まだ戦後間もない1949年、日本学術会議の発足にあたり、第1回総会で決議された決意表明文にはこんな一節がある。「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたつた態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓う[4]」。
戦後、そのように反省したのは科学者だけでなく、教員もまた同じだった。上の決意表明文に出会った時、私が真っ先に思い起こしたのは「教え子を再び戦場に送るな」という戦後教育界の合言葉だった。そして、教育をめぐっては、実は日本学術会議会員の任命拒否問題が発覚するずっと前から政治による介入が行われてきた。その象徴が2006年の第一次安倍政権のもとで行われた教育基本法の改定だった。
「ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」。高らかにそう宣言した改定前の教育基本法(以下、旧教育基本法。改定後は新教育基本法と呼ぶ)の前文が明確にしているのは、「臣民の教育」を国家支配の下に置いた教育勅語(1890年公布)からの脱却であり、民主主義という新たな時代の幕開けだった。教育は国家から施されるものではない。すべての人には自由に教育を受ける権利がある。それが旧教育基本法の理念だった。
しかし、2006年の教育基本法の改定を境に状況は一変する。旧教育基本法の最後にあった第10条には、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と明記されていた。それは言い換えれば、教育における政治の責任はあくまでも教育が行われる環境を整える教育条件整備に専念することであり、「何を教えるか」などの教育内容には立ち入らないとの制約的な意味があったのだが、改定によってその重要な部分が削除されたのだ。故大田堯氏(東京大学・都留文科大学名誉教授)は、新教育基本法では「教育への(国家による)不当な支配を排除すべきだとする、旧教育基本法の締めくくり条項(第10条)が封殺された[5]」と指摘し、教育基本法改定は「憲法改定への大きな布石[6]」だと警告した。
本ウェブ企画第4回に登場し、文科官僚として国家権力と教育の関係を間近で見てきた前川喜平氏は、自民党内における教育基本法改定の計画は中曽根政権まで遡ると指摘する。中曽根元首相は「個人のために国家がある」のではなく、「国家のために個人がある」という自らの全体主義的な価値観を社会に浸透させる手段として、憲法との連動性が高く、憲法よりも改定しやすい教育基本法に目をつけたのだ。
では、「国家のために個人がある」と思っている人間がこの新自由主義の時代に権力を握った時、教育はどのように姿を変えるのか。私なりの答えが、冒頭に述べた言葉だ。子どもたちの自由な教育は、強くて豊かな国をつくるための手段と見なされ、愛国主義とグローバル経済への服従を余儀なくされていくことになるのではないだろうか。
「愛国」による教育への政治介入
それでは、新自由主義時代の「富国強兵」教育はどのように進められていくのだろうか。まず、新教育基本法第2条には、「教育の目標」として、道徳心を培うことや、伝統と文化を尊重すること、愛国心や郷土愛を養うことが新たに設けられた。そして、2011年の滋賀県大津市の中学2年生いじめ自殺事件をきっかけに、第二次安倍政権にて、道徳が評価をともなう教科に格上げされた。しかし、もともとはいじめ防止の理由で教科化されたはずであった道徳は、いつしか愛国教育のツールへと姿を変えていく。
2017年度ギャラクシー賞大賞を受賞したドキュメンタリー番組を書籍化した『教育と愛国――誰が教室を窒息させるのか』[7]は、戦後初の道徳教科書検定結果をめぐる「えっ?と驚くような事態」とそれに関する一連の報道をレポートしている。検定では、「伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」の育成という新教育基本法が打ち出した観点が多くの教科書会社を悩ませた。道徳の教科書に使われるエピソードの中で、一見何の問題もないように見える場面に「不適切」という意見が連発されたのだ。その結果、ある教科書では「パン屋さん」の場面が「和菓子屋さん」に書き換えられ、「大すき、わたしたちの町」という町探検の場面を載せていた他の教科書では、「アスレチックの遊具で遊べる公園」が「和楽器を売る店」に書き換えられていた[8]。
人が愛国心を持ち、郷土を愛する――本来は祝福すべきことなのだが、この一連の件から言えるのは、国家がそれを統制することの危うさだろう。何が「愛国」や「郷土愛」と讃えられ、いったい何がそこから排除されるのだろうか。
「学力向上」による教育への政治介入
教育への政治介入は、「学力向上」という名目でも進められていった。教育基本法改定の翌年、第一次安倍政権によって全国学力調査が43年ぶりに復活された。ポイントは、悉皆式(全員参加形式)で行われ、全国の小学6年生と中学3年生を対象に行ったことだ。その名の通り「調査」であるならば、抽出式で十分だったはずだ。しかし、第一次安倍政権は、あえて総額77.2億円[9]もの巨額を投じて全国の国公立小中学校を管理することを選んだ。その後の民主党政権下で一度は抽出式に変更されたものの、第二次安倍政権は再びそれを悉皆式に戻すという執拗さを見せた。
2014年、規制緩和で自治体別だけでなく学校別の成績開示が教育委員会の判断で可能になると、学校間の比較と序列化が進み、点数競争が激化。都道府県や市独自の学力テストを実施する自治体も増えた。東京や大阪などの都市部では、行政が各学校に「結果責任」を求め、各学校が自らの生存をかけて生徒を奪い合う「市場型」学校選択制を始める自治体も登場し、公教育の市場化の歯車が一気に回り始めた。このように、「学力向上」の名の下に教育の数値化と標準化を行うことで、国家が全国の学校を遠隔評価し、監視、競争させる新自由主義的な教育統制が構築されていった。
教育法学者の髙橋哲氏(埼玉大学准教授)は、教育基本法改定以降、特に2012年の第二次安倍政権誕生以後、新自由主義的な支配体制づくりが加速していったと指摘している[10]。2014年、「地方教育行政の組織及び運用に関する法律の一部を改正する法律」によって、教育行政における首長の権限が強化された。教育委員の中で選ばれていた「教育委員長」が廃止され、自治体の首長が任命する「教育長」に権限が一本化されたことで、首長の意向が教育に反映されやすくなったのだ。それは、戦後、政治が教育に介入できないようにと作られたはずの教育委員会制度の独立性が本質的に崩されたことを意味していた。さらに、同年5月には、教員評価を人事評価と結びつけ、降任や免職処分などの任命権者による制裁措置を導入する「改正地方公務員法」が交付され、「結果責任」の名の下に教員個人に対しても政治的な統制が強化されていった。
近代言語学の権威であるアリゾナ大学名誉教授のノーム・チョムスキーは、「民衆を受け身で従順にする賢い方法は、議論の範囲を厳しく制限し、そのなかで活気ある議論を奨励すること[11]」と鋭く指摘する。「学力向上」というのはまさに国家権力が提示する議論の枠組みそのものなのではないだろうか。本来であれば、何を子どもたちに教えるのか、どんな「学力」を育むのか、教育を通してどんな社会を目指していくのか、そこをまず徹底的に議論するのが民主主義社会の教育だろう。しかし私たちは、政府が提示する「学力向上」という枠組みを従順に受け入れ、実に活発に議論し、知らぬ間に子どもたちをこの新自由主義的な社会に適応させてしまっているのだ。
「グローバル人材」の育成
第二次安倍政権発足以降、国家経済戦略としての学問と教育の推進が加速していく。第二次安倍政権でつくられた教育再生実行会議は、2013年5月の第三次提言で、大学改革を「日本が再び世界の中で競争力を高め、輝きを取り戻す『日本再生』のための大きな柱の一つ」と位置づけ、「初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育を充実する」ことを宣言。同年7月の参議院選挙で自民党は、「世界で勝てる人材の育成」を公約に圧勝、12月には、文科省が「10 年間で世界大学ランキングトップ100に10校以上をランクインさせる」国立大学改革プランを発表している。その半年後、2014年のOECD閣僚理事会では、安倍首相(当時)が基調演説の中で「学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な、職業教育を行う」と明言。2015年、文科省はすぐにそれを実行に移し、全国立大学への通知にて、社会のニーズに合わせた学部組織の見直し、廃止、転換に向けた積極的な取り組みの開始を知らせた。金にならない人文社会系学部が狙い撃ちされた……。大学関係者らはそう呟いた。
中央教育審議会の元会長である安西祐一郎氏が、東京大学を「国民の負託を受けて多額の税金が注入されている明治以来の国策大学だ」と発言したことに対して、東京大学文学部教授の阿部公彦氏は本ウェブ企画第2回でも、その問題点をこう指摘している。「まるで明治時代に逆戻りしたかのような『富国強兵』のレトリックがそこには垣間見える」。そしてそれは、長年中学校で社会を教えてきた平井美津子氏の言葉にも通じている。「誰のための教育なのか? 原点に立ち返って考える必要があります。国益にかない、グローバル企業が求める人材というのは、戦前のお国のため、天皇のために忠義を強制させられた臣民と同じです[12]」。
大村はまが追い続けた希望の光
日本学術会議問題発覚の翌日、京都教職員組合が菅首相に任命拒否撤回を求める要請書を出した。「私たち教職員にとっても、教育の自由と学問・研究の自由は不可分のものです。今回の任命拒否は、6人の科学者の問題にとどまらず、日本の教育研究と民主主義にかけられた攻撃といわなければなりません」。学者だけでなく教師からも抗議の声が上がらないものかと思っていた私は、嬉しくなって戦後の国語教育を長年にわたって牽引した故大村はま先生に想いを馳せた。
戦時中、女学校教師だった大村は、軍需工場と化した女学校の講堂で軍から言われるままに千人針づくりを指導し、戦地へ送る慰問袋を作った。「私は戦争に協力しました」。戦争中のことを訊かれれば、少しの言い訳もせず、むしろ自分を戒めるようにそう語った[13]。戦後は、誕生したばかりの新制中学校に償いの場を求めた。「戦争の後、それまでの世の中のことを振り返ると呆然となってしまって、ほんとうに気持ちが変になるくらいでした。新しい社会をつくるために、捨て身というくらい激しい気持ちで働きたいと思った。それで新制中学へ出て、新しい民主的な国になっていくために、きちんと役に立つ国語教育を本気でやっていこうと決めたのです[14]」。
「『研究』をしない教師は、『先生』ではないと思います[15]」と言い切る大村にとって、「教える」ということは国家権力に流されない教師の自律した精神と、そのために不可欠な学問の自由を取り戻すことだったのだろう。学ぶ喜びと苦しみ、そして感動を子どもたちと分かち合わねば、と大村は常に新しい題材に挑戦し、二度と同じ授業を繰り返さなかったという。
大村の教え子の苅谷夏子は、「戦後の日本の出直しの基本は、民主主義を学ぶということだった。ずるずるっと戦争に突入し、原爆、特攻隊にまで至る過程をふりかえって、大村は、本気になって話し合うことの意味と力とを子どもに伝えようとした」と振り返る[16]。戦争の愚かさ、悲惨さを体験した大村はまにとって、戦争を知らない権力者らが嫌う「戦後レジーム」に基づく新しい社会の実現は、死に物狂いで追い続けた希望の光であったに違いない。今日の学校に、はたして学問の自由はあるのだろうか。教師と子どもが本気になって話し合い、創造的な学びに浸れる環境、そして教育を通して新しい社会を建設するという自由はあるのだろうか。
【注】
[1] 楾大樹『檻の中のライオン――憲法がわかる46のおはなし』かもがわ出版、2016年
[2] 『「多数決を捨て、議論をしよう」イタリア学会会長 藤谷道夫さん』 「東京新聞」2021年1月5日。
[3] Choose Life Project 「政治とは何か? 代表制から考える政治ー―ポピュリズムと代表制」Choose大学 2月講座:網谷壮介。
[5] 大田堯『ひとなる』藤原書店、2016年、25―26頁
[7] 斉加尚代、毎日放送映像取材班『教育と愛国――誰が教室を窒息させるのか』岩波書店、2019年
[8] この件を取り上げた朝日新聞の記事は文科省の見解をこう説明している。
“文科省は「パン屋」についても、「パン屋がダメというわけではなく、教科書全体で指導要領にある『我が国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着をもつ』という点が足りないため」と説明。「アスレチック」も同様の指摘を受け、出版社が日本らしいものに修正した。”
朝日新聞、2017年3月24日『パン屋「郷土愛不足」で和菓子屋に 道徳の教科書検定』https://www.asahi.com/articles/ASK3P7KX3K3PULZU00T.html
[9] 文部科学省HP『平成19年度全国学力・学習状況調査について』
[10] 髙橋哲『新教育基本法は子どもと学校、社会にどんな影響をもたらしたか――新自由主義教育改革の日米比較』「教育と文化」88、2017年夏
[11] Chomsky, N.(1998), The Common Good, Berkeley, CA: Odonian Press. p. 43
[12] 平井美津子『教育勅語と道徳教育――なぜ今なのか』日本機関紙出版センター、2017年、66頁
[13] 苅谷夏子『優劣のかなたに――大村はま60のことば』筑摩書房、2012年、34―36頁
[14] 大村はま、苅谷剛彦・夏子『教えることの復権』ちくま新書、2003年、68―69頁
[15] 大村はま『新編 教えるということ』筑摩書房、2017年、27頁
[16] 苅谷夏子『優劣のかなたに――大村はま60のことば』筑摩書房、2012年、95頁
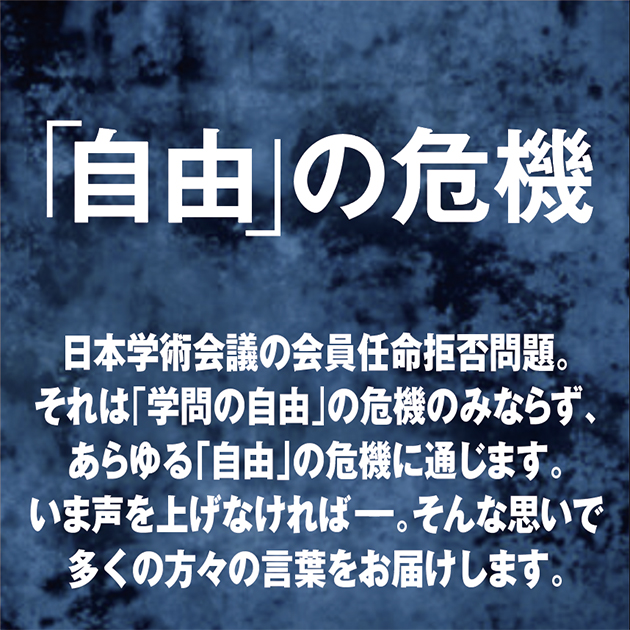
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

教育研究者。1973年神奈川県生まれ。16歳で米ニューハンプシャー州の全寮制高校に留学。そこでの教育に衝撃を受け、日本の教育改革を志す。97年コールゲート大学教育学部卒(成績優秀者)、99年スタンフォード大学教育大学院修了(教育学修士)。その後日本に帰国し、2002~08年、千葉市の公立中学校で英語教諭として勤務。08年に再び米国に渡り、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程に入学。2016年より、高知県土佐郡土佐町に移住。現在、土佐町議会議員を務める。主著は『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)。


 鈴木大裕
鈴木大裕










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


