空腹の中、雨が降ってきて……
気づけば昼過ぎとなっていて、お腹が減ってきたのだが、海外パビリオンの中にあるレストランはどこも長蛇の列ができていて、すぐに利用できるところは見当たらなかった。セブンイレブンを見つけたのだが、せっかくだから海外の料理を食べてみたいという気持ちもあって足が向かなかった。「念のために軽食を準備しておくといい」と昨日の参加者がSNSに投稿しているのを見かけていたので、リュックにパンを一つ入れてきていた。それを食べて空腹を落ち着かせることにする。
ナツメヤシの葉軸を束ねた柱が印象的なアラブ首長国連邦(UAE)パビリオンに入ると、天井の高さに驚く。
現地から派遣されてきたらしき、ヒジャブを着用したスタッフが、1970年の日本万国博覧会に、当時は「アブダビ」と出展していた時のパビリオンの模型について英語で説明してくれる。またパビリオンの前では伝統舞踊である「アル・アイヤーラ」の演奏と踊りが披露されていて、その様子にしばらく見入った。
こんな風に、自分が知らない地域の人や文化の一端に触れられる(といっても万博に展示されている内容は現地そのものとは全然違ったものだろうけど)というのは、やはり楽しいものである。万博の開催に懐疑的であろうと、こうしてたくさんの国からスタッフがやってきて、自分の国の魅力を語ってくれるという事実を目の前に、これを否定することはできないなと思う。それ自体は素晴らしいことだ。だからこそ、万博が一旦始まってしまうと、冷静にその内容を評価しにくいムードができあがっていくのだろうとも思った。
その後、「EXPOホール」という場所で行われる「Physical Twin Symphony」の予約時間が近づいてきたのでそこへ向かう。会場内の地図をプリントアウトして来てはいたが、とにかく会場が広いので、効率的なルートの選び方がなかなか掴めない。私は普段から歩くのが好きな方だが、移動に困難が伴う方はたとえば会場の東側から西側まで行くだけでもかなりの時間を要するだろう。
「EXPOホール」は万博の開会式が行われた場所で、その建物は70年万博のシンボル「太陽の塔」をモチーフにしたものだそう。近くにたこ焼きを売るキッチンカーがあって、8個入り1150円(税込み)という価格を確認する。
「Physical Twin Symphony」は、大きな舞台の上で行われるミュージカルのようなプログラムで、好きなフレーズを端末に入力するとそれをAIが解析して作曲してくれるというテクノロジーを使い、様々な身体特性を持ったダンサーやミュージシャンが音楽を通じて一体感を得るというような内容のものだった。中国出身の人気ピアニスト・ニュウニュウ(牛牛)氏が3D映像で演奏に加わったり、観覧席から数人が選ばれ、実際にパフォーマンスに参加するという演出もあり、終始華やかなショーだった。
いくつかのパビリオンの外観を眺めながら再び歩く。仕方ないことだが、気になるパビリオンがあっても基本的には予約をするか一定時間並ぶかしなければ入れないのがもどかしい。不思議な形をした建物ばかりなので外から見ているだけでも楽しいといえば楽しいのだが。
チェコパビリオンではテイクアウト用の生ビールが販売されていた。チェコの伝統的なビール「ピルスナーウルケル」を本場の注ぎ方で提供してくれるらしい。テイクアウト用のビールは1杯1250円(税込み)と、私としては割高に感じる価格だが、物は試しと思い、列の最後尾に並ぶことに。しばらくはスムーズに動いていた列が途中で止まり、「電波が切れてレジのシステムが動かないんだって」と話す周りの声が聞こえてくる。幸い、ほどなくしてシステムは回復したらしく、無事にビールを買うことができた。
大屋根リングの南端、「ウォータープラザ」と呼ばれる水辺のエリアに向かってベンチに座り、ビールを飲む。しっかり冷えていて、コクがあって美味しい。すると、日中数回行われるらしい噴水ショー「水と空気のマジカルダンス」がちょうど目の前で始まり、得した気分に。時おり、高く吹き上げる噴水が風に流されて吹きかかってくる。
いよいよ本格的に空腹を感じてきた。「ウォータープラザマーケットプレイス東」という建物の2階が「好きやねん大阪 フードコート EAST SIDE」という飲食スペースになっていて、そこではうどんが780円(税別)から、カレーが850円(税別)からと、手頃な価格で販売されている(缶ビールも500円で販売されていた)が、じっくり立ち止まって考えてみると、安いからといって食べたいわけではない。大阪市内ではいくらでも安くて美味しいものが食べられるのだから、「せっかくならここでしか食べられないものを」と考えてしまうもので、そうなると今度は高くて手が出ないという……なんとも難しいところだ。
会場で販売されるフードが今の日本国内での一般的な平均に照らして高額であるということがニュースでも度々報道されていたのだが、それに対し「お弁当の持ち込みも自由だし、安いカレーもある」といった反対意見をSNS上で目にした。が、なんでわざわざ万博会場まで来て家で作った弁当やどこでも食べられるようなカレーを食べなきゃいけないんだと、私は思ってしまう。
情けないことだが、そんな風にしてこれという食事にありつけぬまま、会場を歩く。私が購入した入場チケットでは、事前に一つのパビリオン・イベントを予約することができるのに加え、入場後、さらに予約可能な枠が追加されるというシステムになっていた。そこでなんとか予約できた「ポーランドパビリオン」の予約時間が近くなってきたのでそちらを目指す。無事入館できたパビリオン内では、ポーランドの暮らしとつながりの深いハーブや薬草類の多彩さとその役割が紹介されていた。
ここでも、ポーランドから派遣されてきたらしきスタッフの方が、積極的にそれぞれの展示内容について説明してくれる。私の周囲にいた一団がそのスタッフの一人を見て「めっちゃイケメンやわ!写真撮ってもらわれへんかな」と声を上げていて、スタッフの方は会期中、このような視線にもさらされることになるのかと思った。
ポーランドパビリオンにはレストランが併設されていたので、「よし、もうここで食べよう!絶対に」と思ったが、「ベジタリアンセット」か「肉セット」という二つのコースが用意されていて、どちらも4500円(税込み)という価格だったので結局、尻込みしてしまった。
外に出ると雨が降り始めた。夕方近くから雨になるというのは天気予報で事前に知っていたし、昨日の開幕日も雨模様で、濡れた体に吹き付ける海風の寒さに苦労した方々の感想を見ていたので、傘と防寒用のライトダウンを持ってきていた。
そしてこれはいい経験だったなと思うのだが、雨が降ると万博会場内の人の動きがかなり大きく変化するのだ。まず、多くの人が大屋根リングの下に避難して雨を避けるのだが、大屋根リングの“屋根”はかなり高い位置にあるため、下にいても雨が斜めに吹き込んできてしまう(なので、大屋根リングの下で傘をさしている人もいた)。屋根の下に置かれたベンチも吹き込む雨で濡れてしまい、座れる状態ではなくなる。そしてそこに海風が吹きつけると、一気に体感温度が低下する。
できれば温かい室内に避難したいと思うのだが、パビリオンの多くは予約がないと入場できないか、入場待ちの行列ができていたりする。悪天候になるといきなり行動が制限される。会場にアナウンスが流れ、雷雲が近づいてきているので速やかに大屋根リングから降りるように告げている。大屋根リングから地上に降りるルートは何か所もあるが、とはいえいかんせん長大なものなので、どれだけスムーズに地上まで降りられるだろうかと考えると少し不安になる。幸いその日は雷が近くに落ちるようなこともなく、大きなトラブルはなかったようだった。
日差し同様、すぐに雨を避けられる場所を見つけようと思うと難しい。かなり寒くなってきたので、どこかで暖を取れないかと、吉本興業のパビリオンである「よしもと waraii myraii館」へ入ってみるが、ここは半屋外のパビリオンで、避難できる場所はほとんどなかった。建物の中に入るのはあきらめ、大屋根リングの下を濡れぬように歩いて会場の雰囲気を眺めてまわることにする。ケーブルに通すようにして大きな石を吊るしたデザインの安全性が話題になっている休憩所「石のパーゴラ」も間近に見ることができた。
斜めにデザインされた建物が隣り合うように建ち、迷路のような路地に入り込んだような雰囲気のサウジアラビアパビリオン、古い絵ハガキをモチーフにしたパネルを並べて観光名所を案内していたスペインパビリオンなど、すぐに入れたパビリオンもあり、雨の夕方以降ということで会場内に留まる人の数も少なくなってきたらしかった。ちなみに何度かトイレを利用したが、幸い行列もなく、また事前に、会場内に8か所ある「デザイナーズトイレ」の使い方が難しい旨、SNSで情報が入ってきていたので、それらを避けたせいか、特に不便を感じることはなかった。
昼にビールをテイクアウトしたチェコパビリオンのレストランの前を通ると、少し待てば入れそうだったので、雨を避けがてらそこで食事をしていくことにする。
「鴨のローストを詰めたクネドリーキ(ダンプリング)」という、肉まんの皮のようにふわふわしたパンのようなものに鴨肉が詰まった料理が2600円(税込み)だったのでそれを注文し、一杯1450円(税込み)のピルスナーウルケルを注文する。
もう少し他のフードも食べてゆっくりしたいところだが、時計を見るとすでに20時近くなっており、多くのパビリオンが21時に閉まるというので、焦って外へ出た。
会場内でも一際異彩を放つ、落合陽一氏がプロデューサーを務める「null2(ヌルヌル)」というパビリオンは日中の予約もすべて埋まっていたが、今ならすぐに入れるとのこと(予約して見るものとは違うプログラムが上演されるそうだった)。中に入ってみると、暗い視野の中、鏡面と映像とを使って無数の光の粒が流れるのを体験できた。
最後に再び大屋根リングに登り、会場の夜景をしばらく眺めて出口に向かう。私が夢洲駅の地下鉄ホームにたどり着いたのは閉場時間の22時より少し早い21時半ごろだったが、ホームは混雑しておらず、すぐに来た電車に、座って乗ることがきた。
プロフィール

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』『QJWeb』『よみタイ』などを中心に執筆中。テクノバンド「チミドロ」のメンバーで、大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』(スタンド・ブックス)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、パリッコとの共著に『のみタイム』(スタンド・ブックス)、『酒の穴』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)がある。


 スズキナオ
スズキナオ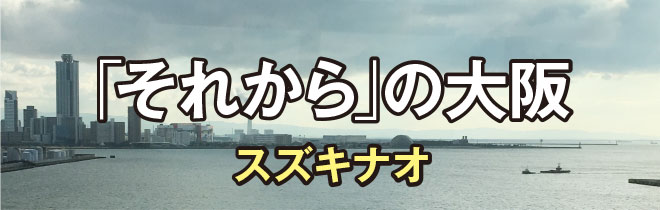
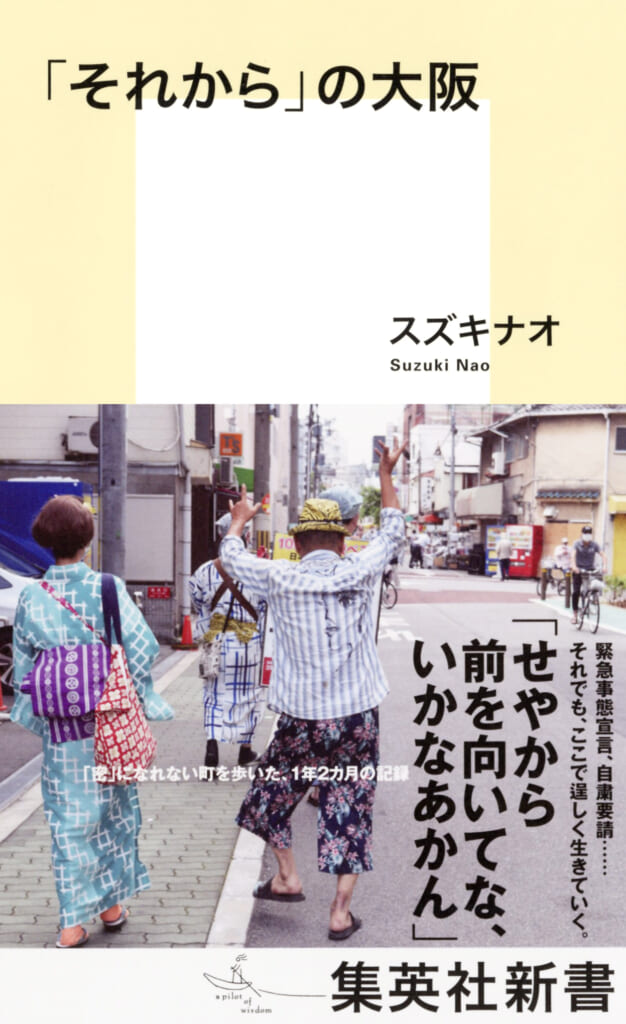










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


