自治区の終焉
CHOPの街が終わっていく。沈みゆく船からひとりふたりと降りるように笑顔が消えてゆく。意気投合した沖縄生まれのACもいつの間にかいなくなった。街が暗くなっていく。なぜか黒人たちが減っているのだ。そして反比例するようにガスマスクをかかえた白人たちが増えていく。
夜になっても所在なくうろうろしている人間たちが増えていく。白人至上主義者の襲撃に備え、理想主義を掲げる白人グループが街に増えていくように感じた。白人対白人である。これでは黒人不在のイデオロギー闘争ではないか。これをBLMと呼んでいいのか? ワシントン州の黒人比率が全米平均の11%の半分に満たない3.57%だからだとしても、黒人不在ではもうこれをBLMと呼ぶことはできないと私は思った。ここから撤退しようかと悩んでいた。
昨晩、深夜3時前に #CHOP 自治区付近に響いた2発の銃声です。車の走り去る音もしました。1名が殺され1名が重傷。#blacklivesmatter のプロテスターは現在、レイシストから攻撃対象にされ、7月4日にも大規模な襲撃予告があります。
身を守るために私もしばらく身を隠します。 pic.twitter.com/nek23BozIe
— 大袈裟太郎/猪股東吾ᵒᵒᵍᵉˢᵃᵗᵃʳᵒ (@oogesatarou) June 29, 2020
その夜、WiFiを求めCHOPに面した一軒屋に移った僕は、外で煙草を吸うこともできない恐怖を感じた。D.C.で買ったBLMロゴの帽子をかぶっているだけで射殺されそうな気配があった。野生の勘というやつだろうか、それから程なくして僕は2発の銃声と走り去る車の音を聞いた。
翌日、その銃声で16歳の少年が殺害され、14歳が重傷を受けたことを知る。僕は生まれて初めて人間が射殺される音を聞いたのだ。あの乾いた銃声は今も耳の奥に残っている。そこから僕も身を隠すことになった。
変装してシアトル郊外、ブルース・リーが眠るLake View Cemeteryを訪れました。covid19の影響で閉鎖中でしたが、香港の危機的な現状、そして #blacklivesmatter の現状を報告して手を合わせました。あなたの教え「#BeWater」は現代に生き続け、大きな影響を与えています。好多謝。#光復香港時代革命 pic.twitter.com/IbApeSjPFw
— 大袈裟太郎/猪股東吾ᵒᵒᵍᵉˢᵃᵗᵃʳᵒ (@oogesatarou) July 1, 2020
2発の銃声から2日後の7月1日。CHOPに警察が介入し、自治区は終焉を迎えた。残っていた最後の30人ほどを強制排除したのだ。相次ぐ銃撃を受け、また7月4日に迫った白人至上主義者の襲撃がさらなる悲劇を生む前にダーカン市長は決断したのだ。英断だったように私は思う。ただ、トランプ派が拡散しているCHOPがアナキストや過激派の巣窟だというのは誤りだ。CHOPはその自治を脅かす銃撃と、内面的な理想主義によって崩壊したのである。
私はその日、変装して自転車に乗り、シアトル郊外、ブルース・リーの眠るLake View Cemeteryを訪れた。コロナで中に入ることはできなかったがフェンス越しに手を合わせ、CHOPの自治の実験の終焉と、その日、香港で施行された国安法について報告した。
「be water, my friend」友よ、水になれ。場所は変わっても、流れる水のように、しなやかに形を変えながら生き続けろ。ブルース・リーが僕にそう言ったような気がした。


CHOPが終わり、メッセージも消された

警察署にはPOLICEの文字が戻った
エピローグ あの日、大坂なおみとすれ違ったかもしれない
アメリカ取材を終え帰ってきた僕を成田で待っていたのは、段ボールのベットだった。PCR検査を終えた人々が迎えの車や隔離施設へ送られる前に、そこで過ごすために割り当てられている。それは海外からの帰国者に対してあまりにも悲しい仕打ちに見えたし、今、この国が置かれている状況の悲惨さを僕に痛感させた。

成田空港での段ボールの仕切り。あまりにももの悲しい風景だ
コロナの影響でGDPはマイナス27.8%、戦後最低を記録し、8月の自殺者は1800人を超え、昨年より15%も増加した。夢をのせた2020東京五輪は延期発表後も風前の灯で、そのグッズは羽田空港の売店に大量に余っていた。
沖縄では独立記念日に米兵がコロナクラスタを発生させ、緊急事態宣言が先日まで続いていた。歴代最長任期の宰相はその記録の更新と共に体調を崩し、断腸の思いで去ったが、代わり映えしない顔ぶれは粛々と居座ったままだ。香港では国安法以降、アグネス・チョウが逮捕され、僕の友人たちも次々に海外へと旅立って行った。
アメリカではバイデンが「黒人女性である」カマラ・ハリスを副大統領に指名するも支持は伸び悩んでいる。あれからも警官による黒人への暴力は続き、プロテスターもまた射殺された。僕はというと少し鬱で、名護の海に浮かんでぼんやりと過ごしていた。辺野古を埋めるための土砂を積んだ台船がそんな僕の向こうを通り過ぎていく。
You already know I had to bring out the headwrap for this one ? pic.twitter.com/YAlLk01hwm
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) September 13, 2020
そんななか、大坂なおみは殺害された黒人たちの名前を刻んだマスクをつけ、あらゆる批判を跳ねつけながらテニスの全米オープンで優勝した。決勝は1セットを完全に支配されながらも逆境から流れを変え、彼女が勝利したとき、僕はそれを噛みしめて泣いた。流れは変わる。変えられる。彼女はテニスを通して世界にそれを印象づけた。
彼女がジョージ・フロイドの事件直後、恋人とミネアポリスを訪れていたことを知った。もしかしたらあの場所で、僕らはすれ違っていたかも知れない。あのマーチの群衆の中に彼女がいたのかもしれない。そう思い僕は過去の写真の中に彼女の姿を探した。しかしそこで気づいた。ここにいる誰もが大坂なおみだったかもしれないし、ジョージ・フロイドだったかもしれない。語弊を恐れずに言えば、私自身だったかもしれないのだ。僕はたまたま黒人じゃなかっただけだ。

6月はじめにミネアポリスで撮った写真。大坂なおみもここを訪れたのだろう
今回のアメリカ取材を通し、ある場面では自分はマジョリティであったし、ある場面ではマイノリティにもなった。差別する側にも差別される側にもなる、個とは常にそういう流動性を秘めている。だからこそ、浮かび上がるのは人権という物差しだ。自分の人権が破壊されたくないならば、他者の人権も破壊してはならないのだ。
BLMが「黒人の権利」を求めているという伝え方は、半分は当たっているが半分は外れているのかもしれない。彼ら彼女らが叫ぶのは、人間として真っ当に扱ってほしいという願いなのだ。黒人でも黄色人種でも女性でも男性でもある前に、ひとりの人間、個人として、当たり前に扱ってほしい。この願いに対して、全ての人間が当事者であることは言うまでもない。大坂なおみが立ち向かっているのは、個人の自己決定を阻害する全てのものであるように見えた。
彼女はモハメド・アリと並ぶ英雄になるだろう。そして僕らも同じ時代を生きていく。彼女の試合が終わった直後、僕はまたアメリカ行きの航空券をネットで取った。この旅はまだ、終わるはずもない。
取材・文・写真/大袈裟太郎=猪股東吾
| << 大袈裟太郎のアメリカ現地レポート④ | 大袈裟太郎のアメリカ大統領選現地レポート①>> |
プロフィール



 大袈裟太郎
大袈裟太郎









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

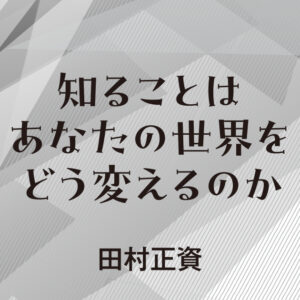
 田村正資
田村正資