私の解放か、私たちの再会か
2022年4月9日、韓国で2つの週末ドラマが同時にスタートした。『私の解放日誌』(JTBC /全16回 22:30)と『私たちのブルース』』(tvN/全20回 21:10)。両者とも今の韓国社会の矛盾や、家族や友人関係、人々の心の奥底に深く踏み込んでおり、「2022年の韓国の自画像である」と大きな話題となった。韓国人自身が「自画像」というのだから、 韓国について深く知りたい人には、まさにオススメ作品である。日本でもネットフリックスで同時配信されたことで、ランキングの上位に並んでいた。
ただ「自画像」と言ってもいろいろある。笑っている顔を描くのか、泣いている顔を描くのか、あるいは怒っている顔を描くのか。韓国では放映当時から2つのドラマについてたくさんのレビューが書かれたが、2つの作品を比較評価したものなどは、そのコントラストに注目していた。「私」と「私たち」、「解放」と「再会」、「ソウル首都圏」と「済州島」。視聴者の年齢に関しても『私の解放日誌』が20~30代の若い世代でブームとなったのに対し、『私たちのブルース』は上の世代まで広範な年齢層を巻き込んだ。
私自身は韓国のテレビで両方同時に見始めて、『私の解放日誌』はそのまま完走したが、『私たちのブルース』の方は途中で挫折してしまった(理由は後ほど)。でも、しばらくして周囲の評価、特に日本の人たちの称賛ムードに押されて、視聴を再開することにした。今度はネットフリックスで最初からじっくり見直しながら、済州島の自然と人々が織りなす美しい風景に、どんどん引き込まれていった。
新型コロナの厳しい行動制限による鬱屈した社会的雰囲気、みんながマスクして家にこもっていた時期に、よくもこんなに美しいドラマが作れたものだ。そして超豪華といわれたキャストの絶妙な配置。特にイ・ビョンホンという、当代のトップスターの凄さをあらためて実感することになった。
そこで今回はドラマ『私たちのブルース』を取り上げることにした。すでに視聴済みの方もいると思うが、ネタバレを避けながらドラマの背景について書いていこうと思う。まずは、なぜ途中で挫折してしまったのか、またイ・ビョンホンという俳優個人についても少しふれたいと思う。
済州島言葉と唯一のネイティブ、コ・ドゥシム
途中で挫折した最大の理由は、「済州島言葉」である。韓国も日本と同じく、地方ごとに豊かな土地の言葉「方言」(バンウォン)がある。たとえばドラマやバラエティなどによく登場するのは釜山などを含む慶尚道の言葉である。高低差の激しい抑揚は独特で、外国人でもわりと区別しやすい。さらに母音の数が少なく、子音も濃音が平音になったり、むしろ日本人にとっては標準語より習いやすいという人もいる。
ただテレビや映画に出てくる慶尚道言葉とちがって、実社会では何を言っているのかわからずに困惑することがある。以前、馬山に行った時に、タクシーの運転手さんの言葉が早口すぎて理解できず、韓国人の友だちですら「ここは韓国語が通じない」と嘆いていた。
しかし最難関は済州島の言葉である。こちらこそ「まるで外国語」と言われるほどで、地元の人同士の会話は韓国の人々でも理解できないと言われてきた。本土(済州島の人は陸地という)から離れた島の言葉は、独自の長い歴史の中で独自の単語や文法を維持してきた。もちろん、私たちが行けば標準語で話してくれる。標準韓国語と済州島言葉の関係は、標準日本語と琉球語の関係と似ているという人も多い。
前置きが長くなってしまったが、私がドラマの視聴を挫折したのは、この済州言葉のせいだった。意味はわかるのだが、文字で書きおこせない。私は後の仕事のために、ドラマは見ながら印象に残ったセリフをノートにメモ書きするのだが、『私たちのブルース』ではそれができなかったのだ。若い世代の言葉は大丈夫なのだが、このドラマには高齢世代も登場する。なかでも海女(ヘニョ)のリーダー、チュニおばさん役のコ・ドゥシムは済州島出身であり、彼女の早口のセリフはもう完全にお手上げだった。
「戻して見たい」
思わず、テレビのリモコンをつかんだが、正規放送ではそれもかなわない。後からネットフリックスで見るしかないなと、オンタイムでの視聴を断念したのである。
コ・ドゥシムは長らく韓国で「国民のお母さん」とも呼ばれてきた大女優だ。1951年済州島生まれ、済州島女子高校を卒業後、MBCテレビのタレント公募に合格してデビューした。済州島が舞台の『私たちのブルース』で、コ・ドゥシムは唯一の済州島出身、ネイティブ・スピーカーである。
「他の俳優さんたちが方言に苦労した中で、そこは楽だったのではないですか?」
朝の情報番組でゲスト出演した彼女に、司会者はそんな質問をした。
「でもキャストの中で済州島出身者は私だけ、本気を出したら浮いてしまうから、そこはちょっと手加減したんです」
なるほどチュニおばさんは、あれでもやはり他の共演者のためにわかりやすく話していたのだ。
プロフィール



 伊東順子
伊東順子
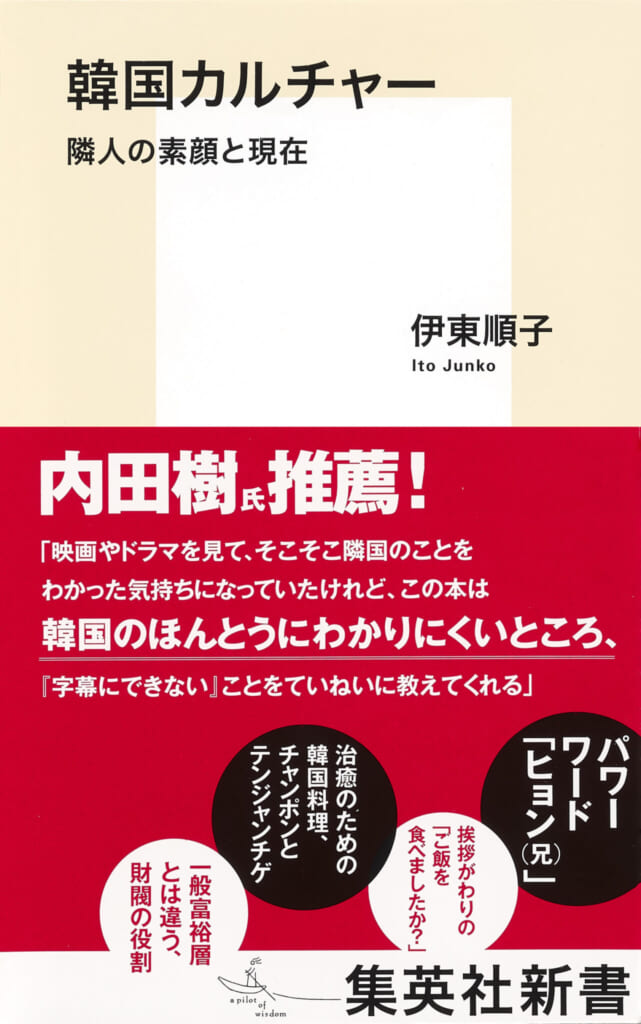














 大塚英志
大塚英志
 石橋直樹
石橋直樹