晴れることのない戦争の影
佐野が持つおだやかな文体に独特な陰影を加えているのは、やはり彼の戦争体験であるように思う。
この本を読んでひとつ重要だと感じたのは、戦争に動員され、かろうじて生き延びた若者であった人物が、戦後は商社員となって外国へ足を運び、どのように違った出自の人々を、世界を見つめていたのかが書かれている点だった。
佐野のエッセイの中には、いくつかの箇所で、彼と同じように、かつて軍隊にいたのではないか、徴兵され、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされたことがあるのではないかという人物たちが登場する。彼らを見つめる佐野の視線には、彼自身が抱えるかつての戦争の影が見え隠れする。例えば、駐在で訪れた西アフリカでの日々についてつづった「西アフリカの春」では、親しくなったある米国人について「何か不思議な雰囲気をもったひと」だったと書き、次のように回想する。

(…)硝煙の匂いがすると云ったら大袈裟であろうか。何か、ただならぬものが、彼の軽快な動作の影に、見えがくれしているような気がしてならなかった。アジアにいたというが、それはベトナムではないのか。エチオピアのあのクーデターと、何か関係があったのではないのか。
同36~37頁
また、『バスラ―の白い空から』では、バスラ空港の酒場で出会う欧州や米国から来た人々の中に「明らかに大戦中どこかの遠く荒い海に、長い間出ていたような匂いをもち続けている人たちがいた」(65~66頁)と書いている。佐野は彼らとのやり取りについて、次のようにつづる。
あの、あお黒く光る鋼鉄と機械油のにおいを、ぼくらは相互のどこかに探り当てながらも、しかしながら、そこから先には踏み入らなかった。お互いに、浅くしか眠ることが出来なかった夜々のことを、おたがいの不運な時代のことを、ぼくらはまだ打ち明けることは出来なかった。
同66頁
こうした描写の中には、自分と同じく戦争に動員されたであろう、他国の人々を探り当てるある種の嗅覚と、いまだに個人の中で晴れることのない戦争の影があらわれている。さらに、そのような記憶や体験を共有していることから生まれる、ある種の連帯の感覚があるのではないか。
佐野が書いていることと重なる場面が、最初にふれた山口瞳の小説『江分利満氏の優雅な生活』(2009年、ちくま文庫、初刊は1963年)の中にもある。作品の終盤会社員の江分利は、かつて終戦間もない頃に米兵たちのアメリカンフットボールの試合をのぞき見したことを思い出す。それは米国陸軍と空軍のチームの試合で、陸軍チームが試合に勝利すると、空軍のひとりの酔っ払いが相手の応援団に殴り込みをかけようとする。その兵士はすぐにMPに捕まってしまったが、江分利はそのとき酔っ払いの空軍兵の気持ちが分かるようであったと書かれる。
(…)しかし、江分利にはたった1人で殴りこみをかけて額を割られ、血だらけになったアイツの気持がわかるのだ。アイツはきっと南太平洋で死んでいった奴等のかわりをしたかったんだろう。口惜しかったんだろう。そいつが引っぱられて行くまでじっとしていた双方の応援団もそいつの心情が分かっていたんだろう。紳士じゃないさ、あいつは。しかし、あいつは「男」だ。(…)そしてその場にいた何万という男たちはあいつの気持を「理解」していたにちがいない。死んで行った男たち、生き残った男たち、牧場やスナック・バーや保険会社や広告代理業のオフィスに帰ってゆく男たち。
『江分利満氏の優雅な生活』234~235頁
このとき、日本はアメリカに占領されており、江分利とアメリカ兵たちとの間には、大きな格差があっただろう。けれども、江分利は「アイツ」は「南太平洋で死んでいった奴等のかわりをしたかったんだろう」という一点において彼を理解し、死んでいった者と生き残った者のうち、自分や「アイツ」は後者なのであり、「戦争」を抱えたまま日常の世界へ帰っていくのだという、同じ境遇を実感しているのだ。
例えばこの場面については、日本モダニズム期を専門とする鈴木貴宇も、著書『〈サラリーマン〉の文化史』(2022年、青弓社)の中で、江分利の米軍兵士への共感には「『戦争』への動員を避けられなかったという、国境を超えた世代的な連帯意識」があり、「『大勢=体制』への単身での抵抗をしたアメリカ兵」への共感が、戦争の記憶を抱えたまま一サラリーマン=エブリマンとして戦後の日常を生きる、という彼自身の決意に響いているのだ(425頁)、と書いている。ぼくはこの鈴木の指摘を読んで初めて、山口瞳は、国家によって戦争に動員されたという、ある種の社会的な「被害」の経験をベースにして、主人公江分利の米軍兵士への連帯を描いていたのだということに気づかされた。
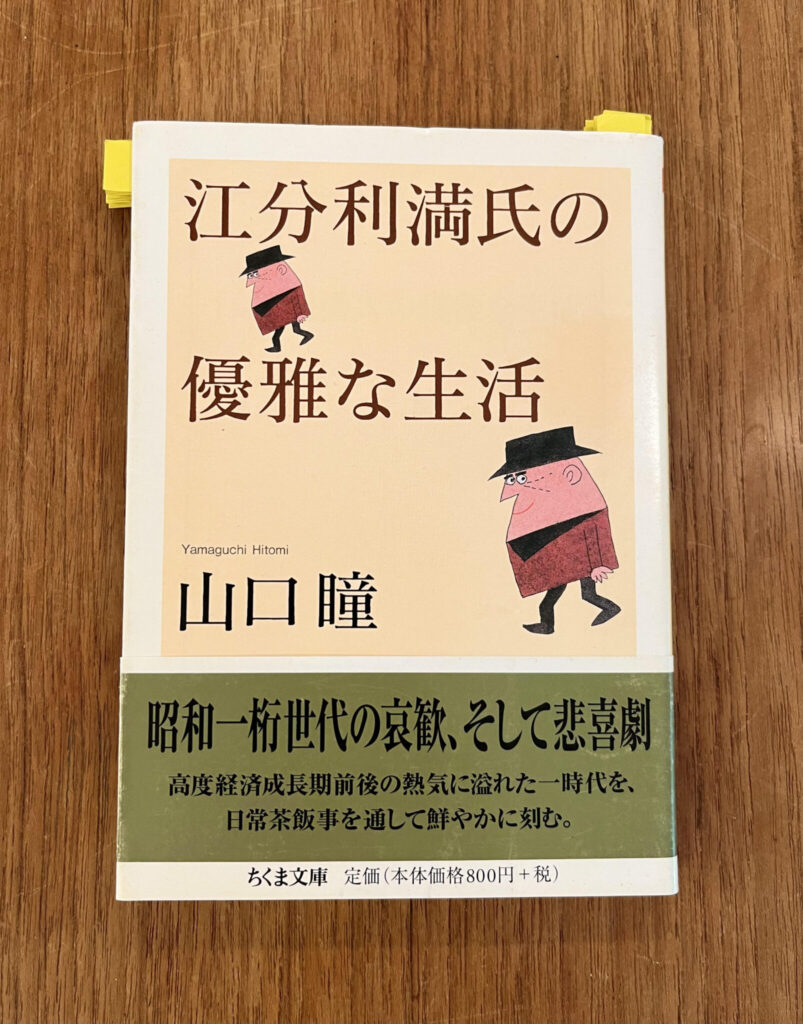
『バスラ―の白い空から』での佐野の欧米人への共感も、山口が『江分利』で描く米軍兵士への共感も、ボンヤリいまの時代から眺めると、敗戦国の人間が戦勝国の欧米の人間に感情移入しているだけの場面に見えたり、もしくはホモソーシャル的な「男」だけの世界を描いているように見えてしまうかもしれないが、ここで重要なのは、それが鈴木が指摘しているように、戦争経験、いや戦争への動員を避けられなかったという、彼らの世代がこうむった被害経験を基礎にしているということなのだと思う。
佐野の共感は、例えば日本の侵略を受けたアジア諸国の被害者たちに向けられたものではないし、『江分利満氏の優雅な生活』の主人公の意識も「男」同士のものであり、その意味では閉じた考え方に見えかねないが、彼ら自身が経験した「被害」というものを基礎に据えることで、その先に開けてくる視界というものもあるのではないか。
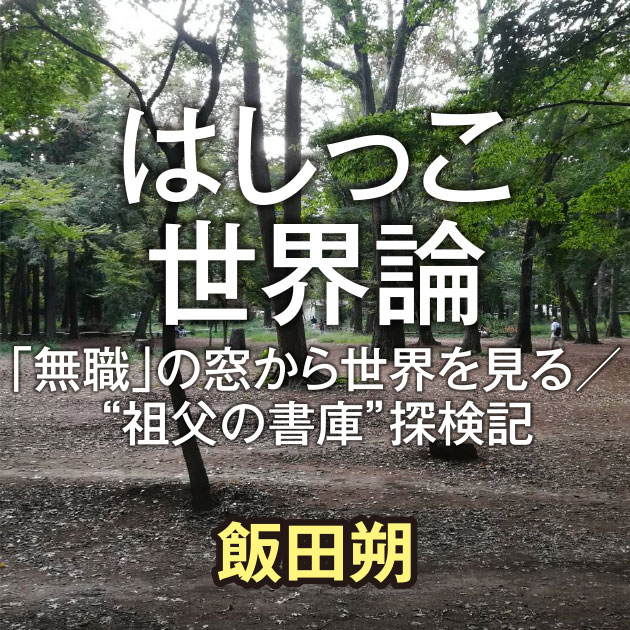
30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。
プロフィール



 飯田朔
飯田朔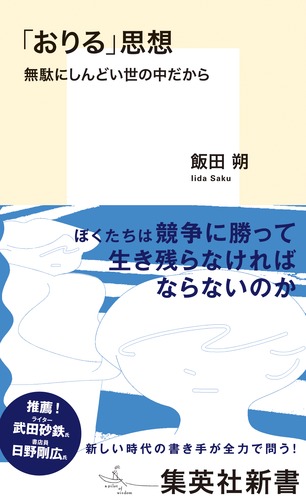










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



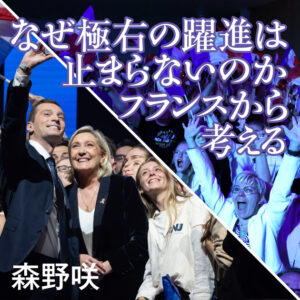
 森野咲
森野咲