「かなしむ人」「怒る人」への連帯
異国でさまざまな人たちと出会い、そこにみずからの戦争経験を投影することで佐野の目には何が見えてくるのか。
本のタイトルになっている一篇「バスラ―の白い空から」では、佐野が戦後間もない時期(おそらく55年頃)に仕事の関係でイラクのバスラ空港のターミナルビルのホテルに数か月滞在した日々について書かれている。その時期は、第二次大戦から十年あまりが経ち、「人々が戦争のことをようやく忘れかけたように見えた」「不思議におだやかだった一時期」の出来事として振り返られる。人々は「やっとのことで良い時代がめぐってきそうな期待に」「胸を寄せ合おうとしかけていた」。このエッセイでは、こうした一時期に佐野がバスラ空港で様々なルーツを持つ人たちと出会い、それぞれが背負う苦難を見つめようとする様子が描かれている。
佐野は空港の中で床屋を営む、黒海地方の国からやってきた男と親しくなる。男は故国の事情から国を出ざるを得なくなった苦悩を抱えている。
「ここはバスラ―の国際連合だ」
『バスラ―の白い空から』65頁
と、ぼくらを歓迎してくれながらも、その、乳と蜂蜜とが、いつもあふれ流れていたといわれる故郷を追われた無念さを、大声をあげて訴えるのであった。時には烈しく泣き出しては怒り続けるのであった。
この空港で佐野はまた、米国空軍兵士の一団や、戦争の影を引きずるスウェーデン人など、欧米人と出会ったことも描いているが、最後にはそうした西側先進諸国の人々への共感から一歩進んで次のように書かれていることが重要だと思えた。
ぼくは、いつか必ずあのバスラ―に行ってみるつもりだ。そして、やさしく流れ続けているであろうアラブ河の岸に先ず立とう。ジャスミンのなつかしい香りを確かめよう。それから、あのかなしむ人、怒る人をたずねてみよう。ぼくもまた、今では、充分に悲しく、充分に立腹していると、彼らに告げよう。そのあとで、あの飛行場を歩くのだ。そうすると、ぼくにはわかるのだ。あの飛行機がどこからともなく上空にあらわれ、やがて翼をさかんに振りながら、ゆっくりと降下してくるであろうことが。
同73頁
ここでは、故国を逃れてきた床屋の主人をはじめとした「かなしむ人」「怒る人」への連帯が語られている。この連帯の基礎には、佐野がかつて戦争に動員されたという経験が生きているのではないか。なぜかというと、佐野が「かなしむ人」「怒る人」に連帯を告げた後にあらわれる飛行機とは、おそらくかつての戦友たちの姿と重なる存在だからだ。
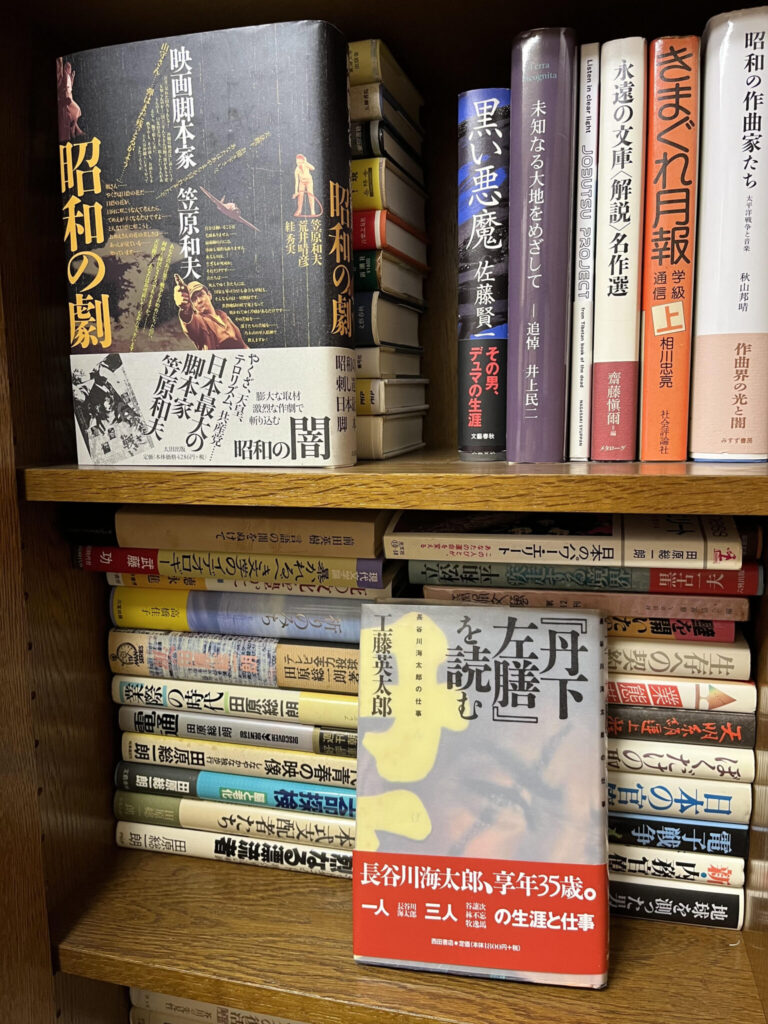
ここで語られる飛行機とは、佐野がバスラ空港で出会った米国空軍兵士たちが乗っていた戦闘機のことである。空軍兵士たちは任務と任務の間の空白期間を空港で過ごしており、彼らからは「戦争の匂い」などまったくしない。しかし佐野は当時の日々を回想する中で、兵士たちが歩んだであろう「その後」についてこう想いを馳せる。
彼らには戦争の匂いなど全くなかったが、その後数年の間に、世界の様子は非常に大きく変わっていったから、彼らの中の何人かは、そのうちにいろいろな国の空を飛ぶことになったであろう。それらの暗い空を、おそろしい顔をして、高くひくく飛んだであろう。そして何人かはその空から撃ちおとされたであろう。
同69~70頁
だが、そのような息づまる瞬間とは永久に無縁であるかのように、あれらの日々、彼らは全くのびのびと動いていた。(…)
ここでの兵士たちの「その後」に関する想像は、あきらかに先の佐野自身の戦時中の回想と響き合うものがあり、米国空軍兵たちが単に空港で出会った旧知の人々としてではなく、かつての佐野自身や戦友たちと同じ経験を持つ人々として強調されている。
これを踏まえた上で先の引用の部分を見直すと、佐野が床屋の主人と再会することで戦闘機が彼のもとにやってくるという想像上の情景は、「かなしむ人」「怒る人」への連帯を、佐野自身の戦争経験が支えている構図とみることができるのではないか。
佐野が書くエッセイでは、言ってみれば、日本だけでなく、世界の各地で困難な、不利な立場に立たされた人たちへの国境を超えた連帯が語られるのだが、それはなんらかの理論によってではなく、彼自身の戦争経験によってこそ支えられている、いわば地べたからの連帯であるということに意味があると思う。
戦中派サラリーマンというと、自身が経験した戦争の記憶にいまも縛られているという負のイメージのみで捉えてしまいそうになるが、佐野や山口が書いていることからは、戦争に動員されたという経験から出発することによってこそ、むしろ他者に対しても開かれていくという、ある種の普遍性につながる回路が見えてくるのではないか。
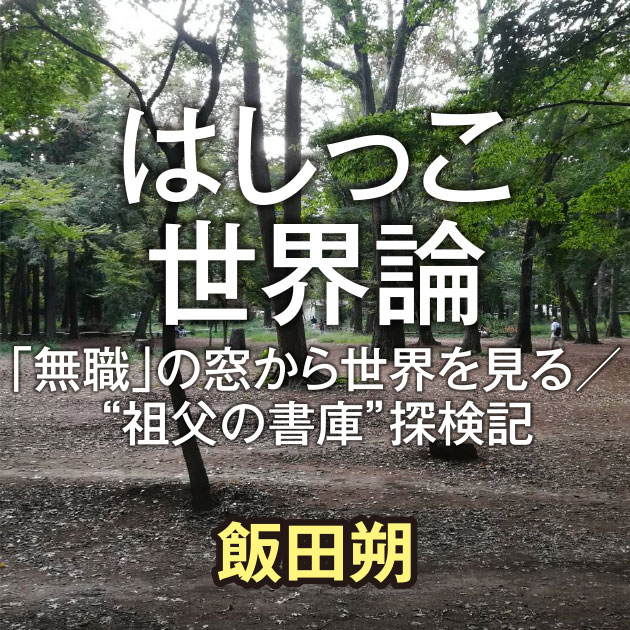
30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。
プロフィール



 飯田朔
飯田朔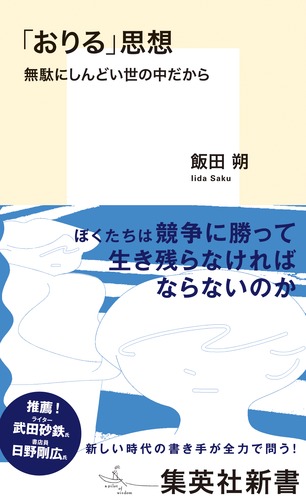










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



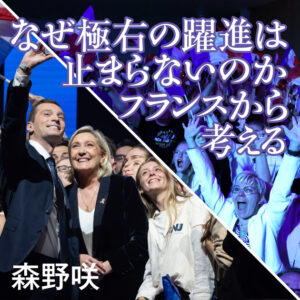
 森野咲
森野咲