戦中派が歩んだ道を辿ること
今回は、佐野の『バスラ―の白い空から』を取り上げ、戦中派サラリーマンが抱えていたもの、また彼らの持っていた可能性ということまでを考えてみたが、こういう本からいま受け取ることができるものは何だろうか。
以前ぼくは『「おりる」思想』という本で、映画監督の深作欣二(1930~2003)の作品を取り上げ、深作が自身の監督作のなかで若者同士の殺し合い=サヴァイヴ/生き残りというテーマをどのように描いたのかを考察したことがある。そのとき考えたのは、いま様々なフィクション作品で個人間の競争や殺し合いを描くものがあるが、深作欣二の場合は、サヴァイヴを理論的に分析して否定するのではなく、終戦時に15歳の少年であった彼自身の戦争経験から否定している点に重要な意味がある、ということだった。
ぼくは、佐野のエッセイから読み取れる、不利な状況におかれた他者への連帯が自身の戦争経験によって支えられているということに、深作欣二が持っていた姿勢と重なるものがあると思えた。それは、戦争や非対称的な暴力ということを理屈によって否定するのではなく(もちろん、それはそれで大事なことだが)、まず自分自身の経験――彼らの場合、被害と加害とが裏表になった戦争というものに自分も参加させられたこと――によって否定するという姿勢である。
いま、こういう彼らの姿勢に重要なものがあると思えるのは、例えば、ある個人が何らかの差別や社会的な不利益を受けたときに、その経験をどう自身の内側で受け止めていくのか、という問題を考える上で手がかりが得られるかもしれないからだ。

ともすればいまは、差別や社会的な不利益を受けた人たちが、社会制度の改善を模索したり、強者の論理を批判するのではなく、自分と異なる状況で弱い立場に追い込まれた人たちを攻撃したり、責任転嫁したりする方向に行ってしまう危うさがある。背景には、そうした人々を利用してみずからの勢力を拡大しようとする極右政治家や新自由主義のインフルエンサーといった人々の存在がある。そんな中で佐野の文章から見えてきたように、みずからの「被害」経験を他者とともに生きることにつなげようとする姿勢から学べることは大きいはずだ。それは、自分がこうむった、広い意味での「被害」という経験を、簡単に他人の、強者の論理に預けない、手放さないことによって、むしろ他者との回路を開いていくという道筋である。
書いているうちに、もうひとつ思ったのは、戦中派のとくに男性たちが徴兵によって経験させられたことは、あらためて社会的な視点で、ひとつの歴史的な「被害」として捉えるべきではないか、ということだった。
ここまで要所要所で、ぼくが佐野や山口が経験した戦争への動員を「被害」と書いてきたことについて違和感を覚えた人がいたかもしれない。なぜなら、戦争へ動員された旧日本軍の兵士たちは日本が侵略した他国の国々ではもちろん、沖縄など日本国内においてさえも、十分すぎるほどに加害者としての側面を持っているからだ。しかし、それを踏まえた上でなお、まずは当時の若者たちが国家から強制される形で戦争に動員されたという事実、その出発点での「被害」性をおさえることが重要だと考えている。
ちょうど最近、作家の周司あきらによる『トランス男性によるトランスジェンダー男性学』(2021年、大月書店)という本を読んだとき、そこで言及されていた、アメリカのメンズリブ運動のリーダーであるワレン・ファレルが考案した「使い捨てられる性」という言葉に目を引かれた。
ファレルは著書『男性権力の神話』(久米泰介訳、2014年、作品社)の中で、男性は軍隊や危険な職業、働き方など、国家や社会の中でみずからの生命をより危険にさらす複数のリスクを背負わされているのではないかと問い、男性性を「使い捨てられる性」という言葉で表現した(第4章115頁~や391~394頁など)。
周司は、このファレルによる考え方を紹介した上で、いまは「戦争」の形態が変わり徴兵制がクローズアップされる機会が減った一方で、「サラリーマン的生活のなかに男性の“戦場”が移って『使い捨てられる性』としての男性役割が持続している」「仕事において死ぬまで働かされる、という男性への抑圧」が生じていると指摘した(周司あきら『トランス男性によるトランスジェンダー男性学』73~74頁)。
これを読んだときに、まず想起させられたのが佐野や山口のような戦中派の男性たちのことであった。まさに彼らは、戦時中は兵士として、戦後はモーレツ会社員として「使い捨てられ」る立場におかれた世代だったのではないか、と。
そして、そういう世代の経験はこれまでそう多くは振り返られてこなかったのではないか。
『サラリーマンの文化史』を書いた鈴木貴宇は、戦後の「ありふれたサラリーマン」という表象が成立するために、戦争による「廃墟と無数の喪失を後景に退かせなければならなかった」こと。高度経済成長期のサラリーマン表象には「戦争の記憶が内包されていたという」こと。それらが後続世代には意識されないまま、現在に至っていると指摘(241頁)している。
鈴木の詳細な分析に目を通すと、戦中派の経験のその中身が後続世代には注目されず、置き去りにされてしまったことは事実だと思える。けれども、このような状況も徐々にではあるが、変わりつつあるのではないか。周司あきらや鈴木貴宇の問題意識もそうであるが、戦中派からすればずっと下の世代にあたる、様々な分野の書き手によって、いま少しずつ戦中派の人々の心情や社会的な待遇に注目が集まってきているように感じる。そこには小さな可能性があるのではないか。
また、アジア・太平洋戦争での旧日本軍兵士が負った「心の傷」について、昨年(2024年)国が初の調査を行ったという。25年度には調査結果が一般に向け公開されるそうだ(※2)。これは遅すぎる対応と言えるかもしれないが、同時にようやく戦争に動員された人々の経験に焦点があてられる重要な一歩となるだろう。
小さいころ祖父母の家にきていたおじいさんたちの姿を時折思い出す。
じつは『バスラ―の白い空から』には、最後に収録されているエッセイの中で、ぼくの祖父が若いときに書いた詩が取り上げられている。読み終えた後、祖母に聞いてみたところ、なんと祖父と佐野英二郎はある時期から交流が生まれたらしい。今回この本を取り上げたのは、もちろん祖父の知り合いだったからではないが、佐野英二郎もまた、ぼくが小さいころに見た「お客さん」のひとりだったのかもしれない。
いまにして思うのは、祖父母の家へ来ていた人たちにこの社会や文化、時代について、もう少し話を聞いてみたかった、ということだ。祖父はぼくが大学4年になる頃に亡くなったのだが、20代の頃の自分にはそうした世代の人たちに話を聞こうとする、とっかかりのようなものが欠けていた。
遅ればせながらいま、祖父と同世代の人たちによる文章や映像にふれ気づかされたのは、意固地にさえ見える彼らの佇まいの中には、見えづらいところからいまの社会を問うてくる、ある種の「まっとう」な問題提起が含まれていたということだった。
いまようやく彼らの足跡を辿る時期がやってきたんじゃないかと思っている。
※1 ・中村稔『私の昭和史』(2004年、青土社)350頁 ・「いいだもも新著を祝う会*記録集*」(1999年)10頁
※2 朝日新聞2025年3月12日「『戦争トラウマ』初の国調査結果を展示へ 家族『さらに広く調べて』」「戦争トラウマ」初の国調査結果を展示へ 家族「さらに広く調べて」 [戦後80年][原爆][被爆][沖縄戦]:朝日新聞
引用・参考文献
佐野英二郎『バスラ―の白い空から』1992年、青土社
周司あきら『男性学入門』2025年、光文社新書
同『トランス男性によるトランスジェンダー男性学』2021年、大月書店
鈴木貴宇『〈サラリーマン〉の文化史 あるいは「家族」と「安定」の近現代史』2022年、青弓社
前田啓介『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』2024年、集英社新書ノンフィクション
山口瞳『江分利満氏の優雅な生活』、2009年、ちくま文庫(原著は1963年、文藝春秋)
ワレン・ファレル『男性権力の神話 ≪男性差別≫の可視化と撤廃のための学問』久米泰介訳、2014年、作品社
参考作品
岡本喜八監督『江分利満氏の優雅な生活』(1963年)
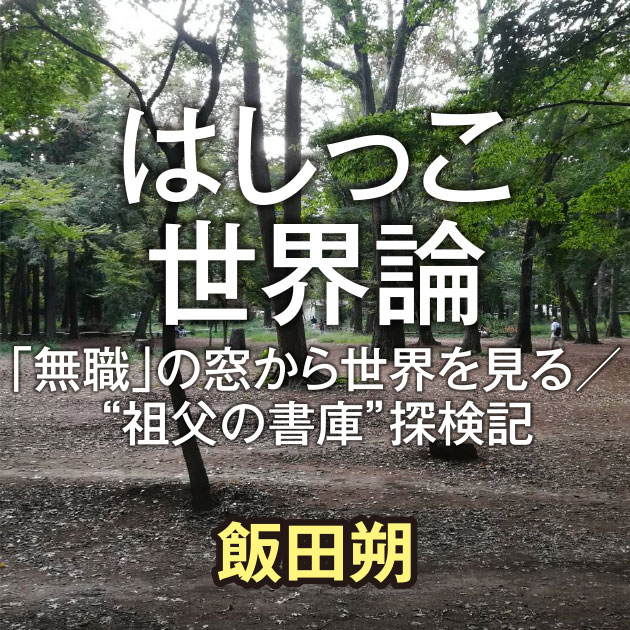
30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。
プロフィール



 飯田朔
飯田朔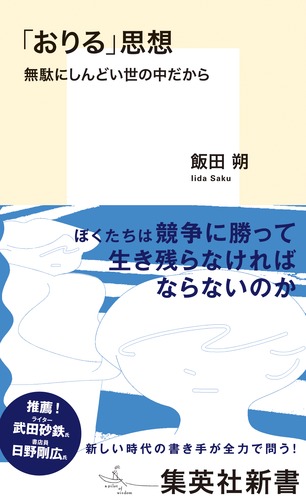










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



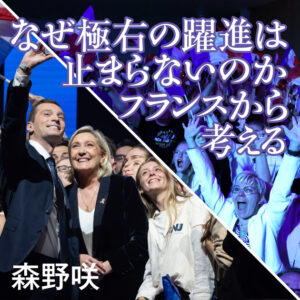
 森野咲
森野咲