級友を失った母 「学園葬」で恩師を送り
宮地さんの母・治子さんは、1929年に長崎県の崎戸島で生まれた。捕鯨と炭鉱が盛んで、かつては佐世保港などから船でしか行けなかった離島だ。長崎市内にある瓊浦高等女学校(現瓊浦高校)に進学し、近くの寄宿舎で暮らしはじめたのが1941年春。この年の冬に太平洋戦争は開戦する。治子さんの青春時代は、戦争とともにあった。
1945年8月9日の状況は、治子さんが死去した後に見つかった手記集『白夾竹桃の下 女學生の原爆記』(社會科學研究社出版部)に詳細につづられていた。女学校教諭の吉松祐一さんが編者で、GHQによる言論統制下の1951年9月25日に発刊されたものだ。
その手記によると、あの日の朝は「朝から蒸し蒸ししたいやな日であった」。体調が悪かったので、学徒動員で行くはずだった工場の作業を休んでいた。ガランとした寄宿舎で雑誌を読んでいると、米軍機が飛来する鈍い音が聞こえてきた。2階の欄干にもたれかかって、空を見上げる。「あッ 大きな機体がわたくしたちの頭上をかすめて、過ぎたとおもう瞬間—黄色い光がぴかりとひかって、物凄い轟音とともに、グラグラと台地がゆらいだ」
寄宿舎は、松山町の爆心地から約3キロ離れていた。気が付くと中庭にいた治子さんは、頭と腰を打って全身に砂ぼこりを浴びていた。顔にべっとりと血をつけたまま、這って校庭の防空壕へ。工場から生徒がボロボロの姿で逃れてくると、走って教員室へ担ぎ込んだ。多くの生徒の安否がわからない中、若い教員は生徒を探しに出かけて行く。学校に残った治子さんは、燃え盛る長崎の街を恐怖のうちに眺めていた。夜になっても火の勢いは衰えず、校庭を昼のように照らしている。柿の木の下で、助かった友人と抱き合いながら一夜を過ごした。
翌朝、生徒を探しに出ていた若い教員が生徒約30人を連れて帰った。校内には「わァッ……」と歓声が沸いたが、「朗らかで美しかった三宅先生」という別の教員の安否がわからない。夕方になって居場所がわかると、治子さんら生徒6人が迎えに行くことに。廃墟と化した街の中、星の明かりを頼りに数時間歩き回って三宅先生を見つけることができた。神社の参拝中に被爆したのだと言い、大やけどを負っていた。担架に乗せて学校へ連れて帰ると、生徒たちは校庭に咲く夾竹桃を枕元に供え、おかゆを炊いた。三宅先生は「みな達者でね、ごきげんよう」と、かすかに、でもしっかりとした声で答えたが、これが別れの言葉になった。棺桶を校庭の真ん中に安置し、「学園葬だ」と言ってみんなで泣いた。女学校では三宅先生を含めて、51人が犠牲になったと前掲書にはある。
その後、治子さんは崎戸に戻って結婚。相手は縁戚にあたる男性で、治子さんが被爆していることは知っていたが、特に問題にはならなかった。仕事の関係で熊本県八代市に移り、そこで宮地さんは生まれた。
治子さんは戦後、原爆の記憶を語ることはあまりなかった。ただ、テレビの原爆特集を見て「あぎゃんもんじゃなかと」とつぶやいていたという。

広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者を親にもつ「被爆二世」。彼らの存在は人間が原爆を生き延び、命をつなげた証でもある。終戦から80年を目前とする今、その一人ひとりの話に耳を傾け、被爆二世“自身”が生きた戦後に焦点をあてる。気鋭のジャーナリスト、小山美砂による渾身の最新ルポ!
プロフィール

ジャーナリスト
1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。


 小山 美砂(こやま みさ)
小山 美砂(こやま みさ)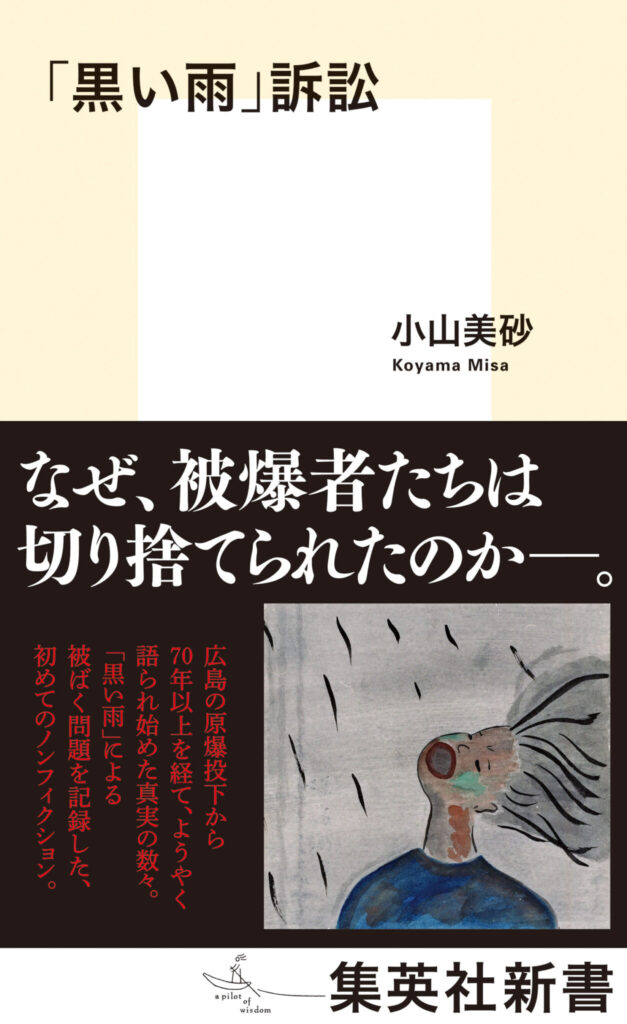









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


