連載
いま世界中でさまざまなヒットコンテンツが生まれている「リアリティーショー」。恋愛、オーディション、金融、職業体験など、そのジャンルは多岐にわたり、出演者や視聴者層の年齢も20代のみならず50代・60代以上にも開かれつつある。なぜいまリアリティショーが人々に求められているのか。芸能コンテンツの批評やウェブメディアの運営を行ってきた著者が代表的な番組を取り上げながら、21世紀のメディアの変遷を読み解く。
-
第6回
一発逆転のための自己啓発―アイドル・オーディション番組からサバイバル番組へ2026.2.11 -
第5回
恋愛リアリティショーの変遷(2)
2025.12.11
-
第4回
恋愛リアリティショーの変遷(1)
2025.9.11
昨今、日本では排外主義や自国第一主義を掲げる政党が選挙で議席を伸ばしている。ヨーロッパをはじめとする世界各地での極右政党躍進の流れが、いよいよ到来したとの見方もある。では、極右の「先進地」とも呼べるヨーロッパでは、極右はどのように勢力を拡大してきたのだろうか? フランスの大学院で哲学を学ぶ森野咲が、現地での最新の研究や報道の成果をもとに、極右の成長、定着の背景やメカニズムを明らかにする。
-
第8回
長崎人権平和資料館2026.1.23~負の歴史に向きあう優しさ・強さ・人間力について
-
第7回
呼吸するような、しなやかで強い資料館を目指して
2025.12.9
-
第6回
久米島 住民虐殺レリーフ製作リポート~加害を展示する覚悟~
2025.10.10
フィクションの世界のなかや、古い歴史のなかにしか存在しないと思われている「魔女」。しかしその実践や精神は現代でも継承されており、私たちの生活や社会、世界の見え方を変えうる力を持っている。本連載ではアメリカ西海岸で「現代魔女術(げんだいまじょじゅつ)」を実践しはじめ、現代魔女文化を研究し、魔術の実践や儀式、執筆活動をおこなっている円香氏が、その歴史や文脈を解説する。
生成AIの登場によって、人類はより情報や知識にアクセスしやすくなった。それゆえ、「知識があるだけの人間は意味がない」「いっぱいものを知っていることより、創造的なアイデアを持っている人のほうがいい」といった言説も流通し始めている。人間にとって「知る」ことの意味とは何か。そして、現代の「知る」ことの困難とは何か。
哲学・批評・クイズ・ビジネスの領域で活動し続ける田村正資氏が、さまざまな分野を横断しながら、「知る」ことの過程をひもといていく。
世界各地で起きる自然災害、忍び寄る戦争の気配やテロの恐怖、どんどん拡がる経済格差、あちこちに散らばる差別と偏見……。明るい未来を描きにくいこの世界では、子どもを持つ選択をしなかった方も、子どもを持つ選択をした方も、それぞれに逡巡や躊躇、ためらいがあるだろう。様々な選択をした方々のインタビューを交え、世界の動向や考え方を紹介する。
プラスをSNSでも
Instagram, Youtube, Facebook, X.com




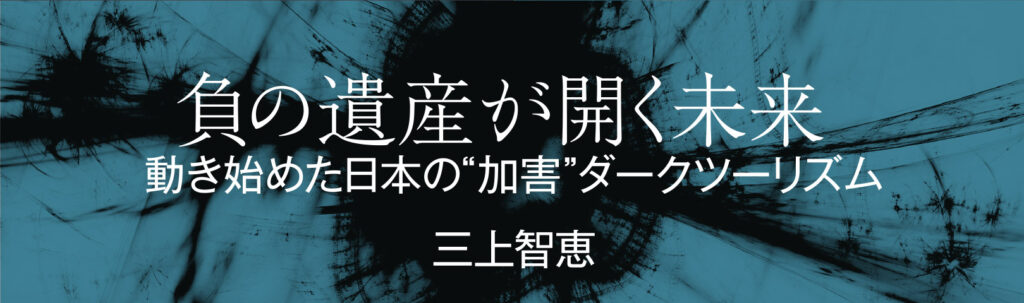

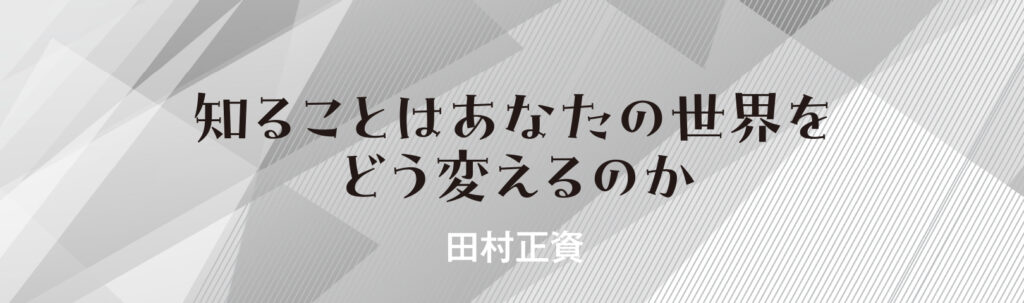
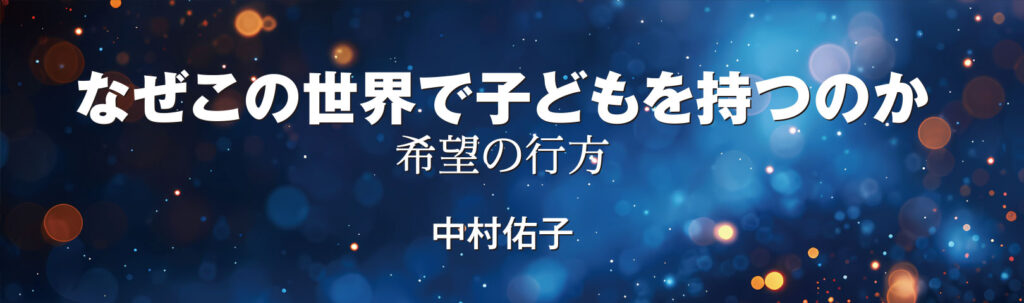










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


