連載
昨今若者の間で広まる「界隈」という言葉。インターネット空間上を通して広まったこのフレーズは、いま若者たちのゆるい繋がりを表すものとして、注目を集めている。この「界隈」の誕生は、現代の文化においてどのような意味合いを持っているのだろうか。本連載「界隈民俗学」では、インターネット上の若者集団をウォッチし続けてきたメディア研究者、山内萌がさまざまな場所で生まれる「界隈」の内実を詳らかにしていく。
-
第5回
羽ばたく天使界隈―なりたい自分を実現できる空間2026.1.14 -
第4回
BeReal.がもたらすパブリックなプライベート―首下界隈の自己演出
2025.11.7
-
第3回
ルッキズムという魔術―健康体型界隈の失敗から
2025.7.17
いまや漫才の大会としてのみならず、年末の恒例行事として人気を博しているM-1グランプリ。いまやその人気は「国民的」とも言える。なぜあらゆるお笑いのジャンルのなかで、M-1だけがそのような地位を確立できたのか。長年、ファンとしてお笑いの現場を見続けてきた評論作家が迫る。
-
第9回
SNSにおけるM-12025.12.28企業アカウント、ファンアート、生成AI、広告から
-
第8回
スポンサーから見るM-1グランプリ
2024.12.28
-
番外編
松本人志の権威はどう作られてきたか
2024.3.18
体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。
-
第5回
オタクと百貨店は個人の夢を見る―1980年代『キャプテン翼』と西武グループ2025.11.25 -
第4回
アルコールからカフェインへの過渡期―『SLAMDUNK』と山一證券
2025.10.10
-
第3回
「仲間の伝統を継ぐ海賊」ことルフィ
2025.9.29
物理的に孤立しているわけではないにもかかわらず、ひとりぼっちだと感じてしまう。この“生きづらさ”や“居心地の悪さ”の正体とは何か。孤独を単に個人問題にとどまらず社会問題として扱い、いかに社会的な条件が人々を孤独へ向かわせているかについて人類学の視点で分析した『孤独社会: 現代日本の〈つながり〉と〈孤立〉の人類学』の著者が「孤独社会」(Lonely Society)ニッポンの問題を分析する。
ショパン国際ピアノ・コンクール2025。熱気渦巻くワルシャワでピアニスト・文筆家である青柳いづみこが現地リポート。
プラスをSNSでも
Instagram, Youtube, Facebook, X.com





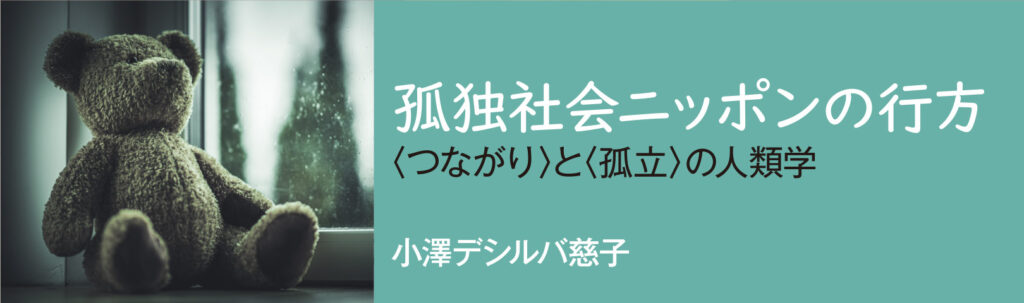
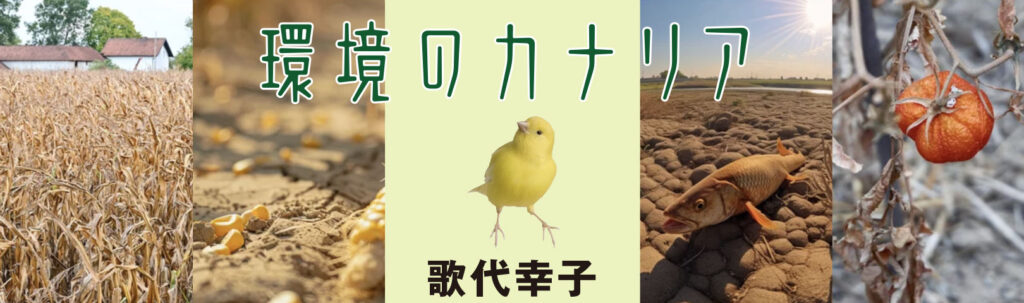
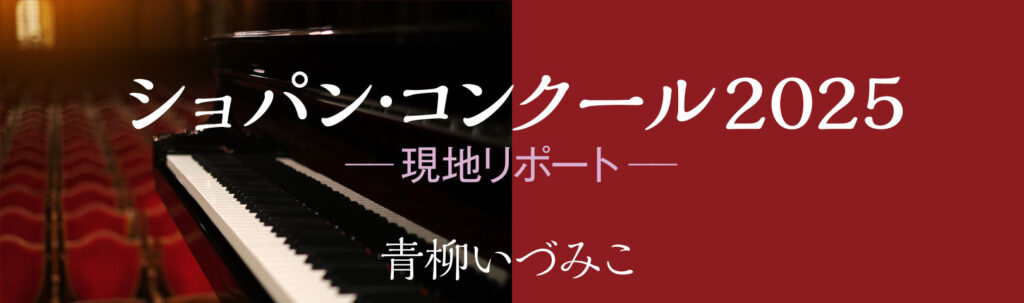










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


