4 移民とは誰なのか
さて、そのポルトガル旅行からはや6か月。いまぼくは、クリスマス直前の冬休みをサラマンカで過ごしている。この秋を通して感じたのは、ポルトで見たようなアフリカからヨーロッパへ渡る移民の人たちのこと。それから、チュロスの件で気づかされた、国と国との境目におかれる不思議な感覚についてだった。

クリスマスのサラマンカ
スペインのニュース番組では、ほぼ毎日、アフリカからヨーロッパへ渡ろうとする移民のニュースが取り上げられる。
ある夜は、スペイン南方の海岸の岩場に何十枚もの衣服が積み重なり、そこに波が打ち寄せる映像が流れる。それらはすべて、海を渡ってきたところを救助されスペインへ上陸した移民の人たちが脱ぎ捨てていったものだ。レポーターは、その衣服の山を背に現状を報告する。またべつの夜には、未成年の移民の少年たちが寝泊まりする場所がなく、バルセロナの警察署のベンチで一晩を明かす様子が映される。どれも日本のニュースなどではなかなか見ることのない、ひとつひとつは小さな出来事だが具体的であり、ぎょっとする映像だ。

そういう中で、ぼくも日本にいたときとはヨーロッパの移民に関するニュースの受け止め方が変わる部分があった。アフリカの移民の存在は、日本ではいまひとつ想像のわかない、自分とは距離のある言葉だけのものだったのだが、こちらではもっと生々しい。自分と同じ生の人間が海や塀を越えて移動しようとしているのだということが伝わってきた。
つまり、移民とは、ただ虐げられ苦労ばかりを重ねた存在ではなく、たしかに過酷な問題に直面しながらも、それ以前に生きようともがく一人の人間であり、そのかれらから伝わってくる実感のようなもの、よりよく生きようと願う個人が命がけで新たな地を踏みしめいまここにいる、というもがきのようなものに、迫力を感じた。
「移民」は特殊な状況におかれてしまった人々なのではなく、よりよく生きようとする個人なのであり、ごく「普通」の人々である、と思ったりした。
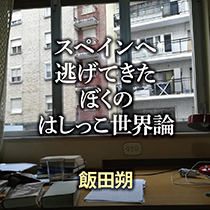
30歳を目前にして日本の息苦しい雰囲気に堪え兼ね、やむなくスペインへ緊急脱出した飯田朔による、母国から遠く離れた自身の日々を描く不定期連載。問題山積みの両国にあって、スペインに感じる「幾分マシな可能性」とは?
プロフィール



 飯田朔
飯田朔









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

