5 移動のたね、をもつこと
また、国と国とのすきまにおかれるということも、少し前に哲学者の鶴見俊輔による『旅と移動』(黒川創編、2013年、河出文庫)という本を読み、自分の中で以前よりも意識化されたように思う。この本には、様々な人物や物語に関して「旅」や「移動」といった観点から書かれた文章が収録されている。
この本に出てくる「移動」は、単なる旅行や留学とは違い、ある人物が状況や時代によって半ば強制されそうせざるを得なかったものとして提示されている。例えば鶴見は、幕末に予期せぬ漂流を経てアメリカへ渡った中浜万次郎や、亡命を経験しながら世界中で難民となった人たちを撮影した、写真家ロバート・キャパについて取り上げる。人が生きる中で予期せぬ形で何かに「移動」を強いられる場合があること。また、そういう旅を経験した人たちが様々なちがった時代、地域に存在してきたということが伝わってくる。
ぼくにとって興味深かったのは、鶴見が移動について書くときに見せる、無名の個人へのまなざしだった。鶴見は、中浜万次郎がみずからアメリカで船乗りとして稼いだ貯金とハワイ市民からの寄付によって日本への帰国事業をたて成功させたことを、アメリカ政府に援助されたペリーの浦賀渡航よりも二年も早かったと書き、わざわざ万次郎ら無名の個人による私的事業のほうを評価している。

また、鶴見は「国家と私」という別の文章の中でも、日本の人々は、幼い頃から「国家指導者のほうが偉いのではないか」という感情があるだろうと書き、それに「私には彼ら国家指導者ほどの悪をなしえない」という考えを対置し、はっきりと個人の側を肯定する。
もちろん鶴見の戦時下での経験などからこうした考えも出てきているのだろうとは思うが、こんな風に個人の側を肯定してしまえることは、ぼくにはどこか新鮮だった。というのもいまぼくの同世代を見渡したとき、こうした考え方をする人が少ない気がしたからだ。
例えば、ブラックな職場で我慢して働き続け、自分の生活や健康を損ねても、この業界はこれが普通だから、とその状況に抵抗しない人たちは多い。他にも、結婚や就職といった世間の尺度に照らしそれに順応できない自分をダメな人間だと卑下する人たち。また有名人やお金を持っている人や、地位の高い人たちを自分よりも偉いと見る人たち。「国家指導者」どころか、それよりよほど権力も持たない、こうした他人にさえ自分を売り渡してしまう人の多い時代だと思う。
ぼくなりにすこし乱暴に捉えなおさせてもらうと、国家との関係だけでなく、いまなら会社や学校といった集団、上司や教師、先輩といった相手、世間の風潮、そういった様々な自分よりも大きな、力を持つ存在と、個人の中のより小さな一部分が対立したときに、その場合小さなものの側にたつこと。そういうあり方を明確にした考え方だと思える。

そう考えたとき、これは移民の人たちの姿から垣間見えたものと重なる部分があると思えた。国の経済や政治状況の中で自分の生活のために故郷を離れることは、国家に対して個人の側に立つという鶴見の考え方と同形をなしているように見える。
移動は好奇心や冒険心による「前向き」なものだけでなく、状況や時代に強制されての「後ろ向き」な場合もありうる。しかしさらに言えば、その「後ろ向き」とされる移動のうらには、より大きなものから与えられる圧力に対して、それに飲み込まれずにより小さなものの側に立つという、ある種の正当性、まっとうさがあるんじゃないか。
こうした移動は、なにも特別な一部の人たちだけがしていることではないだろう。一般的な場面で多くの人も、「移住」や「亡命」といった物理的な移動はしなくても、それに似たことを心のなかで行ったり、もっと目立たない形ではやっていると思う。例えば、上司から叱られたり、説教を受けたりするときに、「うぜえ」と思えるような心理状態にあるとき。また、仕事や学校をサボり一休みしようとするときなど。これらも、すでに一種の心理的な面での避難、もしくは「移動のたね」と呼べそうな気がする。
そう考えるときに、アフリカの移民の命がけの移住も、ポルトの老人がぼやいた地元への違和感も、日本人がTwitterなどでつぶやく職場への不満も、ぼく自身の日本脱出もそれぞれどこかでつながるところはあるのかな、と思えるのだった。

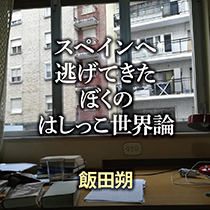
30歳を目前にして日本の息苦しい雰囲気に堪え兼ね、やむなくスペインへ緊急脱出した飯田朔による、母国から遠く離れた自身の日々を描く不定期連載。問題山積みの両国にあって、スペインに感じる「幾分マシな可能性」とは?
プロフィール



 飯田朔
飯田朔









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

