スペインから帰国した「なんでもない」人として著者がつづる「はしっこ世界論」のB面『“祖父の書庫”探検記』。祖父が残したぼう大な書物の山に分け入り、現代社会を読み解く手がかりを探す連載の第2回は、いまの若い人たちにとっての人間らしい時間としての「食」と、背景に根差した「食欲」の死角について考える。
※今回の文章は、昨年2020年の1回目の緊急事態宣言が解除された後に飯田が祖父の書庫を訪れたことについて書かれ、また文章自体は同年の秋に書かれたものである。
久しぶりに会った人から「最近どうしてるの」と近況を聞かれるとき、ぼくは文章を書いているだとか、もしくはいま日本語教師になるための勉強をしているだとか、色々な答え方をする。ただじつは、それらのどの答え方でもなく、ぼくは「なぜかここ数年は食べ歩きと料理に猛烈にハマっていて、日々食べることばかり考えているんだよ」と答えたくなる。しかし、久しぶりの相手にいきなりそこから話を始めても変な気がするので、もう少し普通の近況報告から話をするのだが…。
ぼくはこの3年間ほど、食べ歩きと料理が趣味になっている。今回は、祖父の書庫で「食」に関する本を探してみた。なぜ「食」なのかというと、この3年趣味で食べることに夢中になるうちに、いまの世の中や自分たちの生活について考えるときに「食」が、もっと言うと人が持つ「食欲」がひとつの重要なキーワードになるんじゃないか、とあらためて思えたからだ。
いま若い人たちの間では、休日にひとりで飲食店を食べ歩いたり、SNSに食べたものの写真をアップしたり、「グルメ」というよりはもう少しライトな形で「食」を楽しむスタイルが広がってきているように思う。ぼくは、これが単なるひとつの娯楽としてではなく、いまの若い人たちがおかれた過酷な労働環境であるとか、「自己実現」的な風潮からつかの間抜け出すための、ちょっとした「避難」のような意味合いで行われている側面があるんじゃないか、と推測している。
人が誰かから押しつけられて何かを嫌々する、というあり方ではなく、自分から自然に「これが食べたい」と思い、飲食店へ行き、もしくは自分で料理をして、何かを食べる。そういう素朴な、前向きな欲求として、いま「食欲」というものは重要なものになってきているんじゃないか。この「食欲」について考えられる本はないかと考え、コロナウイルス感染拡大が騒がれる中、しばらくぶりに藤沢の祖父の書庫へ足を運んだ。
前回は3冊の本を取り上げたが、今回紹介するのは1冊のみで、柴谷篤弘『オーストラリア発 柴谷博士の世界の料理』(1998年、径書房)という本である。
今回はこの文章を書くまでにいくつかつまずきがあった。ひとつは、コロナウイルスの感染拡大と政府の緊急事態宣言。もうひとつは、祖父の書庫へ行ってみたら、「食」に関係する本があまりなかった、ということだった。
今年(2020年)5月の終わりに緊急事態宣言が解除され、その後少し間をあけて、ようやく、という気持ちで初夏のある日、藤沢の祖父の書庫を訪れた。実家の吉祥寺から乗った井の頭線と乗り継ぎの小田急線は、ずいぶん空いていた。本当は4月に書庫へ行きたかったのだがだいぶ遅れてしまった。
久しぶりに顔を合わせた祖母は、人と会う頻度は減ったが、庭仕事に精を出しているので退屈していないと話す。ぼくは念のため今回は祖母の家では玄関までしか入らないことにした。祖母は、手作りの夏みかんジュース(カルピスと混ぜてあって、おいしい)を出してくれる。祖母の家の玄関に荷物を置かせてもらい、その後母屋の横にある別棟の祖父の書庫に入った。
書庫を見て回ったところ意外だったのは、「食」に関するテーマの本が少ないことだった。ぼくから見て、祖父はものすごく食いしん坊で、焼き肉屋で石焼ビビンバをぺろりとたいらげたり、極端な甘党でいつも甘いものをバクバク食べている人だったのだが、書庫の本棚を見て回ると、なぜか食べ物の本は見当たらない。
そんな中一度母屋へ戻ると、祖母が以前祖父の蔵書から見つけてきた料理関係の面白そうな本を見せてくれた。分子生物学者の柴谷篤弘(1920-2011)が書いた料理本『オーストラリア発 柴谷博士の世界の料理』(以下『柴谷博士の世界の料理』)である。料理の門外漢が書いたものだが、中をパラパラめくると、「食」への並々ならぬ思い入れがあるように感じられ、興味をひかれた。今回はこの本を読んでみることにした。

30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。
プロフィール



 飯田朔
飯田朔

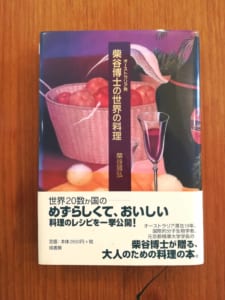











 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

