4 虫のようにうごめく多様性
ももの本を読んで面白いと思ったことの二つ目は、ももの文章の中に、普通とは違う、独特な「多様性」の感覚が垣間見えることだった。ぼくが読んだももの評論のいくつかでは、歴史の中の劣者や敗者、もしくはマイノリティの立場に置かれた人たちへの言及があり、そこに、いま行政などで標語として使われる「ダイバーシティ」という言葉や、理論として考え抜かれた反差別の主張や運動といったものとは違う感触を持つ「多様性」が現れている。
例えば、ももは『「日本」の原型』の中で、日本中世の賤民芸能にふれているのだが、その一文は次のような特徴的な書き方になっている。
さよう、賢明鋭敏な読者が、この本書後半部の日本的中世の舞台が、今様を歌唱する白拍子・遊女ばかりか、説経師・唱門師・論義師・弄弁家・猿楽師・高野聖・琵琶法師・瞽女・鉢たたき・河原者・音曲家等々の、異類異形の唱導文芸家と雑芸技能者たちが自由往来する賤民芸能の盛期として、前代の白鳳・天平・平安時代の日本的古代における貴族文化とは異質な物語世界(、、、、)の交通の場であったことを、連想されたならば、(…)。
同前165頁(傍点原文ママ)
これまた長い一文で読みづらくもあるのだが、ぼくが面白いと思ったのは、賤民芸能について「説経師・唱門師・論義師(…)」と芸能者の名称をどんどん挙げていくことで、読んでいるとまるで妖怪の百鬼夜行の行列のように、小さな芸能者たちが集まって行進しているかのような、妙に「わらわら」とした感覚を呼び起こされる文章になっていることだった。
祖父の文章は、様々な情報や用語が列挙されることで、時折このような「わらわら」としたお祭りのような感覚が現れてくることにひとつの特徴がある。
こういった側面は、他には例えば、同じ本に出ている、次のような文章にも重なるものがある。この一文は、日本列島で最初に暮らし始めた人々を描写している箇所である。
台風・雷鳴・噴煙・地震・梅雨・豪雨・豪雪の火山列島の窪地にやがて「夕凪」がやってきて、そのあかぐろい火山灰地にインドヤポネシア海域的連動性をもって「土蜘蛛」が蠢動しはじめた時(…)、それを「倭」「倭人」として識別し、記録したのは、古代中国の史官であった。
同前15頁
ここでぼくの目が引きつけられたのは、祖父が日本列島で最初に生活を始めた人たち(ももは彼らを「土蜘蛛」と呼ぶ)を「蠢動」という言葉で描写している点だ。「蠢動」とは、虫などがうごめいている様子をあらわす言葉だ。祖父は、いわゆる大和朝廷以来の「日本」が確立する以前の列島に暮らしていた人々、また、朝廷が成立して以後蔑視の対象とされた土着の人々、劣者の立場に置かれた側を、どこか虫のようにうごめく、活力を秘めた「わらわら」とした存在として見ていたのではないか。
こうした「わらわら」感は、他のももの著書では、例えば『にっぽん笑市民派』(1981年、創林社)という本で、「酒呑童子」「物ぐさ太郎」「一寸法師」などの中世の説話や昔話を「乱世のエネルギー」に満ちた物語として列挙している箇所や、江戸中期の思想家・安藤昌益について論じる一冊『猪・鉄砲・安藤昌益』(1996年、農文協)で、日本列島で暮らした人々の生活形態として、農民だけでなく漁民や山民に言及したり、また、日本では米のほかにイモが主食として食べられる地域があった例を出している箇所などにも共通している。
これらの独特な感覚の背景にあるのは、ももの中に、多様な要素をひとつの枠組みに同化、単一化させる力への反発が強くあるからなのではないか。例えば、ももは、『「日本」の原型』や『猪・鉄砲・安藤昌益』で、天皇や大和朝廷を中心とした日本列島の歴史の捉え方や、江戸時代の石高制社会、また、日本列島で暮らしてきた民衆の生活を「コメ一元論」で語ることなどに批判的である。このような単一化の動きに対して、ももは著作の中で賤民芸能や列島先住民が体現したもの、「わらわら」した要素を持ち出し、ぶつけているのだ。
ももは「博覧強記」と言われる人であったし、ぼくは詳しくないがマルクス主義の考え方の中にすでにこうしたものの見方が理論としてあったのかもしれない。しかし、ここまで書いてきたことを踏まえて思うのは、これは、ももがマルクス主義者として、または博覧強記の物書きとして客観的に物事を捉えてこう書くに至ったというよりは、もも自身の中にここまで見てきた、「生まれついての」変わった性質、また、他者からの束縛を強く拒絶するような特異な性質があり、それが文章の中に「こう書かずにはいられない」という形で、単一化の動きに反発する、不思議な「わらわら」感として現れてきているんじゃないか、ということだった。
こうしたももの文章中に見られる「多様性」の要素は、先ほど挙げた、最近よく話題になっている「多様性」のあり方とは違い、もっと未整理で、落ち着きのない性質を持つものに見える。この感覚は、ぼくの中では例えば、人間も動物も入り交じって大騒ぎを繰り広げる、映画監督エミール・クストリッツァの作品の世界観などと重なる。祖父のような、自分の関心ばかりで周囲に気を遣えない、アンバランスな人の文章に、ふと未発達な「多様性」の感覚が現れていることは、ぼくにとってひとつの発見だった。
いまSNSなどをやっていると、多様性に関する議論は、日本でも海外でも頻繁に見かけられる。それらの多くには重要な要素が含まれているとは思うが、一方で多様性が「これをとりあえず守っていればいい」とでもいうような、形式だけを重視する消極的なものになっていると感じることがある。また、「多様性」がなぜ重要なのかは考えられず、ただ世の中の新しい風潮がそうだから、と一種の自分の外側にある概念として受け取られている場合もある気がする。
これはぼくの勝手な考えだが、多様性が大事だと言う前に、その一歩手前の段階として、おさえておかなければならないことがある。それは、そもそも人はみな独自の、その人なりの性質を持っている、ということだ。人は個人個人で、他人から見たら「変」だとさえ思われてしまう部分まで含めて、その人なりのクセや特徴を持っている。そうした要素が不当に攻撃されたり、歪められることがあってはならない。その人なりの生き方が、人種や性別、信仰といった個人の持つ属性によって社会の中で排除されたり、攻撃されることがあってはならない。このように考えたとき初めて「多様性」や「反差別」が大事だと言えるんじゃないか。この「前提」と突き合わせてみると、今回祖父の文章を読んで発見した未発達な「多様性」の感覚は、そもそもなぜ多様性は大事なのか、という問いを個人が自分の内側の要素を出発点にして、足元から考えるためのヒントになるようなものとして見えてくるのである。

30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。
プロフィール



 飯田朔
飯田朔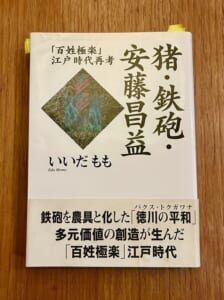










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


